| ғzҒ[ғҖғyҒ[ғWҒcҒcҒBҠ®җ¬ӮөӮДӮўӮҪӮМҒ\Ғ\ҒH |
|
|
|
ғ„ғbғ^Ғ[ҒIғzҒ[ғҖғyҒ[ғWӮЕӮ«ӮҪӮжҒ[Ғ_(ҒOҒO)Ғ^
ғIғҢӮМ–ј‘OӮНғPғ“ҒBғӮғeғJғҸғXғҠғҖӮЕҲӨӮіӮк‘МҺҝӮИ’jҺqҚӮҚZӮ“Ғ\Ғ\ҒBӮсҒ[ҒcҒcҒB–і—қҒAӮ ӮМ“ӘӮМҲ«Ӯў•¶ҸНӮНүҙӮЙӮНғRғsӮкӮЛӮҘӮ—
ӮвӮБӮП•Ғ’КӮЙӮўӮ«ӮЬӮөӮеӮӨӮ—
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ`ғzҒ[ғҖғyҒ[ғWӮрӮВӮБӮӯӮиҒ[ӮЬӮөӮеҒ[ҒфҒ`
ҒuүҪҒcҒcӮҫӮЖҒcҒcҒHҒv
Ғ\Ғ\ӮЬӮіӮ©ҒAӮ»ӮсӮИӮНӮёӮНҒ\Ғ\ҒB
ӮұҒAӮұӮМүҙӮӘғvғҚғoғCғ_Ғ[Ң_–сҸ‘ӮрӮИӮӯӮөӮҪӮБӮДӮўӮӨӮМӮ©ҒIҒH
Ӯ»ӮсӮИӮұӮЖӮӘӮ ӮБӮДӮҪӮЬӮйӮ©ҒBӮ»ӮкӮ¶ӮбӮ ғpғXӮӘӮнӮ©ӮзӮИӮӯӮДҗЬҠpӮВӮӯӮБӮҪғzҒ[ғҖғyҒ[ғWғfғUғCғ“ӮӘ–і‘КӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒB
үҙӮМҲкҺһҠФҺгӮМ“w—НӮНӮЗӮұӮЙҸБӮҰӮҪҒH
ӮўӮвӮўӮв—ҺӮҝ’…ӮӯӮсӮҫҒAүҙҒBӮЬӮёӮН‘fҗ”Ӯрҗ”ӮҰӮйӮұӮЖӮ©ӮзҺnӮЯӮйӮсӮҫҒBӮ»ӮөӮДҺҹ‘жӮЙғҢғxғӢӮрҸгӮ°ӮДӮўӮ«ҒA•Әҗ”ӮМ‘«ӮөҺZӮӘҸo—ҲӮйҸҠӮЬӮЕӮ«ӮҪӮзӮЁ‘OӮНӮаӮӨ—вҗГӮҫҒB
Ӯ»ӮӨҒAӮаӮӨҲк“xKOOLӮЙӮИӮБӮДҢЛ’IӮрӢҷӮйӮсӮҫҒB
ҒuCOOLҒIҒ@COOLҒIҒ@COOLҒIҒ@COOLҒIҒ@COOLҒIҒIҒv
ғKғVғbҒIғ{ғJғbҒIғ_ғҒӮҫӮБӮҪҒBғIғҢӮН’ъӮЯӮҪҒBғXғCҒ[ғcҒiҸОҒj
ӮвӮҹӮЭӮсӮИҒA–lӮНғPғ~Ғ[ҒBҚЎ“ъӮНғzҒ[ғҖғyҒ[ғWӮрҚмӮкӮЖӮўӮӨӮМӮЕӮвӮБӮДӮЭӮҪӮМӮіҒB
ӮЬӮҹӮвӮБӮВӮҜҠҙ•YӮӨ“K“–ӮИҚмӮиӮИӮсӮҫӮҜӮЗҒAӮЖӮиӮ ӮҰӮёҸo—ҲӮҪӮұӮЖӮНҸo—ҲӮҪҒB
ҸгӢLӮМ’КӮиүҙӮНғvғҚғoғCғ_Ғ[Ң_–сҸ‘ӮрҺҶӮМҠCӮ©ӮзғTғӢғxҒ[ғWӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪ–і”\ҺТӮИӮМӮЕҒAҺd•ыӮИӮӯҢ_–сӮөӮДӮўӮйҸҠӮЖӮН•КӮМҸҠӮЖғҢғ“ғ^ғӢғTҒ[ғoҒ[Ң_–сӮрҢӢӮФӮұӮЖӮЙҒB
ӮөӮ©ӮөӮіӮ·ӮӘӮЙӮвӮБӮВӮҜҺdҺ–ӮМ‘¬ӮіӮЙ’и•]ӮМӮ ӮйүҙҒBӮӨҒ[ӮсҒA‘Ҫ•ӘғjғAӮҫӮ©ғҒғҚӮҫӮ©ғlғҚӮҫӮ©–YӮкӮҪӮҜӮЗӮ ӮўӮВӮИӮзӮ«ӮБӮЖӮұӮӨҢҫӮӨҒB
ҒuғWғFғoғ“ғjӮӘ“сҺһҠФӮЕӮвӮБӮДӮӯӮкӮЬӮөӮҪҒv
ӮӨӮсҒAғ}ғWӮЕӮаӮӨӮҝӮеӮБӮЖӮ©Ӯ©ӮйӮЖҺvӮБӮҪӮсӮҫӮҜӮЗҒAғzғ“ғgӮЙғjҺһҠФӮЕҸo—ҲӮҝӮбӮБӮҪӮжҒB
ҢӢҚ\ҠИ’PӮЙҸo—ҲӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮЬӮҹғcҒ[ғӢҺgӮБӮҪӮ©Ӯз“–ӮҪӮи‘OӮИӮсӮҫӮҜӮЗҒB
ӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕҒAӮЖӮЙӮ©ӮӯӮұӮкӮЕғTҒ[ғNғӢӮЖӮөӮДӮМ‘МҚЩӮНҗ®ӮБӮҪҒIҒI
•”ҲхӮҪӮҝӮжҒIӮ»ӮөӮД—Ҳ–KҺТӮМ•ыҒXҒI‘¶•ӘӮЙҠҲ—pӮ·ӮйӮӘ—ЗӮўҒIҒI
Ӯ»ӮкӮ©ӮзӮұӮМғyҒ[ғWӮЙ’Z•ТҸ¬җаӮЖӮ©ҚЪӮ№ӮДӮўӮӯӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB
•”ҲхӮҪӮҝӮНҸ‘ӮўӮДҒAӮЁӢq—l•ыӮН“ЗӮсӮЕӮЁӮӯӮкҒт
Ӯ»ӮӨӮ»ӮӨҒA–ҹүжӮаӮ»ӮМӮӨӮҝҸгӮ°ӮйӮВӮаӮиӮҫӮ©ӮзӮжӮлӮөӮӯӮ—
ӮсӮ¶ӮбӮЁ”жӮкҒт
•ӣ•”’·ӮЕӮөӮҪҒB
|
|
|
|
| ғҒғ^ғӢғMғAғXҒ@Ғ`”јғPғcӮМғXғlҒ[ғNӮqӮQҒ` |
|
|
|
ҲшӮБӮ©Ӯ©ӮБӮҪӮИҒIҒ@ӮұӮұӮӘҗнҸкӮИӮзӮЁ‘OӮМҠзӮНҗHӮнӮкӮДӮўӮйҒIҒI
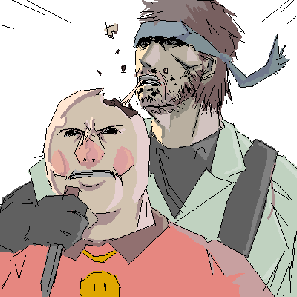
ғCғүғbӮЖӮ«ӮҪӮзҢfҺҰ”ВӮЙ•¶ӢеӮЕӮаҸ‘ӮўӮДӮўӮБӮДӮЛҒIҒI
|
|
|
|
| ҒuҮT'm here, from nature.ҒvҒ@Ғ@ҳAҚЪҺ®Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@’ҳҒ@Ҳк”Nҗ¶ҒF—I |
|
|
|
ҺRҗмҚKӮНӮұӮӨҢҫӮБӮҪҒB
ҒuҚKӮ№Ӯ¶ӮбӮИӮўӮЕӮ·ҒBҺ„ӮНҒAӮЗӮӨӮөӮжӮӨӮаӮИӮӯҒA•sҚKӮ№ӮИӮМӮЕӮ·ҒBӮнӮ©ӮБӮДӮӯӮҫӮіӮўҒBӮнӮ©ӮБӮДӮӯӮҫӮіӮўҒBӮЭӮИӮіӮсӮЙ–вӮўӮЬӮ·ҒB•KӮё“ҡӮҰӮДӮӯӮҫӮіӮўҒBҚKӮ№ӮБӮДӮИӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒHүҪҸҲӮЙӮ ӮйӮМӮЕӮ·Ӯ©ҒHӮўӮВӮӯӮйӮМӮЕӮ·Ӯ©ҒHӮЗӮсӮИғJғ^ғ`ӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮ·Ӯ©ҒHҺ„ӮЙӮЗӮМӮжӮӨӮИүeӢҝӮр—^ӮҰӮйӮМӮЕӮ·Ӯ©ҒHӢіӮҰӮДӮӯӮҫӮіӮўҒBӢіӮҰӮДӮӯӮҫӮіӮўҒB–lӮЙӮНӮнӮ©ӮзӮИӮўӮМӮЕӮ·ҒBӮЗӮӨӮөӮДӮаҒA’НӮЮӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўӮМӮЕӮ·ҒB•ғӮЙӮ»ӮӨҢҫӮБӮҪӮзҒAҒwҚKӮ№ӮНӢуӢCӮЭӮҪӮўӮИӮаӮМӮҫҒBӮНӮНӮНҒAҚKӮЙӮНӮЬӮҫҚKӮ№Ӯр—қүрӮ·ӮйӮМӮЙӮНҸ®‘ҒӮҫӮлӮӨҒxӮЖҢҫӮБӮДӮЬӮөӮҪҒB–lӮН’mӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮкӮНҢл–Ӯү»ӮөӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮрҒBҚKӮ№ӮНӮ·ӮЕӮЙӢЯӮӯӮЙӮ ӮйӮЖӮаҢҫӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮИӮзӮОҒAӮИӮзӮОҚЭӮйӮНӮёӮ¶ӮбӮ Ӯ ӮиӮЬӮ№ӮсӮ©ҒIҢ©Ӯ№ӮйӮұӮЖӮИӮсӮД—eҲХӮЕӮөӮеӮӨҒHӮИӮәҒHӢҒӮЯӮДӮўӮйӮМӮЙҢ©ӮҰӮИӮўӮБӮДҒAӮЗӮӨӮўӮӨӮұӮЖҒH‘¶ҚЭӮ·ӮйӮМӮЙҺАҠҙӮөӮИӮўӮБӮДҒAӮЗӮӨӮўӮӨӮұӮЖҒH–өҸӮҒBӮұӮкӮр–өҸӮӮЖҢДӮФӮМӮрҒA–lӮН’mӮБӮДӮўӮйҒBӮ ӮҹҒA–lӮӘҺҖӮКӮЬӮЕӮЙҒAҢ©ӮВӮҜӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒHҒv
Ғ@ҺRҗмҚKӮНӮұӮӨҢҫӮБӮҪҒB
ҒuҺ„ӮЛҒAҚЎ“ъӮЛҒAӮЖӮБӮДӮаӮІ”СӮӘҚӢүШӮҫӮБӮҪӮМҒIҒIӮЁ“чӮБӮДӮЁӮўӮөӮўӮЛҒIҒIғҢғoҒ[ӮНҢҷӮўӮҫӮҜӮЗӮЛҒAӮ»ӮкҲИҠOӮМӮЛҒAӮЁ“чӮН‘S•”ҚDӮ«ҒIҒIҠрӮөӮўӮЖӮ«ӮБӮДӮЛҒAӮвӮБӮПҗlӮЙҢҫӮўӮҪӮўӮжӮЛҒBӮҫӮ©ӮзӮЛҒAҺ„ӮЛҒAӮЁ•ғӮіӮсӮЙӮЛҒA‘f’јӮЙӮұӮсӮИӮЁӮўӮөӮўӮаӮМӮЖҸoүпӮҰӮйӮИӮсӮДҒAҺ„ҚKӮ№ҒIҒIӮБӮДҢҫӮБӮҪӮМӮЛҒAҚЕӢЯӮЁ•ғӮіӮсҢіӢCӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзҒA—гӮЬӮөӮМҲУ–ЎӮаҚһӮЯӮДӮЛҒBӮ»ӮөӮҪӮзӮЛҒAӮҝӮеӮБӮЖӮЁӮ©ӮөӮИҸo—ҲҺ–ӮҫӮБӮҪӮсӮҫӮҜӮЗӮЛҒAӮЁ•ғӮіӮсӮЛҒAҺ„ӮЙ”чҸОӮЭ•ФӮөӮҪӮзӮЛҒAӢ}ӮЙӢғӮ«ҸoӮөӮҝӮбӮБӮҪӮМҒIҒIӮ ӮкҒAӮЗӮӨӮөӮҪӮМӮ©ӮИҒHӮБӮДӮСӮБӮӯӮиӮөӮҝӮбӮБӮДӮЛҒAҺ„ӮӘ•ПӮИӮұӮЖҢҫӮБӮҝӮбӮБӮҪӮ©ӮзҒHӮБӮД•·ӮўӮҪӮзҒAӮЁ•ғӮіӮсӮҪӮз•@җ…ӮрҗӮӮзӮөӮИӮӘӮзҒiӮ·Ӯ®ӮЙҗ@ӮўӮДӮ Ӯ°ӮҪӮҜӮЗӮЛҒjҒAҒwӮ»ӮӨӮ©ҒAӮ»ӮӨӮ©ҒBҚKӮНҚKӮ№Ӯ©ӮҹҒI–ј‘OӮМ’КӮиҒAҚKӮ№Ӯ©ҒIҒxӮБӮДӮЛҒAӮ·ӮБӮІӮӯ‘еӮ«ӮИҗәӮЕҢҫӮБӮҪӮМҒBҺ„ҒAӮ·ӮІӮӯҚQӮДӮҪӮнҒBӮҫӮБӮДӮЁ—ЧӮМӢҙ–{ӮЁӮ¶ӮіӮсӮрӢNӮұӮөӮҝӮбӮӨӮЖҺvӮБӮҪӮсӮҫӮаӮМҒBӮЬӮҹҒAӮ»ӮМӮЖӮ«ӮН–йӮЕӮаӮИӮӯҒAӮЁ’ӢӮМҺһҠФӮҫӮБӮҪӮсӮҫӮҜӮЗӮЛҒBӮЖӮЙӮ©ӮӯӮЁ•ғӮіӮсӮНӢғӮўӮДӮўӮҪӮҜӮЗҒAҸОӮБӮДӮҪҒIҒIӮҫӮ©ӮзӮ·ӮБӮІӮӯҠрӮөӮ©ӮБӮҪҒIҒIӮЁ•ғӮіӮсӮаҚKӮ№Ӯ»ӮӨӮҫӮБӮҪҒIҒIҚKӮ№ӮБӮДҒAӮұӮсӮИӮаӮМӮИӮМӮ©ӮИҒHҒ\Ғ\Ғ\ӮӨӮсҒIҒIӮ«ӮБӮЖӮ»ӮӨӮИӮс
ӮҫӮЖҺvӮӨҒIҒIҒv
I`m here. From nature.
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғһ
ӮұӮкӮНҒAҗ_—lӮМҲ«ӢYӮИӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒH
Ғ@ӮўӮвҒAӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮНӮИӮўҒBӮ»ӮӨҢҫӮБӮДҒAҢ»ҺАӮ©Ӯз–ЪӮр”wӮҜӮДӮНӮИӮзӮИӮўҒB
Ғ@ӮЖӮЙӮ©ӮӯҒAҺ–ӮНӢNӮ«ӮҪҒB’јҺӢӮ·ӮйӮөӮ©ӮИӮўҒB
Ғ@’NӮӘӮБӮДҒH
Ғ@Ӯ»ӮсӮИӮМ“–ӮҪӮи‘OӮҫҒBӮ»ӮкӮрҢҲӮЯӮҪҒBүдҒXҗlҠФӮӘҒAӮҫҒB
Ғ@җlҠФӮЙӮжӮйҚsҲЧҒAӮ·ӮИӮнӮҝӮ“Ӯ…ӮҳӮЙӮжӮБӮДҒAҸ—ӮМҗg‘МӮЙҗ¶–ҪӮӘҸhӮиҒAҗlҠФӮМ–{”\ӮЙӮжӮБӮДҒAҢ`ӮрӮИӮөҒAҗlҠФӮӘҢҡӮДӮҪ•aү@ӮЕҒAҗlҠФӮМ’mҢbӮЖ“w—НӮЙӮжӮБӮДҒAҗlӮӘҗ¶ӮЬӮкӮйҒBҚЎ“ъӮаӮ»ӮкӮН•ПӮнӮзӮИӮўҒB–ҫ“ъӮаҒAӮ»ӮөӮДҚр“ъӮаҒB
Ғ@ӮPӮV”N‘OӮаӮ»ӮкӮН•ПӮнӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBҗlӮӘҒAҗ¶ӮЬӮкӮҪҒBӮЬӮҪҲбӮӨҸкҸҠӮЕҒAҗlӮӘҒAҗ¶ӮЬӮкӮҪҒBҗ¶ӮЬӮкӮкӮОҒAҗlҠФӮМҺиӮЙӮжӮБӮДҺxӮҰӮзӮкҒAҢҢӮрӮУӮ«ҺжӮзӮкҒAӮЦӮ»ӮрҗШӮзӮкҒA–ј‘OӮрӮВӮҜӮзӮкҒAҗlҠФӮӘҚмӮБӮҪҺһҠФӮЙӮжӮБӮДҒAҗ¶”NҢҺ“ъӮӘӢLҳ^ӮіӮкӮйҒB
Ғ@ӮPӮV”N‘OӮМӮ»ӮМӮЖӮ«ҒAӢф‘RӮӘӢNӮ«ӮҪҒBӮ»ӮкӮН“ҜҺһҚҸӮЙҒA•КҒXӮМҸкҸҠӮЕӮ ӮБӮҪҒB
ӮVҢҺӮQӮO“ъҒiӢаҒjҒ@pm3:33Ғ@
Ғ@ҺRҗмҒ@ҚKҒiӮвӮЬӮ©ӮнҒ@ӮұӮӨҒjҒ@‘МҸd:ӮRӮPӮPӮTӮҮҒ@җ«•К:’j
Ғ@ҺRҗмҒ@ҚKҒiӮвӮЬӮ©ӮнҒ@ӮіӮҝҒjҒ@‘МҸd:ӮQӮWӮXӮXӮҮҒ@җ«•К:Ҹ—
Ғ@ӮQӮВӮМ–ҪӮӘ’aҗ¶ӮөӮҪҒB
Ғ@ӮаӮӨҲк“xҢҫӮӨӮӘҒA‘SӮӯӮМӢф‘RӮЕӮ ӮйҒB“сҗlӮМүЖҢnӮН‘SӮӯҢqӮӘӮБӮДӮЁӮзӮёҒAӮЬӮҫҲкүсӮаҸoүпӮБӮҪӮұӮЖӮаӮИӮўҒBӮИӮМӮЕӮаӮҝӮлӮсҒAӮұӮМҺ–ҺАӮр’NӮа’mӮзӮИӮўҒB
Ғ@үЖ’лҠВӢ«Ӯа‘SӮӯҲбӮӨҒB‘ОҸЖ“IӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮНҒAҢгӮЙӮнӮ©ӮйӮұӮЖӮЕӮ ӮйӮӘҒAҲкҢҫӮЕӮўӮҰӮОҒA’jӮМӮЩӮӨӮМғRғEӮНҒAӮўӮнӮдӮйӮЁӢаҺқӮҝӮМҗeӮМҢіӮЕҒAҸ—ӮМӮЩӮӨӮМғTғ`ӮНҒA•n–RӮМҗeӮМҢіӮЕҗ¶ӮЬӮкӮҪҒB“с‘gӮЖӮа•кҺqӢӨӮЙҸҮ’ІӮЕҒA“БӮЙҸбҠQӮв•aӢCӮЙ”YӮЬӮіӮкӮйӮұӮЖӮИӮӯҲзӮВӮЕӮөӮеӮӨӮЖҒAҠЕҢмҺtӮіӮсӮЙҢҫӮнӮкӮҪҒB
Ғ@ӮЬӮҹҒA“сҗlӮЖӮаҸҮ’ІӮИҗlҗ¶ӮЖӮўӮӯӮнӮҜӮЙӮНӮўӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫӮӘҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғһ
Ғ@ҺRҗмҒ@ҚKҒiғRғEҒjӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҸuҠФҒAҲгҺТ’BӮНҠҪҠмӮМҗәӮрӮ Ӯ°ҒAӮ»ӮөӮД”ҸҺиӮөӮҪҒBӮ»ӮМҠмӮСӮМү№ӮӘҒAғhғAӮМҠOӮЕҚЎӮ©ҚЎӮ©ӮЖ‘ТӮҝ‘ұӮҜӮДӮўӮйҗe‘°ӮPӮTӮO–јӮвӮ»ӮМ‘јҒi–мҺҹ”nҒjӮЙ“НӮӯҒBӢ·ӢкӮөӮӯӮөӮДӮўӮҪҗlҒXӮаҲкҗДӮЙҠҪҠмӮөӮҪҒBҺ–ҸоӮр’mӮзӮИӮўҗe‘°ҲИҠOӮМҺТӮаӮЖӮиӮ ӮҰӮёӢ©ӮсӮЕӮўӮҪҒBҲЩ—lӮИҢхҢiӮИӮМӮҫӮ©ӮзҒA‘јҗlӮӘӢ»–ЎӮрҺқӮҪӮИӮўӮЩӮӨӮӘ–і—қӮИӮМӮҫҒB
Ғ@ҠЕҢмҺtӮӘғRғEӮр‘еҺ–ӮЙ•шӮҰӮДҸoӮДӮ«ӮҪӮЖӮ«ҒAҠҪҠмӮНҚЕҚӮ’ӘӮЙ’BӮөӮҪҒBҢіӢCӮИ’jӮМҺqӮЕӮ·ӮжҒIҒIӮЖ‘еҗәӮЕҠЕҢмҺtӮНӢ©ӮсӮҫҒB
ҒuӮўӮвӮҹҒAӮІ–іҺ–ӮЙӮІҸoҺYӮЕӮ«ӮДӮИӮЙӮжӮиӮЕӮ·ӮИӮҹҺР’·ҒIҒIҒv
Ғu’jӮМҺqӮҫӮ»ӮӨӮЕӮ·ӮжҒIҒIӮЁӮЯӮЕӮЖӮӨӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒIҒIӮұӮкӮЕҲА‘ЧӮЕӮ·ӮИҒIҒIҒv
Ғu’jӮМҺqӮ©ҒHҒIӮ»ӮкӮИӮзӮИӮЁ‘fҗ°ӮзӮөӮўӮұӮЖӮҫҒIҒIҒv
ҒuҺР’·ӮЙҺ—ӮД’j‘OӮИӮЁ‘·ӮіӮсӮҫҒIҒIӮўӮвҒ[Ҡу–]ӮЙ–һӮҝҲмӮкӮҪ–ЪӮрӮөӮДӮЁӮйҒIҒIҒv
ҒuӮжӮӯӮнӮ©ӮзӮИӮҜӮЗӮЁӮЯӮЕӮЖӮӨӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒIҒIҒv
ҒuӮаӮБӮЖӮЁҠзӮрҢ©Ӯ№ӮДӮӯӮҫӮіӮўӮжҒIҒIҒ\Ғ\Ӯ Ғ[ҢіӢCӮ»ӮӨӮЕӮИӮЙӮжӮиҒv
ҒuӮИӮсӮҫӮИӮсӮҫҒHӮИӮЙӮ©Ӯ ӮБӮҪӮМӮ©ҒHҒv
ҒuӮаӮӨӮұӮМҺqӮНӮнӮӘҺРӮМҸ«—ҲҗЭҢvӮрӮЁ• ӮМ’ҶӮЕҢҲӮЯӮДӮўӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮЬӮ№ӮсӮИҒv
ҒuӮЁӮўӮЁӮўҒAӮ»ӮӨӮөӮҪӮзҺР’·ӮМ”CҠъӮӘ’ZӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮжҒv
ҒuӮўӮвҒAӮаӮӨғҸғVӮН‘§ҺqӮЙ”ј•ӘҢpӮўӮЕӮўӮйӮжӮӨӮИӮаӮсӮҫӮ©ӮзӮИҒBӮЖӮБӮЖӮЖҺ«ӮЯӮДӮұӮМүВҲӨӮў‘·ӮЖ—VӮФӮұӮЖӮЙӮ·ӮйӮжҒv
Ғ@ҺР’·ӮӘӮ»ӮӨҢҫӮӨӮЖҒAғXҒ[ғcҺpӮМӮЁӮ¶ӮіӮсӮҪӮҝӮӘӮЗӮБӮЖҸОӮўҸoӮөӮҪҒBӮ»ӮсӮИ‘ӣӮӘӮөӮў’ҶҒAҗжӮЩӮЗӮМҠЕҢмҺtӮН•KҺҖӮЕҒuӮЁ•ғ—lӮНӮЗӮҝӮзӮЙӮўӮзӮБӮөӮбӮўӮЬӮ·Ӯ©ҒIҒIҒvӮЖӢ©ӮсӮЕӮўӮҪҒBӮөӮОӮзӮӯӮөӮДҸӯӮөҺбӮӯҗҙҢүҠҙӮМӮ Ӯй•ғҗeӮӘҠрӮөӮ»ӮӨӮЙҒAӮ»ӮөӮД—вҗГӮр‘•ӮўӮВӮВӮаӢ»•ұӮрүBӮөӮ«ӮкӮИӮўӮЖӮўӮБӮҪ—lҺqӮЕҺиӮрӢ“Ӯ°ӮДӮўӮйӮМӮрҢ©ӮВӮҜҸoӮөҒA”ЮӮр•КҺәӮЦӮЖҲД“аӮөӮҪҒBғRғEӮНӮжӮӨӮвӮӯ—јҗeӮЖ‘О–КӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒB
Ғ@•кҗeӮН”жӮкӮЖҲАӮзӮ¬ӮЖҚKӮ№ӮМ–ЪӮрӮөӮДғRғEӮрҢ©ӮДӮўӮҪҒBҗжӮЩӮЗӮМ•ғҗeӮН—ЬӮӘҺЧ–ӮӮөӮД‘§ҺqӮМҗQҠзӮрҢ©ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮЙӮөӮДҒAҚKӮ№ӮЙ•пӮЬӮкӮИӮӘӮзғRғEӮН–іҺ–ӮЙ’aҗ¶ӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB
Ғ@
ғRғEӮМ‘c•ғӮН‘еҺи’n•ыӢвҚsӮМҺР’·ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМ‘§ҺqҒAӮВӮЬӮиғRғEӮМ•ғҗeӮНӮўӮёӮкӮ»ӮМҗИӮЙҸAӮӯ—\’иӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМӮҪӮЯ”ЮӮН‘c•ғӮМүпҺРӮЕҺdҺ–ӮрӮөӮДӮўӮйҒBҢ»ҸуӮаҒA–ў—ҲӮаҲА’иӮөӮҪ’jӮҫҒB”ЮӮр•ғҗeӮЖҢДӮЧӮйғRғEӮаӮЬӮҪҒAҲА’иӮөӮҪ–ў—ҲӮӘӮ ӮйӮМӮҫҒBҢoҚП–КӮЕ•s–һӮӘӮИӮўӮМӮҫӮ©ӮзҒAҗlҗ¶ӮМ”ј•ӘҲИҸгӮНҗ¬ҢчӮЖҢҫӮБӮДӮўӮўҒBҚKӮўӮЙӮөӮДҗe‘°ӮЙӮЁӢаӮЙ–Ъ•qӮўҗlӮаӮЁӮзӮёҒAҠFғRғEӮМҗ¬’·ӮрҗSӮ©ӮзҠъ‘ТӮөӮДҢ©ҺзӮБӮҪҒBӮўӮёӮкӮұӮМҺqӮН•ғҗeӮМӮжӮӨӮЙ—§”hӮЙӮИӮБӮДҒAӮұӮМҚ‘ӮМ–ў—ҲӮр‘nӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйӮҫӮлӮӨӮжҒAӮЖүҪӮ©ӮМҸWӮЬӮиӮМӮҪӮСӮЙӮ»ӮӨҢҫӮнӮкӮДӮўӮҪҒB
Ғ@ӮИӮЙӮжӮиғRғEӮрҲк”Ф’gӮ©ӮӯҢ©ҺзӮБӮДӮўӮҪӮМӮН•кҗeӮЕӮ ӮБӮҪҒB”ЮҸ—ӮНӢ–ҚҘӮМҢ`ӮЕҢӢҚҘӮөӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮЮӮөӮл‘c•ғӮЙҸРүоӮіӮкӮйӮжӮӨӮИҗlӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮИӮәӮИӮз”ЮҸ—ӮНғRғEӮМ‘c•ғӮМүпҺРӮЕҗҙ‘|ӮМҺdҺ–ҒiғAғӢғoғCғgҒjӮрӮөӮДӮўӮҪӮМӮҫҒB“ҜӮ¶җEҸкӮЕӮНӮ ӮБӮҪӮӘҒA’nҲКӮӘҲбӮўӮ·Ӯ¬ӮҪҒB”ЮҸ—ӮаҺ©•ӘӮНӮұӮсӮИ—§”hӮИӮЖӮұӮлӮЕҺdҺ–ӮрӮөӮДӮўӮйҗlӮЖҢӢҚҘӮЕӮ«ӮйӮнӮҜӮӘӮИӮўӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪҒBӮЮӮөӮлҺ„ӮНҢӢҚҘӮЕӮ«ӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮаӮнӮ©ӮзӮИӮўҒBӮ»ӮкӮжӮиҚЎӮНӮЁӢаӮӘ•K—vӮҫҒBӮҪӮӯӮіӮс“ӯӮўӮДҒA—јҗeӮӘҲвӮөӮҪҺШӢаӮр•ФҚПӮөӮИӮҜӮкӮОҒAҺ„ӮМ–ў—ҲӮН–ҫӮйӮӯӮИӮзӮИӮўҒBӮЖҒAӢкӮөӮўӮЖӮ«ӮН•KӮёҺ©•ӘӮЙҢҫӮў•·Ӯ©Ӯ№ӮДӮ«ӮҪҒBӮҫӮ©Ӯз—цҲӨӮИӮсӮДӮөӮДӮўӮйүЙӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮЁӢаӮӘ•K—vӮИӮзҒAҗFӢCӮЕӮаӮҫӮөӮДӮұӮұӮМҗEҸкӮЖҗlӮЖҢӢҚҘӮөӮҝӮбӮҰӮОҒHӮ»ӮсӮИҚlӮҰӮН”ЮҸ—ӮЙ”чҗoӮаүиҗ¶ӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒBҗУ”CӮНҺ©•ӘӮЕӮЖӮиӮҪӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒB
ғRғEӮМ•ғҗeӮНӮ»ӮсӮИ”ЮҸ—ӮМҗSӢ«Ӯр‘SӮӯ’mӮзӮИӮўӮЕҒAӮҪӮҫӮРӮҪӮ·Ӯз”MҗSӮЙ‘|ҸңӮрӮ·ӮйҺpӮЙҚӣӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB”ЮӮНҒuӮўӮВӮаӮІӢкҳJ—lӮЕӮ·ҒvӮЖҗәӮрӮ©ӮҜӮДӮЭӮҪҒBҗ^ӮБҗФӮИҠзӮЕҒB”ЮҸ—ӮНҺиӮрӢxӮЯӮйӮұӮЖӮИӮӯ–ЩӮБӮДғjғRғҠӮЖ”чҸОӮсӮҫҒBӮ»ӮМҸОҠзӮЙӮЬӮ·ӮЬӮ·”ЮӮНҚӣӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB”ЮӮМ•”ҸҗӮМӢЯӮӯӮМғgғCғҢӮӘҗҙ‘|’ҶӮЙӮИӮйӮ»ӮМҺһӮрҢ©ҢvӮзӮБӮДҒAүҪүсӮаүҪүсӮа”ЮҸ—ӮМҢіӮЦҚsӮ«ҒAҒuӮўӮВӮаӮІӢкҳJ—lӮЕӮ·ҒvӮЖҢҫӮўӮЙҚsӮБӮҪҒBғRғEӮМ•кҗeӮНҒu•ПӮИҗlӮҫӮИӮҹҒBҲҘҺAӮҫӮҜ”MҗSӮЙӮ·ӮйӮИӮсӮДҒvӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©Ӯө”ЮҸ—ӮНҲ«ӮўӢCӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB—BҲкҗәӮрӮ©ӮҜӮДӮӯӮкӮйҗEҸкӮМҗlӮИӮМӮЕҒAҠрӮөӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒB
Ҳк•ығRғEӮМ•ғҗeӮНҒAҚЕҸүӮНҲҘҺAӮ·ӮйӮҫӮҜӮЕҚKӮ№ӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮҫӮсӮҫӮсӢкӮөӮӯӮаӮИӮБӮДӮ«ӮҪҒBӮ«ӮБӮЖӮұӮМ—цӮНҠҗӮнӮИӮўӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҢӢӢЗҲҘҺAӮҫӮҜӮөӮДҸIӮнӮйӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮвӮНӮиүҙӮН•ғӮіӮсӮЙӢ–ҚҘӮрҸРүоӮіӮкӮДҒAӢ@ҠB“IӮЙҢӢҚҘҒuӮіӮ№ӮзӮкӮйҒvӮМӮ©ӮаҒBҸ«—ҲӮМӮҪӮЯӮЙӮ»ӮкӮН•K—vӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮҜӮЗҒA‘гӮнӮиӮЙүҙӮМ–ІӮӘҒuүуӮіӮкӮйҒvӮМӮ©ӮаӮИӮҹҒBӮЖҒA”ЮӮНӮ»ӮсӮИ”YӮЭӮр•шӮҰӮҫӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДӮВӮўӮЙүд–қӮЕӮ«Ӯё•ғҗeҒ\Ғ\Ғ\ғRғEӮМ‘c•ғҒAҺР’·Ғ\Ғ\Ғ\ӮЙ‘Ҡ’kӮөӮҪҒB
Ғu•ғӮіӮсҒAӮ»ӮлӮ»ӮлҢӢҚҘӮрҚlӮҰӮДӮўӮйӮсӮҫӮҜӮЗҒEҒEҒEҒv
ҒuӮЁӮӨҒIӮ»ӮӨӮўӮҰӮОӮЁ‘OӮаӮаӮӨӮ»ӮсӮИҚОӮ©ҒBӮ»ӮлӮ»ӮлғҸғVӮМҲш‘ЮӮаҚlӮҰӮИӮўӮЖӮИҒv
ҒuӮўӮҰҒAҺР’·ӮНӮЬӮҫӮЬӮҫӮұӮМүпҺРӮрҲшӮБ’ЈӮБӮДӮўӮҪӮҫӮ©ӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒv
ҒuҚЎӮН•ғҗeӮЖӮөӮДҗU•‘ӮБӮДӮжӮўҒv
ҒuӮӨӮсҒBӮ»ӮкӮЕҒAӮвӮНӮиүҙӮН•ғӮіӮсӮЖ“ҜӮ¶ҺһӮМӮжӮӨӮЙҒAӢ–ҚҘӮӘӮўӮйӮМҒHҒv
ҒuҒEҒEҒEҒEҒEҒEӮҰҒHҒv
ҒuҒEҒEҒEҒEҒEҒEӮҰҒHҒv
ҒuӮ ӮҹҒAӮўӮвҒAӢ–ҚҘҒAӮЖӮИҒHҒv
ҒuӮӨӮсҒB—§ҸкҸг‘SӮӯҚlӮҰӮДӮўӮИӮўӮнӮҜӮ¶ӮбӮИӮўӮЕӮөӮеӮӨҒHҒv
ҒuҒEҒEҒE‘SӮӯҚlӮҰӮДӮЁӮзӮсҒv
ҒuҒEҒEҒEӮНҒHҒv
ҒuӮҰӮҘҒHӮҫӮБӮДҒAӮЁ‘OӮНӮ»ӮкӮЕӮўӮўӮМӮ©ӮўҒHҒv
ҒuӮҰҒHҒv
ҒuӮҫӮБӮДҒAғҸғVӮНҢҷӮЕӮҪӮЬӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮјҒv
ҒuӮҰӮҘҒIҒIӮ¶ӮбӮ үҙӮН’NӮЕӮаӮўӮўӮМҒHҒIҒv
ҒuӮУӮЮҒEҒEҒE’NӮЕӮаҒAӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЙӮНӮўӮ©ӮсӮӘҒEҒEҒEҒBӮЬӮҹӮЁ‘OӮӘӮЬӮё‘IӮОӮИӮҜӮкӮОӮМҒBҳbӮНҗiӮЬӮКҒv
ҒuҒEҒEҒEӮНӮҹҒv
ҒuӮ»ӮкӮЙӢ–ҚҘӮИӮсӮД–К“|ӮҫӮөӮМҒBӮўӮҝӮўӮҝӮұӮБӮҝӮӘ‘IӮФӮұӮЖӮаӮИӮ©ӮлӮӨӮЙҒBӮЁ‘OӮӘ‘IӮЧҒBӮ»ӮөӮД‘ҠҺиӮЙӢ–ӮөӮрӮаӮзӮҰӮҪӮзүЖӮЙҳAӮкӮДӮұӮўҒBӮ»ӮөӮДғҸғVӮӘ”»’fӮ·ӮйҒBӮИӮҹӮЙҒBғҸғVӮМ–ЪӮЙӢ¶ӮўӮНӮИӮўҒBӮ»ӮсӮИҠҙӮ¶ӮЕӮўӮўӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮМҒHҒv
ҒuҒEҒEҒEӮНӮҹҒv
ҒuӮ»ӮӨӮ©Ӯ»ӮӨӮ©ҒBӮВӮўӮЙҢӢҚҘӮ©ӮҹҒEҒEҒEӮНӮжӮЈ‘·ӮМҺpӮӘҢ©ӮҪӮўӮМӮЈҒEҒEҒEҒv
Ғ@ӮұӮӨӮөӮДӮўӮЖӮаҠИ’PӮЙ”ЮӮМ”YӮЭӮНҸБӮҰӮҪҒBӮ ӮБӮіӮиӮЖҒBӮ ӮЖӮН”ЮҸ—Ӯ©ӮзӢ–ӮөӮрӮаӮзӮӨӮҫӮҜӮҫӮБӮҪҒB”ЮӮНҚҗ”’ӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢҲҲУӮр“`ӮҰӮйӮМӮЙҲкҸTҠФӮаӮ©Ӯ©ӮБӮҪҒBӮжӮӨӮвӮӯҢҫӮҰӮҪҒBӮаӮӨӮЭӮйӮЭӮйҠзӮӘҗ^ӮБҗФӮЙӮИӮБӮДӮ«ӮҪҒBҠҫӮаҸoӮДӮ«ӮҪҒBҢҫӮнӮкӮҪ”ЮҸ—ӮН”YӮсӮЕӮўӮҪҒBҚҗ”’ӮіӮкӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНӮИӮсӮЖӮИӮӯҠҙӮ¶ӮДӮўӮҪҒBӮҫӮБӮДҲкҸTҠФ‘OӮ©ӮзӢ““®•sҗRӮЕҠзӮӘҸҹҺиӮЙҗ^ӮБҗФӮЙӮИӮБӮДҒAӮИӮЙӮаҢҫӮнӮёӮЙҸoӮДӮўӮӯӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮсӮҫӮаӮМҒBӮаӮөҢҫӮнӮкӮҪӮзӮЗӮӨӮөӮжӮӨҒB•Ғ’К’fӮйӮнӮжӮЛҒBҺ„ӮЙӮНӮаӮБӮЖ‘еҺ–ӮИӮұӮЖӮрӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮаӮМҒBӮаӮө•tӮ«ҚҮӮБӮҪӮЖӮөӮДӮаҒAӮ«ӮБӮЖ”ЮӮЙ–АҳfӮрӮ©ӮҜӮйӮнҒBӮ»ӮӨӮжҒB•ӮӮ©ӮкӮДӮўӮйҸкҚҮӮ¶ӮбӮИӮўӮнҒBҒEҒEҒEӮЕӮаӮўӮ«ӮИӮиҒuҢӢҚҘӮөӮДӮӯӮҫӮіӮўҒvӮЖӮӯӮйӮЖӮНҒEҒEҒEҒB•Ғ’К•tӮ«ҚҮӮБӮДӮӯӮҫӮіӮўӮЖӮ©ҒAҚDӮ«ӮЕӮ·ӮЖӮ©ӮӘ•Ғ’КӮ¶ӮбӮИӮўӮМҒHӮұӮкӮНҠИ’PӮЙ—¬ӮөӮҝӮбҲ«ӮўӮнҒBӮЕӮа’fӮзӮИӮ«ӮбҒEҒEҒEӮЗӮӨӮөӮжӮӨҒH
Ғ@”ЮҸ—ӮӘҠИ’PӮЙ’fӮкӮИӮўӮМӮЙӮН—қ—RӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮНҒAҚҗ”’ӮөӮҪ’jҗ«ӮӘҒu•ПӮнӮзӮИӮўҒvӮұӮЖӮҫӮБӮҪҒB‘Ҡ•ПӮнӮзӮёҗ^ӮБҗФӮИҠзӮЕҺ©•ӘӮЙҳbӮөӮ©ӮҜӮДӮўӮйӮМӮҫҒBӮИӮәӮҫӮ©ҒA”ЮҸ—ӮНӮ»ӮсӮИӮЖӮұӮлӮЙҺдӮ©ӮкӮҪҒBӮ»ӮөӮД’NӮ©ӮЙҒuҠГӮҰӮҪӮўҒvӮЖӮўӮӨҠҙҸоӮӘӮіӮзӮЙ”»’fӮр“ЭӮзӮ№ӮҪҒBҚЎӮЬӮЕҗl•АӮЭҲИҸгӮЙ‘е•ПӮИҺvӮўӮрӮөӮДӮ«ӮҪҒBӮ»ӮөӮДүд–қӮөӮДӮ«ӮҪӮМӮҫҒBҗlҠФӮЕӮа•ЗӮЕӮа–ШӮЕӮаӮўӮўӮ©ӮзҒAүҪӮ©ӮЙҠсӮиӮ©Ӯ©ӮиӮҪӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮсӮИҠГӮҰӮрҺ©•ӘӮМҢҫ—tӮЕҺ©ҸdӮөӮДӮ«ӮҪҒB‘јҗlӮМҢҫ—tҒiҺеӮЙҲЈӮкӮЭҒjӮЙӮаҺЁӮрҢXӮҜӮёҒAӮЖӮЙӮ©ӮӯҺdҺ–ӮрӮөӮЬӮӯӮБӮДӮ«ӮҪҒBӮ»ӮөӮДҚЎӮЬӮҪҢ»ӮнӮкӮҪҒuҺ„ӮМ“GҒvӮөӮ©ӮөӮ»ӮМ“GӮрҒAҺ„ӮНҢҷӮўӮЙӮИӮкӮИӮўҒB
ҒuҺ„ӮЙӮНӮвӮйӮұӮЖӮӘӮ ӮйӮсӮЕӮ·ҒBӮ»ӮкӮрҸIӮҰӮҪӮзҒAҲкҸҸӮЙӮИӮиӮЬӮ№ӮсӮ©ҒHҒv
Ғ@”ЮҸ—ӮНӮ»ӮӨҢҫӮБӮҪҒBӢCӮГӮўӮҪӮзӮ»ӮӨҢҫӮБӮДӮўӮҪҒBҢҫӮнӮкӮҪ”ЮӮНҒuӮвӮйӮұӮЖҒAӮЖӮНҒHҒvӮЖҗqӮЛӮҪҒB”ЮҸ—ӮНҗgӮМҸгӮМҳbӮр‘S•”ӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҚЕҢгӮЙҒuӮҫӮ©ӮзҒAҺ„ӮИӮсӮ©ӮжӮиӮа—§”hӮИҗlӮӘӮўӮйӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒEҒEҒEҒvӮЖҸБӮҰӮ»ӮӨӮИҗәӮЕҢҫӮБӮҪҒB”ЮӮНӮөӮОӮзӮӯҚlӮҰӮҪӮ ӮЖҒAӮЖӮиӮ ӮҰӮёүЖӮМүЖ‘°ӮЖүпӮБӮДӮӯӮкӮЖҚ§ҠиӮөӮҪҒB”ЮӮН•ғҗeӮрҗа“ҫӮөӮДӮЁӢаӮрҚH–КӮөӮДӮаӮзӮЁӮӨӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪҒBҗі’јҗiӮЬӮИӮўҚlӮҰӮЕӮНӮ ӮБӮҪӮӘҒA—~–]ӮӘ”ЮӮр—}ӮҰӮ«ӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB”ЮҸ—ӮН”ЮӮМҗЁӮўӮЖҗ^ӮБҗФӮИҠзӮЙӮЁӮіӮкӮДҸaҒXҸі‘шӮөӮҪҒBӮ»ӮӨҒAүпӮӨӮҫӮҜӮИӮзӮИӮсӮЖӮ©ӮИӮйҒEҒEҒEҒB
Ғ@ӮЖӮұӮлӮӘӮИӮсӮЖӮ©ӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB”ЮҸ—ӮӘ”ЮӮМ–ј‘OӮр•·ӮўӮҪҺһӮЙӮаӮөӮвҒEҒEҒEӮЖӢ^ӮўҒAҺҹӮЙ•ғҗeӮМ–ј‘OӮр•·ӮўӮҪҸuҠФҒAӢCҗвӮөӮ»ӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒBӮЬӮіӮ©ӮұӮМүпҺРӮМҺР’·ӮМ‘§Һq—lӮҫӮБӮҪӮЖӮНҒEҒEҒEҺ„ӮНӮИӮсӮДҗуӮНӮ©ӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBҺ„ӮИӮсӮ©ӮӘӮұӮМҗlӮЖҲкҸҸӮЙӮИӮйӮМҒHӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮӘҒAӮ ӮиӮҰӮйӮМҒHӮўӮвҒA‘ҠҺиӮӘӮ»ӮкӮр–]ӮсӮЕӮўӮйҒEҒEҒEҒBӮ ӮкҒHӮұӮӨӮўӮӨҗlӮЙӮН•Ғ’КӢ–ҚҘӮЖӮ©ӮӘӮўӮйӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮМҒH”ЮҸ—ӮН”ЮӮЖ“ҜӮ¶ӮұӮЖӮрҚlӮҰӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮкӮЙҚЎҚXӮМҳbӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮИӮәӮИӮзӮ»ӮМҳbӮр•·ӮўӮҪӮМӮНҒA”ЮӮЖҲкҸҸӮЙ”ЮӮМҺАүЖӮЦҚsӮӯӮЬӮіӮЙӮ»ӮМҺһӮЕӮ ӮиҒA”YӮсӮЕӮўӮҪӮзӮаӮӨ’…ӮўӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBҲшӮ«•ФӮ·ӮЖғNғrӮЙӮИӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB”ЮҸ—ӮНӮ ӮзӮКӢ°•|Ӯр•шӮҰӮДӮўӮҪҒBӮЮӮөӮл’fӮБӮДӮағNғrӮЙҒEҒEҒEҒH
Ғ@Ҳк•ы”ЮӮМ•ғҗeӮН”ЮҸ—ӮЙӢ^ӮўӮМ”OӮр•шӮўӮДӮўӮҪҒB‘§ҺqӮ©ӮзӮМ”ЮҸ—ӮМҳbӮр•·ӮўӮҪӮЖӮұӮлҒAӮаӮөӮ©ӮөӮҪӮзӢаӮӘ–Ъ“–ӮДӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB‘§ҺqӮНҗв‘ОӮЙӮ»ӮкӮНӮИӮўҒBүпӮҰӮОӮнӮ©ӮйӮЖҢҫӮБӮДӮўӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮН”NӮМҢчҒBҗe•ғӮН—lҒXӮИҢoҢұӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮҫҒBҺАҚЫӮЙӮЁӢаӮЖӮИӮйӮЖҗlҠФӮӘ•ПӮнӮйҺТӮрҒAүҪҗlӮаҢ©ӮДӮ«ӮҪӮМӮҫҒBӢ^ӮнӮҙӮйӮр“ҫӮИӮўҒB
Ғ@•ЎҺGӮИҗSӢ«ӮӘҚ¬ӮҙӮиҚҮӮӨ’ҶҒAӮІ‘О–КҒB
”ЮҸ—ӮМ”YӮЭӮЖ”ЮӮМҗe•ғӮМӢ^ӮўӮНӮЗӮұӮ©ӮЦҗҒӮ«”тӮсӮҫҒBҳbӮӘҸIӮнӮБӮҪӮзӮИӮӯӮИӮБӮДӮўӮҪҒB”ЮҸ—ӮН•ғҗeӮМӢ–ҚҘӮЙӮВӮўӮДӮН‘SӮӯҚlӮҰӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҳbӮвҒAҢӢҚ\ӮЗӮӨӮЕӮаӮўӮўӮЖҚlӮҰӮДӮўӮйүпҺРӮМҸ«—ҲӮМҳbҒA‘·ӮН‘ҒӮӯҢ©ӮҪӮўӮИӮҹҒBҚЕҸүӮЙғҸғVӮӘғLғғғbғ`ғ{Ғ[ғӢӮрӮ·ӮйӮсӮ¶ӮбҒIӮЖӮўӮӨҳbӮр•·ӮўӮДҒAӮ·ӮБӮ©ӮиҗSӮрӢ–ӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮұӮМҗlӮӘҺР’·ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮа–YӮкӮДӮўӮҪҒB
Ғ@Ӯ»ӮөӮД”ЮӮМ•ғҗeӮН”ЮҸ—ӮМҺpӮрҢ©ӮҪ“r’[ӮЙҸӯӮөӮОӮ©ӮиӢ^ҳfӮӘҸБӮҰӮҪҒB’PӮЙҚDӮЭӮҫӮБӮҪӮМӮҫҒBӮұӮкӮНҢҢӢШӮ¶ӮбӮИӮЖҗSӮМ’ҶӮЕҺvӮБӮҪҒBӮ»ӮөӮД”ЮҸ—ӮМ‘SӮӯӮаӮБӮД‘fҗ°ӮзӮөӮўӮЁҠиӮўӮЙҒAӮ·ӮБӮ©ӮиҗSӮрӢ–ӮөӮҪҒB
ҒuҺР’·—lҒAҺ„ӮЙӮНӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮұӮЖӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB‘§Һq—lӮ©ӮзҺfӮБӮҪӮЖҺvӮўӮЬӮ·ӮӘҒAҺ„ӮЙӮНҺШӢаӮӘӮ ӮйӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮкӮр•ФӮ·ӮұӮЖӮӘҒAҚЎҺ„ӮӘҲк”ФӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮұӮЖӮИӮМӮЕӮ·ҒB–{“–ӮЙҸҹҺиӮЖӮНҺvӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮ·ӮЧӮД•ҘӮўҸIӮҰӮЬӮөӮҪӮзҒAӮЬӮҪүьӮЯӮДҺfӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮөӮДӮ»ӮМҺһӮНҒAӮЁ•ғ—lӮЖҢДӮОӮ№ӮДӮӯӮҫӮіӮўҒBӮЁҠиӮўӮөӮЬӮ·ҒIҒIҒv
Ғ@”ЮӮМ•ғҗeӮНҸі‘шӮөӮҪҒB”ЮӮН•ғҗeӮЙҚH–КӮөӮДӮаӮзӮӨӮжӮӨ—ҠӮсӮҫӮӘҒA•ғҗeӮӘҒu”ЮҸ—ӮМӢCҺқӮҝӮрҚlӮҰӮДӮЭӮлҒIҚЎӮұӮұӮЕҺиҸ•ӮҜӮөӮДӮЗӮӨӮ·ӮйҒIҒvӮЖҺ¶ӮБӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒuӮҝӮбӮсӮЖ‘ТӮБӮДӮЁӮйӮ©ӮзҒAӮ ӮсӮҪӮНҸЕӮзӮёӮЙӮвӮйӮұӮЖӮрӮөӮИӮіӮўҒBҠж’ЈӮиӮҪӮЬӮҰҒvӮЖҢҫӮБӮД”ЮҸ—ӮЙ”чҸОӮсӮҫҒBӮ»ӮМҢҫ—tӮр•·ӮӯӮЖ”ЮҸ—ӮНӢғӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮД–АӮБӮДӮўӮҪҸ«—ҲӮрҢҲӮЯӮҪҒBҺҹӮМ“ъӮ©Ӯз“сҗlӮН“ҜӮ¶Ҹ«—ҲӮр–ІҢ©ӮИӮӘӮзҺdҺ–ӮЙҗёӮрҸoӮөӮҪҒBӮҝӮИӮЭӮЙ”ЮӮНҢЁӮҪӮҪӮ«ӮрӢЙӮЯӮҪҒB
Ғ@ӮR”NҢгҒA“сҗlӮНҢӢҚҘӮөӮҪҒBҗ·‘еӮЙҚsӮнӮкӮҪӢ“Һ®ӮЕӮНӮұӮсӮИғGғsғ\Ғ[ғhӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮНүпҸкӮрҸОӮўӮЖҚKӮ№ӮМүQӮЕ•пӮсӮҫӮМӮҫӮБӮҪҒB
Ғu”ЮӮЖҸoүпӮБӮҪҺһӮаҒAғvғҚғ|Ғ[ғYӮМҺһӮаҒA”ЮӮЙҢЁӮҪӮҪӮ«ӮрӮөӮДӮаӮзӮБӮҪҺһӮаҒAҸкҸҠӮН’jҺqғgғCғҢӮЕӮөӮҪҒv
Ғ@ӮіӮДҒAӮ»ӮсӮИ“сҗlӮМүәӮЕғRғEӮНҲзӮБӮҪҒBҠFӮ©ӮзӮҪӮӯӮіӮсүВҲӨӮӘӮзӮкҒAҸОҠзӮрҢьӮҜӮзӮкҒA‘ёӮОӮкӮҪҒBғRғEӮӘ—§ӮБӮҪӮҫӮҜӮЕҒAҗe‘°ӮЕүғүпӮӘӮ ӮБӮҪҒBғRғEӮМӮЁҸjӮўӮЕҠOҸoӮ·ӮйҺһӮЙӮНҒA•KӮёӮЖҢҫӮБӮДӮжӮўӮЩӮЗҠПҢхғoғXӮрҲк‘дҺШӮиӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӢіҲз–КӮЕӮа‘fҗ°ӮзӮөӮ©ӮБӮҪҒBҠГӮҰӮҪӮұӮЖӮЙӮН•кҗeӮӘ“O’к“IӮЙҺw“ұӮөӮҪҒBӮІ”СӮрҺcӮ·ӮұӮЖӮаҒAӮЁӢаӮр–і‘КҢӯӮўӮ·ӮйӮұӮЖӮаӢ–ӮіӮИӮ©ӮБӮҪҒB–{ӢCӮЕ“{ӮБӮҪӮиӮаӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮкӮЙӮН•KӮёҲӨӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮаӮҝӮлӮсҚЕҸүӮНҺ©•ӘӮМ—§ҸкӮрӢCӮЙӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAғRғEӮМ‘c•кӮӘҒuӮаӮӨү“—¶ӮИӮӯҺw“ұӮөӮҝӮбӮБӮДҒBӮӨӮҝӮМҺһӮаӮ»ӮӨӮҫӮБӮҪӮ©ӮзҒvӮЖҒAҠ„ӮЖҢyӮӯҢҫӮнӮкҒAӮИӮзӮО‘§ҺqӮМҸ«—ҲӮМӮҪӮЯӮЙӮЖҗSӮр•ПӮҰӮҪҒBӮЬӮҪғRғEӮӘӢ»–ЎӮрҺқӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮН•ғҗeӮӘӮЖӮұӮЖӮсӢіӮҰӮҪҒBғXғ|Ғ[ғcӮаӮҪӮӯӮіӮсӮвӮзӮ№ӮҪҒiӮаӮҝӮлӮсҚЕҸүӮЙӮвӮБӮҪӮМӮН–мӢ…ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮЁӮ¶ӮўӮҝӮбӮсӮЖҲкҸҸӮЙҒjҒBҸ¬ҠwҚZӮЬӮЕӮНӮЮӮөӮлҠwӢЖӮжӮиғXғ|Ғ[ғcӮр”MҗSӮЙӮвӮзӮ№ӮҪҒBӮ»ӮМҢӢүКҗg‘М”\—НӮНғNғүғXӮМ’NӮжӮиӮа”ІӮ«ӮсҸoӮДӮўӮҪҒB•АҚsӮөӮД•ЧҠwӮМӮЩӮӨӮағeғXғgӮНӮўӮВӮаҲкҢ…ҸҮҲКӮҫӮБӮҪҒBғRғEӮНҸmӮЙӮНҚsӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ·ӮЕӮЙүЖӮЙӮН•ғҗeӮЖӮўӮӨ—§”hӮИүЖ’лӢіҺtӮӘӮўӮҪӮ©ӮзӮҫҒB’ҶҠwӮЦҸгӮӘӮБӮДӮаҗ¬җСӮН•ПӮнӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮҫӮ©ӮзҸ—ҺqӮ©ӮзӮаӮаӮДӮҪҒB—F’BӮаӮҪӮӯӮіӮсӮЕӮ«ӮҪҒBӮөӮ©ӮаҠFӮўӮў“zӮзӮЕӮ ӮБӮҪҒBҲкҸҸӮЙ”nҺӯӮрӮвӮкӮОҒAҲкҸҸӮЙ–{ӢCӮЕӢЈӮўҚҮӮБӮҪҒBғPғ“ғJӮаӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮНӮЯӮБӮЫӮӨҺгӮ©ӮБӮҪҒB‘ҠҺиӮрүЈӮйӮМӮӘӮЗӮӨӮөӮДӮаӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒAҺуӮҜӮйӮұӮЖӮөӮ©ӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒB—цӮаӮөӮҪҒBӮұӮБӮҝӮ©ӮзҚҗ”’Ӯ·ӮкӮОҒA‘е’пҠF•tӮ«ҚҮӮБӮДӮӯӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө•КӮкӮйӮМӮа‘ҒӮ©ӮБӮҪҒBӮаӮҝӮлӮсӮўӮ¶ӮЯӮаҺуӮҜӮҪҒBҒuӢаҺқӮҝӮИӮсӮҫӮлҒHӮжӮұӮ№ӮжғRғүғ@ҒIҒIҒvӮЖғgғCғҢӮЕғ{ғRғ{ғRӮЙӮіӮкӮҪҒBғ`ғNӮйӮМӮӘӮЖӮДӮа•|Ӯ©ӮБӮҪӮӘҒA—F’BӮЙ‘Ҡ’kӮөӮҪҒBӮ·ӮйӮЖӮ Ӯй“ъҒAӮЬӮҪғKғүӮМҲ«ӮўҳA’ҶӮЙғgғCғҢӮЦҳAӮкӮДҚsӮ©ӮкӮ»ӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮ»ӮМҺһҒAғgғCғҢӮ©ӮзӮЗӮұӮ©ӮзӮЖӮаӮИӮӯ—F’BӮӘ‘еҗЁӮЕҳA’ҶӮЙҸPӮўӮ©Ӯ©ӮБӮҪҒBҠFӮӘҚЕ‘еҢАӮЙ—EӢCӮрҗUӮиҚiӮБӮҪғoғgғӢӮМ––ҒA•үӮҜӮҪҒBӮөӮ©Ӯаҗжҗ¶ӮЙӮЯӮҝӮбӮЯӮҝӮб“{ӮзӮкӮҪҒBҗeӮӘҠwҚZӮЙҢДӮОӮкӮҪҒBӮаӮӨҸIӮнӮиӮҫӮЖҺvӮБӮҪӮзҒAҠwҚZӮЙ—ҲӮҪӮМӮНӮИӮсӮЖӮЁӮ¶ӮўӮҝӮбӮсӮЕҒA
ҒuҺгӮўӮЁ‘OӮӘҲ«ӮўҒIҒI“ӘӮаҺgӮҰғoғJғӮғ“ҒIҒIҒvӮЖғRғEӮрҲкҠ…ӮөҒA’S”CӮМҗжҗ¶ӮрӮФӮсүЈӮБӮДӢAӮБӮҪҒBғRғEӮМӮЁӮ¶ӮўӮҝӮбӮсӮНҒAҠwҚZӮМ“`җаӮЖӮИӮБӮҪҒB
Ғ@ӮөӮ©ӮөҺ–ӮНүрҢҲӮөӮДӮўӮИӮўҒBӮЗӮӨӮ·ӮйӮ©ӮЖ—F’BӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪӮзҒAӢCӮӘӮВӮўӮҪӮзӮўӮ¶ӮЯӮНӮИӮӯӮИӮБӮДӮўӮҪҒB‘јӮМ“zӮЙғ^Ғ[ғQғbғgӮр•ПӮҰӮҪӮМӮ©ӮЖҺvӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮаҲбӮБӮҪҒBӮўӮВӮМӮЬӮЙӮ©ҳA’ҶӮНӮўӮ¶ӮЯӮр‘SӮӯӮөӮИӮӯӮИӮБӮҪҒB“–ҺһӮН“дӮЕҳb‘иӮЙӮаӮИӮБӮҪӮӘҒAҚӮҚZӮМӮЖӮ«ӮМ“Ҝ‘ӢүпӮЕӮ»ӮкӮН”»–ҫӮөӮҪҒBғRғEӮМҢі”ЮҸ—ӮӘҒAҳA’ҶӮМӮ ӮзӮкӮаӮИӮўҺpӮр”ҳӮөӮҪҺКҗ^ҒiӮЗӮсӮИҺКҗ^Ӯ©ӮН•s–ҫҒBғIғiғjҒ[ҺКҗ^ӮӘҚЕ—L—НҢу•вҒjӮЕ“zӮзӮЙӢәӮөӮрӮ©ӮҜӮҪӮзӮөӮўӮМӮҫҒBҢі”ЮҸ—ӮН’ҶҠwӮМӮЖӮ«ӮНҸ—ҺqӮМ’ҶӮЕғ{ғX“I‘¶ҚЭӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮЙ”ьҗlӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗg‘МӮаҚЧӮӯҒA‘еҗlӮМ•—ҠiӮр•YӮнӮ№ӮДӮўӮҪҒB–іҲӨ‘zӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒBӮҫӮ©Ӯз”ЮҸ—ӮрҢҷӮўӮИҗlӮаӮҪӮӯӮіӮсӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAғRғEӮЙӮҫӮҜӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒA–іҲӨ‘zӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB•Ғ’КӮМҸ—ӮМҺqӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗSӮрӢ–Ӯ№Ӯ鑶ҚЭӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮҫӮ©ӮзӮҫӮлӮӨӮ©ҒA’ҶҠwҗ¶Һһ‘гӮЙҲк”Ф’·Ӯӯ‘ұӮўӮҪ”ЮҸ—ӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө•КӮкӮДӮ©ӮзӮНӮ»ӮкӮБӮ«ӮиӮЕҒA“Ҝ‘ӢүпӮЕӮаҠзӮрҸoӮіӮИӮўҒB
Ғ@ғRғEӮН‘жҲкҺu–]ӮМҚӮҚZӮЦҠyҒXҚҮҠiӮөӮҪҒBӮұӮкӮ©ӮзӮН”ЮӮМҚў“пӮМҺnӮЬӮиӮҫӮБӮҪҒB
Ғ@Ӣ`–ұӢіҲзҠъҠФӮНҒAӮ ӮкӮрӮвӮкҒAӮұӮкӮрӮвӮкӮЖүЫ‘иӮрҸoӮіӮкӮҪҒBғRғEӮНӮ»ӮкӮрӮвӮБӮҪҒB’NӮжӮиӮа‘ҒӮӯҒAҠmҺАӮЙҒBӮ»ӮМӮҪӮСӮЙ”FӮЯӮзӮкӮҪҒBӮҫӮ©ӮзҠмӮСӮрҠҙӮ¶ӮҪҒBӮҫӮ©Ӯз‘ұӮҜӮҪҒB
Ғ@ӮөӮ©ӮөҒAҚӮҚZӮ©ӮзӮНҒAҺ©•ӘӮӘүЫ‘иӮрҢ©ӮВӮҜӮДҒAӮ»ӮкӮЙ‘ОӮөӮДҗ^Ң•ӮЙҺжӮи‘gӮЭҒAҢӢүКӮр“ҫӮйӮЖҠFӮЙ”FӮЯӮзӮкӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBғRғEӮНӮИӮсӮЕӮаӮЕӮ«ӮҪҒBҲк”NӮМӮЖӮ«ӮЙ—ӨҸг•”ӮЙ“ьӮБӮҪҒBӮ·ӮйӮЖӮ ӮБӮіӮиғCғ“ғ^Ғ[ғnғCӮЙҸoҸкӮЕӮ«ӮҪҒBҠFӮ©Ӯз—_ӮЯӮзӮкӮҪҒB—DҸҹӮөӮҪҒBҠFӮ©Ӯз—_ӮЯӮзӮкӮҪҒBҺGҺҸӮЙҒuӮ ӮМҒӣҒӣӢвҚsҺР’·ӮМҢд‘ӮҺiғүғ“ғiҒ[ҒIҒIҒvӮЖӮөӮДҸРүоӮіӮкӮҪҒBҠFӮ©Ӯз—_ӮЯӮзӮкӮҪҒB
Ғ@ғRғEӮН—_ӮЯӮзӮкӮДӮаҠмӮОӮИӮӯӮИӮБӮҪҒB
Ғ@•”ҠҲӮрҺ«ӮЯӮҪҒB—јҗeӮ©ӮзӮНүҪӮаҢҫӮнӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB”з“чӮИӮұӮЖӮЙҒuҺGҺҸӮЙҺжӮиҸгӮ°ӮзӮкӮҪӮМӮӘбӣӮЙӮіӮнӮБӮҪӮсӮҫӮлӮӨҒBӮұӮкӮҫӮ©Ӯзғ}ғXғRғ~ӮНҒEҒEҒEҒvӮЖҒAҠЁҲбӮўӮрӮөӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮсӮИҸ¬ӮіӮИ—қ—RӮ¶ӮбӮИӮ©ӮБӮҪҒBғRғEӮНӮаӮӨҠж’ЈӮйӮУӮиӮрӮөӮДҢӢүКӮр“ҫӮйӮұӮЖӮЙ‘ПӮҰӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒB
Ғ@Һ©•ӘӮНүҪӮрӮөӮДӮаӮЕӮ«ӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮкӮН•Ғ’КӮ¶ӮбӮИӮўҒB•ЧӢӯӮағXғ|Ғ[ғcӮаҒA–{ӢCӮрҸoӮөӮДӮаҸoӮіӮИӮӯӮДӮаҒuӮPҒvӮрӮаӮзӮҰӮйҒB—_ӮЯӮзӮкӮйҒBӮўӮВӮаӮұӮкӮҫҒBӮұӮМғXғpғCғүғӢҒBҗі’јҒA–OӮ«ӮҪҒBүҙӮМҸ«—ҲӮаҒAӮЁӮ»ӮзӮӯӮұӮМғXғpғCғүғӢӮ©Ӯз—ЈӮкӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙӮөӮДүҙӮӘӮИӮЙӮ©Ӯ·ӮкӮО—_ӮЯӮзӮкӮДҒAӢCӮӘӮВӮўӮҪӮзӮ¶ӮўӮҝӮбӮсӮЖ“ҜӮ¶—§ҸкӮЙҸAӮӯӮсӮҫӮлӮӨҒB–һ‘«ҠҙӮИӮсӮД‘SӮӯ“ҫӮзӮкӮвӮөӮИӮўҒBҺqӢҹӮМҚ Ӯ©Ӯз“ҜӮ¶ӮұӮЖӮрҢJӮи•ФӮөӮДӮўӮйӮсӮҫӮ©Ӯз“–‘RӮҫӮлӮӨҒB
үҙӮНҒAүҪӮрӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮсӮҫӮлӮӨҒH
Ғ@ғRғEӮН”YӮсӮҫҒBҠwҚZӮаӢxӮсӮЕӮРӮҪӮ·Ӯз•”ү®ӮЕ”YӮсӮҫҒBҺһҒXӮЁҺи“`ӮўӮіӮсӮ©—јҗeӮ©Ӯ¶ӮўӮҝӮбӮсӮ©ӮӘ•”ү®ӮМ‘OӮЙӮвӮБӮДӮ«ӮДӮНғRғ“ҒAғRғ“ӮЖғmғbғNӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮаҸӯӮөҗ\Ӯө–уӮИӮўӢCҺқӮҝӮЕ–іҺӢӮө‘ұӮҜӮҪҒBӮ»ӮөӮДӮРӮҪӮ·Ӯз–{Ӯр“ЗӮсӮҫҒBӮИӮЙӮ©ғqғ“ғgӮӘӮ ӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮЖҺvӮБӮҪӮМӮҫҒB
Ғ@”YӮЭӮЙ”YӮсӮҫӮ Ӯй“ъҒAҺ©•ӘӮӘҚKӮ№Ӯ¶ӮбӮИӮўӮұӮЖӮЙӢCӮГӮўӮҪҒBғRғEӮНҚKӮ№ӮЙӮВӮўӮДҚlӮҰӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮИӮ©ӮИӮ©“ҡӮҰӮНҢ©ӮВӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBҗ¶ӮЬӮкӮДҺnӮЯӮДӮМӮұӮЖӮҫӮБӮҪҒB’Bҗ¬ӮЕӮ«ӮИӮўҒIӮұӮкӮНӮвӮиӮӘӮўӮӘӮ ӮиӮ»ӮӨӮҫҒIғRғEӮНҺ©•ӘӮМғXғpғCғүғӢӮ©Ӯз”ІӮҜҸoӮ·ӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӢCӮӘӮөӮҪҒBӮҫӮ©ӮзӢ¶ӮӨӮжӮӨӮЙ”YӮсӮҫҒBҺ©–\Һ©ҠьӮЙӮаӮИӮБӮҪҒBӮІ”СӮрҗHӮЧӮйӮМӮаӮаӮБӮҪӮўӮИӮўӮЖҺvӮўҒAҚAӮЙүҪӮа’КӮіӮёҚlӮҰ‘ұӮҜӮҪҒBӮЁӮ©Ӯ°ӮЕӮ©ӮИӮи‘үӮ№ӮҪҒB
Ғ@ҒuҚKӮ№ҒvӮБӮДӮИӮсӮҫҒH
Ғ@җМӮНӮ ӮБӮҪӮНӮёӮИӮМӮЙҒAҚЎӮНҺқӮБӮДӮўӮИӮўӮаӮМҒB
Ғ@ӮЗӮұӮЙӮўӮБӮҪҒH
Ғ@ӮИӮўӮМӮИӮзҒA’TӮөӮЙҚsӮұӮӨҒB
Ғ@ғRғEӮНҲкҗl—·ӮрҢҲҲУӮөӮҪҒB
Ғ@—јҗeӮЖӮ¶ӮўӮҝӮбӮсӮНӮ»ӮкӮр‘ТӮБӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЙҒAғRғEӮЙ—·ҠЩӮМ–і—ҝҸө‘ТҢ”ӮЖҢр’К”пӮр“nӮөӮҪҒBҺOҗlӮНӮ ӮҰӮДҲАӮБӮЫӮў—·ҠЩӮр‘IӮсӮҫҒBҚsӮӯ‘OӮЙӮ¶ӮўӮҝӮбӮсӮНӮұӮӨҢҫӮБӮҪҒB
ҒuғҸғVӮа”YӮсӮҫҒBғRғEӮа”YӮсӮҫҒBӮИӮзӮ ӮЖӮН“®ӮӯӮөӮ©ӮИӮўӮМӮЈҒIҒIҒv
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғһ
Ғ@ҺRҗмҒ@ҚKҒiғTғ`ҒjӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҸuҠФҒA’NӮаҠмӮОӮИӮ©ӮБӮҪҒBҲгҺТӮМ•\ҸоӮЙҸОҠзӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮаӮ»ӮӨӮҫҒBҚЎ“ъӮVҗl–ЪӮЕҒAҲк“ъҗQӮДӮўӮИӮўӮМӮҫӮ©ӮзҒBӮўӮвҒA—қ—RӮНӮ»ӮкӮҫӮНӮИӮўҒBҠЕҢмҺtӮЙӮаҸОҠзӮНӮИӮўҒBӮЮӮөӮлҸӯӮөҠзӮӘӮұӮнӮОӮБӮДӮўӮйҒBӮ»ӮөӮДӮЬӮҪ•КӮМҠЕҢмҺtӮНҒAғTғ`ӮМ•ғҗeӮМҢіӮЦӮЖҢьӮ©ӮБӮҪҒBӢ}Ӯ¬‘«ӮЕҒB
Ғ@•ғҗeӮМғQғ“ғ]ғEӮН•сҚҗӮр•·Ӯ«ҒAҲкҸuӮМҲА“gӮЖүiү“ӮМҚ¬—җӮрӮЭӮ№ӮҪҒB—ЬӮӘӮұӮЪӮкӮНӮ¶ӮЯӮҪҒBӮ»ӮкӮНҒA”ЯӮөӮЭӮМ—ЬӮЕӮ ӮлӮӨҒBҠрӮөӮӯӮДӢғӮӯӮМӮИӮзҒAҸОҠзӮа•tҗҸӮ·ӮйӮНӮёӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөғQғ“ғ]ғEӮМҠзӮНҒAғxғ“ғ`ӮЙ•ҡӮөӮҪӮЬӮЬӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗ”•ӘҢгҒAҠЕҢмҺtӮЙҲД“аӮіӮкҒA•aҺәӮЦ‘–ӮБӮҪҒB
Ғ@•aү@ӮМҲкҺәҒBғxғbғhӮӘҲк‘дҒBӮ»ӮМӮӨӮҰӮЙҒAҗlӮӘҲкҗlҒBғTғ`ӮНӮЬӮҪҲбӮӨ•”ү®ӮЦҳAӮкӮДҚsӮ©ӮкӮҪӮзӮөӮўҒBҗжӮЩӮЗӮМҲгҺТӮаҒAҠЕҢмҺt’BӮаӮўӮйҒBҠFӮӘӮ ӮйҲк“_ӮрҢ©ӮДӮўӮйҒBӮўӮвҒAҢ©ҺзӮБӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМҢіӢҘӮрҒBӮ»ӮМӮ№ӮўӮЕҠFҸОҠзӮЙӮИӮкӮИӮўӮМӮҫҒBғQғ“ғ]ғEӮаӮ»ӮкӮрҢ©ӮҪҒB
Ғ@Ӯ»ӮұӮЙӮНҒA•ПӮнӮиүКӮДӮҪҺpӮМҒAғTғ`ӮМ•кҗeӮӘӮўӮҪҒB
Ғ@ғQғ“ғ]ғEӮЙӮНҒA•кҗeӮӘҗlӮЙӮНҢ©ӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮЬӮё”§ӮМҗFӮӘӮЁӮ©ӮөӮўҒBӮ»ӮкӮЙ‘«ӮМ‘ҫӮіӮаӮЁӮ©ӮөӮўҒBӮИӮсӮЕүE‘«ӮҫӮҜӮұӮсӮИӮЙӮУӮӯӮзӮсӮЕӮўӮйӮсӮҫҒHҗQӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨӮжӮиҒAҺҖӮсӮЕӮўӮйӮЭӮҪӮўӮҫҒBӮўӮвҒAӮИӮЙӮ©Ӣ@ҠBӮМӮжӮӨӮИӮаӮМӮӘҗg‘МӮЙӮЬӮЖӮнӮиӮВӮўӮДӮўӮйҒBӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНҒAҗ¶Ӯ©ӮіӮкӮДӮўӮйӮМӮ©ҒHӮ»ӮкӮИӮМӮЙҒAӮЗӮӨӮөӮДӢCҺқӮҝӮжӮіӮ»ӮӨӮЙ–°ӮБӮДӮўӮйӮсӮҫҒHҗQҢҫӮИӮсӮДҢҲӮөӮДҢҫӮнӮИӮў“zӮҫӮБӮҪӮМӮЙҒAӮіӮБӮ«Ӯ©ӮзғsҒ[ғsҒ[ҢҫӮБӮДӮўӮйӮМӮНӮИӮсӮҫҒH
Ғ@ӮИӮ ҒAӮЁӮўҒA–ЪӮрҠoӮЬӮ№ӮжҒBӮЁ‘OӮӘӮёӮБӮЖӮёӮБӮЖ‘ТӮҝҸЕӮӘӮкӮДӮўӮҪҗФӮҝӮбӮсӮӘҒAӮ ӮБӮҝӮМ•”ү®ӮЕ‘ТӮБӮДӮўӮйӮсӮҫӮјҒH
Ғ@ғQғ“ғ]ғEӮӘӮ»ӮӨҗәӮрӮ©ӮҜӮжӮӨӮЖҲк•а“ҘӮЭҸoӮөӮҪҸuҠФҒA•кҗeӮМ—ЧӮЙӮ ӮйӢ@ҠBӮӘғsҒ[Ғ[Ғ[Ғ[ӮЖү№ӮрӮҪӮДӮҪҒBӮөӮОӮзӮӯӮ·ӮйӮЖҒAӮ»ӮкӮНҺ~ӮсӮҫҒB
Ғ@ғTғ`ӮМ•кҗeӮНҒA–әӮМ–ҪӮЖҲшӮ«Ҡ·ӮҰӮЙҺ©ӮзӮМ–ҪӮрҗвӮБӮҪҒB
Ғ@Ӯ»ӮМҸuҠФҒA•КҺәӮЕғTғ`ӮНҸОӮБӮДӮўӮҪҒB”ЮҸ—Ӯр•шӮўӮДӮўӮй—DӮөӮ»ӮӨӮИӮЁӮОӮіӮсӮМҠЕҢмҺtӮрӮёӮБӮЖҢ©ӮВӮЯӮИӮӘӮзҒBӮ«ӮбӮБӮ«ӮбӮЖҗәӮрҸгӮ°ӮИӮӘӮзҒB
Ғ@ӮЬӮйӮЕҒAӮ»ӮМҠЕҢмҺtӮрҒuӮЁ•кӮіӮсҒvӮЖӮЕӮаҢДӮФӮжӮӨӮЙҒB
Ғ@ҲгҺТӮ©Ӯз•кҗeӮМ—ХҸIҺһҚҸӮрҢҫӮўӮнӮҪӮіӮкҒAӮұӮкӮ©ӮзӮМҸ”Һ–ҚҖӮр“`ӮҰӮзӮкӮҪғQғ“ғ]ғEӮНҒA“ӘӮӘҚ¬—җӮөҒAүҪӮрҢҫӮнӮкӮДӮўӮйӮМӮ©ӮіӮБӮПӮиӮҫӮБӮҪӮҪӮЯҒAҒuғgғCғҢӮЙҚsӮ©Ӯ№ӮДӮӯӮҫӮіӮўҒvӮЖҚҗӮ°ҒA‘«‘ҒӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒB•ЦҠнӮЙ“ЛӮБ•ҡӮөҒA”ЮӮНӢғӮ«ҒAӮнӮЯӮ«ҒAӮЬӮҪӢғӮ«ҒAҠPӮрӮөҒAӢкӮөӮӯӮИӮиҒA“fӮ«ҒAӮ»ӮөӮДӢғӮўӮҪҒBҺOҸ\•ӘҒAӮұӮкӮрҢJӮи•ФӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҠзӮрҗфӮўҒAҺ©•ӘӮМҠзӮрҢ©ӮВӮЯӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAҒuӮЗӮӨӮ·ӮйҒHҒvӮЖҷкӮўӮҪҒBӮөӮОӮзӮӯӮ»ӮМӮЬӮЬ“®Ӯ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ӮұӮкҲИҚ~ғQғ“ғ]ғEӮНӢғӮӯӮМӮрӮвӮЯӮҪҒBҲгҺТӮМҳbӮрӮ«ӮҝӮсӮЖ•·ӮўӮҪҒBҠҙҸоӮМ—]үCӮН‘SӮӯҺcӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBүiү“ӮМ–°ӮиӮЙӮВӮўӮҪүдӮӘҚИӮЙ•КӮкӮрҚҗӮ°ҒA”’Ӯў•zӮрӮ©ӮФӮ№ӮҪҒBӮ»ӮөӮД–әӮЖҸү‘О–КӮөӮҪҒBғQғ“ғ]ғEӮНҸОҠзӮЕғTғ`Ӯр•шӮўӮҪҒBҒu’xӮӯӮИӮБӮДӮІӮЯӮсӮжҒvӮЖҢҫӮўҒA•цӮкӮ»ӮӨӮИӮЩӮЗҸ_ӮзӮ©ӮЕҗV‘NӮИғTғ`ӮМ–jӮрғvғjӮБӮЖӮВӮВӮўӮҪҒBғTғ`ӮНҸОӮБӮҪҒBӮұӮМҺqӮНӮВӮўҗжӮЩӮЗӮМ•sҚKӮИӮЗ’mӮзӮИӮўӮМӮҫҒBғTғ`ӮМҸОҠзӮНӮ»ӮМ•sҚKӮр–YӮкӮіӮ№ӮДӮӯӮкӮҪҒBӮҫӮ©ӮзғQғ“ғ]ғEӮНҒAӮёӮБӮЖ”ЮҸ—ӮрҢ©ӮВӮЯӮДӮўӮҪҒBҢ©ӮВӮЯӮзӮкӮҪғTғ`ӮНҒA•ғҗeӮМ•EӮЬӮЭӮкӮЕҒA“ъҸДӮҜӮөӮҪӮжӮӨӮЙҗFҚ•ӮИ”§ӮӘ“Б’ҘӮМ•ғҗeӮМҺpӮрҢ©ӮДҲАҗSӮөӮДӮўӮҪҒBӮҫӮ©ӮзҸОӮў‘ұӮҜӮДӮўӮҪҒB
Ғ@Ӯ»ӮМҸОҠзӮМҗ”ӮНҒAҸ\ҺөҚОӮМҢ»ҚЭӮЬӮЕҗвӮҰӮйӮұӮЖӮӘӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ғ@”д—бӮөӮД”ЮҸ—ӮЙ•sҚKӮӘӮЁӮЖӮёӮкӮҪҒBӮЬӮёӮНҒA•ғҗeӮМ—қҗ«•цүуӮҫӮБӮҪҒB”ЮӮН’jҺиҲкӮВӮЕҺqҲзӮДӮЖүЖҺ–ӮЖҺdҺ–ӮрҢ©Һ–ӮЙ—ј—§ӮіӮ№ӮҪҒB”ЮӮМҺdҺ–ӮН“y–ШҚHҺ–ӮЖӮўӮӨҠ®‘SӮИ—НҺdҺ–ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҚb”гӮ ӮБӮДҒAғQғ“ғ]ғEӮМҗg‘МӮНӮЖӮДӮаҸд•vӮҫӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA‘ОӮөӮДҗёҗ_–КӮЕӮН‘Ҡ“–ҺQӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮкӮНҒAӮөӮеӮӨӮӘӮИӮ©ӮБӮҪҒB”ЮӮМҗSӮНҲӨӮ·ӮйҗlӮМҺҖӮЙӮжӮБӮД’v–ҪҸқҗЎ‘OӮЕӮ ӮБӮҪӮ©ӮзӮҫҒBӮҫӮӘүуӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBғTғ`ӮМ‘¶ҚЭӮӘӮ ӮБӮҪӮ©ӮзҒBғTғ`ӮМҸОҠзӮӘӮ ӮБӮҪӮ©ӮзҒB–Ҳ“ъҺdҺ–Ӯ©ӮзӢAӮБӮДӮН“VҺgӮр’ӯӮЯӮҪҒBӮ»ӮөӮДҺ©•ӘӮаҸОӮБӮДҸқӮр–ьӮөӮҪҒBӮ»ӮӨӮвӮБӮД–{“–ӮЙ’ZӮўҸОҠзӮМ“ъҒXӮӘ‘ұӮ«ҒAӮ»ӮкӮӘҸIӮнӮБӮҪӮМӮНғTғ`ӮӘ—c’tүҖӮр‘ІӢЖӮөӮҪҚ ӮЕӮ ӮБӮҪҒBғQғ“ғ]ғEӮМҗSӮЙҢьӮҜӮзӮкӮҪҸeӮМҲшӮ«ӢаӮрҲшӮўӮҪӮМӮНӢЯҸҠӮМӮЁӮОӮіӮсӮЕӮ ӮБӮҪҒB“Л‘RүЖӮЙ–KӮЛӮДӮ«ӮДҒAӮіӮБӮҝӮбӮсӮНӮжӮӯӮұӮұӮЬӮЕҠж’ЈӮБӮҪӮЛӮҘӮЖӢғӮ«җәӮЕҳbӮөӮҫӮөҒAӮұӮӨҢҫӮБӮҪҒB”–ӮзҸОӮЭӮр•ӮӮ©ӮЧӮИӮӘӮзҒB
ҒuӮЛӮҘғQғ“ӮіӮсҒBӮіӮБӮҝӮбӮсӮрҸ¬ҠwҚZӮЙҚsӮ©Ӯ№ӮйӢаӮНӮ ӮйӮсӮ©ӮўҒHҒv
Ғ@ҢҫӮнӮкӮҪҷӢ“ЯҒAғQғ“ғ]ғEӮЙ“{ӮиӮр’ҙӮҰӮҪӮаӮМӮӘ—NӮ«ҸoӮДӮ«ӮҪҒBҚЎӮЬӮЕӮМ“w—НӮрӮ·ӮЧӮД”Ы’иӮіӮкӮҪҒB“ҜҸоӮіӮкӮйӮЩӮЗғIғҢӮМҗlҗ¶ӮНҗhӮўӮаӮМӮҫӮЖҺvӮнӮкӮДӮўӮҪӮМӮ©ҒBҠж’ЈӮБӮҪӮМӮНғIғҢӮҫҒBғTғ`ӮНғIғҢӮӘ‘nӮБӮҪҚKӮ№ӮржҗүМӮөӮДӮўӮҪӮҫӮҜӮҫҒBҸғҗҲӮИ’ҶӮЕҗ¶Ӯ«ӮДӮ«ӮҪҒBӮ»ӮкӮИӮМӮЙҒA–ЪӮМ‘OӮЙӮўӮйӢS’{ӮНғTғ`ӮӘҠж’ЈӮБӮҪӮЖҢҫӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮНҒAғTғ`ӮрүҳӮ·ӮұӮЖӮЖ“ҜӢ`ӮҫҒB
Ғ@ғRғmғ„ғҚғEҒEҒEҒEҒI
Ғ@ӮұӮсӮИҒAҚұҚЧӮИӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒB•Ғ’КӮҫӮБӮҪӮзӮұӮсӮИӮұӮЖӢCӮЙӮ№Ӯё—¬ӮөӮҪӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮ»ӮӨҒAӮаӮӨӮ·ӮЕӮЙӮұӮМҺһ“_ӮЕғQғ“ғ]ғEӮН•Ғ’КӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒBӮұӮМӮЖӮ«”ЮӮМ’ҶӮЕүҪӮ©ӮӘ”ҡ”ӯӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДӢCӮӘӮВӮўӮҪӮзғTғ`ӮМ–ЪӮМ‘OӮЕӮЁӮОӮіӮсӮМҺсӮрҚiӮЯҺEӮөҒAӢCӮӘӮВӮўӮҪӮзҠДҚ–ӮЙ•ъӮиҚһӮЬӮкӮДӮўӮҪҒBҚЕӮаӮИҢӢ––ӮҫҒBҺьӮиӮ©ӮзҢ©ӮкӮОҚЯӮМӮИӮўҺТӮрҺEӮөӮҪӮжӮӨӮЙӮөӮ©Ң©ӮҰӮИӮўӮ©ӮзӮҫҒBӮұӮӨӮөӮД“Л‘RғTғ`ӮН•ғҗeӮрҺёӮўҒA“ҫӮҪӮаӮМӮНҺьӮиӮ©ӮзӮМ—вӮҪӮўҺӢҗьҒA”l“|ҒA‘һҲ«ӮҫӮБӮҪҒBҺһӮӘҢoӮВӮЙӮВӮкҗўҠФӮНғTғ`ӮМ–јӮр•ПӮҰӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҒuҺEҗlҺТӮМ–әҒvҒuҺҖҗ_ҒvӮЖҒB
Ғ@ӮұӮкӮӘ•sҚKӮМ”ӯ’[ӮҫӮБӮҪҒBҺҹӮНҠwҚZӮЕӮМӮўӮ¶ӮЯӮЕӮ ӮБӮҪҒB‘еӮМ‘еҗlӮӘҚЯӮМӮИӮў–әӮрӮўӮ¶ӮЯӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒAҺqӢҹӮӘӮөӮИӮўӮнӮҜӮӘӮИӮ©ӮБӮҪҒBҸ¬ҠwҚZӮ©Ӯз’ҶҠwҚZӮЬӮЕҒA“TҢ^“IӮЕ“O’к“IӮИӮўӮ¶ӮЯӮрҺуӮҜӮҪҒB“а—eӮНӮ ӮЬӮиӮЙҺcҚ“Ӯ·Ӯ¬ӮДҸ‘ӮҜӮИӮўҒBҗ”ҺҡӮЕ•\ӮнӮ·ӮЖҒAӢг”NҠФӮМӮӨӮҝғTғ`ӮНӮўӮ¶ӮЯӮЙӮжӮБӮДӢCҗвӮрӮPӮOӮWүсҒAҚңҗЬӮрӮPӮPүсҒA”јҺEӮөӮЙӮіӮкӮ©ӮҜӮҪӮМӮӘӮTүсҒAӮ»ӮөӮДҗёҗ_“IғXғgғҢғXӮ©ӮзӮӯӮйҲЭ’ЧбҮӮрӮPүсҢoҢұӮөӮҪҒB
Ғ@Ӯ»ӮөӮДҺё—цӮаӮPүсӮөӮҪҒBӮұӮкӮНғTғ`ӮМҲк”ФҢҷӮИҺvӮўҸoӮЕӮ ӮйҒBҸ¬ҠwҚZҺl”Nҗ¶ӮМҚ ӮЕӮ ӮБӮҪҒBғTғ`ӮНӮЖӮИӮиӮМҗИӮМҠwӢүҲПҲхӮМ’jӮМҺqӮЙҚDҲУӮр•шӮўӮҪҒB”ЮӮНҠFӮЖҲбӮБӮД—DӮөӮ©ӮБӮҪҒBӮўӮ¶ӮЯӮДӮұӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҺqӮМ—F’BӮНӮіӮсӮҙӮсӮўӮ¶ӮЯӮДӮ«ӮҪӮМӮҫӮӘҒA’jӮМҺqӮНӮ»ӮкӮрӮҫӮЬӮБӮДҢ©ӮДӮўӮйӮҫӮҜӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮНӮ»ӮкӮЕӮўӮ¶ӮЯӮДӮўӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪӮМӮҫӮӘҒAҺАҚЫӮЙҗUӮйӮнӮкӮйӮжӮиғ}ғVӮҫӮЖғTғ`ӮНҺvӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМҺqӮЙҢ©ӮВӮЯӮзӮкӮйӮЖҒAҺьӮиӮ©ӮзӮМ’ЙӮЭӮӘ”јҢёӮөӮҪӮМӮҫӮБӮҪҒBғTғ`ӮНӮұӮкӮӘҒuҚDӮ«ҒvӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮЖӢCӮГӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮДӮ»ӮӨӮўӮӨӮұӮЖӮЙӢCӮГӮҜӮҪҺ©•ӘӮЙҠмӮсӮҫҒBҺ„ҒAҠFӮЖ“ҜӮ¶Ӯ¶ӮбӮИӮўӮМӮ©ӮИҒEҒEҒE
Ғ@Ӯ»ӮӨҺvӮБӮҪҺO“ъҢгҒAғTғ`ӮНҠwҚZӮЕӮЬӮҪӮўӮ¶ӮЯӮрҺуӮҜӮДӮўӮҪӮМӮҫӮӘҒAҚЎ“xӮМӮНҸӯӮө•ПӮИғ^ғCғvӮМӮаӮМӮҫӮБӮҪҒB’ӢӢxӮЭӮЙ“Л‘RғNғүғXӮМҸ—ӮМҺqӮМғҠҒ[ғ_Ғ[ғOғӢҒ[ғvӮӘӮұӮсӮИӮұӮЖӮр•·ӮўӮДӮ«ӮҪҒB
ҒuӮЛҒAӮ ӮсӮҪӮБӮДҚDӮ«ӮИҗlӮўӮйӮМҒHҒv
Ғ@ғTғ`ӮНӮўӮВӮаӮМӮжӮӨӮЙ–іҺӢӮрӮөӮҪҒB“ҡӮҰӮҪӮБӮДҒAӮИӮӯӮҪӮБӮДҒAӮЗӮӨӮ№ҚЕҢгӮН–\—НӮҫӮЖҺvӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҚЎүсӮНҲбӮБӮҪҒBӮИӮЙӮ©–{ӢCӮЕӢіӮҰӮДӮЩӮөӮўӮжӮӨӮИ•өҲНӢCӮҫӮБӮҪҒBӮөӮОӮзӮӯ–ЩӮБӮДӮўӮйӮЖҒAҸ—ӮМҺq’BӮНғNғүғXӮМ’jӮМҺqӮМ–ј‘OӮр“K“–ӮЙӢ“Ӯ°ҺnӮЯӮҪҒBӮ»ӮкӮЙғTғ`ӮНҺсӮрүЎӮЙҗUӮБӮД“ҡӮҰӮҪҒBҢіҒXӮ·ӮЧӮДӮМ–ј‘OӮЙ‘ОӮөӮДӮ»ӮӨӮ·ӮйӮВӮаӮиӮҫӮБӮҪҒB‘ҒӮӯӮұӮсӮИӮұӮЖҸIӮнӮБӮД—~ӮөӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзҒBӮөӮ©ӮөғTғ`ӮМҺvӮўӮЖӮН— • ӮЙҒA•Ғ’iҢ©ӮДӮЭӮКӮУӮиӮрӮөӮДӮўӮҪҸ—ӮМҺq’BӮа’PҸғӮИӢ»–Ў–{ҲКӮЕҸWӮЬӮБӮДӮ«ӮҪҒBӮ»ӮМҸWӮЬӮиӮЙӮИӮсӮҫӮИӮсӮҫӮЖ’jӮМҺqӮаҸWӮЬӮиӮҫӮөӮҪҒB’ӢӢxӮЭӮЙғTғ`ӮМҠчӮМҺьӮиӮрҠFӮӘҲНӮсӮЕӮўӮҪҒBғTғ`ӮНӮЖӮДӮа•|Ӯ©ӮБӮҪҒBӮҜӮЗ“ҜҺһӮЙӮИӮәӮ©ҠрӮөӮ©ӮБӮҪҒBҺ„ӮМӮұӮЖӮрҒAҠFӮӘҢ©ӮДӮӯӮкӮДӮўӮйҒEҒEҒEҒB
Ғ@Ӣ“Ӯ°ӮзӮкӮҪ’jӮМҺqӮЙ‘ОӮөӮДғTғ`ӮӘҺсӮрҗUӮйӮҪӮСҒAӮ»ӮМ’jӮМҺqӮНҠҪҠмӮөҒAғKғbғcғ|Ғ[ғYӮөҒAҒuғIғҢғZҒ[Ғ[ғtҒфҒvӮЖӮНӮөӮбӮўӮҫҒBӮ»ӮкӮрҢ©ӮДҠFӮӘҸОӮБӮҪҒBҺcҚ“ӮИҚsҲЧӮИӮМӮҫӮӘҒAҠyӮөӮўҸкӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAӮ»ӮМҺһӮНӮ«ӮҪҒB
ҒuӮ¶ӮбӮ Ӯ¶ӮбӮ ҒA—ЧӮМҗИӮМғiғMғgҢNӮНҒHҒv
ӮұӮМӮЖӮ«Ҳк”ФғNғүғXӮӘ’Қ–ЪӮөӮҪҒBүВ”\җ«ӮӘҲк”ФӮ ӮйӮ©ӮзӮҫҒBғTғ`ӮНҺсӮрҗUӮБӮҪҒB
ҸcӮЙҒB
Ғ@ғNғүғXӮӘ”ҡ”ӯӮөӮҪҒBҺАҚЫӮөӮҪӮнӮҜӮҫӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮсӮИү№ӮӘӮөӮҪҒBҲкҗДӮЙ–ЪӮрҠЫӮӯӮөӮД”Я–ВӮрҸгӮ°ӮйҸ—ӮМҺq’BҒBӮНӮөӮбӮ¬үсӮБӮДғiғMғgҢNӮрӮ©ӮзӮ©ӮӨ’jҺq’BҒBҳлӮўӮҪӮЬӮЬҸӯӮөҸЖӮкӮДҸОӮӨғTғ`ҒBӮ»ӮөӮДҠFӮЙ“ҡӮҰӮрҠъ‘ТӮіӮкҒAҺӢҗьӮрҲкҗДӮЙ—ҒӮСӮҪғiғMғgҢNӮНӮұӮӨҢҫӮБӮҪҒB
ҒuғIғҢӮвӮҫӮжҒBӮұӮсӮИӮОӮБӮҝӮўӮМҒv
Ғ@ғNғүғXӮМҠFӮӘ”ҡҸОӮөӮҪҒB
Ғ@ғTғ`ӮН“ҖӮиӮВӮўӮҪҒBҠFӮМҸОӮўҗәӮӘ’ЙӮ©ӮБӮҪҒB–\—НӮжӮиӮаҒBғTғ`ӮН‘–ӮБӮДғgғCғҢӮЦ“ҰӮ°ӮДҒAҗ…•ӘӮӘӮИӮӯӮИӮйӮЩӮЗҚҶӢғӮөӮҪҒBғNғүғXӮМҠFӮНӮНӮөӮбӮ¬ӮИӮӘӮзғgғCғҢӮЙӮВӮўӮДҚsӮ«ҒA”ЮҸ—ӮМӢғӮ«җәӮр•·Ӯ«ӮЬӮҪҸОӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮЬӮЬғTғ`ӮНӮ»ӮұӮЕҲк”УӮрүЯӮІӮөӮҪҒB
Ғ@ӮұӮМӮЩӮ©ӮЙӮаҒAүЖӮӘ•ъүОӮЙӮжӮБӮД‘SҸДӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮиҒAӮ`ӮuғXғJғEғgӮМҺүӮБӮұӮўӮЁӮ¶ӮіӮсӮЙӢӯҠӯӮіӮкӮ©ӮҜӮҪӮиӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮИӮәӮҫӮлӮӨҒBғTғ`ӮНҺҖӮсӮҫӮжӮӨӮИ–ЪӮрӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒBҗ¶ӮЬӮкӮҪӮЖӮ«ӮЖҲкҸҸӮЕҒA—DӮөӮў–ЪӮМӮЬӮЬҗ¶Ӯ«ҒAҸ\ҢЬ”NӮӘҢoӮБӮҪҒBӮ»ӮөӮДӮ»ӮМҚОӮЕҒuҲЈӮкӮЭӮМҠбҒvӮр‘ҠҺиӮЙҢьӮҜӮйӮұӮЖӮрҠoӮҰӮҪҒBғTғ`ӮМҠбӮӘ‘ҠҺиӮМҠбӮЖҚҮӮӨӮЖҒAӮЗӮсӮИҲ«ҲУӮЙ–һӮҝӮҪ”yӮЕӮаҲкҸuӢҜӮсӮЕӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮөӮДғTғ`ӮМ“ҫҲУӮМҸОҠзӮр–ЈӮ№ӮйӮЖҒA‘ҠҺиӮНӮҪӮҝӮЬӮҝ–ЪӮрӮ»ӮзӮөӮД”s–kӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮкӮН”ЮҸ—ӮМүЯӢҺӮӘҚмӮиҸoӮөӮҪҺ’•ЁӮҫӮБӮҪҒBӮЁӮ©Ӯ°ӮЕ’ҶҺOӮНӮўӮ¶ӮЯӮзӮкӮйӮұӮЖӮӘӮИӮ©ӮБӮҪҒB—F’BӮН‘Ҡ•ПӮнӮзӮёӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ӮұӮұӮЬӮЕҺUҒXӮИ–ЪӮЙӮ ӮБӮҪғTғ`ӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҺ©ҺEӮМүсҗ”ӮНӮOӮЕӮ ӮБӮҪҒB•Ғ’КӮИӮзӮұӮсӮИӢкӮөӮЭӮ©Ӯз“ҰӮкӮйӮҪӮЯӮЙҒAҗVӮҪӮИӢ«’nӮрӢҒӮЯӮйӮҪӮЯӮЙҺ©ӮзӮЙҺEҗlӮр”ЖӮ·ӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮ»ӮкӮН”ЪӢҜӮЖӮаӮўӮҰӮйҒBӮөӮ©ӮөҗіӮөӮўӮЖӮаӮўӮҰӮйҒBғ{ғҚғ{ғҚӮИҗёҗ_ӮМӮЬӮЬҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮӯӮЩӮӨӮӘҒAҺҖӮКӮжӮиӮаҗhӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮ©ӮзӮҫҒBғTғ`ӮНҗ¶Ӯ«ӮҪҒBӮ»ӮкӮЕӮаҗ¶Ӯ«ӮҪҒB—қ—RӮН’NӮЙӮаӮнӮ©ӮзӮИӮўҒB
ғTғ`ӮН’ҶҠwҚZӮр‘ІӢЖӮөҒAҗiҠwӮНӮ№ӮёӮЙ“ӯӮӯӮұӮЖӮр‘IӮсӮҫҒBҢoҚП“IӮЙҗiҠwӮНҚў“пӮҫӮ©ӮзӮЕӮ ӮБӮҪҒB“ӯӮӯӮЖӮўӮБӮДӮаӮұӮМҚОӮЕӮНҸAҗEӮМ•қӮНӢ·ӮўӮМӮН“–ӮҪӮи‘OӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҸ—җ«ӮМҸкҚҮҠз—§ӮҝӮӘҗ®ӮБӮДӮіӮҰӮўӮкӮО•—‘ӯҠЦҢWӮМҺdҺ–ӮЕҠyӮЙүТӮ®ӮұӮЖӮаүВ”\ӮҫҒBҒiғTғ`ӮМҚОӮЕӮНҲб–@ӮҫӮӘҒjҒBӮӘҒAғTғ`ӮНӮ»ӮҝӮзӮМ“№Ӯр‘IӮОӮИӮ©ӮБӮҪҒB•Ғ’КӮЙ”hҢӯӮМҺdҺ–ӮЙ“сҺР“oҳ^ӮөӮҪҒB•Ҫ“ъӢx“ъҠЦҢWӮИӮӯҒAҺdҺ–ӮӘӮ ӮкӮОӮ·Ӯ®ӮЙ“ӯӮўӮҪҒBҺdҺ–“а—eӮаӢCӮЙӮ№ӮёҒAҲшүzӮөӮвҺ©“]ҺФӮМү^”АӮЖӮўӮӨ’jӮӘҺеӮЙӮвӮй—НҺdҺ–ӮаӮ»ӮВӮИӮӯӮұӮИӮөӮҪҒB–іӢC—НӮЙҒBӮЬӮйӮЕғҚғ{ғbғgӮМӮжӮӨӮЙ•\ҸоҲкӮВ•ПӮҰӮйӮұӮЖӮИӮӯ“ӯӮўӮҪҒB
Ғ@ӮвӮӘӮДҲк”NӮӘүЯӮ¬ӮҪҒBғTғ`ӮМ’ҷӢаҠzӮН‘Ҡ“–ӮИҠzӮЙ’BӮөӮДӮўӮҪҒBӮЬӮҪ‘қӮҰӮҪӮМӮНӢаӮҫӮҜӮҫӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB”hҢӯҗжӮЕ—F’BӮаӮЕӮ«ӮҪҒB—c’tүҖҲИ—ҲӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮЖӮНӮўӮБӮДӮаҗіҠmӮЙ—F’BӮЖҢДӮЧӮйҠЦҢWӮИӮМӮ©ӮНӢ^–вӮЕӮ ӮБӮҪҒBғTғ`ӮНӮ»ӮМӮұӮЖӮрҺ©•үӮөӮДӮўӮҪҒBӮЖӮўӮӨӮМӮаҒA“ӯӮ«ҺnӮЯӮДӮ©Ӯз”ј”NӮӘүЯӮ¬ӮҪҚ ҒB’Ӣ”СӮМӢxҢeҺһҠФӮИӮЗӮЕҒAғTғ`ӮНҗГӮ©ӮИӮЖӮұӮлӮЕҗHӮЧӮҪӮўӮӘӮҪӮЯӮЙӮнӮҙӮЖҗlӢCӮМҸӯӮИӮўҸкҸҠӮЙҲЪ“®Ӯ·ӮйӮМӮҫӮӘҒAӮ»ӮМҸкҸҠӮЙ’NӮ©ӮөӮзӮВӮўӮДҚsӮ«ҒAҸҹҺиӮЙҳbӮ©ӮҜҺnӮЯӮйӮМӮҫҒBҗ«•КҠЦҢWӮИӮӯҒAӮөӮ©Ӯа’NӮаӮӘғTғ`ӮМ–ј‘OӮр’mӮБӮДӮЁӮиҒAӮЬӮйӮЕҸү‘О–КӮЕӮНӮИӮўӮжӮӨӮИҢыӮФӮиӮЕҗЪӮөӮДӮӯӮйӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮнӮҜӮӘӮнӮ©ӮзӮИӮўғTғ`ӮНӮЗӮӨӮөӮДҺ„ӮМ–ј‘OӮр’mӮБӮДӮўӮйӮМӮ©Ӯр•·ӮӯӮЖҒA‘ҠҺиӮН•KӮё–ЪӮрҠЫӮӯӮөӮД
ҒuӮҰҒHҢNӮұӮұӮМ”hҢӯүпҺРӮЕӮНӮ©ӮИӮи—L–јӮҫӮжҒB’mӮзӮИӮўҗlӮўӮИӮўӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮИҒBӮўӮВӮаӮөӮБӮ©Ӯи“ӯӮўӮДӮйӮсӮЕӮөӮеҒHҲМӮўӮжҒAғzғ“ғgӮЙҒBӮЖӮұӮлӮЕ–ј‘OӢіӮҰӮДӮжҒv
Ғ@ӮЖ“ҡӮҰӮҪҒB’ҶӮЙӮНҒuғ}ғXғRғbғg“IӮИҒH‘¶ҚЭӮЙӮИӮБӮДӮйӮжҒBӮҫӮБӮДӮИӮсӮ©үВҲӨӮзӮөӮўӮаӮсҒvӮЖҸОӮБӮДҢҫӮӨҗlӮаӮўӮҪҒBӮҪӮҫӮ»ӮкӮҫӮҜӮМӮұӮЖӮӘӮ«ӮБӮ©ӮҜӮЕҒAӮ»ӮұӮ©ӮзӮҝӮеӮӯӮҝӮеӮӯҳbӮрӮ·Ӯй’ц“xӮҫӮБӮҪӮ©ӮзҒAҒu—F’BҒvӮЖӮНҗіҠmӮЙҺvӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒBӮ»ӮкӮЙӢЯӮў‘¶ҚЭҒAҒu’mӮиҚҮӮўҒvӮ®ӮзӮўӮЙӮөӮ©ғTғ`ӮНҚlӮҰӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮҫӮӘҒAҠmӮ©ӮИӮұӮЖӮНҒAғTғ`ӮМ“w—НӮӘҗlҒXӮЙүeӢҝӮр—^ӮҰӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB–{җlӮН‘SӮӯҺьӮиӮрҢ©ӮёӮЙӮРӮҪӮ·Ӯз—^ӮҰӮзӮкӮҪҺdҺ–ӮрӮұӮИӮөӮДӮўӮҪӮҪӮЯҒAӢCӮГӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒBүсӮиӮЙӢ»–ЎӮӘӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮМӮаӮ ӮБӮҪҒB
Ғ@ғTғ`ӮНӮ ӮйӮұӮЖӮЙӮөӮ©–ЪӮӘӮўӮБӮДӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮҫҒB
Ғ@Ӯ»ӮкӮНҒAҚӮҚZӮМҚ ғlғbғgғtғFӮЕҗQ”‘ӮиӮөӮҪҺһӮЙӢф‘RӮ Ӯй“®үжғTғCғgӮЕҢ©ӮҪҒu—·ӮМӢLҳ^ҒvӮӘӮ»ӮаӮ»ӮаӮМӮ«ӮБӮ©ӮҜӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮН“®үж“ҠҚeҺТӮӘ“ъ–{ҲкҺьӮөӮИӮӘӮзҠe’nӮМ–јҸҠӮИӮЗӮрҺBүeӮөҒAӮ»ӮМғTғCғgӮЙӮtӮoӮөӮДӮўӮйӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBғTғ`ӮНӮ»ӮкӮЙ–ЈӮ№ӮзӮкӮҪҒBҲк”УӮ©ӮҜӮДҒu—·ӮМӢLҳ^ҒvӮМ“®үжӮр‘S•”Ң©ӮҪҒBӮ»ӮөӮДҢҲӮЯӮҪҒB
Ғ@ӮұӮкӮЕӮўӮўӮвҒBӮұӮкӮӘӮөӮҪӮўҒBӮЁӢа’ҷӮЯӮДҚsӮұӮӨҒB
Ғ@—·ӮМҺ‘ӢаӮрҸWӮЯӮйӮҪӮЯӮЙҒAғTғ`ӮНҲк”NҠФ–Т“ӯӮ«ӮөӮҪӮМӮҫҒBӮ»ӮМ’ҶӮЕғTғ`ӮНҲкӮВӮМӮұӮЖӮрҢҲӮЯӮйӮЖҺьӮиӮӘҢ©ӮҰӮИӮӯӮИӮйҺ©•ӘӮМҗ«ҠiӮрҒAҗgӮрӮаӮБӮД’mӮБӮҪҒBӮіӮБӮ«ӮМҳbӮөӮ©ӮҜӮзӮкӮҪӮұӮЖӮНӮ»ӮМҲкӮВӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAҳJ“ӯ’ҶӮЙүҪүсӮ©ҲУҺҜӮӘ”тӮсӮҫӮұӮЖӮаҒAӮ»ӮМҲкӮВӮЕӮ ӮйҒB
Ғ@Ӯ»ӮсӮИғTғ`ӮрҒAҺьӮиӮНҲЈӮкӮЭӮМҠбӮЕҢ©ӮйҗlӮаӮўӮҪҒB”NӮрүzӮөӮҪҚ ӮМӮұӮЖӮҫҒBҺOүУ“ъӮМҺҹӮМ“ъӮ©ӮзғTғ`ӮНӮіӮБӮ»Ӯӯ“ӯӮўӮҪҒB”N–ҫӮҜҚЕҸүӮМҺdҺ–ӮМҢ»ҸкӮН”p•iүсҺыҚHҸкӮЕҒAҢЬҸ\ӮрүЯӮ¬ӮҪӮЁӮОӮҝӮбӮсҲкҗlӮЖҲкҸҸӮЙҢ»ҸкӮЦ•ӢӮўӮҪҒBҒuӮЬӮҹҒA”N–ҫӮҜӮИӮсӮЕӮдӮБӮӯӮиӮвӮБӮДӮӯӮҫӮіӮўҒBҢЯҢгӮа‘ҒӮЯӮЙҗШӮиҸгӮ°ӮЬӮ·ӮсӮЕҒvӮЖҢ»ҸкӮМӮЁӮ¶ӮіӮсӮЙҢҫӮнӮкҒAҺЁӮМҠҙҠoӮӘӮИӮӯӮИӮйӮЩӮЗҠҰӮўҠOӮЕҒA“сҗlӮНӮЁҢЭӮўӮМӮұӮЖӮрҸӯӮөӮёӮВҳbӮөӮИӮӘӮзҒA”p•iӮЙ•tӮўӮДӮўӮйғVҒ[ғӢӮр”ҚӮӘӮөӮҪҒBғTғ`ӮӘҲк’КӮиҺ©•ӘӮМүЯӢҺӮрҳbӮ·ӮЖҒAӮЁӮОӮҝӮбӮсӮНҗГӮ©ӮЙӢғӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒuӮ ӮИӮҪӮа‘е•ПӮЛҒBүВҲӨӮ»ӮӨӮЙҒEҒEҒEҒvӮЖҢҫӮБӮҪҒBғTғ`ӮНҢгүчӮөӮҪҒB—]ҢvӮИӮұӮЖӮрӮЧӮзӮЧӮзӮЖ’қӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҺ©•ӘӮӘҸӯӮөҢҷӮЙӮИӮиҒAӮ»ӮкӮ«ӮиӮЁӮОӮҝӮбӮсӮМҳbӮр•·ӮӯӮұӮЖӮҫӮҜӮЙӮөӮҪҒB
“ҜҸоӮіӮкӮйӮМӮНҒAӮИӮсӮМ“ҫӮаӮИӮўӮ©ӮзҢҷӮҫҒB
ӮЁ’ӢӮМҺһҠФӮЙӮИӮБӮДҒAғTғ`ӮНӮЁӮОӮҝӮбӮсӮ©ӮзҺ©үЖҗ»ӮМӮЁӮЙӮ¬ӮиӮрӮаӮзӮБӮҪҒBӮЬӮҪӢғӮ«Ӯ»ӮӨӮИ–ЪӮЕҒuҠж’ЈӮБӮДӮЛҒEҒEҒEҒvӮЖҢҫӮнӮкӮҪҒBӮЬӮҪ“ҜҸоӮіӮкӮДҢҷӮЙӮИӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҠрӮөӮіӮМӮЩӮӨӮӘҸгӮҫӮБӮҪҒB
Ғ@ҠOӮНҒAҢ¶‘z“IӮИҗбӮӘҚ~ӮиҺnӮЯҒAӮ«ӮБӮЖ’ЙӮўӮЩӮЗҒAӮ»ӮөӮД”ЯӮөӮӯӮИӮйӮЩӮЗҠҰӮ»ӮӨӮИӮМӮЙҒAӮЁӮЙӮ¬ӮиӮНғVғғғPӮМӮөӮеӮБӮПӮіӮЖҠC‘ЫӮМҚҒӮиӮӘӮЖӮДӮаүщӮ©ӮөӮӯӮДӮЁӮўӮөӮӯӮДҒA‘ТҚҮҺәӮНғXғgҒ[ғuӮӘӮ«ӮўӮДӮЖӮДӮа’gӮ©ӮӯӮДҒEҒEҒE
Ғ@Һ„ӮМҺьӮиӮНҒAӮИӮсӮД’gӮ©ӮўӮсӮҫӮлӮӨҒB
Ғ@Һ„ӮНҒAҚKӮ№ӮИӮсӮҫҒBӮ¶ӮбӮ ҒA“ҜҸоӮЖӮ©ҒAүВҲӨӮ»ӮӨӮЖӮ©ҒAӮИӮсӮЕӮЭӮсӮИӮ»ӮӨҢҫӮӨӮМҒH
Ғ@“~ҒAҸtӮӘүЯӮ¬ҒAҺөҢҺҒB
Ғ@ҸӯҒXӮМҲЯ—ЮӮЖҒAҸӯҒXӮМҗH—ҝӮЖҒAҗ”ҚыӮМ–{ӮЖҒA•K—vҚЕ’бҢАӮМҗҙҢү—p•iӮЖҒAҗQ‘ЬҲкҺ®ӮЖҒAӮҪӮӯӮіӮсӮМӮЁӢаӮрҺқӮБӮДҒAғTғ`ӮН—·ӮЙҸoӮҪҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғһ
Ғ@үДҒB
Ғ@–ШҒXӮН—НӢӯӮўҒB”ZӮў—ОӮӘ—DӮөӮӯ—hӮкҒAүМӮӨҒBӮ»ӮкӮЙҚҮӮнӮ№ӮД’ЈӮи•tӮўӮҪҗд’BӮӘ•sҠн—pӮЙӢ©ӮФҒB•—ӮН‘“ӮӯҒAҚЕҸүӮ©ӮзҺ©—RӮИӮМӮҫӮЖҢҫӮнӮсӮОӮ©ӮиӮЙ—VӮС—xӮйҒBӢуӮНҒAӮҪӮҫӮЗӮұӮЬӮЕӮаӢCӮЬӮЬӮЙҗВӮўҒB
Ғ@ӮЩӮЖӮсӮЗӮМҗlҠФӮНҒAӮ»ӮкӮзӮЙӢ»–ЎӮрҺқӮҪӮИӮўҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғһ
Ғ@—БӮөӮўҒBӮўӮВӮЬӮЕӮаҒAӮұӮМҠCӮЖҗмӮМ—¬ӮкӮЙҺЁӮрҗҹӮЬӮөӮДӮўӮҪӮўҒBӢуӢCӮаҒAӮЁӮўӮөӮўҒBғRғ“ғNғҠҒ[ғgғWғғғ“ғOғӢ“ъ–{ӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйӮӘҒA•—ҸоӮаҺcӮБӮДӮўӮйӮсӮҫӮИҒBҠOӮНҒAҗўҠEӮНҒAӮвӮНӮиҚLӮўҒB–lӮН–{“–ӮЙӢ·ӮўӢуҠФӮЕҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮҪӮсӮҫӮИӮҹҒEҒEҒEҒB
ӮжӮөҒAӮаӮӨӮөӮОӮзӮӯҒAӮөӮОӮзӮӯҚҹҸҲӮЙӮўӮжӮӨӮ©
Ғ@Ҳкҗl—·ҒBӮ»ӮкӮрҚЎ–lӮНӮөӮДӮўӮйҒBӮИӮсӮ©ҒAӮұӮӨҒA‘ЮӢьӮҫҒBӮЁӮ¶ӮўӮіӮсӮ©ӮзҺ‘ӢаӮН’ёӮўӮҪӮ©ӮзӢаҢҮӮНӮ ӮиӮҰӮИӮўӮөҒA“№ӮЙ–АӮБӮҪӮиӮЖӮвӮҪӮзӮЖҚўӮБӮҪӮзҒAғlғbғgғJғtғFӮЙҚsӮҜӮОӮ·Ӯ®ӮЙүрҢҲӮ·ӮйҒBӮөӮ©ӮаӮ»ӮұӮЕҲк”УӮрүЯӮІӮ№ӮйӮөҒAҗHҺ–ӮаҸoӮДӮӯӮйҒBӮЁӮЬӮҜӮЙӮИӮЙӮ©ӮЖӮЁӮўӮөӮўӮ©ӮБӮҪӮиӮ·ӮйҒBӮ·ӮІӮўҺһ‘гӮҫҒB–{“–ӮЙҒB
Ғ@ӮөӮ©Ӯө•Ц—ҳӮИҗўӮМ’ҶӮМӮ№ӮўӮЕҒA–lӮНҚЎүЙӮрҺқӮД—]ӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮМ–өҸӮҒB—·ӮЖӮўӮҰӮОҗlҒXӮЖӮМ‘fҗ°ӮзӮөӮўҸoүпӮўӮӘ‘зҢн–ЎӮЖҺvӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮаҚЎӮМӮЖӮұӮлӮИӮўҒBӮөӮеӮӨӮӘӮИӮўӮ©ӮзҺ©•ӘӮ©ӮзҗәӮрӮ©ӮҜӮДӮЭӮДӮаҒA‘ҠҺиӮНӢ^ҳfӮМ–ЪӮЕ–lӮЖҳbӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮӘҠЫҢ©ӮҰӮҫҒBҸз’kӮрҢҫӮБӮДӮаҸоӮМӮИӮўҸОӮўӮр•ФӮөӮДӮӯӮйҒBҢӢӢЗ‘јҗlӮМӮЬӮЬӮЕ•КӮкӮДӮөӮЬӮўҒAҢЬ•ӘҢгӮЙӮН‘ҠҺиӮМҠзӮіӮҰ–YӮкӮйҒBғtғҢғ“ғhғҠҒ[ӮЙҗәӮрӮ©ӮҜӮДӮӯӮкӮйҗlӮаӮўӮйӮӘҒAӮ»ӮўӮВӮНӮҪӮҫӮМғ`ғ“ғsғүӮҫӮБӮҪӮиӮ·ӮйҒBҚЕҸI“IӮЙӮН–Ъ“IӮН–lӮЕӮНӮИӮӯӮДӢаӮҫӮБӮҪӮМӮҫҒB
Ғ@ӢЙ’[ӮИҺһ‘гӮҫҒB–{“–ӮЙҒB
Ғ@ӮБӮЖӮұӮсӮИҠҙӮ¶ӮЕҺ©–вҺ©“ҡӮр–lӮНҠC‘ҠҺиӮЙӮөӮДӮўӮйҒBӢ•ӮөӮўҒBӮаӮӨӮЗӮкӮӯӮзӮўҺһҠФӮӘҢoӮБӮҪӮҫӮлӮӨӮ©ҒB‘ҫ—zӮМӮ№ӮўӮЕҒA“ӘӮӘ”MӮўҒB
Ғ@ӮИӮсӮ©ӮаӮӨҒA–YӮкӮҪӮўүЯӢҺӮЖӮ©ӮаҺvӮўҸoӮ№ӮИӮўӮИҒBӮўӮўӮұӮЖӮҫӮҜӮЗҒBӮ»ӮкӮрӢҒӮЯӮДӮўӮйҺ©•ӘӮаӮўӮДҒAӮ»ӮкӮӘҺ©‘RӮИӮнӮҜӮЕҒA•sҚKӮ ӮиӮ«ӮМҚKӮИӮұӮБӮДҒEҒEҒE
Ғ@ӮсҒH
Ғ@ҺqӢҹҒHҸ—ӮМҺqӮ©ҒBӮұӮсӮИ•l•УӮЙҲкҗlӮЕӮ©ҒBӮИӮсӮ©үцӮөӮўӮИӮҹҒB
Ғ@Ӯ ӮўӮвҒAҸ—җ«Ӯ©ҒB
Ғ@–lӮМӮҝӮеӮБӮЖҚ¶җжӮЙҒAӮ»ӮМҺqӮНӮўӮҪҒB”g‘ЕӮҝҚЫӮЕҒAүEҺиӮЙ–ШӮМ–_ӮрӮВӮ©ӮЭӮИӮӘӮз”gӮрҗШӮБӮДӮўӮйҒB•һ‘•ӮНҸӯӮө—cӮўӮЖӮўӮӨӮ©ҒA’n–ЎӮЕӮ ӮйҒBӮҜӮЗҠзӮН‘еҗlӮМ•өҲНӢCӮӘӮ ӮйҒB”ҜӮНҢЁӮЬӮЕӮМ’·ӮіҒB’ҶҠwӮМҢіғJғmӮрҺvӮўҸoӮөӮҪҒBӮӯӮйӮФӮөӮЬӮЕҠCҗ…ӮӘҗZӮ©ӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮҫҒBӮ»ӮМҺqӮНӮёӮБӮЖҸОҠзӮЕҠCӮЖӢYӮкӮДӮўӮйҒB
Ғ@җі’јҒAӢCҺқӮҝҲ«ӮўҒB
Ғ@ӮӘҒAҺдӮ©ӮкӮйҒB
Ғ@Ӯ»ӮМҗlӮН”ьҗlӮЕӮ ӮБӮҪӮ©ӮзҒB
Ғ@ҸӯҒXӮМ—EӢCӮрҗUӮиҚiӮБӮДҳbӮөӮ©ӮҜӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒB–lӮМӢҒӮЯӮДӮўӮҪҒuҸoүпӮўҒvӮМӢ@үпӮӘҒAҚЎ–KӮкӮҪҒB
ҒuӮұҒAӮұӮсӮЙӮҝҒEҒEҒEҒv
ҒuӮ«ӮбӮБҒv
Ғ@‘ҠҺиӮНӢCӮГӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒB
ҒuӮ ҒAӮІӮЯӮсӮИӮіӮўҒB”GӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪӮ©ҒHҒv
ҒuӮ ҒA‘еҸд•vӮЕӮ·ҒEҒEҒEҒv
ҒuӮ·ӮўӮЬӮ№ӮсҒv
ҒuӮўӮҰҒA‘еҸд•vӮЕӮ·Ғv
ҒEҒEҒE
Ғ@
ҒuӮҰӮҘӮЖҒAҸӢӮўӮЕӮ·ӮЛҒv
ҒuӮ»ӮӨӮЕӮ·ӮЛҒv
ҒuҲкҗlӮЕүҪӮөӮДӮўӮйӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
ҒuӮӨӮсҒBӮҝӮеӮБӮЖ”YӮЭӮӘҒv
ҒuӮ»ӮӨӮЕӮ·Ӯ©ҒB–lӮаҒA“ҜӮ¶ӮжӮӨӮИӮаӮМӮЕӮ·Ғv
ҒuӮ ӮИӮҪӮНҒHҒv
ҒuӮ ҒA–lӮНӮИӮсӮЖӮўӮӨӮ©ҒA—·ӮрҒv
ҒuӮЦӮҘҒBӮ»ӮкӮ¶ӮбҺ„ӮЖ“ҜӮ¶ӮЕӮ·ӮЛҒv
ҒuӮ»ӮӨӮИӮсӮЕӮ·Ӯ©Ғv
ҒuӮ ӮМҒEҒEҒEҚӮҚZҗ¶ӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
ҒuӮ ҒAӮНӮўҚӮ“сӮЕӮ·ҒBӮ ӮИӮҪӮаӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
ҒuӮ»ӮкӮа“ҜӮ¶ӮЛҒv
Ғ@ӮвӮБӮЖҸОҠзӮрҢ©Ӯ№ӮҪҒBҸӯӮөҲАҗSӮөӮҪҒB•ПӮИҗlӮЕӮНӮИӮіӮ»ӮӨӮҫҒB
ҒuӮ ӮИӮҪӮНҒEҒEҒEӮЖӮўӮӨӮ©ҒA–ј‘O•·ӮўӮДӮаӮўӮўӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
”ЮҸ—ӮНҚ»ӮЙ–ј‘OӮрҸ‘ӮўӮҪҒB
–lӮМ–ј‘OӮрҒB
ҒuӮҰӮҘҒIҒHҒv
ҒuӮҰӮБҒvҸ—җ«ӮНҗГӮ©ӮЙӢБӮўӮҪҒB
ҒuӮҰӮБҒEҒEҒEӮҰҒ[ӮЖӮҰҒ[ӮЖҒAӮ ӮкҒHҒv
ҒuӮ ӮМҒEҒEҒEүҪӮ©ҒHҒv
Ғuғ„ғ}ғJғҸҒEҒEҒEғRғEҒHҒv
ҒuӮўӮҰҒAғTғ`ӮЕӮ·ҒvҸОӮБӮҪҒB
Ғ@ӮөӮОӮөӮМҚ¬—җҢгҒAӮжӮӨӮвӮӯӮҪӮБӮҪҚЎғ~ғүғNғӢӮӘӢNӮ«ӮҪӮұӮЖӮр’mӮБӮҪҒB
Ғ@ӮЬӮіӮ©ҒA“Ҝҗ©“Ҝ–јӮЕҒAҚОӮаҒAӮЖӮўӮӨӮ©ҒAҸз’kӮЕ•·ӮўӮҪҗ¶”NҢҺ“ъӮаҒAӮұӮұӮЙӮўӮй–Ъ“IӮа“ҜӮ¶ӮҫӮЖӮНҒB
ӮөӮ©ӮөҸ—җ«ӮНҒEҒEҒEғTғ`ӮіӮсӮНӮ ӮЬӮиӢБӮўӮҪ—lҺqӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮжӮиӮаӮіӮБӮ«ҢҫӮБӮДӮўӮҪ”YӮЭӮЙӮжӮБӮДҚЎӮӘҢ©ӮҰӮДӮўӮИӮўӮжӮӨӮҫҒBҠCӮрҒAӮўӮвӮ»ӮМҗжӮМү“ӮӯӮр’ӯӮЯӮҪӮЬӮЬӮҫҒBӮұӮМҢгҢЬ•ӘӮЩӮЗӮЁҢЭӮўӮЙӮВӮўӮДҳbӮрӮөӮҪҒBӮЖӮўӮБӮДӮаӮЩӮЖӮсӮЗ–lӮӘҲк•ы“IӮЙҳbӮөҺиӮЕҒAғTғ`ӮіӮсӮН•·Ӯ«ҺиӮҫӮБӮҪҒB’ӘӮМҚҒӮиӮМ’ҶҒAӮРӮ®ӮзӮөӮМҗәӮрү“ӮӯӮЙҒA‘ҫ—zӮНҗFӮр•ПӮҰҒA—[“ъӮЦӮЖҺpӮр•ПӮҰҺnӮЯӮҪҒBӮ»ӮкӮрҒAғTғ`ӮіӮсӮН‘Ҡ•ПӮнӮзӮёӮёӮБӮЖ’ӯӮЯӮДӮўӮҪҒB
ҒuгY—нҒvғ|ғcғҠӮЖҷкӮўӮҪҒB
ҒuӮЩӮсӮЖҒA”nҺӯӮЭӮҪӮўҒvӮЬӮҪғ|ғcғҠҒB
Ғ@–lӮНҳb‘иӮр•ПӮҰӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒB
Ғu’n•ҪҗьӮӘүҪҢМҠЫӮӯҢ©ӮҰӮйӮ©’mӮБӮДӮйҒHҒv
Ғu’nӢ…ӮӘҠЫӮўӮ©ӮзӮЕӮөӮеҒvҺӢҗьӮр•ПӮҰӮИӮўӮЬӮЬ“ҡӮҰӮҪҒB
ҒuӮ»ӮкӮБӮДӮЛҒAҺАӮНғ_ғEғgӮИӮсӮҫҒB’nӢ…Ӯ¶ӮбӮИӮӯӮДҒA–ЪӮӘҠЫӮўӮ©ӮзӮ»ӮӨҢ©ӮҰӮДӮөӮЬӮӨӮсӮҫҒB–ЪӮМҚцҠoӮЙӮжӮБӮДҒAү“ӮӯӮМҗ^ӮБ’јӮ®ӮИҗьӮаҠФҲбӮБӮД”FҺҜӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӮЬӮ ӮұӮкӮНғTғ`ӮіӮсӮЙӮНҠЦҢWӮИӮўӮ©Ғv
ҒuғTғ`ӮЕӮўӮўӮжҒBғRғEҢNҒvҸӯӮөҸОӮБӮҪҒB
ҒuӮ¶ӮбҒAғTғ`ӮағRғEӮЖҢДӮсӮЕӮўӮўӮжҒvӮвӮБӮЖӢ——ЈӮӘӢЯӮӯӮИӮБӮҪӢCӮӘӮ·ӮйҒB
Ғu“ӘҒAӮўӮўӮсӮҫӮЛҒBӮЖӮўӮӨӮ©ҒAӮЖӮДӮаҢbӮЬӮкӮДҲзӮБӮҪҠҙӮ¶ӮӘӮ·ӮйҒv
Ғ@үsӮўҒBӮӘҒAҲбӮӨҒB
ҒuӮҫӮўӮҪӮў“–ӮҪӮБӮДӮйӮ©ӮаҒBғTғ`ӮаҒAӮ»ӮсӮИҠҙӮ¶ӮӘӮ·ӮйӮИҒB–ј‘OӮ©ӮзӮөӮДҒv
ҒuӮ»ӮкӮНҲбӮӨӮнҒv—НӮрҚһӮЯӮДҢҫӮнӮкӮҪҒBӮҝӮеӮБӮЖӮСӮСӮБӮҪҒB
ҒuӮҜӮЗҒA–ј‘OӮМ’КӮиҒAҚKӮ№ӮЙҲзӮБӮҪҒEҒEҒEӮ©ӮаҒv
Ғ@—[“ъӮӘҚЎҒA’ҫӮсӮҫҒBүД–йӮМҺһҠФӮҫҒB–lӮНӮаӮӨҸӯӮөҳbӮӘӮөӮҪӮ©ӮБӮҪҒBғTғ`ӮНүҪӮ©Ӯр”йӮЯӮДӮўӮйӮНӮёӮҫҒBӮҫӮ©ӮзҺдӮ©ӮкӮҪҒBӮұӮкӮНҒA—цӮЖӮНҲбӮӨҒB
Ғ@–lӮӘ“ҡӮҰӮрҢ©ӮВӮҜӮйӮҪӮЯӮЙҒAҳbӮӘӮөӮҪӮ©ӮБӮҪҒB
Ғ@ӮҜӮЗҒAғTғ`ӮН–lӮрҢ©ӮДӮўӮИӮўӮЖҺvӮӨҒBүҪӮ©Ӯр’TӮөӮДӮўӮйӮ©ӮзҒBӮҫӮ©Ӯз–lӮМӮұӮЖӮрҺЧ–ӮӮЙҺvӮБӮДӮўӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮҫӮ©ӮзҺқӮБӮДӮўӮҪҢg‘СҗH•iӮЖғnғ“ғJғ`ӮрӮ Ӯ°ҒAӮұӮМӮЬӮЬ•КӮкӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒB•s–{ҲУӮҫӮӘҒAӮ»ӮӨӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒB
ҒuӮаӮӨҸӯӮөҒAҳbӮрӮөӮИӮўҒHҒv
Ғ@ғTғ`ӮН–lӮМ”w’ҶӮЙӮ»ӮӨҢҫӮБӮҪҒB
Ғ@Ӣф‘RӮЙӮаҒAҚЎ“ъӮНӮұӮМ‘әӮМҢц–ҜҠЩӮЕӮЁҚХӮиӮӘӮ ӮйҒBӮРӮ®ӮзӮөӮМ•ПӮнӮиӮЙҚХӮи‘ҫҢЫӮӘ•·ӮұӮҰӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB–lӮзӮНӮ»ӮМү№Ӯр—ҠӮиӮЙҢц–ҜҠЩӮЦӮЖҸкҸҠӮр•ПӮҰӮҪҒBҗЬӮиӮҪӮҪӮЭҺ®ӮМғeҒ[ғuғӢӮӘҠOӮЙ•АӮЧӮзӮкӮДӮЁӮиҒAӮ»ӮұӮЙ–јӮа’mӮзӮКҗlҒXӮӘғrҒ[ғӢӮр•РҺиӮЙҚLҸкӮрҢ©ӮИӮӘӮзҗ·ӮиҸгӮӘӮБӮДӮўӮйҒBҚLҸкӮЙӮН‘еӮ«ӮИ‘ҫҢЫӮӘҲкӮВӮ ӮиҒA“`“қ“IӮИӮЁ–КӮрӮ©ӮФӮБӮҪҗlӮӘқӣӮрҺқӮҝӮИӮӘӮз—xӮБӮДӮўӮйҒBҺqӢҹ’BӮНӮ»ӮсӮИӮМӮрҢ©ҢьӮ«ӮаӮ№ӮёӮЙӮ ӮҝӮұӮҝӮЕӮНӮөӮбӮўӮЕӮўӮйҒB
Ғ@–lӮЖғTғ`ӮНҢц–ҜҠЩӮМӢЯӮӯӮМғxғ“ғ`ӮЕҲщӮЭ•ЁӮрҲщӮЭӮИӮӘӮзҳbӮМ‘ұӮ«ӮрӮөӮҪҒBҚЎ“xӮНғTғ`ӮӘҳb‘иӮрӮУӮБӮДӮ«ӮҪҒB
ҒuӮұӮұӮЙ—ҲӮй‘OӮЙӮЛҒAӮЁ•ғӮіӮсӮӘӮўӮйҢY–ұҸҠӮЙҚsӮБӮДӮ«ӮҪӮсӮҫҒv
ҒuӮҰӮБҒAҢY–ұҸҠҒHҒv
ҒuӮӨӮсҒBҺ„ӮӘҸ¬ӮіӮўҚ ӮЙҒAҚЯӮр”ЖӮөӮҪӮзӮөӮўҒBҺ„ӮНӮжӮӯҠoӮҰӮДӮўӮИӮўӮҜӮЗҒv
Ғ@ҢbӮЬӮкӮДҲзӮБӮҪӮжӮӨӮЙҢ©ӮҰӮйӮЖҢҫӮБӮҪҗуӮНӮ©ӮИҺ©•ӘӮЙ• ӮӘ—§ӮБӮҪҒBӮ»ӮсӮИҒAӮ¶ӮбӮ ӮұӮМҗlӮН•Ғ’КӮЙҲзӮБӮҪӮНӮёӮИӮўӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒBӮЮӮөӮлҒAҗўҠФ“IӮЙӮНҒEҒEҒE
ҒuӮ»ӮкӮЕӮЛҒvҳbӮН‘ұӮўӮҪҒB
ҒuӮўӮ«ӮИӮиӮН–і—қӮҫӮБӮҪӮҜӮЗҒAӮ«ӮҝӮсӮЖ–КүпӮЕӮ«ӮҪӮМҒBӮИӮсӮ©ӮЁ•ғӮіӮсӮН•EӮЖӮ©ӮаӮ¶ӮбӮаӮ¶ӮбӮЕҒAӮвӮБӮПӮиҺ„ӮМ’ҶӮЙӮўӮйӮЁ•ғӮіӮсӮЖӮН‘SӮӯҲбӮБӮДӮўӮҪҒBӮЬҒA“–ӮҪӮи‘OӮҫӮҜӮЗӮЛҒBӮЁ•ғӮіӮсӮНӮёӮБӮЖӢғӮ«ӮБӮПӮИӮөӮЕҒwӮ·ӮЬӮсҒAӮ·ӮЬӮсҒxӮБӮДӮёӮБӮЖӢғӮ«ӮИӮӘӮзӮ»ӮӨҢҫӮБӮДӮҪҒBҲк‘М’NӮЙҺУӮБӮДӮўӮҪӮМӮ©ӮөӮзӮЛҒvғTғ`ӮНҸӯӮөҹT“©ӮөӮ»ӮӨӮЙҷкӮўӮҪҒB
Ғ@ҢY–ұҸҠӮБӮДҒcҚЯӮр”ЖӮөӮҪӮБӮДӮұӮЖӮҫӮлӮӨҒBӮ»ӮМҒAғTғ`ӮМӮЁ•ғӮіӮсӮӘҒB“–ӮҪӮи‘OӮ©ҒBӮ»ӮӨӮИӮсӮҫӮҜӮЗҒAӮЗӮӨӮөӮДӮаҺуӮҜ“ьӮкӮзӮкӮИӮўҒBӮұӮсӮИҗГӮ©ӮИҗlӮМҗeӮӘҚЯӮрҒc
Ғ@ӮБӮДҒAүҪӮрҢҫӮБӮДӮўӮйӮсӮҫ–lӮНҒB”ЮҸ—ӮЖҺEҗlӮНҠЦҢWӮИӮўӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒBҒcӮИӮЙҸҹҺиӮЙҢҲӮЯ•tӮҜӮДӮўӮйӮсӮҫҒcӮаӮӨҒc
Ғ@җуӮНӮ©ӮҫҒB–lӮН–{“–ӮЙ–ўҸnӮҫҒB–lҺ©җgӮӘҸҹҺиӮЙҢҲӮЯ•tӮҜӮзӮкӮйӮұӮЖӮрҢҷӮӘӮБӮДӮҪӮМӮЙҒAӮ»ӮкӮр‘јҗlӮЙӮөӮжӮӨӮҫӮИӮсӮДҒc
ҒuӮЛӮҰҒB‘еҸд•vҒHҒv–lӮН‘Ҡ“–ҺvӮўӮВӮЯӮДӮўӮҪӮзӮөӮўҒBғTғ`ӮӘ–lӮрҢ©ӮДӮўӮҪҒB
ҒuӮ ҒAӮӨӮсҒBҸӯӮөӢБӮўӮҝӮбӮБӮҪҒBӮІӮЯӮсҒv
ҒuӮӨӮӨӮсҒBӮўӮ«ӮИӮиӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮрҳbӮіӮкӮДӮНӮ»ӮӨӮИӮйӮжҒv
ҒuӮИӮсӮЕҒAӮ»ӮкӮр–lӮЙҒHҒv
ҒuӮҰҒHҒv
ҒuӮИӮсӮЕҒAӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮр–lӮЙ•·ӮўӮҪӮМҒHҒv
ҒuҒc•КӮЙҒBӮҪӮҫӮИӮсӮЖӮИӮӯҒcӮ©ӮИҒv
ҒuҒcӮ ӮМӮіҒAҺё—зӮИӮұӮЖӮр•·ӮӯӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮҜӮЗҒAҢNӮНҒAүҪӮ©ӮрҠъ‘ТӮөӮДӮўӮйҒHҒv
ҒuҒcҒv
Ғ@ӮөӮОӮзӮӯӮМҠФҒAғTғ`ӮН–ЩӮБӮҪҒBҳлӮ«ӮИӮӘӮзҒAүҪӮ©ӮрҚlӮҰӮДӮўӮйӮжӮӨӮҫӮБӮҪҒB–lӮН”ЮҸ—ӮӘ“{ӮБӮҪӮМӮ©ӮЖҺvӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮМӮжӮӨӮИ—lҺqӮНҢ©ҺуӮҜӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB–lӮН“ҡӮҰӮр‘ТӮБӮҪҒB
Ғ@ү“ӮӯӮ©Ӯз•·ӮұӮҰӮйӮРӮ®ӮзӮөӮМү№ӮӘ•·ӮұӮҰӮИӮӯӮИӮБӮҪҒB
ҒuӮӨӮсҒcҒBӮ»ӮӨӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒvҳлӮ«ӮИӮӘӮзӮдӮБӮӯӮиӮЖ“ҡӮҰӮҪҒB
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒAӮ»ӮкӮНҒAүҪҒHҒv–lӮНҗі’јӢ°ӮйӢ°Ӯй•·ӮўӮҪҒB–lӮН“ҡӮҰӮрҗі’ј•·Ӯ«ӮҪӮӯӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮИӮсӮЖӮИӮӯӮнӮ©ӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮ©ӮзӮҫҒB
җдӮМү№ӮӘ•·ӮұӮҰӮИӮӯӮИӮБӮҪҒB
ҒuӢM•ыӮНҒAҚKӮ№ҒHҒv
Ғ@ҲкҸuҒAү№ӮӘҸБӮҰӮҪҒB
ҒcӮҰҒH
Ғ@ҚЎҒAӮИӮсӮДҢҫӮБӮҪҒH
Ғ@ғAғiғ^ғnҒAғVғAғҸғZҒH
Ғ@“ҜҸоӮЖӮ©ҒAҲФӮЯӮЖӮ©ҒAӮ»ӮӨӮўӮӨӮаӮМӮрӢҒӮЯӮДӮўӮҪӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮМӮ©ҒHӮұӮМҗlӮНҒB
Ғ@ӮўӮвҒAӮ»ӮкӮжӮиӮаҒc
Ғ@үҪҢМӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮр–lӮЙ•·ӮӯҒH
Ғ@үҪҢМҒA–lӮМ—·ӮМ–Ъ“IӮрҒA’mӮБӮДӮўӮйҒcҒH
Ғ@’№”§ӮӘ—§ӮБӮҪҒBӮұӮМҗlӮНҒA–lӮМҗSӮрҢ©ӮДӮўӮйӢCӮӘӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮӘ•|ӮӯӮИӮБӮҪҒB—вҗГӮіӮрҺжӮи–ЯӮөӮҪӮЖӮ«ӮЙӮНӮ·ӮЕӮЙӮ·ӮЧӮДӮМү№ӮӘ•·ӮұӮҰӮДӮўӮҪҒB
Ғ@ғTғ`ӮН–lӮрӮЬӮБӮ·Ӯ®Ң©ӮВӮЯӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМ•\ҸоӮНҒAҲкҸu“VҺgӮИӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮБӮҪӮЩӮЗгY—нӮҫӮБӮҪҒB–lӮНүд–қӮЕӮ«ӮёӮЙҳлӮўӮҪҒBҠзӮНҗФӮ©ӮБӮҪҒBҗS‘ҹӮМү№ӮӘ•·ӮұӮҰӮҪҒBӮұӮМҠҙҠoӮНӮ»ӮӨҒA—ӨҸгӮМҺҺҚҮӮЕғXғ^Ғ[ғg’n“_ӮЙ’…ӮӯӮЖӮ«ӮЖ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮИҠҙҠoӮҫҒBӢЩ’ЈӮЙӮжӮБӮДҒAҲУҺuӮНӮ ӮЬӮиӮИӮўӮМӮЙ–іҲУҺҜӮЙ‘МӮӘ“®ӮўӮДӮўӮйҒBӮ»ӮсӮИҠҙҠoӮҫҒB
Ғu‘еҸд•vҒHҒvғTғ`ӮМҸӯӮө‘еӮ«ӮўҗәӮЙӢCӮГӮўӮДҒAӮ»ӮМҠҙҠoӮНӮдӮБӮӯӮиӮЖүрӮ©ӮкӮҪҒB
ҒuҒcӮ ҒAӮӨӮсҒBӮІӮЯӮсҒv
ҒuӮіӮБӮ«Ӯ©ӮзҺ„ӮӘүҪӮ©ҢҫӮӨӮҪӮСӮЙҺ~ӮЬӮБӮДӮйӮҜӮЗҒAӮИӮсӮ©Ҳ«ӮўӮұӮЖӮЕӮаҢҫӮБӮҪҒHҒv
ҒuӮўӮвҒAҸӯӮөӢБӮўӮДҒv
ҒuӮЬӮҪҒHҒcӮУӮУӮБҒBӮИӮсӮ©ғRғEӮБӮДӮЁӮаӮөӮлӮўӮЛҒv
Ғ@–lӮН–ЩӮБӮДӮўӮйӮөӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuӮЕҒHҚKӮ№ҒHҒvғTғ`ӮНҢJӮи•ФӮө•·ӮўӮДӮ«ӮҪҒB
Ғ@Ғc
Ғ@ҒcҳbӮөӮДӮЭӮжӮӨӮ©ҒB
ҒuӮсҒAӮўӮвӮ ҒAӮЬӮ ҒAӮ»ӮкӮрҠmӮ©ӮЯӮйӮҪӮЯӮЙ—·ӮрӮөӮДӮўӮйӮжӮӨӮИӮаӮМӮИӮсӮҫӮжӮЛҒBҺАӮНҒv
Ғ@үBӮ·•K—vӮаӮИӮўӮөҒAӮЁҢЭӮў—lӮҫӮлӮӨӮЖҺvӮБӮДҒA–lӮНӮ»ӮұӮ©ӮзҺ©•ӘӮМӮұӮкӮЬӮЕӮМӮұӮЖӮвҒAҺ©•ӘӮӘ”YӮсӮЕӮўӮйӮұӮЖӮвҒAӮ»ӮкӮрүрҢҲӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҚЎҺ©•ӘӮН—·ӮрӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮИӮЗӮрҲкӢCӮЙҳbӮөӮҪҒBҳbӮр•·ӮўӮДӮўӮйӮЖӮ«ӮМғTғ`ӮНүёӮвӮ©ӮИ•\ҸоӮрӮөӮДӮўӮҪҒBҺһҠФӮр–YӮкҒAҺ©•ӘӮЕӮаӮСӮБӮӯӮиӮ·ӮйӮЩӮЗӮЧӮзӮЧӮзӮЖҳbӮөӮҪҒBғTғ`ӮИӮз“ҡӮҰӮрӢіӮҰӮДӮӯӮкӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮ»ӮӨҠъ‘ТӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮҫӮЖҺvӮӨҒB
Ғ@Ҳк’КӮиҳbӮөҸIӮҰӮйӮЖҒAҚAӮӘҠүӮўӮҪҒBү®‘дӮЕӮИӮЙӮ©ҲщӮЭ•ЁӮр”ғӮБӮДӮӯӮйӮЖҢҫӮБӮДғxғ“ғ`Ӯ©ӮзҚҳӮрӮ Ӯ°ӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮЖӮ«ҒA–ЪӮМ‘OӮЙҢ©’mӮзӮКӮЁӮОӮ ӮіӮсӮӘӮўӮҪҒBҚҳӮӘӮЩӮЪӮXӮO“xӮЙӢИӮӘӮБӮДӮўӮДҒA—јҺиӮЕҸсӮЙӮ·ӮӘӮБӮДӮўӮҪҒB–lӮЖ–ЪӮӘҚҮӮӨӮЖӮЙӮұӮиӮЖӮөӮДҒAҗkӮҰӮҪҺиӮЕ–lӮЙғWғ…Ғ[ғXӮр“nӮөӮҪҒBҲкӮВӮҫӮҜӮҫӮБӮҪҒBӮЁӮОӮ ӮіӮсӮНӮөӮОӮзӮӯӮ»ӮМҸкӮЙ–ЩӮБӮД–lӮрӮЬӮ¶ӮЬӮ¶ӮЖҢ©ӮВӮЯӮҪҒBҢЛҳfӮўӮИӮӘӮзӮаҒuӮ ӮиӮӘӮЖӮӨӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒvӮЖҢҫӮӨӮЖҒAҸ¬ӮіӮИҗәӮЕ
ҒuӮўӮёӮкҒAӮЬӮҪҒvӮЖҢҫӮБӮДӮдӮБӮӯӮиӮЖ—§ӮҝӢҺӮБӮДӮўӮБӮҪҒB
Ғ@Ғc
ҒuӮИӮсӮ©ҒAӮаӮзӮБӮҝӮбӮБӮҪӮжҒvӢкҸОӮўӮөӮИӮӘӮз–lӮӘҢҫӮӨӮЖҒAғTғ`ӮНҒuӮ»ӮӨӮўӮӨӮаӮМӮИӮМӮжҒvӮЖ”чҸОӮсӮҫҒBҺ„ӮН”ғӮўӮЙҚsӮӯӮнӮЖү®‘дӮЙҚsӮұӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕҒA–lӮНӮЁӮОӮ ӮіӮсӮ©ӮзӮаӮзӮБӮҪғWғ…Ғ[ғXӮр“nӮ»ӮӨӮЖӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯө”ЮҸ—ӮНҠжӮИӮЙӮ»ӮкӮр’fӮБӮҪҒBҢӢӢЗ”ЮҸ—ӮНҒuҺ„ӮНӮ»ӮкӮрҗв‘ОӮЙҲщӮЮӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўӮМҒBҗв‘ОӮЙӮЛҒvӮіӮзӮиӮЖӮ»ӮӨҚҗӮ°ӮДҒAү®‘дӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒBӮаӮзӮБӮҪғWғ…Ғ[ғXӮН’YҺ_Ҳщ—ҝӮҫӮБӮҪҒBӮҫӮ©Ӯз’YҺ_ӮНҲщӮЯӮИӮўҗlӮИӮМӮҫӮлӮӨӮЖҒA–lӮН–і—қӮвӮи”[“ҫӮөӮҪҒB
Ғ@ҚХҡ’ҺqӮЖ‘ҫҢЫӮМү№ӮӘ‘еӮ«ӮӯӮИӮБӮДӮ«ӮҪҒBҲЕӮНӮҫӮсӮҫӮсӮЖӮұӮМ’¬ӮрҺx”zӮөӮҫӮөӮҪҒB–lӮЖғTғ`ӮНҲкҸҸӮЙғWғ…Ғ[ғXӮрҲщӮсӮҫҒB
ҒuӮіӮБӮ«ӮМҳbӮМ‘ұӮ«ӮҫӮҜӮЗҒvҲꑧӮўӮкӮҪӮ ӮЖҒAғTғ`ӮӘҳbӮөҸoӮөӮҪҒB
Ғuҗі’јҒAҚKӮ№ӮӘүҪҸҲӮЙӮ ӮйӮ©ӮИӮсӮДҒAҺ„Ӯ©ӮзӮНҢҫӮҰӮИӮўӮнҒBӮҝӮбӮсӮЖ‘¶ҚЭӮНӮ·ӮйӮЖҺvӮӨӮнҒBӮҜӮЗӮЛҒAҺ„ӮӘҚҹҸҲӮЙӮ ӮйӮЖҢҫӮБӮДӮаҒAӮ»ӮкӮӘҠm’иҺ–ҚҖӮҫӮЖӮНҢАӮзӮИӮўҒBҢҫӮБӮДӮөӮЬӮҰӮОҒAӮЁӮ»ӮзӮӯғRғEӮНӮ»ӮкӮМӮЭӮӘ“ҡӮҰӮЖ’f’иӮөӮДӮөӮЬӮӨӮЖҺvӮӨӮМҒBҸӯӮөҒAҸЕӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮҫӮөҒBҺ„ӮН“ҡӮҰӮМ•қӮрӢ·ӮЯӮҪӮӯӮИӮўҒBӮВӮЬӮиҒAҚKӮ№ӮМҠоҸҖӮИӮсӮДҒAҗlӮ»ӮкӮјӮкӮБӮДӮұӮЖӮ©ӮИҒv
Ғ@ӮЬӮйӮЕ–lӮМҗSӮрҢ©“§Ӯ©ӮөӮИӮӘӮзӮМҢҫ—tӮЙҺvӮҰӮҪҒB–lӮНҒuӮИӮйӮЩӮЗҒEҒEҒEҒvӮЖӮҫӮҜ“ҡӮҰӮҪҒB
ҒuӮИӮсӮҫӮлӮӨҒcӮЖӮЙӮ©ӮӯҺАҠҙӮр“ҫӮй“ҡӮҰӮӘ—~ӮөӮўӮМӮ©ӮаҒv–lӮН‘ұӮҜӮҪҒB
ҒuӮжӮӯҒwҒ`ӮрӮөӮДӮўӮйҺһӮӘҲк”ФҚKӮ№ҒxӮЖӮ©ҢҫӮӨӮжӮЛҒBӮ ӮкӮБӮДҒAҒw—ЗӮўҺ–ҒxӮМӮЭӮӘҚKӮ№ӮЭӮҪӮўӮИҢҫӮў•ыӮЕӮөӮеҒBӮ»ӮкӮБӮДҒAӮ·ӮІӮӯӢ·ӮўҢ©ҺҜӮИӢCӮӘӮ·ӮйҒBӮаӮБӮЖҲбӮӨӮЖӮұӮлӮЙӮ ӮйӮЖҺvӮӨӮсӮҫҒBӮИӮсӮДӮўӮӨӮ©ҒAӮаӮБӮЖҚӘ–{“IӮИӮЖӮұӮлӮЙҒBӮ»ӮұӮрҚKӮ№ӮЖ–јӮГӮҜӮйӮЧӮ«ӮИӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮМӮ©ӮИӮҹӮБӮДҒBӮұӮкӮЬӮЕ—·ӮрӮөӮДӮ«ӮҪӮИӮ©ӮЕҒAӮ»ӮӨҺvӮҰӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒBӮұӮкӮӘҚҮӮБӮДӮўӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўӮҜӮЗҒBӮЕӮаӮіӮБӮ«ғTғ`ӮӘҢҫӮБӮҪӮжӮӨӮЙҒAҠоҸҖӮНҗlӮ»ӮкӮјӮкӮҫӮлӮӨҒH“ҡӮҰӮНҲкӮВӮҫӮҜӮЗҒAҺӢ“_ӮНҗlӮМҗ”ӮҫӮҜӮ ӮйӮЖҺvӮӨҒBӮҫӮ©Ӯз“ҡӮЬӮЕӮМ“№ӮНҒAҚмӮиҸoӮіӮИӮ«ӮбӮўӮҜӮИӮўӮ©ӮзҒAҗMӮ¶ӮИӮҜӮкӮОҺnӮЬӮзӮИӮўӮЖҺvӮӨҒv
Ғ@җі’јҺ©•ӘӮЕӮаүҪӮӘҢҫӮўӮҪӮўӮМӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒA“`ӮҰӮҪӮўӮұӮЖӮНҢҫӮҰӮҪӮжӮӨӮИӮ«ӮӘӮөӮҪҒBғTғ`ӮНҗ^Ң•ӮЙҺЁӮрҢXӮҜӮДӮӯӮкӮҪҒBӮ»ӮөӮД“ҡӮҰӮҪҒB
ҒuҚKӮ№ӮрҠҙӮ¶ӮйӮЙӮНӮіҒA•KӮёҚKӮ№ӮрҸҠ—LӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйҺА‘МӮӘ•K—vӮжӮЛҒBӮ»ӮкӮБӮДҒAӮВӮЬӮиҺ„ӮвғRғEӮМӮұӮЖӮЕӮөӮеҒBҗlҠФӮӘ•K—vӮБӮДӮұӮЖҒBӮВӮЬӮиҗlҠФӮӘӮўӮИӮҜӮкӮОҚKӮ№ӮЖӮўӮӨ‘¶ҚЭӮаӮИӮ©ӮБӮҪҒB“–ӮҪӮи‘OӮМӮұӮЖӮрҢҫӮБӮДӮйӮҜӮЗҒAӮұӮкӮБӮД‘еҺ–ӮҫӮЖҺvӮӨӮМҒBҗlҠФӮӘӮўӮИӮҜӮкӮО‘¶ҚЭӮөӮИӮўӮИӮзҒAҚKӮ№ӮНҗlҠФӮЙӮөӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўӮаӮМӮ¶ӮбӮИӮўҒv
ҒuӮҜӮЗҒAҚЎӮМғҢғ”ғFғӢӮ¶ӮбӮнӮ©ӮзӮИӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҗlҠФӮН“ъҒXҗiү»ӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘ‘O’сӮИӮзҒAӮаӮӨҸӯӮөҗжӮЙӮИӮБӮДӮ©ӮзӮ¶ӮбӮИӮўӮЖӮнӮ©ӮзӮИӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮЕӮаӮЛҒAҢ»‘гӮ©ӮзӮМҺӢ“_ӮҫӮЖҒA“NҠw“IӮИҠT”OӮБӮДҒAӮұӮМӮіӮ«Ӯ ӮЬӮи•ПӮзӮИӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮЩӮзҒAҚЎҗi•аӮөӮДӮйӮМӮНҒAүИҠwӮЖӮ©Ӯ»ӮӨӮдӮӨҒAӮЗӮБӮҝӮ©ӮЖҢҫӮӨӮЖ—қҢnӮМӮЩӮӨӮЕӮөӮеҒHҒv
Ғ@үҪӮрҢҫӮўӮҪӮўӮМӮ©ӮЬӮҪӮнӮ©ӮзӮИӮӯӮИӮБӮДӮ«ӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB
ҒuӮИӮсӮДӮўӮӨӮМӮ©ӮИҒB“№ӢпӮҫӮҜӮӘӮЗӮсӮЗӮс”м‘еү»ӮөӮДҒAү»ӮҜ•ЁӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮйӢCӮӘӮ·ӮйҒBҲк•ыӮ»ӮкӮрҲөӮӨҗlҠФҒA–l’BӮН•ПӮнӮБӮДӮўӮИӮўӮ©ӮзҒAӮ»ӮкӮзӮЙӮ ӮҪӮУӮҪӮөӮДӮўӮйҒBӢ»•ұӮөӮДӮўӮйҗlӮаӮўӮйҒB‘S‘МӮЖӮөӮДӮНҚ¬—җӮөӮДӮйҒBҚЎӮБӮДҒAӮ»ӮсӮИҺһ‘гӮИӢCӮӘӮ·ӮйҒBӮ»ӮМ’ҶӮЕӮұӮсӮИ’PҸғӮИҒwҚKӮ№ӮБӮДӮИӮЙӮ©ҒxӮИӮсӮДӮМӮрҢ©ӮВӮҜӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӮИӮсӮДҒA’ҶҗўӮМҲМҗl’BӮЙҸоӮҜӮИӮўӮБӮДҢҫӮнӮкӮ»ӮӨӮ©ӮаҒBӮўӮвҒAҗв‘ОҢҫӮнӮкӮйӮжҒv
ҒuӮ»ӮкӮИӮМӮЙҒA’TӮ·ӮМҒHҒv
ҒuӮӨӮсҒBӮИӮсӮ©ҒAӮЖӮЙӮ©ӮӯӮ·ӮБӮ«ӮиӮөӮИӮўӮМӮБӮДҢҷӮИӮсӮҫҒBӮ»ӮкӮЙҠ®‘SӮИ“ҡӮҰӮрӢҒӮЯӮжӮӨӮЖӮНӮөӮДӮИӮўҒBҺ©•ӘӮЕҢ©ӮВӮҜӮДҒAӮЖӮЙӮ©ӮӯҢӢҳ_ӮГӮҜӮҪӮўӮБӮДӮўӮӨӮЩӮӨӮӘӢӯӮўҒBүҙӮМӮЁ•ғӮіӮсӮӘҢҫӮБӮДӮҪӮсӮҫӮҜӮЗӮЛҒAҒw”YӮЮӮұӮЖӮр’pӮ¶ӮйӮИҒBӮЮӮөӮлжҗүМӮөӮлҒxӮЖӮ©ӮИӮсӮЖӮ©ҒB”YӮсӮЕҒAҢӢҳ_ӮрҸoӮөӮДҒAӮ»ӮкӮрӮЬӮҪ”Ы’иӮ·ӮйҺ–ҺАӮЙ‘ЕӮҝӮМӮЯӮіӮкӮД”YӮЯӮБӮДҒBӮёҒ[ӮБӮЖҲкүУҸҠӮЕ—§ӮҝҺ~ӮЬӮБӮДӮўӮДӮа–і‘КӮҫӮөҒAҗжӮрҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮҜӮИӮўӮјҒBӮЖӮаҢҫӮБӮДӮҪҒv
ҒuӮ»ӮӨҒcҒvғTғ`ӮН—DӮөӮӯ”чҸОӮсӮҫҒBӮ»ӮөӮДҒA
ҒuӮЕӮаҒAӮҝӮеӮБӮЖҸЕӮБӮҪӮЩӮӨӮӘӮўӮўӮ©ӮаҒvӮ»ӮӨҸӯӮөҚўӮБӮҪҠзӮЕҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮҰҒHӮЗӮӨӮөӮДҒHҒv
ҒuҒcҒv“ҡӮҰӮИӮўҒBҢҫ—tӮр‘IӮсӮЕӮўӮйӮжӮӨӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮўӮёӮкҒAӮнӮ©ӮйӮнҒv
Ӯ»ӮкӮБӮ«ӮиӮЁҢЭӮўӮЙ’ҫ–ЩӮөҒAғTғ`ӮЖӮМҠФӮЙӮИӮЙӮ©—вӮҪӮўӢуӢCӮӘ—¬ӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮИӢCӮӘӮөӮҪҒB”ЮҸ—ӮНҒA•sҺvӢcӮҫҒBҢ©ӮҪ–ЪӮНӮЖӮДӮаҸ¬ӮіӮўӮҜӮкӮЗҒA‘¶ҚЭҠҙӮН‘еӮ«ӮўҒB•өҲНӢCӮ©ӮзӮИӮМӮ©ҒBӮ»ӮкӮЙҒAӮіӮБӮ«Ӯ©ӮзҺһҒX•sүВүрӮИӮұӮЖӮрҢҫӮӨҒB
Ғ@Ӯ»ӮкӮНҒA–lӮрҢ©ӮҰӮИӮўҗәӮЕҢДӮсӮЕӮўӮйҠҙҠoӮЖҺ—ӮДӮўӮҪҒB
Ғ@ҠФӮр–„ӮЯӮйӮВӮаӮиӮЕҳbӮөӮ©ӮҜӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮӘҒAзSзOӮөӮҪҒBүҪӮрҢҫӮҰӮОӮўӮўӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBҢҫӮБӮДӮНӮўӮҜӮИӮўӢCӮӘӮөӮҪҒBӮҫӮ©ӮзҒA–lӮНҺvҚхӮЙӮУӮҜӮйӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒBҚЎӮЙӮИӮБӮДӢCӮГӮўӮҪӮӘҒAӮіӮБӮ«ғTғ`ӮЙҺ©•ӘӮМҚlӮҰӮрғoҒ[ғbӮЖҢҫӮБӮДӮЭӮҪӮұӮЖӮЕҒAҚlӮҰӮӘӮЬӮЖӮЬӮБӮДӮ«ӮҪҒBҺ©•ӘӮӘӢҒӮЯӮДӮўӮйӮМӮӘӮИӮЙӮ©ӮӘ–ҫҠmӮЙӮИӮБӮДӮ«ӮҪҒB—]ҢvӮИиЙӮӘӮИӮӯӮИӮБӮДҒAӮ·ӮБӮ«ӮиӮөӮҪӢCҺқӮҝӮЙӮіӮ№ӮДӮӯӮкӮҪҒB
Ғ@ӮЗӮкӮӯӮзӮўӮМҺһҠФӮӘҢoӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB–lӮНҳrҺһҢvӮрҺқӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒAҗіҠmӮИҺһҠФӮНӮнӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAӮўӮЬӮҫӮЙ”w’ҶӮ©ӮзӮН‘ҫҢЫӮМү№ҒAҺqӢҹ’BӮМӮНӮөӮбӮ¬җәҒAҸДӮ«Ӯ»ӮОӮМҚҒӮиӮӘӮ·ӮйӮМӮЕҒAӮіӮЩӮЗүЯӮ¬ӮДӮНӮўӮИӮўӮЖ”FҺҜӮөӮҪҒB
Ғ@Ғc
Ғuғqғ“ғgҒAӮ Ӯ°ӮйӮЛҒv•sҲУӮЙҒAғTғ`ӮӘҸ¬ӮіӮИҗәӮЕҷкӮўӮҪҒB
Ғ\Ғ\Ӯ ӮзӮдӮй•ЁӮЙӮНҒAҠjҒAҚӘҢ№ӮӘӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮНҒAҗlҠФӮМҠбӮҫӮҜӮЕӮНҢ©ӮҰӮИӮўӮаӮМҒB
Ғ@Ғ@Ғ@ҚKӮ№ӮаҒAӮ»ӮсӮИӮаӮМӮҫӮЖҺvӮӨӮнҒ\Ғ\
”ЮҸ—ӮН—§ӮҝҸгӮӘӮиҒAҒuӮ¶ӮбҒAӮЬӮҪҒvӮЖҢҫӮБӮДӢҺӮБӮДӮўӮБӮҪҒB
–lӮӘ”ЮҸ—ӮМҢҫӮБӮҪӮұӮЖӮр—қүрӮөӮИӮўӮЬӮЬҢДӮСҺ~ӮЯӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӮЖҒAӮ»ӮМҸ—җ«ӮНҗUӮи•ФӮиҒAҚЕҢгӮЙӮЬӮҪ•sүВүрӮИҢҫ—tӮрҺcӮөӮҪҒB
ҒuҒcӮЁҚХӮиӮНҒAӮЖӮБӮӯӮЙҸIӮнӮБӮДӮўӮйӮнӮжҒv
Ғ@Ӯ»ӮөӮДғTғ`ӮН–йӮМҲЕӮЦӮЖҸБӮҰӮҪҒB
ҒuҒcӮИӮсӮҫӮБӮҪӮсӮҫҒHҲк‘МҒcҒv
Ғ@–lӮМҷкӮ«ӮНҒAҚХ‘ҫҢЫӮМү№ӮЙҸБӮҰӮҪҒB
Ғ@Ғ@ҒһӮUҒD
Ғ@ғRғEӮНҠC•УӮЦӮЖҢьӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮұӮНғTғ`ӮЖҚЎ“ъҸoүпӮБӮҪҸкҸҠӮҫӮБӮҪҒB
Ғ@ү®‘дӮЕ”ғӮБӮҪҸДӮ«Ӯ»ӮОӮЖғWғ…Ғ[ғXӮрҺиӮЙҒAҗQҠӘӮ«Ӯр•~ӮўӮД’з–hӮЙҚАӮйҒBғRғEӮМ–ЪӮМ‘OӮЙӮН’iҒXӮЖҗ®ӮБӮДғRғ“ғNғҠҒ[ғgӮӘүәӮЦӮЖҗПӮЬӮкӮДӮЁӮиҒAҠCӮЦӮЖҢqӮӘӮйҒB”ЮӮМ”w’ҶӮЙӮНӮұӮМ“cҺЙ•—ҢiӮЙӮН•sҺ©‘RӮИҒA•Ь‘•ӮіӮкӮҪгY—нӮИ“№ҳHӮӘӮ ӮиҒAҺФӮН–Е‘ҪӮЙ’КӮзӮИӮўҒBҠX“”ӮаӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮўҒBӮ»ӮМӮ©ӮнӮиӮЙҒAүЖҒXӮМ‘ӢӮ©ӮзҳRӮкӮй–ҫӮ©ӮиӮЖҒAҺ©•ӘӮЕ—pҲУӮөӮҪғүғ“ғvӮӘӮӘӮ ӮиҒAҲЕӮр”–ӮЯӮДӮўӮйҒB
Ғ@ғRғEӮНҗжӮЩӮЗғTғ`Ӯ©ӮзҢҫӮнӮкӮҪӮұӮЖӮрӮдӮБӮӯӮиӮЖҺvӮўҸoӮөӮДӮўӮҪҒB
ҒuҠjӮЖҒAҚKӮ№ӮНҒcҒv
ҠCӮЙҢьӮ©ӮБӮДӮ»ӮӨӮЪӮвӮ«ӮИӮӘӮзҒAҠwҚZӮМ—қүИӮМҺцӢЖӮрҺvӮўҸoӮөӮДӮўӮҪҒBҢ°”чӢҫӮ©ӮзҢ©ӮҰӮй–іҗ”ӮМӢКӮНҒAҺАӮН–ЪӮМҚцҠoҒAӮИӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖӢ^ӮБӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮЩӮЗғRғEӮЙӮЖӮБӮДӮНҗV‘NӮИ”ӯҢ©ӮҫӮБӮҪҒB
Ғ\Ғ\ҠjӮЖӮНҒAҢ№ҒBӮ ӮзӮдӮй•ЁҺҝӮЙ‘¶ҚЭӮ·ӮйҚӘҢ№ҒBӮ»ӮкӮӘӮИӮўӮаӮМӮНӮИӮўҒBҸӯӮИӮӯӮЖӮаҺ©‘RҠEӮЙӮНҒ\Ғ\–lӮМ‘МӮЙӮаӮ ӮйҒBҚЧ–EӮМғJғ^ғ}ғҠӮӘ–lӮҫӮ©ӮзҒ\Ғ\ғ~ғGғiғCҒAғӮғmҒ\Ғ\
Ғ@ҚKӮ№ӮЖӮўӮӨӮаӮМӮаҒAҚӘҢ№Ғc
Ғ@ӮИӮсӮМҒH
Ғ@ҚKӮ№ӮНҒAҗlҠФӮЙӮөӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўҒcғTғ`ӮӘӮ»ӮӨҢҫӮБӮДӮҪҒB
Ғ@Ӯ¶ӮбӮ ҒAҗlҠФӮМҒAӮ©ҒB
Ғ@җlҠФӮМҒAҚӘҢ№ӮНҒAҚKӮ№Ғc
Ғ@ӮЕӮаҒAҗlҠФӮН‘¶ҚЭӮөӮИӮҜӮкӮОҚKӮ№Ӯр”FҺҜӮЕӮ«ӮИӮўҒB
Ғ@Ғcғ\ғ“ғUғCҒH
Ғ@Ғc
Ғ@ҒuҚЭӮйҒvӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮӘҒAҚKӮ№ӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮ©ҒcҒH
Ғ@ҒuҚЭӮйҒvӮИӮзӮОҒuҚKӮ№ҒvӮр“ҫӮйӮМӮЕӮНӮИӮӯҒc
Ғ@ҒuҚЭӮйҒvҒҒҒuҚKӮ№ҒvӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮ©ҒB
Ғ@Ғc
Ғ@ғRғEӮНҒAӮИӮсӮЖӮИӮӯӮҫӮӘҒAғTғ`ӮЙҸoүпӮБӮДҚKӮ№ӮЙӮВӮўӮД”[“ҫӮөӮҪҒB—қүрӮЬӮЕӮЖӮНӮўӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮнӮ©ӮБӮҪӮЖҠмӮФӮЬӮЕӮЖӮНӮўӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAүҪӮ©Ӯр’НӮсӮҫӮұӮЖӮНҠmӮ©ӮҫӮБӮҪҒBҲк•а‘OҗiӮөӮҪҒB“ҡӮҰӮНӮаӮӨӮ·Ӯ®Ӯ»ӮұӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB
Ғ@ҚKӮ№ӮЖӮНҒAҚӘҢ№ҒBӮ»ӮұӮ©Ӯзҗ¶ӮЬӮкӮҪӮаӮМӮӘҒAҢ»ҺАҒBҠм“{ҲЈҠyӮНӮ·ӮЧӮДҚKӮ№Ӯ ӮБӮДӮМӮұӮЖҒBҒuҠмҒvӮвҒuҠyҒvӮҫӮҜӮӘӮ»ӮМҢӢүКӮЕӮНӮИӮўҒB”ЯӮөӮЭӮЙӮӯӮкӮйӮұӮЖӮаҒAҗв–]ӮМҸАӮЙӢzӮўҚһӮЬӮкӮйӮұӮЖӮаҒAҚKӮ№Ӯ ӮБӮДӮМӮұӮЖҒBӮўӮёӮкӮЙӮ№ӮжҒAҠҙҸоӮрҺАҠҙӮЕӮ«ӮйҒBӮ»ӮкӮНҒA‘¶ҚЭӮ·ӮйӮ©ӮзӮҫҒB
Ғ@ӮИӮЙӮаӮИӮҜӮкӮОҒAӮИӮЙӮаҺАҠҙӮЕӮ«ӮИӮўҒBҺ©•ӘӮЖӮўӮӨӮаӮМӮӘӮИӮўӮМӮИӮзҒAҺ©•ӘӮр•\Ң»Ӯ·ӮйӮұӮЖӮаӮЕӮ«ӮИӮўҒBҢіӮӘӮИӮўӮИӮз“–‘RӮҫҒB
Ғ@Ӯ»ӮөӮДҒAҚKӮ№ӮНҒAҺ©‘RӮӘӮИӮҜӮкӮОҗ¶ӮЬӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒB
Ғ@ғRғEӮН”YӮсӮҫӮ Ӯ°ӮӯҒAҢӢӢЗӮұӮсӮИӮӯӮҫӮзӮИӮӯӮДҠФҲбӮўӮҫӮзӮҜӮМүр“ҡӮр“ұӮ«ҸoӮөӮҪҒB–{җlӮН‘SӮӯҺ©ҠoӮрӮөӮДӮўӮИӮўӮӘҒB
Ғ@ӮЕӮаҒAӮұӮсӮИӮаӮсӮҫҒBҗВҸtӮИӮсӮДҒB
Ғ@ғRғEӮНӮжӮӨӮвӮӯҗSҚЧӮӯӮИӮиҒAүЖӮЙӢAӮиӮҪӮўӮЖҒAҸүӮЯӮДӮ»ӮӨҺvӮӨӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB
ҒuӢAӮлӮӨӮ©ӮИҒcҒvҸӯӮөҹTӮЙӮИӮБӮҪӮ Ӯ°ӮӯҒA
ҒuҗQӮжӮӨҒcҒvҗQҠӘӮ«ӮМ’ҶӮЙӮӨӮёӮӯӮЬӮйӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒB
Ғ@Ғ@Ғc
Ғ@җ^ӮБ”’ӮИҒAҗўҠEҒB
Ғ@Ӯ»ӮұӮЙ–lӮНӮНӮўӮйҒB
Ғ@–lӮН–ІӮрҢ©ӮДӮўӮйӮМӮ©ӮЖҺvӮБӮҪҒB
Ғ@Ӯ«ӮкӮўӮИҒA”’ҒB
Ғ@Ӯ»ӮұӮЕ–lӮНүЎӮЙӮИӮБӮДӮӨӮёӮӯӮЬӮБӮДӮўӮйҒB
Ғ@Ӯ Ӯ ҒAӮИӮсӮҫӮ©ҒA
Ғ@үщӮ©ӮөӮўҠҙҠoӮӘӮ·ӮйҒB
Ғ@ҢьӮұӮӨӮ©ӮзҒAүҪӮ©ӮӘӮвӮБӮДӮӯӮйҒB
Ғ@Ӯ Ӯ ҒAғTғ`Ӯ©ҒB
Ғ@ӮЗӮӨӮөӮДӮұӮұӮЙҒH
Ғ@ғTғ`ӮНҸОҠзӮМӮЬӮЬҒA–lӮЖ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙүЎӮЙӮИӮБӮДӮӨӮёӮӯӮЬӮйҒB
Ғ@–lӮЖҒAҢьӮ©ӮўҚҮӮнӮ№ӮЙӮИӮБӮДҒB
Ғ@Ғ\Ғ\ӮPӮV”NҠФҒc–{“–ӮЙҒc’ZӮ©ӮБӮҪӮЛҒcҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮЕӮаҒAӮвӮБӮЖҲкҸҸӮЙӮИӮкӮйӮ©ӮзҒAҠрӮөӮўӮ©ӮИҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮИӮЙӮрҢҫӮБӮДӮўӮйӮМҒHғTғ`Ғc
Ғ@Ғ@Ғ@Ӯ ӮИӮҪӮНӮЬӮёҒA–с‘©ӮрҺvӮўҸoӮіӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮЛҒc
Ғ@Ғ@Ғ@–с‘©ҒH
Ғ@Ғ@Ғ@ӮӨӮсҒcӮPӮV”N‘OӮМҒA–с‘©ҒBӮұӮұӮНҒAӮ»ӮкӮрҢрӮнӮөӮҪҸкҸҠҒc
ҒcӮнӮ©ӮзӮИӮўӮжҒcӮҜӮЗҒAӮИӮсӮ©ҒAӮЖӮДӮаүщӮ©ӮөӮўҠҙӮ¶ӮӘӮ·ӮйҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮўӮўӮМҒBӮ»ӮкӮНҒAӮўӮўӮұӮЖӮҫӮ©ӮзҒB–YӮкӮйӮӯӮзӮўҒAҠyӮөӮ©ӮБӮҪӮБӮДӮұӮЖӮЕӮөӮеҒH‘еҸд•vҒBҺ„ӮӘҒAӮ»ӮМ–с‘©ӮрҳbӮ·ӮЛҒcҒ\Ғ\
Ғ@Ғ\Ғ\Һ„ӮЖӮ ӮИӮҪӮНҒAӮұӮұӮЕҸoүпӮБӮҪҒBӮ ӮМӮЖӮ«ӮНӮЗӮұӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮҜӮЗҒAҚЎӮИӮзӮнӮ©ӮйҒcҺ„’BӮНӮ»ӮұӮ©ӮзҠOӮМҗўҠEӮЙҸoӮй—\’иӮҫӮБӮҪӮМҒBӮҜӮЗӮЛҒAҸoҢыӮНӮЖӮДӮаӢ·Ӯ©ӮБӮҪҒc“сҗlӢӨҸoӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪӮМҒBҺ„’BӮӘӮўӮҪҗўҠEӮНҒAӮЗӮҝӮзӮ©Ҳк•ыӮӘҸoӮДҚsӮӯӮжӮӨӮЙӮЖҚҗӮ°ӮҪҒBӮ»ӮӨӮөӮИӮўӮЖҒAӮұӮМҗўҠEӮӘүуӮкӮйӮ©ӮзӮБӮДҒc
Ғ@Ғ@Ғ@
ӮЕӮаҒAҺ„’BӮНӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒB“сҗlӮЕҠOӮМҗўҠEӮЙҚsӮ«ӮҪӮ©ӮБӮҪҒB’ҮӮӘӮжӮ©ӮБӮҪӮБӮДӮнӮҜӮ¶ӮбӮИӮўӮҜӮЗҒAӮёӮБӮЖҲкҸҸӮЙҒuӢҸӮҪҒvӮ©ӮзҒc‘Ҫ•ӘҒAӮ»ӮӨӮўӮӨү^–ҪӮҫӮБӮҪӮМҒc
Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@Ғ@Ғ@ҸoҢыӮНӮўӮВӮ©•ВӮЬӮйӮ©ӮзҢҲ’fӮрӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮЖҒAӮ»ӮМҗўҠEӮНҚҗӮ°ӮҪҒBҺ„’BӮН”YӮсӮҫҒBҲкҸҸӮӘӮжӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзҒc
Ғ@Ғ@Ғ@Ӯ·ӮйӮЖҒAӮ»ӮМҗўҠEӮНҒAҲкҗlӮНҠOӮМҗўҠEӮЦҒAӮаӮӨҲкҗlӮН•КӮМҗўҠEӮЦҚsӮӯӮұӮЖӮр’сҲДӮөӮҪҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Һ„’BӮНҒAӮұӮМҗўҠEӮЖҲкҸҸӮЙүуӮкӮЬӮ·ӮЖҢҫӮБӮҪҒBӮҜӮЗҒAӮ»ӮкӮН‘К–ЪӮҫӮЖҢҫӮнӮкӮҪҒBӮ»ӮкӮНӮұӮМҗўҠEӮр”Ы’иӮ·ӮйӮұӮЖӮҫӮЖҒA“{ӮзӮкӮҪҒc
Ғ@Ғ@Ғ@Һ„’BӮНҢӢӢЗҒAӮ»ӮМҗўҠEӮМҢҫӮӨӮЖӮЁӮиӮЙӮөӮҪҒBӮЖӮДӮа”ЯӮөӮ©ӮБӮҪҒBӮҜӮЗҒAӮ»ӮӨӮ·ӮйӮөӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ ӮИӮҪӮНҒuҢNӮӘҠOӮМҗўҠEӮЙҚsӮБӮДҒvӮЖҢҫӮБӮДӮӯӮкӮҪҒcҺ„ӮӘ—ЈӮкӮҪӮӯӮИӮўӮЖҢҫӮӨӮЖҒAӮ ӮИӮҪӮНҒuӮЬӮҪүпӮҰӮйӮ©ӮзҒAӮ»ӮМҺһӮЙҠOӮМҗўҠEӮрӢіӮҰӮДҒvӮЖҢҫӮБӮДӮҜӮкӮҪҒcӮ ӮИӮҪӮӘҒAӮ»ӮӨҢҫӮБӮДӮӯӮкӮҪӮМҒ\Ғ\
Ғ@ҒcғIғӮғCҒcғ_ғVҒcғ^ҒcҒc
Ғ@Ӯ»ӮӨӮҫҒAӮ»ӮөӮД–lӮНӮ»ӮМҗўҠEӮЙ•КӮМҗўҠEӮЖӮНӮЗӮұӮЙӮ ӮйӮМҒHӮЖ•·ӮўӮҪӮМӮҫҒB
Ғ@Ӯ·ӮйӮЖӮ»ӮМҗўҠEӮНҒAҒuҺ©•ӘӮЕҚмӮкӮОӮўӮўҒvӮЖҚҗӮ°ӮҪҒc
Ғ@ҒcӮ»ӮӨӮ©Ғc–lӮзӮНҒcҒc‘oҺqӮҫӮБӮҪӮсӮҫҒcҒc
Ғ@ҒcӮ»ӮӨӮ©ҒcӮұӮұӮНҒcҒcҺnӮЬӮиӮМҗўҠEӮҫҒcҒc
Ғ@‘М’ҶӮЙҒA’gӮ©ӮіӮӘӮвӮБӮДӮӯӮйҒB
Ғ@ү·ӮаӮиӮЙҒA•пӮЬӮкӮйҒB
Ғ@Ғc•·ӮұӮҰӮйҒB
Ғ@ғhғNғ“ҒAғhғNғ“ӮЖӮўӮӨҒA–ҪӮМҢЫ“®ӮӘҒc
Ғ@Ғ\Ғ\ҒcҺvӮўҸoӮөӮҪҒH
Ғ@Ғ@Ғ@ӮӨӮсҒcӮ ӮиӮӘӮЖӮӨҒc–lӮзӮНҒA–ЯӮБӮДӮ«ӮҪӮсӮҫӮЛҒc
Ғ@Ғ@Ғ@Ӯ»ӮӨҒAӮPӮV”NӮФӮиӮМҒAҚДүпҒc
Ғ@Ғ@Ғ@–с‘©ӮМҒAӮЖӮ«Ғc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮӨӮсҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ҒcӮ¶ӮбӮ ҒA–lӮзӮНҒAӮұӮкӮ©ӮзӮёӮБӮЖҲкҸҸӮҫӮЛҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ҒcӮ»ӮӨӮЛҒAӮаӮӨҺ„’BӮНҒAүiү“ӮҫӮаӮМҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮёӮБӮЖҒAҲкҸҸҒc
Ғ@Ғ@Ғ@Ӯ»ӮӨӮЛҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮұӮӨӮөӮДҒAҲкҸҸӮЙӮӨӮёӮӯӮЬӮБӮДҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮӨӮсҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ҢЭӮўӮрҒAҢ©ӮВӮЯҚҮӮӨҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮӨӮсҒc
Ғ@Ғ@Ғ@–lӮзӮМҒA–с‘©ӮрҒAүКӮҪӮ»ӮӨӮ©Ғc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮӨӮсҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ҒcӮ¶ӮбӮ ҒA•·Ӯ©Ӯ№ӮДҒBӮЁҳbӮМҒc‘ұӮ«ӮрҒc
Ғ@Ғ@Ғ@ӮНӮўҒcҒ\Ғ\
Ғ@Ӯ»ӮӨҒAӮPӮV”N‘OҒA–lӮзӮН–с‘©ӮрӮөӮҪ
Ғ@Һ„ӮНҒAҒuҢ»ҺАҒvӮЖӮўӮӨҠOӮМҗўҠEӮЦ
Ғ@–lӮНҒAҒu—қ‘zҒvӮЖӮўӮӨ‘nӮзӮкӮҪҗўҠEӮЦ
Ғ@ӮЁҢЭӮў•КҒXӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮҜӮкӮЗ
Ғ@ӮЬӮҪҒAүпӮЁӮӨ
Ғ@ҺnӮЬӮиӮМҗўҠEӮЕ
Ғ@ӮЁҢЭӮўӮЙҚsӮБӮҪҗўҠEӮрӮЁҳbӮөӮжӮӨ
Ғ@Ӯ»ӮөӮДҒAҢЭӮўӮМ‘¶ҚЭӮрҒAҠm”FӮ·ӮйӮсӮҫ
Ғ@ҢЭӮўӮМҚKӮ№ӮрҒAжҗүМӮ·ӮйӮсӮҫ
Ғ@Ӯ»ӮӨ
Ғ@–lӮН
Ғ@Һ„ӮН
Ғ@ғRғRғjғCғӢҒAӮЖҒc
Ғ@Ғ@ҒһғGғsғҚҒ[ғO
Ғ@ӮЖӮ Ӯй“cҺЙ’¬ӮЙӮДҒB
ҒuӮЛӮҰ•·ӮўӮҪҒHҚр“ъӮМ–йӮМҳbҒv
ҒuӮ Ӯ Һ„ӮаӮ»ӮкӮрҳbӮ»ӮӨӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪӮЖӮұӮлӮИӮМӮжҒ`Ғv
ҒuӮЛӮҰҒc’©ӮЙӮИӮБӮДғpғgғJҒ[ӮвӮзӢ~Ӣ}ҺФӮвӮзғEҒ[ғEҒ[–ВӮБӮДӮДҒcҒv
ҒuӮ»ӮӨӮ»ӮӨҒcӮИӮсӮЕӮаӮ Ӯ»ӮұӮМ•l•УӮЙҺҖ‘МӮӘӮ ӮБӮҪӮБӮДӮўӮӨҒcҒv
ҒuҺEҗlҺ–ҢҸӮ©ӮөӮзҒcҒv
ҒuӮіӮҹӮЛӮҘҒcӮИӮсӮЕӮа–°ӮйӮжӮӨӮЙҺҖӮсӮЕӮўӮҪӮзӮөӮўӮнӮжҒcҒv
Ғu•|ӮўӮнӮЛҒ`ҒBӮЕӮаҒAӮұӮМ’¬ӮЕӢNӮұӮйӮИӮсӮДҒc–Е‘ҪӮЙӮИӮўӮнӮжӮЛӮҰҒcҒv
Ғu‘ә’·ӮіӮсӮНҸ\”NӮФӮиӮМҺ–ҢҸӮӘӢNӮ«ӮҪӮЖӮ©ҢҫӮБӮДӮҪӮнӮжҒv
ҒuӮ ӮзӮ ӮзӮ»ӮсӮИӮЙ’ҝӮөӮўӮМҒHҒv
ҒuӮ»ӮӨӮжҒcӮҫӮ©Ӯзҗв‘ОӮЙҺEҗlӮИӮсӮ©Ӯ¶ӮбӮИӮўӮБӮДҢҫӮБӮДӮҪӮнҒv
ҒuӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮ·ӮйҗlҒAҚҹҸҲӮЙӮНӮўӮИӮўӮаӮсӮЛӮҘҒcҒv
ҒuӮ»ӮӨӮжҒ`ҒBӮ»ӮкӮЙ–SӮӯӮИӮБӮҪ•ыӮНӮұӮМ’¬ӮМҗlӮ¶ӮбӮИӮўӮөҒcӮ»ӮкӮЙҒAҚр“ъӮМҚХӮиӮЙӮа–ЪҢӮӮіӮкӮДӮўӮИӮўҗlӮзӮөӮўӮнӮжҒcҒv
ҒuӮ ӮзҒ`ҒcҒv
ҒuӮ»ӮкӮЙҒAӮЬӮҫ”N’[ӮаӮўӮ©ӮИӮўҸ—ӮМҺqӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўӮөҒcҒv
ҒuӮЛӮҰҒcғzғ“ғgүВҲЈ‘zӮЙҒcҒv
Ғ@ӮPӮV”N‘OҒAӮЖӮ Ӯй•aү@ӮЙӮД
ҒuӮЁ”жӮкҒ`Ғv
ҒuӮЁ”жӮк—lӮЕҒ`Ӯ·Ғv
ҒuҚЎ“ъӮНӮаӮӨӮ ӮӘӮиҒHҒv
ҒuӮНӮўҒB–йӢОӮЙ”хӮҰӮДӢAӮБӮД‘ҰҢшӮЕҗQӮДӮ«ӮЬӮ·Ғv
ҒuӮ»ӮӨӮЛӮҘӮөӮБӮ©ӮиғpғҸҒ[ӮҪӮЯӮЖӮ«ӮИӮіӮўҒv
ҒuӮНҒ`ӮўҒBӮ ҒAӮ»ӮӨӮўӮҰӮОҗж”yҒBҚр“ъҺY•wҗlүИӮЕ‘oҺqӮМҸoҺYӮӘӮ ӮБӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ·ӮжҒv
ҒuӮ ӮзҒAӢvӮөӮФӮиӮЛҒBҲк—‘җ«ҒH“с—‘җ«ҒHҒv
ҒuӮ»ӮкӮӘӮ·ӮІӮўӮсӮЕӮ·ӮжҒBҲЩҗ«Ҳк—‘җ«ӮҫӮБӮҪӮсӮЕӮ·ӮБӮДҒv
ҒuӮҰҒIҒHӮ»ӮкӮБӮДӮаӮМӮ·ӮБӮІӮўӮұӮЖӮ¶ӮбӮИӮўҒIҒHғjғ…Ғ[ғXӮЙӮИӮйӮнӮжӮБҒIҒv
ҒuҒcӮИӮйӮНӮёӮЕӮөӮҪӮӘҒcҒv
ҒuҒcӮИӮйӮНӮёҒwӮЕӮөӮҪҒxҒHҒv
ҒuӮ ҒAӮНӮўҒcҺАӮНҗ¶ӮЬӮкӮй‘OӮЙӮЁ• ӮМ’ҶӮЕҒAҠщӮЙ’jӮМҺqӮН–SӮӯӮИӮБӮДӮўӮҪӮзӮөӮўӮсӮЕӮ·Ғv
ҒuӮ ӮзҒcӮ»ӮкӮНҒcӢCӮМ“ЕӮЙӮЛҒcҒcҸ—ӮМҺqӮМӮЩӮӨӮНҒHҒv
Ғu–іҺ–ҸoҺYӮіӮкӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒBӮЕӮ·ӮҜӮЗҒcҒv
ҒuҒcҒcғ^Ғ[ғiҒ[ҒHҒv
ҒuҒcӮ©ӮаӮөӮкӮЬӮ№ӮсҒcҒv
ҒuӮ»ӮӨҒc–{“–ӮЙҒAӢCӮМ“ЕӮЙҒcҒcҒv
Ғv
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ҡ®ҢӢ
|
|
|
|
| ҒuғAғNғeғB•¶Ң|•”ҒvҒ@Ғ@Ғ@Ғ@ҳAҚЪҺ®Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@’ҳҒ@Һl”Nҗ¶ҒFӮПӮЛӮҘӮ—Ғ@ҒiүпҢvҒj |
|
|
|
–ЪҺҹ
‘жҲкҸНҒ@үДӮМ’ӢӮМҸҳӢИ
‘ж“сҸНҒ@үДӮМ–йӮМ•П‘tӢИ
‘жҺOҸНҒ@үДӮМ’©ӮМ’БҚ°ӢИ
‘жҺlҸНҒ@үДӮМү©ҚЁӮМҺwҠцҺТ
“oҸкҗl•Ё
Ӯs‘еҠwҒ@ғAғNғeғB•¶Ң|•”
ҚІҒX–ШҒ@Қ„‘ҫҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҺl”N
Ҹгү®•~Ғ@—№ҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҺl”N
’фҒ@ҷy“№ҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҺO”N
җҙҸтҒ@–һүиҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҺO”N
җВҺRҒ@җГҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҺO”N
“Ў“cҒ@”ь‘ҒҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҺO”N
Ҹ¬“№Ғ@–ВҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠw“с”N
ҳZаVҒ@—Ъ—һҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠw“с”N
“ҢҒ@җқҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠw“с”N
җV’JҒ@җҗҺчҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҲк”N
үМҗмҒ@•—ҺqҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҲк”N
”С’ЛҒ@үФҺqҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҲк”N
ӢҫҒ@ӢҫҺqҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcӮs‘еҠwҲк”N
Ӯ»ӮМ‘ј
ҳaӢv“cҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒcҒc•xҺmҢ©‘‘ҠЗ—қҗl
‘жҲк–ӢҒ@үДӮМ’ӢӮМҸҳӢИ
ӮP
ҒuӮЁҒ[ӮўҒAӮ»ӮұӮМғuғTғҒғ“Ҹ”ҢNҒIҒ@‘ҒӮӯӮөӮИӮўӮЖ’uӮўӮДӮўӮӯӮјӮ§Ғ[Ғv
Ғ@җҙҸт–һүиҒiғVғҮғEғWғҮғEғ~ғcғҒҒjӮӘ‘еӮ«ӮӯҺиӮрҗUӮиүсӮөӮИӮӘӮз‘еҗәӮЕҢДӮСӮ©ӮҜӮйҒB”ЮҸ—ӮМҢг•ы“сҸ\Ӯ©ӮзҺOҸ\ғҒҒ[ғgғӢӮМҲК’uӮЙӮНҗ”–јӮМҠwҗ¶ӮМҺpӮӘҢ©ӮҰӮйҒB
Ғuҗж”yҒcҒc•·Ӯ«ӮЬӮөӮҪӮ©ҒHҒ@ғuғTғҒғ“Ҹ”ҢNӮҫӮ»ӮӨӮЕӮ·ӮжҒv
Ғ@’фҷy“№ҒiғCғJғҠғXғYғ~ғ`ҒjӮНҠzӮЙҠҫӮр•ӮӮ©ӮЧӮИӮӘӮз‘OӮр•аӮӯҚІҒX–ШҚ„‘ҫҒiғTғTғLғSғEғ^ҒjӮЙҳbӮөӮ©ӮҜӮйҒB
ҒuҒcҒcӮЦҒHҒv
ҒuӮҫӮ©ӮзҒAҗҙҸт–һүиӮЕӮ·ӮжҒv
ҒuӮ Ӯ ҒAӮ ӮўӮВӮИҒcҒc‘ҒӮўӮИҒBӮвӮБӮПӮи‘МҗПӮМ–в‘иӮИӮМӮ©ҒcҒcӮўӮвҒAӮЕӮаӮҝӮбӮсӮЖ’©ӮІӮНӮсӮНҗHӮЧӮҪӮнӮҜӮҫӮөҒcҒcғGғlғӢғMҒ[“IӮЙӮНӮЬӮҫ“®ӮҜӮйӮНӮёӮҫӮөҒcҒcҒv
Ғ@ҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮН‘МӮӘ‘еӮ«ӮўҒAӮ»ӮкҢМӮЙ’·ҺһҠФӮМү^“®ӮН“ҫҲУӮЖӮ·ӮйӮЖӮұӮлӮЕӮНӮИӮўҒB
ҒuӮ ӮМҒcҒcҗж”yҒB‘еҸд•vӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv’фӮӘҚІҒX–ШӮМӮұӮЖӮрҗS”zӮ·ӮйҒB
ҒuҒcҒc‘еҸд•vҒHҒ@ӮаӮҝӮлӮсӮіҒBүҙӮНҺOҸ\ғҒҒ[ғgғӢӮ ӮйғҚғ{ғbғgӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮзӮИҒBӮұӮМ’nӢ…ҸгӮЕӮНӢм“®үВ”\ӮИ‘«ҚҳӮрҸҠ—LӮөӮДӮўӮйӮНӮёӮҫӮ©ӮзҒcҒcҒv
Ғ@’фӮМ•ыӮ·ӮзҗUӮиҢьӮ©ӮёӮЙ—ЗӮӯ•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮұӮЖӮрҢы‘–ӮБӮДӮўӮйӮЖӮұӮлӮрӮЭӮйӮЖҒAӮЖӮДӮа‘еҸд•vӮЕӮНӮИӮіӮ»ӮӨӮҫҒBҚІҒX–ШӮМ”w’ҶӮ©ӮзӮН“’ӢCӮ·Ӯз—§ӮҝҸгӮиӮ»ӮӨӮИҗЁӮўӮҫҒB
Ғ@’фӮНҢг•ыӮрҢ©“nӮ·ҒB
Ғ@‘OӮр•аӮӯҗҙҸт–һүиҒAҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮрҠЬӮЯҢvҸ\ҺO–јҒBӮs‘еҠwҒAғAғNғeғB•¶Ң|•”ӮЕӮ ӮйҒB
Ғ@ҸкҸҠӮН“ҢӢһ“s–^ҺR“№ҒB
Ғ@”Ю“ҷӮНҺR“oӮиӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮНӮИӮӯҒAҚҮҸhҸҠӮЦҢьӮ©ӮБӮДӮўӮй“r’ҶӮИӮМӮЕӮ ӮйҒB
Ғ@”ЮӮзӮМҸҠ‘®Ӯ·ӮйғAғNғeғB•¶Ң|•”ӮНҒAҗж‘гӮМҲУҢьӮЙӮжӮиҸнӮЙғAғNғeғBғuӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮӘӢ`–ұ•tӮҜӮзӮкӮДӮўӮйҒB
Ғw•¶Ң|ӮН–іӮ©Ӯзҗ¬ӮзӮёҒx
Ғ@•¶ҸНӮрҚмӮйӮЙӮөӮДӮаҢoҢұӮв’mҺҜӮЖӮўӮӨӮаӮМӮӘӮИӮӯӮДӮНҢҲӮөӮДҚмӮиҸoӮ·ӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮўҒBүҪӮзӮ©ӮМҢoҢұӮв’mҺҜӮӘӮ ӮиҒAӮ»ӮкӮзӮрҺ©ӮзӮМ’ҶӮЕ‘gӮЭ‘ЦӮҰ‘n‘ўӮөӮДҸүӮЯӮДҚм•iӮрҚмӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйҒB
Ғ@ӮұӮМғTҒ[ғNғӢӮр—§ӮҝҸгӮ°ӮҪҗж‘гӮНҒAӮұӮкӮзӮМҲУҗ}ӮрҠЬӮсӮҫҢ`ӮЕғAғNғeғB•¶Ң|•”ӮЖӮўӮӨ–ј‘OӮӘӮВӮўӮДӮўӮйҒB
Ғ@Ӯ»ӮӨӮўӮБӮҪҢoҲЬӮ©ӮзүДҚҮҸhҸҠӮЕӮ Ӯй•xҺmҢ©ҺR‘‘ӮЦ‘«Ӯрү^ӮсӮЕӮўӮй–уӮЕӮ ӮйҒB
Ғ@•¶Һҡ’КӮи‘«ӮЕҒB
Ғ@’фӮНҸӢӮіӮЖ”жҳJӮЕҒAӮөӮбӮнӮөӮбӮнӮЖӮ»ӮұӮзӮ¶ӮгӮӨӮ©ӮзӢҝӮӯҗд’BӮМҗәӮаӢCӮЙӮИӮзӮИӮӯӮИӮБӮДӮ«ӮҪҒB
Ғ@‘Ғ’©ҒAҳZҺһӮЙҗVҸhүwӮЙҸWҚҮӮөӮҪғAғNғeғB•¶Ң|•”ҒB
Ғ@–с“с–јҒAҺO”NӮМҗВҺRҗГҒiғAғIғ„ғ}ғVғYғJҒjӮЖ“с”NӮМҸ¬“№–ВҒiғRғ~ғ`ғiғӢҒjӮӘ’xҚҸӮөӮҪӮӘҒA‘SҲх–іҺ–ӮЙҸWӮЬӮиҒAҸo”ӯӮөӮҪҒB
Ғ@“dҺФӮЕ–с“сҺһҠФҒAғoғXӮЕҺOҸ\•ӘҒB
Ғ@‘ӢӮМҠOӮНҲкҺһҠФҺгӮЕ“ҢӢһӮЖӮўӮӨғCғҒҒ[ғWӮ©ӮзӮНӮ©ӮҜ—ЈӮкӮҪ“cҺЙ•—ҢiӮЙ“ьӮк‘ЦӮнӮБӮДӮўӮҪҒB
Ғ@ғoғXӮрҚ~ӮиӮҪҸкҸҠӮНҺӢҠEӮЙ—ОӮӘ“ьӮзӮИӮўӮұӮЖӮӘӮИӮўӮЩӮЗӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮұӮЕҢ»•”’·ӮЕӮ ӮйҚІҒX–ШӮӘ‘еҗәӮЕҺRӮрҺwҚ·ӮөҒuӮұӮкӮ©Ӯз•xҺmҢ©‘‘ӮЬӮЕ“oӮйӮјҒIҒvӮЖ•”ҲхӮЦҢьӮҜӮДҲкҠҮӮөӮҪҒB
Ғ@ҚҮҸhӮМҠйүжӮрӮөӮҪӮМӮНҺl”NӮМҚІҒX–ШҚ„‘ҫҒAҺO”NӮМ’фҷy“№ӮЖҗҙҸт–һүиӮИӮМӮЕҺOҗlӮНӢБӮ«ӮаӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒA•”ҲхӮҪӮҝӮНӢБӮўӮҪҒBҚҮҸhӮЙӮ ӮҪӮиҒuҚҮҸhӮМӮөӮЁӮиҒvӮИӮсӮДӮаӮМӮаҚмӮБӮДӮЭӮҪӮӘӮ»ӮұӮЙӮНҸЪҚЧӮНҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮИӮўӮМӮЕӮ ӮйҒBҢҲӮөӮД–К“|ӮӯӮіӮ©ӮБӮҪ–уӮЕӮНӮИӮўҒB
Ғ@Ӯ»ӮұӮ©Ӯз•аӮ«ҺnӮЯӮДҠщӮЙ“сҺһҠФӮӘҢoүЯӮөӮДӮўӮйҒB
Ғ@’фӮМ‘z‘ңҲИҸгӮЙ•xҺmҢ©‘‘ӮЬӮЕӮМ“№ӮМӮиӮНҢөӮөӮўӮаӮМӮҫӮЖҠҙӮ¶ӮДӮўӮҪҒBӢAӮиӮаӮұӮМ“№Ӯр•аӮӯӮМӮ©ӮЖҺvӮӨӮЖҢҷӢCӮӘӮіӮөӮДӮӯӮйҒB
Ғ@ӮұӮМӢCү·ҒAҺјӢCҒA‘ҫ—zҢхҒAҺҮҠOҗьҒA•WҚӮӮЙӮжӮйӢНӮ©ӮИҺ_‘f•s‘«ҒBӮўӮвҒAӮұӮМ–і•—ӮұӮ»ӮӘҚЕ‘еӮМ“GӮЖӮўӮҰӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB
Ғu’фҒAӮ ӮЖӮЗӮМӮӯӮзӮўӮЕ’…ӮӯӮсӮҫӮжҒvҢг•ыӮр•аӮӯҺO”NӮМҗВҺRҗГҒiғAғIғ„ғ}ғVғYғJҒjӮҫҒB
ҒuӮ ӮЖҒAҸӯӮөӮМӮНӮёӮҫӮжҒBҠFҠж’ЈӮБӮДҒIҒv
Ғuҗж”yҒAӢxҢeӮр—vӢҒӮөӮЬӮ·Ғv“с”NӮМ“ҢҗқҒiғAғYғ}ғXғYғҒҒjҒB
ҒuӮаӮӨҚЕҲ«ҒIҒ@ӮЛӮҰҗГҒAҲщӮЭ•ЁӮИӮўҒHҒvҗВҺRӮМ”ЮҸ—ӮЕҺO”NӮМ“Ў“c”ь‘ҒҒiғtғWғ^ғ~ғTғLҒjӮӘҠГӮҰӮҪҗәӮрҸoӮ·ҒB
ҒuӮұӮМ“ъӮНҒAӮіӮжӮӨӮИӮзҒBӢҖӮҝӮй‘OӮЙ–ҫ“ъӮЦҒcҒcҒv”һҳm–XҺqӮр”нӮБӮҪ”wӮМҚӮӮўҸгү®•~—№ҒiғJғ~ғ„ғVғLғҠғҮғEҒjҺl”Nҗ¶ӮӘҢыӮрҠJӮӯҒB
ҒuүҪҢҫӮБӮДӮйӮсӮЕӮ·Ӯ©—№җж”yҒHҒ@ӮаӮӨҸӯӮөӮЕӮ·Ӯ©ӮзҠж’ЈӮБӮДӮӯӮҫӮіӮўӮжҒv’фӮН‘«ҸкӮӘҲ«ӮўӮМӮЕҺиӮрҚ·ӮөҗLӮЧӮйҒB
Ғ@—№ӮНҲкҸu–АӮўҺиӮрҲ¬ӮБӮҪҒB
Ғu’фҒIҒ@ӮЁҒ[ӮўҒA•xҺmҢ©‘‘ӮБӮДӮ ӮкӮ¶ӮбӮИӮўӮ©Ғv
Ғ@–һүиӮӘҺwҚ·Ӯ·җжӮЙғRғeҒ[ғWӮМӮжӮӨӮИҠOҢ©ӮМҢҡ’z•ЁӮМү®ҚӘӮМҗжӮӘҢ©ӮҰӮйҒB
—ОҗFӮМү®ҚӘҒB
ҠmӮ©җж”yӮЖҺOҗlӮЕҳbӮөҚҮӮБӮДӮўӮйҺһӮЙҗж”yӮӘҺқӮБӮДӮ«ӮҪҺКҗ^ӮЙүfӮБӮДӮўӮҪҢҡ•ЁӮаү®ҚӘӮӘ—ОӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮЁӮЁҒAӮвӮБӮЖ’…ӮўӮҪӮ©ӮҹҒcҒcҒvҚІҒX–ШӮНӮаӮНӮвҸБӮҰ“ьӮиӮ»ӮӨӮИ–м‘ҫӮўҗәӮрӮаӮзӮ·ҒB
ҒuҢх–ҫӮИӮзӮКҢх—ОҒA‘f“GӮҫҒvҸгү®•~—№ӮӘҢҫӮӨҒB
ӮQ
ҺR“№Ӯр”ІӮҜӮйӮЖҒAҚ»—ҳӮӘ•~Ӯ©ӮкӮҪ•Ҫ’nӮЙҸoӮҪҒB
ӢЯӮӯӮЕҢ©ӮйӮЖҲУҠOӮЖ‘еӮ«ӮЯӮМҢҡ•ЁӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮйҒB
ҠO•ЗӮвғxғүғ“ғ_ӮЬӮЕ–ШӮЕӮЕӮ«ӮДӮўӮйҒB“ьӮиҢыӮНӮҝӮеӮӨӮЗҗ^Ӯс’ҶӮЙӮ ӮиҒAүEӮЙӮНғfғbғLӮӘҢҡ•ЁӮМ‘Ө–К•”ӮЙӮЬӮЕ‘ұӮўӮДӮўӮйҒBҚ¶ӮЙӮН‘ӢӮӘ“сӮВҒAӢ°ӮзӮӯ“с•”ү®Ӯ»ӮұӮЙӮ ӮйӮМӮҫӮлӮӨҒB•ЁҠұӮөҠЖӮӘӮ ӮиҒAҗф‘у•Ё‘ҫ—zҢхӮр”ҪҺЛӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮМ“VӢCӮИӮзҲкҺһҠФӮЕҠЈӮӯӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB
“сҠKӮНҲк‘ұӮ«ӮЙӮИӮБӮДӮўӮйғoғӢғRғjҒ[ӮӘҢ©ӮҰӮйҒB‘ӢӮМҗ”ӮНҺlӮВҒB
Ңҡ•Ёҗі–КӮМғXғyҒ[ғXӮН’“ҺФҸкӮаҢ“ӮЛӮДӮўӮйӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒBӢ°ӮзӮӯҚ»—ҳ“№ӮрҗiӮсӮҫӮЖӮұӮлӮЙӮҝӮбӮсӮЖӮөӮҪ“№ҳHӮЙ‘ұӮўӮДӮўӮйӮМӮҫӮлӮӨҒB
ғAғNғeғB•¶Ң|•”ӮӘҸгӮБӮДӮ«ӮҪҺR“№ӮНӮұӮұӮ©ӮзҺR’ёӮЙӮЬӮЕ‘ұӮўӮДӮўӮйӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
җҙҸт–һүиӮНӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮр“ӘӮМӢчӮЕҚlӮҰӮИӮӘӮзҒA•xҺmҢ©‘‘ӮМ“ьӮиҢы–TӮЙүЧ•ЁӮр“ҠӮ°’uӮўӮҪҒB
ҒuӮӨҒ[ӮсҒv‘еӮ«ӮӯҗLӮСӮрӮ·ӮйҒBҒuӢCҺқӮҝӮўӮўӮнӮЛҒBӮұӮМ“VӢCҒAӮұӮМҠВӢ«ҒAӮЬӮіӮЙғҚҒ[ғJғӢҒIҒv
ҒuғҚҒ[ғJғӢҒHҒ@үҪҢҫӮБӮДӮсӮҫӮжҒv’фӮаҸdӮ»ӮӨӮИүЧ•ЁӮр’n–КӮЙ’uӮўӮДҒAӮ»ӮМҸкӮЙҚАӮиҚһӮсӮҫҒBҒu”жӮкӮҪӮҹҒv
ҺR“№Ӯ©ӮзӮМҸoҢыӮ©ӮзҺcӮиӮМ•”ҲхӮҪӮҝӮаӮјӮлӮјӮлӮЖҢ»ӮнӮкӮҪҒB
ҒuӮЩӮзҒAӮИӮсӮДӮўӮӨӮМҒHҒ@ӮұӮМ“cҺЙӮБӮЫӮўҠҙӮ¶ӮЖӮ©ҢҙҺn“IӮИҠҙӮ¶ғҚҒ[ғJғӢӮ¶ӮбӮИӮ©ӮБӮҪӮБӮҜҒHҒvҗlҚ·ӮөҺwӮрӮӯӮйӮӯӮйӮЖүсӮөӮИӮӘӮзҢҫӮӨҒB
ӮұӮкӮН”ЮҸ—ӮМ•ИӮЕӮ ӮйҒBүҪӮ©ҚlӮҰҺ–ӮрӮ·ӮйҺһӮжӮӯӮұӮМ“®ҚмӮрӮ·ӮйҒB
ҒuӮ»ӮиӮбҲбӮӨӮҫӮлҒBғҚҒ[ғJғӢӮБӮД’n•ыӮЖӮ©’nҲжӮЖӮ©ӮҫӮлҒBүҙӮЕӮа•ӘӮ©ӮйӮнҒAӮ»ӮМӮӯӮзӮўҒcҒcҒvҺсӮрҸгӮ°–һүиӮрҢ©ҸгӮ°ӮйҒB
–һүиӮН–jӮр–cӮзӮЬӮ№ӮйҒB
ҒuӮӨӮйӮіӮўӮнӮЛҒAүp’PҢкӮИӮсӮД‘еҠwҺуҢұӮМӮЖӮ«ҲИ—ҲӮвӮБӮДӮИӮўӮсӮҫӮ©ӮзҠoӮҰӮДӮўӮйӮнӮҜӮИӮўӮЕӮөӮеҒHҒ@ӮұӮМӮӘӮи•ЧҒv
ӮӘӮи•ЧӮБӮДӮўӮВӮМҺһ‘гӮҫӮжҒAӮЖ’фӮНҺvӮӨҒB
ҒuӮИӮсӮҫӮлҒcҒcғvғҠғ~ғeғBғuӮЖӮ©Ӯ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒHҒv
ҒuғvғҠғ~ғeғBғuҒHҒv–һүиӮӘ•·Ӯ«•ФӮ·ҒB
ҒuҒcҒcғvғҠғ~ғeғBғuҒAҢҙҺn“IҒA–ўҠJҒv
ӮжӮӨӮвӮӯ“һ’…ӮөӮҪӮЖӮўӮБӮҪҠҙӮ¶ӮЕ”һҳm–XҺqӮр”нӮБӮҪҸгү®•~—№ӮӘ‘гӮнӮиӮЙ“ҡӮҰӮйҒB
ҒuӮЁӮЁҒIҒ@ӮіӮ·ӮӘ—№җж”yҒv–һүиӮӘӢ№ӮМ‘OӮЕҺиӮрҚҮӮнӮ№ӮйҒBҒuӮИӮйӮЩӮЗҒAғvғҠғ~ғeғBғuӮЛҒB•ЧӢӯӮЙӮИӮБӮҪӮнҒBҚЎ“xӮ©ӮзҺgӮӨӮжӮӨӮЙӮ·ӮйҒv
ӢCӮӘӮВӮҜӮО“ьӮиҢыӮМ‘OӮЙҠFҚАӮиҚһӮсӮЕӮўӮҪҒB
ҒuӮжҒ[ӮөҒA‘SҲхӮўӮйӮ©ҒHҒv“ьӮиҢыӮМҠK’iӮЙҚАӮБӮҪӮЬӮЬӮЕҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮӘҚҶ—ЯӮрӮ©ӮҜӮйҒB
“_ҢДӮаҸIӮнӮи‘SҲхӮМҠm”FӮӘҺжӮкҒAҚІҒX–ШӮНғ`ғFғbғNғCғ“ӮрӮөӮДӮӯӮйӮЖҢҫӮўҢҡ•ЁӮМ’ҶӮЙ“ьӮБӮДӮўӮБӮҪҒB
җҙҸт–һүиӮӘ•@үМӮрүМӮўӮИӮӘӮзғJғoғ“ӮМӮИӮ©Ӯр’TӮБӮДӮўӮйҒB
ҒuӮЁ‘OҒAүҪӮЕӮ»ӮсӮИӮЙҢіӢCӮИӮсӮҫӮжҒcҒcҒv•рӮкӮҪӮжӮӨӮЙ’фӮӘ•·ӮӯҒB
’фҷy“№ӮЖҗҙҸт–һүиӮН‘еҠwӮМҲк”NӮМӮЖӮ«Ӯ©ӮзӮұӮМғTҒ[ғNғӢӮЕҲкҸҸӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAӢCҗSӮМ’mӮкӮҪ’ҮӮЕӮ ӮйҒB
Ғu–һүиӮіӮсӮН•җ“№ӮвӮБӮДӮйӮ©ӮзӮЛҒBӮ»ӮМӮЁӮ©Ӯ°ӮЕ–lӮзӮЖӮН‘М—НӮӘҲбӮӨӮсӮҫӮжҒv
Ӯ»ӮӨ—БӮөӮ°ӮИҠзӮЕҢҫӮБӮҪӮМӮНҗВҺRҗГӮЕӮ ӮйҒB
”ЮӮаҲк”NӮМҚ Ӯ©ӮзғTҒ[ғNғӢӮЙҸҠ‘®Ӯ·Ӯй’ҮӮЕӮ ӮйҒB
ҒuӮ»ӮӨӮўӮӨӮЁ‘OӮа”жӮкӮДӮИӮіӮ»ӮӨӮҫӮИҒv
ҒuӮЬӮ ӮЛҒAҲкүһ•Ғ’iӮ©Ӯзү^“®ӮНӮөӮДӮўӮй•ыӮҫӮөҒcҒc’фӮЖӮНҲбӮӨӮМӮіҒvҗВҺRӮНӮЙӮвӮиӮЖҢыҢіӮрҸгӮ°ӮйҒB
ҒuүҪҢҫӮБӮДӮйӮМӮжҒAҗГҢNҒBҺ„ӮН•җ“№ӮвӮБӮДӮИӮӯӮҪӮБӮДӮұӮМӮӯӮзӮў•ҪӢCӮИӮВӮаӮиӮжҒHҒ@Ҹ—ӮМҺqӮНӮЬӮҫӮөӮа‘јӮМ’jҳA’ҶӮӘӮҫӮзӮөӮИӮіүЯӮ¬ӮйӮМӮжҒv–һүиӮНүхҠҲӮЙҸqӮЧҒA—НӮМӮ Ӯй–ЪӮЕ’фӮрҢ©ӮйҒB
ҒuӮЁӮўӮЁӮўҒAӮ»ӮкҚ·•КӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒHҒ@Ӯ»ӮкӮЙүҙӮЖҚІҒX–Шҗж”yӮНғTҒ[ғNғӢӮМүЧ•ЁҺқӮБӮДӮҪӮсӮҫӮөҒcҒcҒv
ҒuҺ„ӮЙ”CӮ№ӮД’ёӮҜӮкӮОүЧ•ЁӮӯӮзӮўӮИӮсӮДӮұӮЖӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪӮМӮЙҒv
үЎӮ©Ӯз“с”NӮМ“ҢҗқӮӘҢыӮрӢІӮЮҒB
ҒuӮӨӮБӮнҒAҸoӮҪӮжҗқӮМҒwҺ„ӮЙ”CӮ№ӮД’ёӮҜӮкӮОҒxҒv“с”NӮМҳZаV—Ъ—һӮӘ”nҺӯӮЙӮ·ӮйӮжӮӨӮЙҢҫӮӨҒB
ҒuӮИҒAӮИҒAӮИӮсӮДӮұӮЖҢҫӮӨӮсӮҫӮжҳZаVӮіӮсҒIҒ@Һ„ӮНҗж”yӮҪӮҝӮМӢкҳJӮрҺ@ӮөӮДӮҫӮИҒcҒcҒv
ҒuӮНӮўӮНӮўҒAҗқӮН—КҺYҢ^ғUғNӮМҗ®”хӮЕӮаӮөӮДӮўӮкӮОӮўӮўӮМӮжҒv
ҒuӮөҒAҺё—зӮИӮұӮЖӮрҢҫӮӨӮИҒIҒ@ғUғNӮЙӮағUғNӮМӮжӮіӮӘӮ ӮйӮсӮҫҒIҒv
ӮИӮсӮҫӮ©ғ}ғjғAғbғNӮИүпҳbӮЙӮИӮБӮДӮ«ӮҪӮИӮЖҺO”NӮМҺOҗlӮНҠзӮрҢ©ҚҮӮнӮ№ӮйҒB
ҒuӮ ҒAӮ ӮБӮҪҒIҒv–һүиӮНғJғoғ“Ӯ©ӮзғfғWғ^ғӢғJғҒғүӮрҲшӮБ’ЈӮиҸoӮөӮҪҒBҒuҠFҒAҺКҗ^ҺBӮлӮӨӮжҒBүДҚҮҸhҲк”ӯ–ЪӮМӢL”OҺКҗ^Ғv
Ҳк“ҜҒA–һүиӮЙ’Қ–ЪӮөҺ^“ҜӮ·ӮйҒB
ҒuӮўӮўӮЕӮ·ӮЛҒBҗж”yӮ ӮЖӮЕғfҒ[ғ^‘—ӮБӮДӮӯӮҫӮіӮўҒv
Һ„ӮаҺ„ӮаҒAӮЖҺOҗlӮӘ—§ӮҝҸгӮӘӮйҒBҲк”NӮМүМҗм•—ҺqҒiғEғ^ғKғҸғtғEғRҒjҒA“ҜӮ¶Ӯӯ”С’ЛүФҺqҒiғCғCғdғJғnғiғRҒjҒA“ҜӮ¶ӮӯӢҫӢҫҺqҒiғJғKғ~ғLғҮғEғRҒjӮҫҒBӮұӮМҺOҗlӮНӮўӮВӮаҲкҸҸӮЙҚs“®ӮөӮДӮўӮйҒB
Ғu–һүиҒIҒ@Ӯ ӮЖӮЕғJғҒғү‘ЭӮөӮДҗГӮЖ“сҗlӮЕҺКӮБӮҪӮМ—~ӮөӮўӮ©ӮзҒv“ъүAӮЕ—БӮсӮЕӮўӮҪ“Ў“c”ь‘ҒӮӘ‘еҗәӮЕҢҫӮӨҒB
ӮжҒ[ӮөҒAӮЖ–һүиӮӘғJғҒғүӮр”`Ӯ«ғ`ғFғbғNӮрӮ·ӮйҒB
ҢӢӢЗҢҡ•ЁӮрғoғbғNӮЙҺBӮйӮұӮЖӮЙӮИӮи“ьӮиҢыӮЙҠFҸWӮЬӮБӮҪҒB
ҒuӮЩӮзҒAҚЎӮұӮ»Һ„ӮЙ”CӮ№ӮДӮӯӮҫӮіӮўӮБӮДҢҫӮҰӮОӮўӮўӮ¶ӮбӮИӮўҒvҗқӮрҸ¬“ЛӮӯҳZаV—Ъ—һҒB
ҒuӮ»ӮкӮ¶ӮбӮ ҒAҺ„ӮӘҺКӮзӮИӮўӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒBӮ»ӮсӮИӮМӢ–ӮіӮкӮИӮўҒvӮЖҗқҒB
ҒuӮўӮўӮжҒAүҙӮҪӮҝӮӘҢр‘гӮЕҺBӮйӮ©ӮзӮіҒvҢ©Ӯ©ӮЛӮҪ’фӮӘҢҫӮӨҒB
Ӯ»ӮкӮр•·ӮўӮД“ҢҗқӮН“°ҒXӮЖ’ҶүӣӮЙ—§ӮБӮҪҒB
ҒuӮЩӮзҒIҒ@’фӮИӮЙӮвӮБӮДӮсӮМӮжҒv–һүиӮӘ’фӮрҢДӮФҒB
ҒuӮЦҒHҒ@ӮИӮсӮҫӮжҒv
ҒuӮ ӮсӮҪӮӘҺBӮйӮМӮжҒIҒ@“–ӮҪӮи‘OӮЕӮөӮеҒv“–‘RӮҫӮЖӮўӮӨӮжӮӨӮЙ–һүиӮНҢЁӮрӮ·ӮӯӮЯӮйҒB
ҒuӮ ҒAӮ ӮМҒcҒcҒv
Ӯ»ӮұӮЕҸ¬“№–ВӮӘҒAӮ©ҚЧӮўҗәӮЕҗ\Ӯө–уӮИӮіӮ»ӮӨӮЙ—ҘӢVӮЙҺиӮрӢ“Ӯ°ӮҪҒB
ҒuҸ¬“№ӮіӮсӮЗӮӨӮ©ӮөӮҪҒHҒv’фӮӘҸ•Ӯ©ӮБӮҪӮЖӮОӮ©ӮиӮЙҗUӮи•ФӮйҒB
ҒuӮ ӮМҒcҒcҚІҒX–Шҗж”yӮӘӮЬӮҫӮўӮЬӮ№ӮсӮӘҒcҒcӮ»ӮМҒAҺКҗ^ӮўӮўӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHҒvҸ¬“№–ВӮН–{“–ӮЙҗ\Ӯө–уӮИӮіӮ»ӮӨӮЙҢҫӮӨҒB
Ғu–ВӮНӮвӮіӮөӮўӮЛҒvҳZаV—Ъ—һӮӘҸ¬“№–ВӮМ“ӘӮрӮИӮЕӮйҒBҒuӮЕӮаӮЛҒAӮұӮӨӮўӮӨӮЖӮ«ӮН‘К–ЪӮжҒB–YӮкӮҪҗUӮиӮөӮЖӮ©ӮИӮўӮЖҒv
ҠmӮ©ӮЙҸӯӮө’xӮўӮЖӮаҺvӮБӮҪӮӘ–в‘иӮЕӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӮ»ӮӨӮўӮӨӮұӮЖҒvӮ»ӮӨҢҫӮБӮД’фӮНҚҳӮЙҺиӮр“–ӮДӮЮӮӯӮкӮДӮўӮй–һүиӮЙҢДӮСӮ©ӮҜӮйҒBҒuӮЖӮиӮ ӮҰӮёҺҺӮөӮЙҲк–ҮҺBӮБӮДӮӯӮкӮжҒB‘SҲхӮНӮўӮйӮ©ӮЖӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮҫӮлҒv
Ӯ»ӮкӮр•·ӮўӮДҗҙҸт–һүиӮНӮөӮФӮөӮФғJғҒғүӮрҚ\ӮҰӮйҒB
ҒuӮіӮ·ӮӘ’фҒAҲөӮўӮӘӮИӮкӮДӮйӮЛҒvҗВҺRҗГӮӘ’фӮМҺЁҢіӮЕҷкӮӯҒB
ғnғCҒAғ`Ғ[ғYҒI
ӮR
ҒuӮӨӮнӮҹҒA—БӮөӮўӮЕӮ·ӮЛҒvӮдӮБӮӯӮиӮЖӮөӮҪӮөӮбӮЧӮи•ыӮЕҸ¬“№–ВӮНҠҙҢғӮМҗәӮрӮаӮзӮ·ҒB
ҠOӮМҸӢӮіӮЙ”дӮЧӮйӮЖ“VӮЖ’nӮМҚ·ӮЕӮ ӮйҒBҢҺӮЖӮ·ӮБӮЫӮсӮЖӮаҢҫӮӨҒB
ҒuӮұӮкӮЕҺ„ӮН–і“GӮҫҒv”һҳm–XҺqӮрҺжӮи–Јҳf“IӮИ•\ҸоӮрҢ©Ӯ№ӮйҸгү®•~—№ҒB
ҒuӮҝӮеӮБӮЖҒAүҪӮ©ҲщӮЭ•Ё–іӮўӮМӮ§ҒHҒ@ӮЛӮҰҗГҒA•”ү®ӮНҲкҸҸӮҫӮжӮЛҒHҒv
ҢәҠЦӮ©ӮзҚ¶ҺиӮЙғzҒ[ғӢӮӘҚLӮӘӮБӮДӮЁӮиҸ¬ӮіӮИғeҒ[ғuғӢӮЖғ\ғtғ@ӮӘ’uӮ©ӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМүңӮЙғJғEғ“ғ^ӮзӮөӮ«ӮаӮМӮӘӮ ӮйҒB
ҒuӮіӮ ӮЛҒAҚЎүсӮМҠйүжӮН–lҺQүБӮөӮДӮИӮўӮ©ӮзӮЛҒB’фӮҪӮҝӮЙ•·Ӯ«ӮИӮжҒvҗВҺRӮНҸОҠзӮрҢ©Ӯ№ӮйҒB
ҒuӮ ҒAӮ»ӮкҺ„ӮҪӮҝӮаӢCӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒIҒ@•”ү®ӮМҠ„Ӯи“–ӮДӮБӮДҢҲӮЬӮБӮДӮўӮйӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒvҺOҗl‘gӮМҲк”Nҗ¶ӮМӢҫӢҫҺqӮӘҺиӮрҸгӮ°ӮйҒB
Ӯ»ӮұӮЕҒAҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮӘғJғEғ“ғ^Ӯ©Ӯз–ЯӮБӮДӮӯӮйҒB
ҒuӮЁӮӨҒAҲкүһҢҲӮЬӮБӮДӮўӮйӮјҒvҺиӮЙҺқӮБӮҪҺ‘—ҝӮрҗUӮиӮИӮӘӮзҚІҒX–ШӮӘ“ҡӮҰӮйҒB
•”ҲхӮҪӮҝӮӘӮЙӮнӮ©ӮЙ‘ӣӮӘӮөӮӯӮИӮйҒB
ҒuӮЬӮ ‘ТӮДҒBӮ»ӮМ‘OӮЙӮұӮМ•xҺmҢ©‘‘ӮМҠЗ—қҗlӮіӮсӮЙҲҘҺAӮҫҒvӮ»ӮӨҢҫӮБӮДғJғEғ“ғ^ӮЙ—§ӮВ”wӮМҚӮӮў’jӮМӮЩӮӨӮрҢьӮӯҒB
ҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮаӮ©ӮИӮиӢҗҠҝӮИ•ыӮҫӮӘҒAҗg’·ӮҫӮҜӮЕҢҫӮӨӮИӮзӮОғJғEғ“ғ^ӮЙ—§ӮБӮДӮўӮй’jӮМ•ыӮа•үӮҜӮДӮўӮИӮўҒB
ҒuӮЗӮӨӮаҒA•xҺmҢ©‘‘ӮМҠЗ—қҗlӮрӮөӮДӮўӮйҳaӢv“cӮЖҗ\ӮөӮЬӮ·ҒB’ZӮўҠФӮЕӮ·ӮӘӮжӮлӮөӮӯӮЁҠиӮўӮөӮЬӮ·ҒvҳaӢv“cӮН’ҡ”JӮЙ“ӘӮрүәӮ°ӮйҒB
Ӯ»ӮкӮЙӮВӮзӮкӮД•”ҲхӮҪӮҝӮаҠFӮ»ӮкӮјӮкӮЙ“ӘӮрүәӮ°ӮҪҒB
ҒuӮўӮҰӮўӮҰҒAӮұӮБӮҝӮұӮ»–АҳfӮ©ӮҜӮйӮ©ӮаӮөӮкӮЬӮ№ӮсӮ©ӮзӮжӮлӮөӮӯӮЁҠиӮўӮөӮЬӮ·ӮЛҒvӮЖҚІҒX–ШҒB
ҒuӮЕӮНҒAӮЬӮёӮұӮМҺ{җЭӮЙӮВӮўӮДӮІҗа–ҫӮөӮЬӮөӮеӮӨӮ©ҒHҒvҳaӢv“cӮӘҚІҒX–ШӮЙҢьӮ©ӮБӮД•·ӮӯҒB
ҒuӮҰӮҰҒAӮЁҠиӮўӮөӮЬӮ·ҒvҚІҒX–ШӮНихӮӯҒB
Ӯ»ӮкӮЙ“ҡӮҰӮйӮжӮӨӮЙҳaӢv“cӮНҸ¬ӮіӮӯихӮўӮҪҒB
ҒuӮЬӮёҒAӮұӮұӮНҺу•tӮЖӮИӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBҺу•tӮЖӮўӮБӮДӮа•Ғ’iӮ©ӮзӮұӮұӮЙӮўӮйӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўӮМӮЕ•K—vӮИӮЖӮ«ӮНӢCҢ“ӮЛӮИӮӯҢДӮсӮЕӮӯӮҫӮіӮўҒBҢg‘С“dҳbӮМ”ФҚҶӮНҚІҒX–ШӮіӮсӮЙ’mӮзӮ№ӮДӮ ӮиӮЬӮ·ӮөҒAғpғ“ғtғҢғbғgӮМӮЩӮӨӮЙӮаӢLҚЪӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮұӮМғXғyҒ[ғXӮНӮЁҚDӮ«ӮЙӮІ—ҳ—pӮӯӮҫӮіӮўҒv–ЪӮМ‘OӮЙӮ Ӯйғ\ғtғ@ӮИӮЗӮрҺҰӮ·ҒB
ҒuӮ»ӮөӮДҒAҢәҠЦүЎӮМғhғAӮр’КӮиӮЬӮ·ӮЖғҠғrғ“ғOҒAғ_ғCғjғ“ғOӮЖӮИӮБӮДӮЁӮиӮЬӮ·ҒBғҠғrғ“ғOӮМ‘ӢӮМҠOӮЙӮНғfғbғLӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ӮМӮЕғoҒ[ғxғLғ…Ғ[ӮИӮЗӮаҸo—ҲӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮДӮўӮЬӮ·Ғv
ҺOҗl‘gӮӘҸ¬ӮіӮӯҠҪҗәӮрҸгӮ°ӮйҒB
Ғuғ_ғCғjғ“ғOӮ©ӮзғLғbғ`ғ“ӮЬӮЕ‘ұӮ«ӮМ•”ү®ӮЖӮИӮБӮДӮЁӮиӮЬӮ·ҒBҢәҠЦҗі–КӮЙӮ ӮиӮЬӮ·ғhғAӮӘғLғbғ`ғ“ӮЦ’КӮ¶ӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҺу•tҒAҠFӮіӮсӮ©ӮзҢ©ӮДүEҺиӮМҳLүәӮрҗiӮЭӮЬӮ·ӮЖ•—ҳCӮӘӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒBҲкүһ’jҸ—•КӮкӮДӮўӮЬӮ·ӮМӮЕӮІҲАҗSӮӯӮҫӮіӮўҒBӮ»ӮөӮДҒAҺу•tӮМҢгӮл‘ӨҒAҳLүәӮМҚ¶ҺиӮЙҺ„ӮМ•”ү®ӮӘӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒBҺ„ӮӘӮўӮйӮ©ӮзӮЖӮўӮБӮД‘ӣӮ®ӮМӮНү“—¶ӮөӮИӮўӮЕӮўӮўӮЕӮ·Ӯ©ӮзӮЛҒAӮИӮ©ӮИӮ©ӮЙҠжҸдӮИҚмӮиӮрӮөӮДӮЁӮиӮЬӮ·ӮөҒAүҪӮжӮиҠyӮөӮсӮЕӮўӮҪӮҫӮ©ӮИӮҜӮкӮО–{––“]“|ӮЕӮ·Ӯ©ӮзӮЛҒBӮ ҒAүғүпӮИӮЗӮНғҠғrғ“ғOӮИӮЗӮЕӮвӮБӮДӮўӮҪӮҫӮўӮДӮаӮ©ӮЬӮўӮЬӮ№ӮсӮМӮЕӮЗӮӨӮјӮІ—ҳ—pӮӯӮҫӮіӮўҒv
ӮвӮНӮиҠwҗ¶ӮӘҺgӮӨӮЖүғүпӮӘ‘ҪӮўӮМӮҫӮлӮӨӮЖ’фӮНҚlӮҰӮҪҒB
ҒuҚЕҢгӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪӮӘҒAҠFӮіӮсӮМ•”ү®ӮрӮІҲД“аӮөӮЬӮөӮеӮӨҒvӮ»ӮӨҢҫӮБӮДҳaӢv“cӮНғJғEғ“ғ^Ӯ©ӮзҸoӮйҒB
ҠFӮ»ӮкӮјӮкӮЙүЧ•ЁӮрҺқӮҝ—§ӮҝҸгӮӘӮйҒB
ҠFӮӘӮўӮҪғXғyҒ[ғXӮМ’Ҷүӣ•tӢЯӮЙӮ ӮйҠK’iӮрҳaӢv“cӮӘҸгӮиҒAӮ»ӮкӮЙ•”ҲхӮҪӮҝӮӘӮјӮлӮјӮлӮЖӮВӮўӮДӮўӮӯҒB
ҠK’iӮрҸгӮиӮ«ӮйӮЖҚ¶үEӮЙҗLӮСӮҪҳLүәӮЙҸoӮҪҒBҳLүәӮМ‘ӢӮ©ӮзӮНҢҡ•ЁӮМ— ҺиӮМҗXӮӘҢ©ӮҰӮйҒB
ҒuӮЕӮНҒAӮ ӮҝӮз‘ӨӮ©ӮзҒvӮЁӮжӮ»ғҠғrғ“ғOӮМҸгӮЙӮ ӮҪӮйӮЖӮұӮлӮЙӮ ӮйғhғAӮрҺҰӮ·ҒBҒuӮQӮOӮPҚҶҺәҒAӮQӮOӮQҚҶҺәҒAҠK’iӮрӢІӮЭӮЬӮөӮДҒAӮQӮOӮRҚҶҺәҒAӮQӮOӮSҚҶҺәӮЖӮИӮБӮДӮЁӮиӮЬӮ·ҒBҢ®ӮН“а‘ӨӮ©Ӯз•ВӮЯӮзӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBҠOӮ©ӮзҢ©ӮҰӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮЬӮ№ӮсӮӘҒAғoғӢғRғjҒ[ӮНҲк‘ұӮ«ӮЙӮИӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBҲИҸгӮЕӮ·ҒBүҪӮ©Һҝ–вӮНӮ ӮиӮЬӮ·Ӯ©ҒHҒv
ҳaӢv“cӮӘҸОҠзӮЕҳLүәӮЙ•АӮсӮҫ•”ҲхӮҪӮҝӮрҢ©үсӮ·ҒB
ҒuӮ ӮМҒAҠOӮ©ӮзҒcҒcӮВӮЬӮиӮұӮҝӮз‘ӨӮ©ӮзҠJӮҜӮйҢ®ӮН–іӮўӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒvҗВҺRҗГӮӘҺҝ–вӮрӮөӮҪҒB
‘јӮМ•”ҲхӮҪӮҝӮаихӮӯҒB
ҒuӮНӮўҒAӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒBӮҪӮҫҒAҚЎүс‘ЭӮөӮ«ӮиҸу‘ФӮЖӮИӮБӮДӮЁӮиӮЬӮ·ӮМӮЕҚІҒX–Ш—lӮ©Ӯз•K—vӮИӮўӮЖӮМӮұӮЖӮЕӮөӮҪӮМӮЕҒcҒcӮаӮөӮаҒAӮІ—ҳ—pӮМҚЫӮНҺу•tӮЙӮІӮҙӮўӮЬӮ·ӮМӮЕҒv
ҠFҒAҚІҒX–ШӮрҢ©ӮйҒB
ҒuӮИҒAӮИӮсӮҫӮжҒB•КӮЙӮўӮзӮИӮўӮҫӮлҒHҒ@үҙӮҪӮҝӮөӮ©ӮўӮИӮўӮсӮҫӮөҒA–йӮН’ҶӮ©ӮзӮ©ӮҜӮиӮбӮўӮўӮҫӮлҒv
ҒuӮЬҒAҠmӮ©ӮЙӮЛҒvҳZаV—Ъ—һӮӘҢЁӮрӮ·ӮӯӮЯӮйҒB
Ғu‘јӮЙӮІҺҝ–вӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮ©ҒHҒvҳaӢv“cӮНӮаӮӨҲк“xҠFӮрҢ©үсӮ·ҒB
”ҪүһӮӘ–іӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒuӮЕӮНҒAӮұӮкӮЕҒvӮЖҢҫӮБӮДҠK’iӮрүәӮиӮДӮўӮБӮҪҒB
ӮS
вь—]ӢИҗЬҒAӮЖӮўӮӨӮЩӮЗӮЕӮаӮИӮўӮӘӢНӮ©ӮЙӮаӮЯӮҪҒB
Ҳк”Ф•¶ӢеӮрҢҫӮБӮҪӮМӮН“Ў“c”ь‘ҒӮҫӮБӮҪҒB
ӮұӮкӮН’NӮаӮӘ—\‘zӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖӮҫӮБӮҪӮМӮЕҒAҺАҚЫ–в‘иӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮБӮДӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB
•”ү®Ҡ„ӮиӮЕӮ ӮйҒB
Ңҡ•ЁӮМ“Ң‘ӨҒAғҠғrғ“ғOӮМҸгӮЙ“–ӮҪӮйӮQӮOӮPҚҶҺәӮЙҚІҒX–ШҚ„‘ҫҒAҸгү®•~—№ҒA’фҷy“№ҒB
Ӯ»ӮМ—ЧҠK’iӮМ“Ң—ЧӮЙӮ ӮйӮQӮOӮQҚҶҺәӮЙҗВҺRҗГҒA“ҢҗқҒAҗV’JҗҗҺчҒB
ҠK’iӮМҗј—ЧӮМӮQӮOӮRҚҶҺәӮЙҗҙҸт–һүиҒA“Ў“c”ь‘ҒҒAҸ¬“№–ВҒB
Ӯ»ӮөӮДҒAҲк”Фҗј‘ӨӮМӮQӮOӮSҚҶҺәӮЙҳZаV—Ъ—һҒAүМҗм•—ҺqҒA”С’ЛүФҺqҒAӢҫӢҫҺqҒB
ӮЖӮўӮӨ”z’uӮЙӮИӮБӮҪҒB
ҒuӮЁӮўӮЁӮўҒAӮИӮәҺ„ӮҫӮҜ’jҸ—“ҜҺәӮИӮсӮҫҒHҒvҸгү®•~—№ӮӘ•·ӮӯҒB
ҚRӢcӮЖӮўӮӨӮжӮиӮНғ~ғ…Ғ[ғWғJғӢӮМғZғҠғtӮрҢҫӮӨӮ©ӮМӮжӮӨӮИ’ІҺqӮҫҒB
ҒuӮсӮ ҒHҒ@ӮўӮўӮҫӮл•КӮЙҒvҚІҒX–ШӮӘӮQӮOӮPҚҶҺәӮМғhғAӮрҠJӮҜӮДҢҫӮӨҒBҒuӮұӮкӮ¶ӮбӮИӮўӮЖ’jҸ—ӮМғoғүғ“ғXӮӘҲ«ӮўӮсӮҫӮжҒBҲк”Nҗ¶ӮҪӮҝӮр“ҜҺәӮЙӮ·ӮйӮнӮҜӮЙӮўӮ©ӮИӮўӮөҒAүҙӮҪӮҝӮ¶ӮбҠФҲбӮўӮаӢNӮұӮзӮсӮҫӮлҒv
ҒuҢNӮ»ӮкӮНҒcҒcҒvҸгү®•~—№ӮНӮ»ӮұӮЬӮЕҢҫӮўӮ©ӮҜӮДүҪӮ©ӮЙӢCӮӘӮВӮўӮҪӮжӮӨӮЙихӮӯҒB
’фӮНғhғAӮМӮЖӮұӮлӮЕӢ}ӮЙ—§ӮҝҺ~ӮЬӮБӮҪҸгү®•~—№ӮЙӮФӮВӮ©ӮиӮ»ӮӨӮЙӮИӮйҒBӮ»ӮМҢхҢiӮр“сӮВҢьӮұӮӨӮМӮQӮOӮRҚҶҺәӮЙ“ьӮлӮӨӮЖӮөӮДӮўӮҪҗҙҸтӮНҢ©ӮДӮўӮҪҒB
ҒuӮЗӮӨӮөӮҪӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒ@Ҹгү®•~җж”yҒv’фӮӘ•·ӮӯҒB
ҒuҸ—җ«Қ·•КӮМғWғҢғ“ғ}ӮЙӢCӮӘӮВӮўӮҪӮМӮҫҒBҺ„ӮНӮЬӮҪҢ«ӮӯӮИӮйҒvҗUӮиҢьӮ«ӮаӮ№ӮёӮЙҸгү®•~—№ӮӘ“ҡӮҰӮҪҒB
Ҹ—җ«Қ·•КӮМғWғҢғ“ғ}ҒH
ҒuӮЬҒ[ӮҪҒAӮӯӮҫӮзӮИӮўӮұӮЖӮҫӮлӮӨҒAӮЗӮӨӮ№ҒvҚІҒX–ШӮНӮўӮМҲкӮЙҺ©•ӘӮМғxғbғhӮрҢҲӮЯ‘ӢҚЫӮМғxғbғhӮЙғJғoғ“Ӯр’uӮўӮҪҒBҒuӮЁӮЁҒ[ҚLӮўӮИҒv
“ҜӮ¶ӮӯҺ©•ӘӮМғxғbғhӮрҢҲӮЯӮҪӮзӮөӮўҸгү®•~—№ӮағxғbғhӮЙғJғoғ“ӮрҸжӮ№ӮйҒB
ҒuӮӯӮҫӮзӮИӮўӮЖӮНӮИӮсӮҫӮЛҒBҺё—зӮИҒvӮ»ӮӨҢҫӮБӮДғxғbғhӮЙҚҳӮрүәӮлӮөҒAғXғ^ғCғӢӮМӮўӮў‘«Ӯр‘gӮЮҒB
Ҳк•ыӮQӮOӮQҚҶҺәҒB
җВҺRҗГӮНҒAӮЬӮ ӮұӮсӮИ”z’uӮЙӮИӮйӮЕӮ ӮлӮӨӮұӮЖӮр—\‘zӮөӮДӮўӮҪҒB
Ӣ°ӮзӮӯҺ©•ӘӮНҒAӮұӮМ“сҗlӮрӮЬӮЖӮЯӮйӮЖӮўӮӨҲУ–ЎҚҮӮўӮЕӮұӮМ•”ү®ӮИӮМӮҫӮлӮӨҒB‘јӮМ•”ү®ӮНҗҙҸт–һүиҒAҳZаV—Ъ—һӮӘӮ»ӮкӮјӮкҠДҺӢ–рӮМӮжӮӨӮИ–рҠ„ӮЖӮөӮДҠ„Ӯи“–ӮДӮзӮкӮДӮўӮйҒB
ҒuҗВҺRҗж”yҒAҺ©•ӘӮӘҗжӮЙҗQҸ°ҢҲӮЯӮДӮўӮўӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒvӮЖ“ҢҗқӮӘҠрӮөӮ»ӮӨӮЙҢҫӮӨҒB
җВҺRӮН—\‘zӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮМӮжӮӨӮЙҸОҠзӮЖӢӨӮЙ—№ҸіӮ·ӮйҒB
ҒuҗV’JҢNӮаҚDӮ«ӮИӮЖӮұҺgӮБӮДӮўӮўӮжҒBүҙӮНҚЕҢгӮЕӮўӮўӮ©ӮзҒv
•”ү®ӮЙҢ©ӮЖӮкӮДӮўӮйӮМӮ©ӮЪӮӨӮБӮЖӮөӮДӮўӮҪҲк”Nҗ¶ӮМҗV’JҗҗҺчӮЙҳbӮөӮ©Ӯ©ӮйҒB
ҒuӮНҒAӮНӮўҒBӮ ӮиӮӘӮЖӮӨӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒB–lӮұӮсӮИӮЙӮ·ӮІӮўӮЖӮұӮлӮҫӮЖҺvӮўӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪӮжҒv
җV’JҗҗҺчӮНҺqӢҹӮМӮжӮӨӮИҸОҠзӮрҢ©Ӯ№ӮйҒB
”ЮӮН–{“–ӮЙ‘еҠwҗ¶Ӯ©ӮЖҺvӮӨӮЩӮЗ—cӮўҠзӮрӮөӮДӮўӮйҒBӮЬӮ ҒAӮВӮўӮұӮМҠФӮЬӮЕҚӮҚZҗ¶ӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮр”ІӮ«ӮЙӮөӮДӮаӮҫҒB
ҒuӮӨӮсҒAүҙӮаӮұӮұӮЬӮЕҚӢүШӮИӮЖӮұӮлӮҫӮЖӮН’mӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒvҗV’JӮӘ“ьӮиҢы–TӮМғxғbғhӮЙүЧ•ЁӮр’uӮўӮҪӮМӮрҢ©ӮДҒAҗВҺRӮН•ЗӮЙ•ҪҚsӮЙ•АӮЧӮзӮкӮДӮўӮйғxғbғhӮрҺжӮБӮҪҒBҒuүҪӮ©ғRғlӮЕӮаҺgӮБӮҪӮМӮ©ҒHҒv
ҒuӮ ӮкҒHҒ@ӮұӮұӮБӮДӢҺ”NӮаҺgӮБӮҪӮЖӮұӮлӮЖӮ©ӮЕӮНӮИӮўӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒvҗV’JӮӘҺсӮрӮ©ӮөӮ°ӮйҒB
Ӯ»ӮкӮр•·ӮўӮД“ҢҗқӮӘӮЙӮвӮиӮЖҸОӮӨҒB
ҒuӮУӮУӮсҒAҗV’JҢNӮНҸүӮЯӮДӮҫӮ©Ӯз’mӮзӮИӮўӮҫӮлӮӨӮҜӮЗҒAғAғNғeғB•¶Ң|•”ӮМӢҺ”NӮМҚҮҸhӮНӮұӮұӮЕӮНӮИӮӯҒAҠCӮЕӮөӮҪӮжҒBҺ„ӮӘ•”’·ӮЙӮИӮйҚД—Ҳ”NӮЙӮНҢNӮМҲУҢ©Ӯа•·ӮўӮДӮ Ӯ°ӮзӮкӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮЛҒv“ҢҗқӮӘ‘еӮ°ӮіӮЙғxғbғhӮЙҚҳӮр—ҺӮЖӮ·ҒB
ҒuӮ»ҒAӮ»ӮӨӮИӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒcҒcҒvҗV’JӮМҸОҠзӮӘҲшӮ«ӮВӮБӮДӮўӮйӮМӮНӢCӮМӮ№ӮўӮҫӮлӮӨӮ©ҒBҒuӮ¶ӮбӮ ҒA–Ҳ”NҲбӮӨӮЖӮұӮлӮБӮДӮұӮЖӮИӮсӮЕӮ·Ӯ©ӮЛҒv
җV’JӮНҠзӮрҗВҺRӮЦӮЖҢьӮҜӮйҒB
ҒuӮӨӮсҒAӮЖӮиӮ ӮҰӮёүҙӮМҺQүБӮөӮҪҺOүсӮНҲбӮӨҸкҸҠӮҫӮЛҒB—\ҺZӮМ–в‘иӮЖӮ©ӮаӮўӮлӮўӮлӮ ӮйӮҫӮлӮӨӮ©ӮзҒAӮ»ӮМ’Іҗ®ӮЖҠFӮМҲУҢ©ӮЕ•ПӮнӮйӮсӮ¶ӮбӮИӮўҒBҚЎүсӮНҲУҢ©ӮИӮсӮД•·ӮўӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮҜӮЗҒcҒcҒvҗВҺRӮН•”ү®ӮрҠПҺ@Ӯ·ӮйҒB
ӮұӮМҢҡ•ЁӮЙ“ьӮБӮҪҺһӮ©ӮзӮҫӮӘҒAӮЗӮұӮрҢ©ӮДӮа–ШӮЕӮ ӮйҒBғRғeҒ[ғWӮИӮЗӮНӮвӮНӮиӮұӮӨӮўӮӨҚмӮиӮӘ‘ҪӮўӮМӮҫӮлӮӨҒB
ҺRӮН–ШҒAү·җтӮНҸфҒA—·ҠЩӮНгOҹ~ҒA“sүпӮНғRғ“ғNғҠҒ[ғgҒAҗВҺRӮНӮ»ӮсӮИғCғҒҒ[ғWӮр“ӘӮЙ•`ӮӯҒB
ӮұӮМ•”ү®ӮНҺOҗl•”ү®ӮМӮжӮӨӮҫҒBӮИӮәӮИӮзӮОғxғbғhӮӘҺOӮВӮөӮ©ӮИӮўӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBҠK’iӮӘӮ Ӯй‘ӨӮМ•ЗӮЙ•ҪҚsӮ·ӮйӮжӮӨӮЙҲкӮВҒAӮQӮOӮPҚҶҺә‘ӨӮМ•ЗӮ©Ӯз“ЛӮ«ҸoӮ·ӮжӮӨӮЙ“сӮВғxғbғhӮӘӮ ӮйҒBӮ»ӮМ‘јӮЙӮНғNғҚҒ[ғ[ғbғgӮӘ“ьӮиҢыӮ·Ӯ®үЎӮЙӮ ӮиҒA‘ӢҚЫӮЙӮНғeғҢғrӮӘӮ ӮйӮҫӮҜӮЕӮ ӮйҒB
ӮұӮӨӮўӮБӮҪҚмӮиӮМҢҡ•Ё“Б—LӮМ‘«ү№ӮӘӢҝӮӯӮжӮӨӮИӮұӮЖӮаӮИӮӯҒA—ЧӮМ•”ү®Ӯ©Ӯзү№Ӯа•·ӮұӮҰӮИӮўҒBҠOҢ©ӮӘ–ШӮЕӮ ӮйӮҫӮҜӮЕҒAҺе—vӮИ•”•ӘӮН“SҚңҚ\‘ўӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҳaӢv“cӮЖӮўӮӨҠЗ—қҗlӮӘҢҫӮБӮДӮўӮҪҒAҠжҸдӮИ‘ўӮиӮЖӮўӮӨӮМӮНӮұӮМӮұӮЖӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
җВҺRҗГӮНӢLүҜ—НӮӘӮўӮўҒB
ғhғAӮН“а‘ӨӮ©ӮзӮ©ӮҜӮзӮкӮйғVғҠғ“ғ_Ғ[ҸщҒAӮВӮЬӮиӢЙҲк”К“IӮИҢ®ӮӘӮВӮўӮДӮўӮйҒB‘ӢӮН‘еӮ«ӮӯӮұӮҝӮзӮаҢ®ӮӘӮВӮўӮДӮўӮйҒB
җВҺRҗГӮНҢ®ӮрҠJӮҜӮДғoғӢғRғjҒ[ӮЙҸoӮйҒB‘ӢӮМӮ·Ӯ®–TӮЙ“ъҸДӮҜӮөӮДҗFӮМ”–ӮкӮҪғXғҠғbғpӮӘӮ ӮйӮМӮЕӮ»ӮкӮрҺgӮӨҒB
ғxғүғ“ғ_ӮЙӮНҠщӮЙүҪҗlӮ©ӮӘҸoӮДӮўӮҪҒB
ғoғӢғRғjҒ[‘ӨӮН“мӮЙ–КӮөҺRӮМүәӮЙҚLӮӘӮй•—ҢiӮӘү“ӮӯӮЙҢ©ӮҰӮйҒBүОҸқӮөӮ»ӮӨӮИ“ъҚ·ӮөӮЖ”MӢCӮЙ–һӮҝӮҪ•—ӮӘүДӮрҗgӮЙҗхӮЭӮіӮ№ӮДӮӯӮкӮйҒBҗВҺRҗГӮНҺиӮЕӮРӮіӮөӮрҚмӮи‘ҫ—zӮрҺХӮйҒB
•xҺmҢ©‘‘ӮМ’“ҺФҸкӮ©ӮзӮМ“№ӮНҒAҸӯӮөҚsӮБӮҪӮЖӮұӮлӮЕҚ¶ҺиӮЙҗЬӮкҢ©ӮҰӮИӮӯӮИӮБӮДӮўӮйҒB
ҒuӮӨӮБӮРӮбҒ[Ғvҗј‘ӨӮМ•”ү®ӮМ‘OӮЕҒAҗВҺRӮЖ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙҺиӮЕӮРӮіӮөӮрҚмӮиғoғӢғRғjҒ[Ӯ©ӮзҗgӮрҸжӮиҸoӮөӮДӮўӮйӮМӮНҗҙҸт–һүиӮҫҒBҒuӮіӮБӮ·ӮӘ“oӮБӮДӮ«ӮҪӮҫӮҜӮ ӮйӮЛҒBҢ©ӮДӮЭӮДҒAҢҡ•ЁҸ¬ӮіӮўҒIҒv
ҒuӮ№ҒAҗж”yҒBӮ ӮсӮЬӮиҸжӮиҸoӮ·ӮЖҒAҠлӮИӮўӮЕӮ·ӮжҒvӮ»ӮМҢгӮлӮЕҗҙҸт–һүиӮрҲшӮ«–ЯӮ»ӮӨӮЖҸ¬“№–ВӮӘӮ ӮнӮДӮДӮўӮйҒB
ӮўӮвҒAҲшӮ«–ЯӮ»ӮӨӮЖӮөӮДӮўӮйӮжӮӨӮЙҢ©ӮҰӮйӮҫӮҜӮЕҒA“ЛӮ«—ҺӮЖӮ»ӮӨӮЖӮөӮДӮўӮйӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮӘҒBӮИӮЗӮЖҗВҺRӮНҚlӮҰӮҪҒB
“ҜӮ¶•”ү®ӮМ“Ў“c”ь‘ҒӮӘҢ©ӮҰӮИӮўӮӘҒAӢ°ӮзӮӯ”ЮҸ—ӮМӮұӮЖӮҫҒB“ъҸДӮҜӮрӢCӮЙӮөӮДҸoӮДӮұӮИӮўӮМӮҫӮлӮӨҒB
ҒuҲіҠПҒAҲіҠПҒv
җВҺRӮМҢгӮлӮЕ’фӮМҗәӮӘӮ·ӮйҒB
ҒuӮИӮЙӮ»ӮкҒAҠЦҗј•ЩҒHҒvҗВҺRӮНӮЙӮвӮиӮЖҢыҢіӮрҸгӮ°“ҡӮҰӮйҒB
ҒuӮұӮМҢiҗFӮҫӮжҒBҗҰӮўӮаӮсӮҫӮИҒAӮұӮсӮИҢiҗFҺRӮ¶ӮбӮИӮ«ӮбҢ©ӮкӮИӮўӮаӮсӮИҒv
’фҷy“№ӮНҗҙҸт–һүиӮЖ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙғoғӢғRғjҒ[ӮМҺиӮ·ӮиӮ©ӮзҸжӮиҸoӮ»ӮӨӮЖӮ·ӮйҒBҒuӮ»ӮкӮЖӮаҒAӮЁ‘OӮНүҪӮаҠҙӮ¶ӮИӮўӮ©ҒHҒv’фӮНҠЬӮЭӮМӮ ӮйҢҫӮў•ыӮЕҢҫӮӨҒB
ҒuӮИӮсӮҫҒAӮ»ӮМҢҫӮў•ыӮНҒHҒv
ҒuӮУӮБӮУӮБӮУҒBӮЁ‘OӮӘҢҫӮўӮ»ӮӨӮИӮұӮЖӮИӮз•ӘӮ©ӮйӮјҒAүҙҒv
ҒuҺ©җM–һҒXӮҫӮИ’фҒAӮЖӮўӮӨӮ©ӢCҺқӮҝҲ«ӮўӮјҒv”ыҠФӮЙӮөӮнӮрҠсӮ№ӮИӮӘӮзҢҫӮӨҒB
Ӯ»ӮкӮЙӮЁҚ\ӮўӮИӮөӮЕ’фӮНҗВҺRӮМҢыҗ^Һ—ӮрӮ·ӮйҒB
ҒuҒwӮЬӮ ҒAҺRӮ¶ӮбӮИӮўӮЖҢ©ӮкӮИӮўӮЖӮўӮӨӮМӮНӢtӮЙҺRӮИӮзӮўӮВӮЕӮаҢ©ӮкӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮҫӮлҒBҠҙ“®Ӯ·ӮйӮЩӮЗӮМӮұӮЖӮ¶ӮбӮИӮўҒxӮИӮсӮДӮЖӮұӮлӮҫӮлҒv
ҒuӮИӮсӮ©ӮЮӮ©ӮВӮӯӮИӮҹҒBӮ»ӮсӮИҗәӮөӮДӮйӮ©ҒHҒvӮ»ӮӨҢҫӮўӮВӮВӮаҠзӮНҸОӮБӮДӮўӮйҒB
ҒuӮўӮВӮЕӮаҢ©ӮкӮйӮӘҒA•Ғ’iҢ©ҠөӮкӮИӮў•—ҢiӮҫӮ©ӮзӮұӮ»”ьӮөӮўӮЖҠҙӮ¶ӮйҒBӮ»ӮкӮұӮ»ӮӘ”ьӮөӮўҢҙ—қӮҫҒvҸгү®•~—№ӮН”һҳm–XҺqӮрӮӨӮҝӮн‘гӮнӮиӮЙӮ ӮЁӮўӮЕӮўӮйҒB
Ғu”ьӮөӮўҢҙ—қӮБӮДҒcҒcҗж”yӮ»ӮкҺ©•ӘӮЕҚlӮҰӮҪӮҫӮҜӮЕӮөӮеҒv’фӮНҺиӮ·ӮиӮЙ”wӮр”CӮ№ӮйҺpҗЁӮЕӮўӮйҒB
ҒuҢҫӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮНҗіӮөӮўӮжҒA’фҒvҗВҺRҗГӮӘҸгү®•~—№ӮЙҺ^“ҜӮ·ӮйҒB
җј‘ӨӮЕҲк”Nҗ¶ӮМҺOҗl‘gӮӘ‘ӣӮўӮЕӮўӮйҒBҠFҲк—lӮЙ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮИ”ҪүһӮрҢ©Ӯ№ӮйӮМӮНҲзӮҝӮӘ“ҜӮ¶ӮҫӮ©ӮзӮҫӮлӮӨҒB
Ӯ»ӮұӮЙҢiҗFӮрҢ©ҸIӮҰӮҪҗҙҸт–һүиӮӘҚ¬ӮҙӮйҒB
ҒuӮИӮсӮҫӮўӮИӮсӮҫӮўҒBҢNӮҪӮҝӮНӮұӮсӮИ‘f“GӮИҸкҸҠӮЕӢcҳ_ӮИӮсӮДҒA‘f“GӮр’КӮиүzӮөӮДүЯҢғӮҫӮИҒv
җҙҸт–һүиӮӘ’фӮМ—ЧӮЕ“ҜӮ¶‘Мҗ§ӮЕҺиӮ·ӮиӮЙҠсӮиӮ©Ӯ©ӮиӮИӮӘӮзҒA’фӮМҢЁӮЙӮҰӮзӮ»ӮӨӮЙ•IӮр“ЛӮӯҒB
ҒuӮЬӮ ҒAҢҫӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮН—ЗӮӯ•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮҜӮЗҲк—қӮ ӮйӮИҒBҗГӮаҗж”yӮаҲкҠKӮЙҚsӮ«ӮЬӮ№ӮсӮ©ҒHҒv’фӮН’сҲДӮ·ӮйҒB
ӮіӮ·ӮӘӮЙӮұӮұӮНҸӢӮўӮЖҠҙӮ¶ӮДӮМӮұӮЖӮҫҒB
ӮT
ҲкҠKӮЙҚ~ӮиӮДӮ«ӮҪӮМӮНҸгү®•~—№ҒAҗҙҸт–һүиҒA’фҷy“№ҒAҗВҺRҗГӮЕӮ ӮйҒB
ҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮНҒAҠЗ—қҗlӮЙҳbӮӘӮ ӮйӮЖҢҫӮБӮДҠЗ—қҗlҺәӮрғmғbғNӮөӮД“ьӮБӮДӮўӮБӮҪҒB
ҒuӮЦӮҰҒAӮұӮкӮНӮИӮ©ӮИӮ©ҒcҒcҒvҸгү®•~ӮӘ‘§ӮрӮаӮзӮ·ҒB
ғҠғrғ“ғOӮМҚLӮіӮЖҚмӮиӮӘҒAҲкғRғeҒ[ғWӮМӮаӮМӮҫӮЖӮНҺvӮҰӮИӮўӮЩӮЗӢГӮБӮҪӮаӮМӮҫӮБӮҪӮ©ӮзӮҫҒB
ҠK’iӮрүәӮиӮҪӮЖӮұӮлӮМғhғAӮр“ьӮйӮЖүE‘ӨӮЙӮНҒAҸфҲкҸфӮНӮ ӮлӮӨӮ©ӮЖӮўӮӨ‘«ӮМ’ZӮўҗ[Ӯў’ғҗFӮМғeҒ[ғuғӢӮрғRӮМҺҡӮЙҲНӮЮӮжӮӨӮЙғ\ғtғ@ӮӘӮ ӮйҒBүEҺиӮМ•З‘ӨӮЙӮНӮұӮкӮЬӮҪ‘еӮ«ӮИғeғҢғrҒ\Ғ\ҺlҸ\“сғCғ“ғ`ӮҫӮлӮӨӮ©Ғ\Ғ\ӮӘӮ ӮиҒA—ј—ЧӮЙ”wӮМ’бӮў–{’IӮӘӮ ӮйҒBӮ»ӮМҸгӮЙӮНҺКҗ^Ӯв’u•ЁӮӘӮ ӮйҒB
ӮжӮӯҺи“ьӮкӮіӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮЕҡәӮаӮ©ӮФӮБӮДӮўӮИӮўҒB
’“ҺФҸк‘ӨӮЙӮН‘еӮ«ӮИ‘ӢӮӘӮ ӮиҒAҠOӮ©Ӯз“ьӮйҢхӮӘҚLӮў•”ү®ӮрҸЖӮзӮөҸoӮөӮДӮўӮйҒBӮҫӮӘӮіӮ·ӮӘӮЙ•”ү®ӮМҚ¶үңӮН”–ҲГӮӯӮИӮБӮДӮўӮйӮӘҒAӮ»ӮкӮӘӮЬӮҪ—БӮөӮ»ӮӨӮИҲуҸЫӮрҺқӮҪӮ№ӮДӮӯӮкӮйҒB
ӮұӮҝӮзӮЙӮН‘«ӮМ’·ӮўҗHҺ–—pӮМғeҒ[ғuғӢӮӘ“сӮВ•АӮсӮЕӮўӮйҒBҲЦҺqӮМҗ”Ӯ©ӮзӮөӮДҲк“xӮЙ‘SҲхҗHҺ–ӮрӮ·ӮйӮМӮН–і—қӮ»ӮӨӮИҠҙӮ¶ӮҫҒB
ҒuӮөӮ©ӮөҒAғzғ“ғgҠOӮЖӮНҠi•КӮіӮкӮҪҗўҠEӮБӮДҠҙӮ¶ӮҫӮИҒv
’фӮН•”ү®ӮрӮ®ӮйӮиӮЖҢ©үсӮ·ҒB
ҒuӮЬӮ ҒAүЖӮИӮсӮДӮ»ӮсӮИӮаӮсӮЕӮөӮеҒBҠi•КӮіӮкӮҪҗўҠEӮҫӮЖҠҙӮ¶ӮйӮ©ӮзӮұӮ»ҲАҗSӮөӮД–°ӮкӮйӮсӮҫӮжҒvҗВҺRӮНҗ^ӮБҗжӮЙғ\ғtғ@ӮЙҚАӮйҒBҒuҚЎӮ¶ӮбҒA“ЭҠҙӮЙӮИӮиӮ·Ӯ¬ӮДүҪҸҲӮЕӮа•КӮМҗўҠEӮҫӮБӮДҠҙӮ¶ӮДӮўӮйҗlӮМ•ыӮӘ‘ҪӮўӮҜӮЗӮЛҒv
ҒuӮЬӮ ӮЬӮ ҒAҳbӮНӮ ӮЖӮ ӮЖҒIҒv
ҺиӮрӮРӮзӮРӮзӮіӮ№ӮИӮӘӮз–һүиӮӘ•”ү®ӮМҗ^Ӯс’ҶӮЕҗmүӨ—§ӮҝӮрӮ·ӮйҒB
ҒuӮИӮсӮҫӮжҒAӮ ӮЖӮБӮДүҪӮ©Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЕӮаӮ ӮйӮМӮ©ҒHҒv’фӮӘ•·ӮӯҒB
үҪӮөӮлғhғAӮМӮЖӮұӮлӮЙӮўӮҪ’фӮЙҢьӮ©ӮБӮД–һүиӮӘҗmүӨ—§ӮҝӮрӮөӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒA’фӮӘ•·Ӯ©ӮҙӮйӮр“ҫӮИӮўҒBҸгү®•~—№ӮН–{’IӮЙ“B•tӮҜӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒB
ҒuӮМҒAӮЭҒAӮаҒAӮМҒIҒ@ӮаӮӨҒAҚAҠЈӮўӮҝӮбӮБӮДӮіӮҹҒBғLғbғ`ғ“ӮБӮДҸҹҺиӮЙҺgӮБӮДӮўӮўӮсӮҫӮжӮЛҒHҒv
ӮҰӮЦӮЦҒ[ӮЖ”’ӮўҺ•ӮрҢ©Ӯ№ӮИӮӘӮзҢ’ҚN“IӮЙҸОӮӨ–һүиӮНӮ©ӮнӮўӮўҒB’фҷy“№ӮНӮ»ӮӨҺvӮӨҒB
Ғu•ӘӮ©ӮБӮҪӮжҒAҠЗ—қҗlӮіӮсӮЙ•·Ӯ«ӮЙҚsӮұӮӨҒBҒcҒcҳaӢv“cӮіӮсӮҫӮБӮҜҒv
ҠЗ—қҗlӮНүхӮӯ—№үрӮрҺҰӮөӮДӮӯӮкӮҪҒBҒu—в‘ ҢЙӮМ’ҶӮМ”һ’ғӮНҲщӮсӮЕӮ©ӮЬӮўӮЬӮ№ӮсӮжҒBӮҪӮҫҒAҗHҚЮӮН‘К–ЪӮЕӮ·ӮжҒAҚЎ“ъӮМӮІ”СӮӘӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮМӮЕӮЛҒv
ғLғbғ`ғ“ӮН•Ғ’КӮМүЖ’лӮМӮаӮМӮЖ•ПӮнӮиӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB‘јӮӘҗҰӮўӮМӮЕ’фӮНҸӯӮө”ҸҺq”ІӮҜӮөӮДӮөӮҪӮӘҗeӢЯҠҙӮӘ•ҰӮӯӮМӮрҠoӮҰӮҪҒB
–һүиӮН‘еӮ«ӮИ—в‘ ҢЙӮрҠJӮҜҒA”һ’ғӮрҢ©ӮВӮҜҺжӮиҸoӮ·ҒBӮ»ӮМҠФӮЙ’фӮӘғOғүғXӮрҗlҗ”•ӘҢ©ӮВӮҜ•АӮЧӮДӮўӮҪҒB
ҒuӮұӮМғ`Ғ[ғҖғҸҒ[ғNҒAӮ·ӮОӮзӮөӮўӮЛҒv–һүиӮӘҠрӮөӮ»ӮӨӮЙҢҫӮБӮҪҒB
’фӮНҢЁӮрӮ·ӮӯӮЯӮйҒB
’фӮЖ–һүиӮӘҒAӮ»ӮкӮјӮк“сӮВӮёӮВғOғүғXӮрҺқӮБӮДғҠғrғ“ғOӮЙ“НӮҜӮҪҒB
ҒuӮЁӮЁҒA—ҲӮйӮаӮМӮӘ—ҲӮҪӮ©ҒcҒcҒvҚЎӮЬӮЕ–{’IӮрҢ©ӮДӮўӮҪҸгү®•~—№ӮӘ—§ӮҝҸгӮӘӮйҒB
Ӯ»ӮӨӮўӮҰӮОҒAҗВҺRӮЖҸгү®•~җж”yӮӘҳbӮөӮрӮөӮДӮўӮйӮЖӮұӮлӮрӮ ӮЬӮиӮЭӮҪӮұӮЖӮӘӮИӮўҒAӮЖ’фӮНӮУӮЖҺvӮӨҒB
ҒuӮУӮҹҒ[ҒcҒcҒv‘еӮ«Ӯӯ‘МӮр”ҪӮзӮөӮДӮ©ӮзҒA–һүиӮН‘«Ӯр“ҠӮ°ҸoӮөӮДғ\ғtғ@ӮЙҚАӮйҒB
ҒuӮЁӮўҒAҸ—ӮИӮсӮҫӮ©ӮзҸӯӮөӮН’pӮ¶ӮзӮўӮБӮДӮаӮсӮрҺқӮДӮжӮИҒv
ҒuӮИӮҹӮЙӮЎҒHҒ@’фҒA—~ҸоӮөӮҪӮҹҒ[ҒHҒv
ҒuғoҒAғoғJҢҫӮБӮДӮсӮ¶ӮбӮЛӮҰӮжҒIҒ@Ҹгү®•~җж”yҢ©ҸKӮҰӮБӮДӮМӮіҒv’фӮӘҸЕӮБӮДҢҫӮӨҒB
’фӮӘҸЕӮБӮДӮўӮйӮМӮрҢ©ӮД–һүиӮӘӮ©ӮзӮ©ӮзӮЖҸОӮӨҒB
Ғu’фӮНҚӘӮӘҗі’јӮИӮсӮҫӮжҒvҗВҺRӮӘӮ©ӮзӮ©ӮӨҒB
ҒuҚјӢ\ӮЙҲшӮБӮ©Ӯ©Ӯйғ^ғCғvҒHҒv
ҒuӮўӮвҒAҗ^ҠдӮрҢ©Ӯй–ЪӮНҠmӮ©ӮҫӮ©ӮзӮЛҒBӮНӮБӮ«ӮиӮЖ’fӮйғ^ғCғvҒcҒcӮ©ӮИҒHҒv
ҒuӮЁ‘OӮзҗlӮМӮұӮЖӮрҸҹҺиӮЙҒcҒcӮ»ӮкӮжӮиӮіӮБӮ«ӮМӮЗӮұӮЕӮа•КӮМҗўҠEӮБӮДӮМӮНӮИӮсӮҫӮБӮҪӮсӮҫӮжҒv’фӮНҳb‘иӮр•ПӮҰӮйҒB
ҒuӮЁҒAӮ»ӮкҺ„ӮаӢCӮЙӮИӮйҒIҒ@үЖӮМ’ҶӮӘ•КӮМҗўҠEӮИӮсӮЕӮөӮеҒAӮ»ӮМҠOӮНӮЗӮӨӮ ӮБӮДӮаҠOӮМҗўҠEӮ¶ӮбӮИӮўӮМҒHҒv–һүиӮНӮұӮлӮиӮЖҳb‘иӮЙҸжӮБӮҪҒB
Ҹгү®•~ӮӘҒAӮУӮсҒAӮЖӮжӮӨӮвӮӯ•·ӮұӮҰӮйӮЩӮЗӮМӮҪӮЯ‘§ӮрӮВӮӯҒB
ҒuӮӨӮсҒAҚЕҸүӮМҚlӮҰӮЕҢҫӮҰӮОӮ»ӮӨӮИӮйӮсӮҫӮҜӮЗӮЛҒBҚlӮҰӮДӮЭӮИӮжҒBҚЎ–lӮзӮӘ’КӮБӮДӮўӮй‘еҠwҒAӮ»ӮМҺь•УӮМҠXҒAӮЗӮұӮӘҠOӮҫӮЖӮўӮҰӮйҒHҒ@Ҹ—ӮМҺqӮНӮЬӮёӮўӮЖҺvӮӨӮҜӮкӮЗҒA’jӮҫӮБӮҪӮзӢCү·ӮіӮҰҚӮӮҜӮкӮОҠOӮЕҗQӮДӮДӮаүҪӮМ–в‘иӮаӮИӮўҒBҸнӮЙҠX“”ӮН“”ӮБӮДӮўӮйӮөҒAҢg‘СӮЕӮўӮВӮЕӮа’NӮЖӮЕӮаҳA—ҚӮӘҺжӮкӮйҒvӮ»ӮұӮЬӮЕҢҫӮӨӮЖҗВҺRӮНҲꑧӮВӮӯҒB
җВҺRӮМӮұӮМҚsҲЧӮНҺOҗlӮЙҚlӮҰӮйҺһҠФӮр—^ӮҰӮҪҒBӮўӮвҒAӮ ӮЬӮиӢ»–ЎӮИӮіӮ°ӮЙӮөӮДӮўӮйҸгү®•~—№ӮН“БӮЙҚlӮҰӮДӮаӮўӮИӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB
–һүиӮНҗВҺRӮМҢҫӮӨӮұӮЖӮрҚlӮҰӮДӮЭӮҪҒB
ӮЬӮ ҒAҗВҺRӮМҢҫӮӨӮұӮЖӮНӮИӮсӮЖӮИӮӯ•ӘӮ©ӮйҒBҠOӮЕҲк–йӮрүЯӮІӮөӮҪӮЖӮөӮДӮа•ҪӢCӮЕӮ ӮйҒBӮЖӮўӮӨӮМӮНҗl‘МӮМҗ¶‘¶ӮЖӮўӮӨҲУ–ЎӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҢ»ҚЭӮМҺРүпӮМҠX’ҶӮЕӮ ӮкӮОҒAӮЗӮұӮЕӮ ӮБӮДӮаүҪӮзӮ©ӮМҠЦҢWӮН•ЫӮҪӮкӮҪӮЬӮЬӮўӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮДӮўӮйҒcҒcӮЖӮўӮӨӮЖӮұӮлӮ©ҒB
’фӮӘ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮИӮұӮЖӮрҢыӮЙҸoӮөӮДҢҫӮБӮҪҒBҒuҒcҒcӮБӮДӮұӮЖӮ©ҒHҒ@Ӯ»ӮиӮбҠmӮ©ӮЙҠOӮЖӮўӮӨӮЙӮНҠГӮўӢ«ҠEӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮҜӮЗҒAүЖӮБӮДӢуҠФӮН•К•ЁӮҫӮәҒv
ҒuӮ»ӮкӮНҒAҢoҢұҒHҒ@Ӯ»ӮкӮЖӮаҒAҺv‘zҒHҒv
ҒuӮӨҒ[ӮсҒAӮЗӮҝӮзӮ©ӮЖҢҫӮБӮҪӮзҢoҢұӮЙӮИӮйӮ©ӮИҒcҒcӮ ҒA‘К–ЪӮҫҒBӮ»ӮкӮ¶Ӯбҗа“ҫ—НӮИӮөӮ¶ӮбӮсҒv
’фӮНҒAҢҫӮБӮДӮўӮй“r’ҶӮЕҺ©•ӘӮМҲУҢ©Ӯр”Ы’иӮ·ӮйҒB
ҒuӮұӮӨӮўӮӨӮМӮН•Пү»ӮөӮвӮ·ӮӯӮБӮДһB–ҶӮҫӮ©ӮзӮЛҒBӮ¶ӮбӮ ҒAүҪӮЕүЖӮЕҲАҗSӮрҠҙӮ¶ӮйӮМӮ©ӮнӮ©ӮйҒHҒv
ҒuӮіӮБӮ«ҢҫӮБӮҪҢoҢұӮӘ‘еӮ«ӮўӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮМҒHҒ@Ӯ»ӮкӮЖӮаүЖ‘°ӮӘҲкҸҸӮЙӮўӮйӮБӮДӮұӮЖӮ©Ӯз”hҗ¶ӮөӮДҒAҺзӮзӮкӮДӮўӮйӮБӮДӮўӮӨ•ЫҢм–П‘zӮЙӮаӮИӮйӮ©ӮИӮҹҒcҒcҒvҚЎ“xӮН–һүиӮӘ“ҡӮҰӮйҒB
ҒuҲкҗl•йӮзӮөӮИӮзүЖ‘°ӮНӮўӮИӮўӮнҒvҸгү®•~—№ӮӘ—ј’fҒB
ҒuӮӨҒcҒcӮ»ӮБӮ©ҒBӮҫӮжӮЛӮҘҒv–һүиӮН—Һ’_Ӯө‘«ҢіӮрӮЭӮйҒB
ҒuӮЕӮаҢoҢұӮБӮДҢҫӮӨӮМӮНҗіӮөӮўҒv
ҒuӮҰҒAғ}ғWҒHҒv–һүиӮНҠзӮрҸгӮ°ӮйҒBҒuӮжӮБӮөӮбҒIҒv
ҒuүҪ“xӮа’КӮБӮДӮўӮй“№ӮЖӮ©ҒA“XӮЖӮ©ӮЕӮіҒAӮЗӮұӮЙүҪӮӘӮ ӮйӮ©ҒAӮЗӮұӮӘҗl’КӮиӮӘ‘ҪӮўӮ©ӮЖӮ©ҢoҢұӮЖӮөӮД’mӮБӮДӮўӮйӮЕӮөӮеҒBӮ Ӯ»ӮұӮМӢИӮӘӮиҠpӮНӮ ӮЬӮиҗlӮӘҸoӮДӮұӮИӮўӮ©ӮзҒAӢCӮрӮВӮҜӮИӮӯӮДӮа‘еҸд•vӮЖӮ©ҺvӮӨӮЕӮөӮеҒBҠmӮ©ӮЙҢoҢұҸгҠлҢҜҗ«ӮНҸӯӮИӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮҜӮкӮЗҒAүВ”\җ«ӮНғ[ғҚӮЖӮНҢҫӮўҗШӮкӮИӮўӮНӮёҒBӮ»ӮкӮЕӮаүҙӮзӮНҲАҗSӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӮЗӮӨӮөӮДӮҫӮ©•ӘӮ©ӮйҒHҒv
ҒuӮҫӮ©ӮзҢoҢұӮЕӮөӮеҒHҒv
ҒuӮаӮӨҲк•аҒv
ҒuҢoҢұҒcҒcҒv’фӮН“ӘӮЙҢҢүtӮЕҺ_‘fӮрҸ„ӮзӮ·ҒBҒuҠөӮкҒAҺvӮўҚһӮЭҒA–ы’fҒAҠГӮҰҒcҒcҗф”]ҒHҒv
Ғu’фӮН”ҺҠwӮҫӮЛҒBӮ»ӮМӮЗӮкӮаҗіүрҒAҚЕҸI“IӮЙүҙӮзӮНҺ©•ӘӮрҺ©•ӘӮЕҗф”]ӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮұӮНҲА‘SӮИҸкҸҠӮҫӮБӮДӮЛҒvҗВҺRҗГӮНҺиӮрҚLӮ°ӮДӢуӮрӮИӮЕӮйҺd‘җҒBҒuӮ¶ӮбӮИӮўӮЖ‘МӮӘҺқӮҪӮИӮўӮсӮҫӮжҒAӮЗӮкӮаӮұӮкӮаӢ^ӮнӮөӮўӮ¶ӮбҸнӮЙӢCӮр’ЈӮиӢlӮЯӮДӮИӮ«ӮбӮўӮИӮӯӮҝӮбӮИӮзӮИӮӯӮИӮйҒBӮҫӮ©ӮзӮИӮйӮЧӮӯ•ү’SӮрӮ©ӮҜӮИӮўӮжӮӨӮЙӮўӮлӮўӮлӮИүВ”\җ«ӮрҗШӮиҺМӮДӮДӮйӮсӮҫӮжҒv
’фӮЖ–һүиӮНҠзӮрҚҮӮнӮ№ӮҪҒB
ӮўӮвҒAӮаӮөӮ©ӮөӮҪӮз“сҗl“ҜҺһӮЙӮ»ӮкӮјӮкӮМ”wҢгӮӘӢCӮЙӮИӮиӮ»ӮҝӮзӮрҢьӮўӮҪӮҫӮҜӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮӘҒBӮаӮөӮӯӮНӮЗӮҝӮзӮ©ҲкҗlӮӘӮ»ӮӨӮҫӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB
җВҺRӮНӮ»ӮсӮИ“сҗlӮрҢ©ӮДҒA–{“–ӮЙӮЁҺ—ҚҮӮўӮМ“сҗlӮҫӮЖҺvӮӨҒB“сҗlӮЖӮа“ӘӮН—ЗӮӯүсӮиҒAҠҙҸоӮМӢN•ҡӮаҺ—ӮДӮўӮйҒB
ӮҪӮҫҺc”OӮИӮМӮӘ’фӮНҺ©•ӘӮЙӮИӮўӮаӮМӮрӢҒӮЯӮҪӮӘӮиҒAҗҙҸтӮНҺ©•ӘӮЖҺ—ӮҪҗ«ҺҝӮМӮаӮМӮрӢҒӮЯӮДӮўӮйӮЖӮұӮлӮҫҒB’фӮНҗҙҸтӮМӢCҺқӮҝӮЙӢCӮӘӮВӮўӮДӮўӮйӮҫӮлӮӨӮҜӮкӮЗҒA’фӮМӢҒӮЯӮйӮаӮМӮНҺ©•ӘӮЖӮНҲЩҺҝӮИӮаӮМӮҫҒB
Ӯ»ӮӨӮўӮӨҲУ–ЎӮЕ“сҗlӮНҲЩҺҝӮИӮМӮҫӮҜӮкӮЗҒAӮЖҗВҺRӮН•ЫҢмҺТӮМӢC•ӘӮЕ“сҗlӮрҢ©ӮДӮўӮйҺ©•ӘӮӘӮЁӮ©ӮөӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuүЖӮӘҲАҗSӮЕӮ«ӮйӢуҠФӮБӮДӮўӮӨӮМӮНӮ»ӮкӮЕҗа–ҫӮЕӮ«ӮйҒB–в‘иӮНҠOӮҫҒBүҙӮзӮН•Ғ’iҲбӮӨҗlҠФӮЕҲбӮӨҺvҚlӮрӮөӮДҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮйӮҜӮкӮЗҒAҺАӮНҸо•сӮрӢӨ—LӮ·Ӯй“®•ЁӮЕӮаӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮНғӮғүғӢӮЖӮўӮӨҢ`ӮЕҺРүпӮрҢ`җ¬ӮөӮДӮўӮӯҸгӮЕҺ©‘RӮЖҚ\’zӮіӮкӮДӮўӮӯӮаӮМӮҫӮҜӮкӮЗҒAүҙӮзӮЭӮҪӮўӮЙҸүӮЯӮ©ӮзӮұӮМ”nҺӯӮЕӮ©ӮўҺРүпӮМ’ҶӮЙҗ¶ӮЬӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҗlҠФӮЙӮНҒAҺАӮЙҸ¬ӮіӮўҚ Ӯ©Ӯзҗ[‘wҲУҺҜӮЙҚҸӮЬӮкӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮйҒBӮ»ӮөӮДҒA‘јҗlӮӘ“ҜӮ¶ҠВӢ«ӮЕҲзӮБӮҪӮБӮДӮұӮЖӮа’mӮБӮДӮўӮй–уӮҫҒv
ҒuӮЬӮ ҒA”ӘҠ„•ыӮ»ӮӨӮҫӮнӮИҒv
Ғuҷy“№Ӯ»ӮМ”ӘҠ„ӮБӮДӮЗӮұӮ©Ӯз—ҲӮҪӮМӮіҒv
ҒuғAғoғEғgҒv
ҒuҒcҒcҒv
ҒuӮЬӮ ӮЬӮ ҒcҒcӮ»ӮсӮИҠВӢ«ӮЕүҙӮзӮӘӮ·ӮйҚмӢЖӮБӮДӮМӮНүј‘z“IӮЙ‘ҠҺиӮЙӢЯӮГӮӯӮұӮЖӮИӮсӮҫҒBӮ ӮўӮВӮНүҙӮЖ“ҜӮ¶ҠВӢ«ӮЕҲзӮБӮДӮйӮсӮҫӮ©ӮзҚlӮҰ•ыӮаҺ—ӮДӮўӮйӮНӮёӮБӮДӮЛҒBӮ»ӮөӮДҒAүҙӮзӮМҚlӮҰӮНӮұӮМҚ‘ӮМҠX’ҶӮНҲА‘SҒBӢЙ’[ӮИҳbҒAӮ»ӮсӮИҚlӮҰӮрҠFӮӘҺқӮБӮДӮўӮйҸҠӮ¶ӮбҠOӮа’ҶӮа•ПӮнӮзӮИӮўӮБӮДӮұӮЖӮіҒBҠX’ҶӮ¶ӮбҠOӮЖ’ҶӮМӢ«ҠEӮӘӮИӮӯӮИӮБӮДӮЗӮұӮЕӮаҺ©•ӘӮҪӮҝӮМҲАҗSӮИҗўҠEӮЙӮИӮБӮДӮйӮБӮДӮнӮҜҒBӮ»ӮкӮЕҒAҠOӮӘӮ ӮйӮұӮЖӮр–YӮкӮДӮўӮйҒA“ЭҠҙӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒvҗВҺRӮН”һ’ғӮрҲкҢыҲщӮЮҒBғOғүғXӮЙӮНҗ…“HӮӘӮВӮўӮДӮўӮйҒBҒu—бӮҰӮОӮҫӮҜӮЗҒAӮ»ӮсӮИҗl’BӮӘҗ[ӮўҗXӮЕҲк–йӮр–ҫӮ©Ӯ»ӮӨӮЖӮөӮҪӮз‘е•ПӮИҳbӮҫӮжҒBҸ¬ӮіӮИ•Ёү№ӮӘӢCӮЙӮИӮиҒAҸbӮМ–ВӮ«җәӮЙӢҜӮҰҒAҲГҲЕӮЙүҪӮ©ӮўӮйӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮИӮсӮД–П‘zӮр•шӮўӮҪӮиҒAӢCӮМҺгӮўҗlӮҫӮБӮҪӮз”ӯӢ¶ӮЬӮЕҚsӮ©ӮИӮӯӮБӮДӮаҲкҗҮӮаӮЕӮ«ӮИӮўӮМӮНӮҙӮзӮҫӮлӮӨӮЛҒB”ӯӢ¶ӮөӮҪӮЖӮұӮлӮЕӮ»ӮұӮНҠOӮИӮсӮҫӮ©Ӯз“ҰӮ°ҸкӮИӮсӮДӮЗӮұӮЙӮаӮИӮўӮсӮҫӮҜӮЗӮЛҒB–YӮкӮДӮўӮйӮМӮіӮұӮМҗўҠEӮН•КӮМҗўҠEӮИӮсӮ©Ӯ¶ӮбӮИӮўӮБӮДӮұӮЖӮрӮЛҒv
ӮҪӮЗӮи’…ӮўӮҪҢӢҳ_ӮЙҺlҗlӮНҢыӮрҠJӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuҳbӮН’eӮсӮЕӮўӮЬӮ·Ӯ©ҒHҒv
Ӣ}ӮЙғhғAӮМӮЖӮұӮлӮ©ӮзҗәӮӘӮ©Ӯ©Ӯи”wӮрҢьӮҜӮДӮўӮҪ’фӮЖ–һүиӮНӢБӮўӮҪҒB
ҒuӮнӮБҒIҒ@ӮСӮБӮӯӮиӮөӮҪӮҹҒBҳaӢv“cӮіӮсӮ©ҒcҒcӮ ҒA•”’·ӮаҒv
ҳaӢv“cӮМ—ЧӮЙӮНӮӘӮБӮөӮиӮөӮҪҚІҒX–ШҚ„‘ҫ•”’·ӮӘ—§ӮБӮДӮўӮҪҒB
Ӯ»ӮӨӮўӮҰӮОӮұӮұӮЕҳbӮөҺnӮЯӮДӮ©ӮзҢӢҚ\ҢoӮБӮДӮўӮйӮӘҒAӮ»ӮМҠФӮёӮБӮЖҚІҒX–Ш•”’·Ӯа•xҺmҢ©‘‘ӮМҠЗ—қҗlӮЖҳbӮөӮДӮўӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒAӮЖ–һүиӮНӢCӮЙӮИӮБӮҪҒBӮ»ӮсӮИҳbӮ·ӮұӮЖӮИӮЗӮ ӮйӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒcҒcҒB
ҒuӮ»ӮлӮ»ӮлҒA’ӢҗHӮМҸҖ”хӮрҺnӮЯӮЬӮ·ӮЛҒB’ӢҗHӮНҠИ’PӮИӮаӮМӮЕӮ·ӮМӮЕҸӯҒXӮЁ‘ТӮҝӮӯӮҫӮіӮўҒvҳaӢv“cӮН’ҡ”JӮЙӮўӮБӮҪҒB
ҒuӮ ӮкҒA’ӢҗHӮБӮДҸoӮИӮўӮсӮ¶ӮбӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪӮБӮҜҒHҒv’фӮӘҺсӮрӮ©ӮөӮ°ӮйҒB
ҠmӮ©ӮЙ’©–йҗHҺ–•tӮЖғpғ“ғtғҢғbғgӮЙӮНҸ‘ӮўӮДӮ ӮБӮҪӮНӮёӮҫҒB
ҚІҒX–ШӮЖҳaӢv“cӮӘҺӢҗьӮрҚҮӮнӮ·ҒB
ҒuӮЬӮ ҒcҒcғTҒ[ғrғXӮЕӮ·ҒvҳaӢv“cӮНҸОҠзӮЕ“ҡӮҰӮҪҒB
ӮU
’ӢҗHӮНҳaӢv“cӮМҢҫӮБӮҪӮЖӮЁӮиғVғ“ғvғӢӮИӮаӮМӮЕӮІ”СҒAӮЁӮРӮҪӮөҒAҺП•ЁҒA–Ў‘XҸ`ҒAӮЖӮўӮБӮҪғҒғjғ…Ғ[ӮҫӮБӮҪҒB
ғeҒ[ғuғӢӮН“сӮВӮ ӮиҒAӮ»ӮкӮјӮкҳZҗlҠ|ӮҜӮЕ•”ҲхҲкҗlӮӘ—]ӮБӮДӮөӮЬӮӨҗ}Һ®ӮЙӮИӮБӮҪҒBҢӢӢЗҒAғeҒ[ғuғӢӮЙӮНҲк”NӮ©Ӯз“с”NӮЬӮЕӮЖҗВҺRҗГӮЖ“Ў“c”ь‘ҒӮӘ—Ч“ҜҺmӮЕҚАӮиҒAҺcӮиӮМҺl”NӮЖ’фҷy“№ҒAҗҙҸт–һүиӮӘғҠғrғ“ғOӮМғeҒ[ғuғӢӮЕҗHҺ–ӮрҚПӮЬӮ№ӮҪҒB
Ҳк”NӮМҺOҗl‘gӮЭүМҗм•—ҺqҒA”С’ЛүФҺqҒAӢҫӢҫҺqӮН“–‘RӮМӮжӮӨӮЙҺOҗlӮЕҢЕӮЬӮиҒAүДӢxӮЭӮМҢvүжӮрҳbӮөӮДӮўӮҪҒBүҪӮөӮл‘еҠwӮЙ“ьӮБӮДӮНӮ¶ӮЯӮДӮМүДӢxӮЭӮЕӮ ӮйҒB‘еҠwӮМүДӢxӮЭӮН’·ӮӯҒAҺ©—RӮЕҒAҢvүжӮ·ӮйӮҫӮҜӮЕӮаҠyӮөӮўӮаӮМӮҫҒB
Ҳк•ыҒAҗВҺRҗГӮЖ“Ў“c”ь‘ҒӮМғyғAӮНҗHҺ–ӮЙ—ҲӮҪғJғbғvғӢӮ»ӮМӮаӮМӮҫӮБӮҪҒB‘ҪҸӯҒA“Ў“c”ь‘ҒӮМғAғsҒ[ғӢӮӘӢӯӮӯӮ»ӮкӮрҸгҺиӮӯҺуӮҜ“ҡӮҰӮДӮўӮйӮМӮӘҗВҺRҗГӮЖӮўӮӨҚ\җ}ӮҫҒB
Ӯ ӮЖӮН—]ӮБӮҪӮаӮМ“ҜҺmӮЕҳbӮ·ӮөӮ©ӮИӮўӮӘҒA—]ӮиӮЙӮН“ҢҗқӮЖҳZаV—Ъ—һҒAҲк”NӮМҗV’JҗҗҺчӮҫҒB“ҢҗқӮН‘јҗlӮЖӮМғRғ~ғ…ғjғPҒ[ғVғҮғ“”\—НӮЙ—DӮкӮДӮўӮйӮЖӮНҢҫӮўӮГӮзӮўҗlҠФӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAҳZаV—Ъ—һӮЖҸoүпӮБӮДӮ©ӮзӮН‘ҪҸӯғҢғxғӢӮӘӮ ӮӘӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮҰӮйӮҫӮлӮӨҒB
ҳZаV—Ъ—һӮЖӮўӮӨҸ—җ«ӮНҒAҺАӮЙ–К“|Ң©ӮӘӮжӮӯҚDӮ«ҢҷӮўӮрүсӮиӮМ”»’fӮЕӮНҢҲӮөӮДӮөӮИӮўӮМӮЕӮ ӮйҒB“ҢҗқӮЖҢҫӮў‘ҲӮўӮрӮөӮДӮўӮДӮаҒA“ҜӮ¶җИӮЙҚАӮБӮДӮўӮйҗV’JҗҗҺчӮМӮұӮЖӮаӮ©ӮЬӮўӮВӮВҸгҺиӮӯҳbӮрҗiӮЯӮДӮўӮйҒB
җV’JҗҗҺчӮНҺqӢҹӮБӮЫӮўҠOҢ©ӮМӮнӮиӮЙ—ҺӮҝ’…ӮўӮҪҗ«ҠiӮрӮөӮДӮўӮйҒB
Һl”NӮЖ’фҒA–һүиӮМғOғӢҒ[ғvӮНҚҮҸhӮМ—\’иӮМҠm”FӮрӮөӮДӮўӮйҒB
•”’·ӮӘҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮЖӮИӮБӮДӮўӮйӮӘҒAғAғNғeғB•¶Ң|•”ӮНүДӮЙҺl”NӮ©ӮзҺO”NӮЦҠІ•”ӮМҲшҢpӮ¬ӮӘҚsӮнӮкӮйҒB•Ғ’К‘еҠwӮМғTҒ[ғNғӢӮЖӮўӮҰӮОҺO”NӮ©Ӯз“с”NӮЦӮМҲшҢpӮ¬ӮЖӮўӮӨӮМӮӘҲк”К“IӮҫӮӘҒAғAғNғeғB•¶Ң|•”ӮЕӮНӢӯҗ§—НӮМӮ ӮйғTҒ[ғNғӢӮЕӮаӮИӮӯҗlҗ”ӮаҸӯӮИӮўӮМӮЕӮұӮӨӮўӮБӮҪғXғ^ғCғӢӮрҺжӮБӮДӮўӮйӮМӮҫҒB
ӮВӮЬӮиҒAӮұӮМҚҮҸhӮНҺl”NӮ©ӮзҺO”NӮЦӮМҲшҢpӮ¬ӮЖӮўӮӨҲк‘еғCғxғ“ғgӮаҠЬӮЬӮкӮДӮўӮйӮМӮҫҒB
җHҺ–ӮрҸIӮҰӮҪҲк“ҜӮНғҠғrғ“ғOӮрҺgӮўҢ»ҚЭӮЬӮЕӮМ•ңҸKӮвҒAҺАҚЫӮЙҚмҗ¬ӮөӮҪҚм•iӮЙӮВӮўӮДӮМ”б•]ҒA—L–јӮИҚм•iӮвҚмүЖӮМҢӨӢҶӮрҚsӮБӮҪҒBӮұӮӨӮўӮБӮҪ•”•ӘӮНҒA‘јӮМғTҒ[ғNғӢӮЙ”дӮЧӮДӮаҗ^–К–ЪӮИ•”—ЮӮЙ“ьӮйӮЕӮ ӮлӮӨҒB
ғeғҢғrӮЙҺқӮБӮДӮ«ӮҪғpғ\ғRғ“ӮрӮВӮИӮ¬ғfғBғXғvғҢғCӮЖӮөӮДҺgӮБӮҪҒBғeҒ[ғuғӢӮМғ\ғtғ@ӮЙӮНҲк”NӮЖҗВҺRҗГӮЖ“Ў“c”ь‘ҒӮӘҚАӮиҒAғeғҢғrӮМүЎӮЙҚІҒX–ШӮӘҸ°ӮЙҚАӮиӮ»ӮМӮЩӮ©ӮМғҒғ“ғoӮНҲЦҺqӮрҺқӮБӮДӮ«ӮДҚАӮБӮҪӮиӮөӮҪҒB
ҸIҺnӢ»–ЎӮИӮіӮ»ӮӨӮЙӮөӮДӮўӮҪӮМӮН“Ў“c”ь‘ҒӮҫӮҜӮҫӮБӮҪҒBүҪӮөӮл”ЮҸ—ӮНӮаӮЖӮаӮЖ•¶Ң|ӮЙӢ»–ЎӮӘӮ ӮйӮнӮҜӮЕӮаӮИӮӯҒAӮҪӮҫҗВҺRӮӘҸҠ‘®ӮөӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨӮҫӮҜӮЕӮұӮМғTҒ[ғNғӢӮЙӮўӮйӮҫӮҜӮИӮМӮҫҒBӮ»ӮкӮН–{җlӮаҳbӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBҢoҚПҠw•”ӮЙҸҠ‘®Ӯ·Ӯй“Ў“c”ь‘ҒӮНҒAӮўӮнӮдӮйҚЛҸ—ӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕ•¶Ң|ӮрӮвӮкӮОӮ»ӮкӮИӮиӮМ”\—НӮр”ӯҠцӮЕӮ«ӮйӮМӮНҠФҲбӮўӮИӮўӮЖ‘јӮМ•”ҲхӮҪӮҝӮа”FӮЯӮйӮЖӮұӮлӮҫҒBӮөӮ©ӮөҒA”ЮҸ—ӮЙӮН‘SӮӯӢ»–ЎӮМӮИӮўӮЖӮұӮлӮзӮөӮӯҒAӮұӮкӮЬӮЕҗВҺRӮМӮўӮИӮўӮЖӮ«ӮЙғTҒ[ғNғӢӮЙҢ»ӮнӮкӮҪӮұӮЖӮ·ӮзӮИӮўӮӯӮзӮўӮҫҒB
Ӯ»ӮаӮ»ӮаҒA”ЮҸ—ӮӘӮұӮМғTҒ[ғNғӢӮМғҒғ“ғoӮИӮМӮ©үцӮөӮўӮЖӮұӮлӮҫҒB
ҢҳӢкӮөӮўҺцӢЖӮв”б•]ӮНҸүӮЯӮМҗ”ҺһҠФӮЕҸIӮнӮиҒAӮ»ӮМӮ ӮЖӮНҠeҒXҚDӮ«ӮИӮжӮӨӮЙҳbӮөҚҮӮБӮҪӮиҒAҸ‘Ӯ«•ЁӮрӮөӮҪӮиҒAӮЖӮўӮВӮаӮЖҲбӮӨҸкҸҠӮЕӮўӮВӮаӮЖ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮИҺһҠФӮрүЯӮІӮөӮҪҒB
ҺOҗl‘gӮНҚҮӮўӮа•ПӮнӮзӮёҠyӮөӮ»ӮӨӮЙҳbӮөӮДӮўӮйҒBӮЗӮӨӮвӮзҳb‘иӮН–ҹүжӮЙҸoӮДӮӯӮйҗl•ЁӮЙҲЪӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮҫҒB
“ҢҗқӮНҒAҗжӮЩӮЗҗHҺ–ӮрӮөӮҪғeҒ[ғuғӢӮЙҺ©•ӘӮМғpғ\ғRғ“Ӯр’uӮ«ғAғjғҒҠУҸЬӮЙҗZӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮҫҒBҳZаV—Ъ—һӮНҲк”NӮМҗV’JҗҗҺчӮЙҺ©•ӘӮМҸ‘ӮўӮҪҚм•iӮр“ЗӮсӮЕӮаӮзӮБӮДӮўӮйҒBӮҝӮИӮЭӮЙҳZаV—Ъ—һӮМҗк–еӮН—цҲӨҸ¬җаӮЕӮ ӮйҒB
ҒuӮВӮБӮДӮаҒAӮ ӮҪӮөӮИӮсӮ©—цҲӨӮЙӢ»–ЎӮӘӮ ӮйӮнӮҜӮЕӮаӮИӮсӮЕӮаӮИӮўӮсӮҫӮҜӮЗӮЛҒBӮҫӮ©ӮзӮұӮ»—қ‘z“I—цҲӨӮБӮДӮМӮрӢҒӮЯӮДҸ‘ӮўӮҝӮбӮӨӮнӮҜҒBӮұӮкӮБӮДӮЗӮӨҚlӮҰӮДӮаҺ©ҢИ–һ‘«ӮЕӮөӮ©ӮИӮўӮсӮҫӮҜӮЗӮіҒv
Ӯ»ӮӨҢҫӮБӮДҒAҳZаV—Ъ—һӮНӮИӮсӮЖӮаӮўӮҰӮИӮўӮжӮӨӮИҠзӮрӮ·ӮйӮМӮҫҒB
ғTҒ[ғNғӢӮМғҒғ“ғoӮЙӮаӮўӮлӮўӮлӮ ӮйҒBҸ¬җаӮрҸ‘Ӯ«ӮҪӮўӮЖӮўӮӨҲУҺvӮрҺқӮБӮДӮўӮйҺТӮаӮўӮкӮОҒAҸ¬җаӮӘҚDӮ«ӮЖӮўӮӨӮҫӮҜӮЕҸ‘ӮӯӢCӮНӮИӮўӮЖӮўӮӨҺТҒAғAғjғҒҒ[ғVғҮғ“ӮӘҚDӮ«ӮИҺТҒA–ҹүжӮӘҚDӮ«ӮИҺТҒAӮЖӮЬӮіӮЙҺG‘ҪӮЕӮ ӮйӮӘӮ»ӮкӮјӮкӮЙҲУҗ}ӮӘӮ ӮиғTҒ[ғNғӢӮЙҸҠ‘®ӮөӮДӮўӮйӮМӮНҠФҲбӮўӮНӮИӮўҒBӮ»ӮөӮДғTҒ[ғNғӢӮМҠҲ“®ӮМҺе“ұҢ ӮрҲ¬ӮйӮМӮНҸгӢүҠw”NӮМҗlҠФӮЙӮИӮйҒB
Ң»ҚЭӮНҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮӘҠҲ“®“а—eӮрҢҲӮЯӮДӮўӮйҒBӮҝӮИӮЭӮЙҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮНғtғ@ғ“ғ^ғWҒ[Ҹ¬җаӮӘҗк–еӮЕӮ ӮйҒB
җlӮНҢ©ӮҪ–ЪӮЙҠсӮзӮИӮўҒAӮЖӮўӮӨҺА—бӮЖӮөӮД”ЮӮНҚvҢЈӮөӮДӮўӮйӮЖҢҫӮБӮДӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB
ӮҫӮӘҒA’·Ӯӯ‘ұӮўӮДӮўӮйҠөҸKӮНҢгҗўӮЙӮ Ӯй’ц“xӮМ‘©”ӣӮр—^ӮҰӮйӮаӮМӮзӮөӮӯҒAҚЎӮМӮЖӮұӮ땶Ң|•”ӮЖӮўӮӨ–БӮМ’КӮ蕶Ң|ӮрҺеҺІӮЙҠҲ“®Ӯр‘ұӮҜӮДӮўӮйҒB
ҒuӮЬӮҪҒAғtғ@ғ“ғ^ғWҒ[ӮЕӮ·Ӯ©Ғv’фҷy“№ӮӘҒAҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮ©Ӯз“nӮіӮкӮҪҗЭ’иҺ‘—ҝӮЙ–ЪӮр’КӮөӮИӮӘӮз•рӮкӮҪҗәӮрҸoӮ·ҒBҒuӮҫӮЯӮБӮ·ӮжҒBҲкҺн—ЮӮОӮБӮ©ӮиӮвӮБӮДӮҝӮᕶ‘МҢЕӮЬӮБӮҝӮбӮўӮЬӮ·ӮжҒHҒv
ҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮНҗЭ’иӮрҲкӮВӮМ‘еҠwғmҒ[ғgӮЙҸ‘Ӯ«ҚһӮсӮЕҒAӮ»ӮкӮЖ“ҜҺһҗiҚsӮЕҚм•iӮрҚмӮБӮДӮўӮӯғXғ^ғCғӢӮрӮЖӮБӮДӮўӮйҒBӮИӮсӮЕӮа“ІӮкӮМҗж”yӮӘӮ»ӮӨӮвӮБӮДҚм•iӮрҚмӮБӮДӮЁӮиҒAӮ»ӮМҗlӮЙӢіӮҰӮДӮаӮзӮБӮҪӮМӮҫӮ»ӮӨӮҫҒB
ғmҒ[ғgӮЙӮНҗўҠEҠПӮ©ӮзҒA“oҸкҗl•ЁӮМ—eҺpӮвҗ«ҠiӮЖ—lҒXӮИӮұӮЖӮӘӢLӮөӮДӮ ӮйҒB
ҒuӮўӮвҒAӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮўӮБӮДӮаӮИҒBӮЗӮӨӮаӮұӮӨӮўӮӨӮМӮөӮ©үҙӮЙӮНҢьӮўӮДӮИӮўӮсӮҫӮБӮДҒv
Ӯ»ӮМ‘МҠiӮЖҺR’jӮЭӮҪӮўӮИҠзӮЕҢҫӮӨӮ©ҒHҒ@ӮЖ“аҗSӮЕ“ЛӮБҚһӮЮҒB
Ғuҗж”yҒAӮ»ӮМ‘МҠiӮЖҺR’jӮЭӮҪӮўӮИҠзӮЕӮ»ӮкӮрҢҫӮўӮЬӮ·Ӯ©ҒHҒvӮЖ’фӮНҗәӮЙӮаҸoӮөӮДӮЭӮйҒB
ҒuӮЕӮаҒAӮжӮӯӮаӮЬӮ ӮұӮсӮИӮЙғtғ@ғ“ғ^ғWҒ[ӮОӮБӮ©ӮиҸ‘ӮҜӮЬӮ·ӮЛҒBӮ»ӮсӮИӮЙҚDӮ«ӮИӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv’фӮМ—ЧӮ©ӮзғmҒ[ғgӮр”`Ӯ«ҚһӮсӮЕӮўӮҪ–һүиӮӘ•·ӮӯҒB
ҒuӮ»ӮиӮбҒAҚDӮ«ӮіҒvҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮНҺR’jӮзӮөӮӯҸ°ӮЙӮ Ӯ®ӮзӮрӮ©Ӯ«ҚАӮБӮДӮўӮйҒBҒuӮұӮсӮИӮЙӮ·ӮОӮзӮөӮўғWғғғ“ғӢӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨҒBҗўҠEӮ»ӮМӮаӮМӮрҲкӮ©ӮзҚмӮБӮДӮўӮӯӮсӮҫӮјҒHҒ@ӮөӮ©ӮаӮ»ӮұӮЙҸнӮЙҠЦӮнӮБӮДӮўӮйӮМӮӘҒwҲӨҒxӮҫҒBғVғFғCғNғXғsғAӮаҢҫӮБӮДӮўӮйӮҫӮлӮӨҒAҗlӮНүҪӮ©ӮрүүӮ¶ӮДӮўӮйӮБӮДӮИҒBғtғ@ғ“ғ^ғWҒ[ӮЕӮНӮ»ӮкӮӘӮ Ӯ©ӮзӮіӮЬӮҫӮлҒHҒ@ӮҫӮ©ӮзӮұӮ»“oҸкҗl•ЁӮӘүhӮҰӮйҒB–Ј—НӮЙҲшӮ«ҚһӮЬӮкӮйҒBӮЗӮсӮИӮӯӮіӮўғZғҠғtӮЕӮа•sҺ©‘RӮЙҠҙӮ¶ӮИӮўҒBӮЬӮіӮЙ—қ‘zӮҫӮлҒv
ҚІҒX–ШӮН–һ‘«Ӯ°ӮЙҢҫӮБӮДӮМӮҜӮД–ЪӮрҺqӢҹӮЭӮҪӮўӮЙҢхӮзӮ№ӮҪҒB
ҒuӮВӮЬӮиҒAӮЬӮіӮЙҚЎӮМҗж”yӮЭӮҪӮўӮЙ’pӮёӮ©ӮөӮўӮБӮДӮұӮЖӮӘӮИӮўӮБӮДӮұӮЖӮЕӮ·ӮЛҒvҗlҚ·ӮөҺwӮрӮӯӮйӮӯӮйүсӮөӮД–һүиӮӘҢҫӮӨҒB
ҒuӮЁӮЁҒIҒ@ӮЁ‘OүsӮўӮИҒv
ҒuӮУӮБӮУӮБӮУҒBҺ„ӮМҠУҺҜҠбӮрҢ©ӮӯӮСӮБӮҝӮбӮҹӮўӮҜӮЬӮ№ӮсӮжҒAҷy“№ҢNҒv
ҒuӮЬӮ ҒAҢҫӮБӮДӮй–{җlӮӘӮӯӮіӮўғZғҠғtӮрҢҫӮБӮДӮМӮҜӮҝӮбӮӨӮсӮҫӮ©ӮзҗўҳbӮИӮўӮИҒBӮЕӮаҒAҲӨӮБӮДӮМӮНӮЗӮӨӮжҒHҒv
ҒuӮўӮвӮўӮвҒAҢ©ӮҪ–ЪӮЕ”»’fӮ·ӮйӮМӮНӮжӮӯӮИӮўӮнӮжҒBғOғҢғCӮЭӮҪӮўӮИүF’ҲҗlӮҫӮБӮДҲӨӮрҢкӮйӮұӮЖӮаӮ ӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮөӮіҒv
ҒuӮЁ‘OӮзҒAүҙӮН–ўҠm”Fҗ¶•ЁӮ©ҒvӮЖҺR’jӮНҢҫӮБӮҪҒB
‘ж“с–ӢҒ@үДӮМ–йӮМ•П‘tӢИ
ӮP
Ҹгү®•~—№ӮНӢ@ҢҷӮӘ—ЗӮ©ӮБӮҪҒB
•\ҸоӮв‘Ф“xӮЙ•\ӮкӮЙӮӯӮўӮВӮӯӮиӮрӮөӮДӮўӮйӮӘҒA“аҗSӮЕҺ©•ӘӮМҚЎӮМҗSӢ«ӮНҺиӮЙҺжӮйӮжӮӨӮЙ•ӘӮ©ӮйҒB
ӮЖӮНӮўӮБӮДӮаҒAҺ©•ӘӮМӮұӮЖӮИӮМӮҫӮ©Ӯз“–‘RӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮӘҒcҒcҒB
үҪӮӘӢ@ҢҷӮрӮжӮӯӮөӮДӮўӮйӮМӮ©ӮЖӮўӮҰӮОҒAӮвӮНӮиӮұӮМ“БҲЩӮИҠВӢ«ӮҫӮлӮӨҒB•ВҚҪ“IӮИҠВӢ«ӮМ’ҶӮЕҒA•Ғ’iҲкҸҸӮЙҗ¶ҠҲӮрӮ·ӮйӮНӮёӮаӮИӮўҗlҠФӮҪӮҝӮӘӮ ӮйҠЦҢWӮр’КӮ¶ҒAҗ”“ъӮЖӮНӮўӮҰҲЯҗHҸZӮрӢӨӮЙӮ·ӮйҒBӮ»ӮкӮЙ”әӮИӮўҚӮ—gӮ·ӮйҗlҠiҒAӮаӮөӮ©ӮөӮҪӮзүҪӮ©“Б•КӮИӮұӮЖӮӘӢNӮұӮйӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖӮўӮӨҺу“®“IӮИ–П‘zҒBӮ»ӮМҲУҺvӮрӢӨ—LӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҒA—НӮӘ“ӯӮӯӮұӮЖӮаӮ ӮйҒB
Ӯ»ӮкӮр’mӮБӮДӮўӮйҺ©•ӘӮӘ•sҚKӮҫӮЖӮөӮДӮаҒAӮ»ӮМӮұӮЖӮӘҺ©•ӘӮрӢ@ҢҷӮр—ЗӮӯӮөӮДӮўӮйҒB
Ғ\Ғ\ӮаӮөӮ©ӮөӮДҺ„ӮБӮДғ}ғ]ғqғXғgҒH
ӮұӮұӮЙӮўӮйҗl’BӮНҺАӮЙ‘ҪҺнӮЙ•xӮсӮЕӮўӮйҒBӢПҲкӮр•ЫӮЖӮӨӮЖӮ·ӮйӮұӮМҺРүпӮЙӮЁӮўӮДҒAӮұӮұӮНғIғAғVғXӮЖӮаҢҫӮӨӮЧӮ«‘Ҫ—lҗ«ӮрҲЫҺқӮөӮДӮўӮйҒBӮ»ӮкӮӘҠрӮөӮўҒAӮ»ӮкӮӘҺ©•ӘӮрҗ¬’·ӮіӮ№ӮДӮўӮйҒBӮ»ӮӨҸгү®•~—№ӮНҚlҺ@ӮөӮДӮўӮҪҒB
Ғuҗж”yҒAӮQӮOӮSҚҶҺәӮӘҢ®Ӯ©Ӯ©ӮБӮДӮйӮЭӮҪӮўӮЕҠJӮ©ӮИӮўӮсӮЕӮ·ӮҜӮЗӮЗӮӨӮөӮҪӮзӮўӮўӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
Ғu’ҶӮЙ’NӮ©ӮўӮйӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮМӮ©ҒHҒv
Ғu‘Ҫ•ӘҒA•—ҺqӮӘӮўӮйӮЖҺvӮӨӮсӮЕӮ·ӮҜӮЗҗQӮДӮйӮЭӮҪӮўӮЕҒcҒcҒv
ҒuӢNӮ«ӮИӮўӮМӮ©ҒHҒv
ҒuӮ ӮМҺqҲк“xҗQҺnӮЯӮҝӮбӮӨӮЖӮИӮ©ӮИӮ©ӢNӮ«ӮИӮўӮөҒcҒcҒv
ҒuӮ»ӮӨӮ©ҒAҚЎ“ъӮНӮ©ӮИӮи•аӮўӮҪӮ©Ӯз”жӮкӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮИҒBҳaӢv“cӮіӮсӮЙӮўӮБӮДҢ®‘ЭӮөӮДӮаӮзӮЁӮӨҒv
Ҹгү®•~—№ӮН–{Ӯ©Ӯз–ЪӮр—ЈӮіӮёӮЙҚІҒX–ШӮЖӢҫӢҫҺqӮМүпҳbӮр•·ӮўӮДӮўӮҪҒB
ҚІҒX–ШӮМҗl–]ӮНҢъӮўҒB
Ӯ»ӮкӮНҺ©•ӘӮЙӮНӮИӮў”\—НӮҫӮЖҺvӮӨҒBҺАҚЫӮұӮкӮҫӮҜӮМҗlҠФӮ©Ӯз•зӮнӮкӮйӮжӮӨӮИ—§ҸкӮЙ—§ӮБӮҪӮзҒAӮӯӮ·Ӯ®ӮБӮҪӮӯӮБӮДҺd•ыӮӘӮИӮўӮЖҺvӮӨҒBӮ»ӮөӮДҒAӮ»ӮсӮИҺ©•ӘӮрҢҷҲ«Ӯ·ӮйҒB
ҒuӮЁӮӨҒAҸгү®•~ҒBӮ»ӮлӮ»Ӯл”СӮМҸҖ”хӮ·ӮйӮјҒv
Ҹгү®•~—№ӮНғyҒ[ғWҗ”ӮҫӮҜҠoӮҰӮД–{Ӯр•ВӮ¶ӮйҒB
ҒuӮ»ӮӨҒBҲк”Nҗ¶ӮНӮўӮўӮМҒHҒv
ҒuӮ Ӯ ҒAҗВҺR’BӮЙ”CӮ№ӮҪӮ©ӮзӮИҒBӮЖӮиӮ ӮҰӮёҗHҚЮӮЖүОӮМҸҖ”хӮҫӮҜӮНӮөӮДӮЁӮ©ӮИӮўӮЖҒcҒcӮ ӮЖҒAҺMӮ©Ғv
ҒuӮ»ӮӨӮўӮҰӮОҚЎ“ъӮМ”УҢд”СӮНүҪҒHҒv
‘ӢӮМҠOӮрҢ©ӮйӮЖӢуӮНҢQҗВҗFӮЙ“hӮзӮкҒAӮ»ӮлӮ»ӮлӮ»ӮМҗFҚКӮ·ӮзҺёӮЁӮӨӮЖӮөӮДӮўӮҪҒB
Ғ\Ғ\ӮВӮЬӮиҒA–йӮЙӮИӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮҫҒB
ҒuҚЎ“ъӮНҠOӮЕғoҒ[ғxғLғ…Ғ[ӮҫҒvҚІҒX–ШӮН“сғJғbӮЖҺ•ӮрҢ©Ӯ№ӮДҸОӮӨҒB
ҒuӮ ӮзҒA‘f“GӮЛҒBүбҺжӮиҗьҚҒӮр•°ӮўӮДӮЁӮ©ӮИӮӯӮБӮҝӮбҒvҸгү®•~—№Ӯа”чҸОӮЮҒBҒuғuғ^ӮМүбҺжӮиҗьҚҒ’uӮ«ӮН–іӮўӮМӮ©ӮөӮзҒcҒcҒv
ӮвӮНӮиҒAүбҺжӮиҗьҚҒӮЖӮўӮҰӮОӮ ӮМ’u•ЁӮЕӮ ӮлӮӨҒB
ӮQ
ҒuӮ ӮБҒAӮЬӮҪҺhӮіӮкӮҪҒcҒcҒv
җҙҸт–һүиӮНӮРӮ¶ӮМ•УӮиӮрҺwҗжӮЕғ|ғҠғ|ғҠӮЖ‘~ӮӯҒB
ҒuҢ’ҚN“IүЯӮ¬ӮйӮБӮДӮМӮаҚlӮҰ•ЁӮҫӮИҒBүҙӮИӮсӮ©ӮЯӮБӮҪӮЙҺhӮіӮкӮИӮўӮҜӮЗӮИҒv
’фҷy“№ӮНҒAӮўӮўҸДӮ«ӮІӮлӮМ“чӮр“S”ВӮ©ӮзӢ~ӮўҸoӮөҒAӮҪӮкӮЙҗZӮөӮДҢыӮЦӮЖү^ӮФҒB
ӢуӮўӮҪғXғyҒ[ғXӮЙӮ·Ӯ©ӮіӮё“чӮр•~Ӯ«ӢlӮЯӮйӮМӮНҳZаV—Ъ—һӮЕӮ ӮйҒB
ҒuүбӮЙӮНӮЁӮўӮөӮўҢҢӮЖӮЁӮўӮөӮӯӮИӮўҢҢӮӘ“хӮўӮЕ•ӘӮ©ӮйӮ»ӮӨӮЕӮ·ӮЛҒvҳZаV—Ъ—һӮН“чӮМҸжӮБӮДӮўӮйҺMӮрҚ¶ҺиӮЙҒAүEҺиӮЙғgғ“ғOӮрҺқӮБӮДӮўӮйҒBҒuӮ ҒAҗж”yӮ»ӮБӮҝӮМӮЁ“чӮаҸДӮҜӮДӮЬӮ·ӮжҒv
ҒuҢҢүtҢ^ӮаҠЦҢWӮ ӮйӮБӮДҢҫӮӨӮжӮЛҒBӮ ӮЖҒAӮЖӮсӮЕӮаӮИӮӯҡkҠoӮӘӮўӮўӮБӮДӮМӮа•·ӮӯӮжӮЛҒv–һүиӮӘ“чӮЙҺиӮрҗLӮОӮ·ҒBҒuӮЬӮБӮҪӮӯҒAӮИӮсӮҫӮБӮДӮ ӮсӮИҸ¬ӮіӮИ‘МӮЙ–АҳfӮИӢ@”\ӮӘӮВӮўӮДӮсӮҫӮ©ҒcҒcҒv
ғTҒ[ғNғӢӮМғҒғ“ғoӮӘғoҒ[ғxғLғ…Ғ[ӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮНҒAғҠғrғ“ғOӮМҠOӮЙӮ ӮйғfғbғLӮМҸгӮЕӮ ӮйҒB‘SҲхӮӘғfғbғLӮМҸгӮЙҸжӮйӮЙӮНҸӯӮөӢ·ӮўӮӘҒAғfғbғLӮ©ӮзҗжӮНүҪӮаӮИӮў•Ҫ’nӮИӮМӮЕғXғyҒ[ғXӮН–в‘иӮИӮ©ӮБӮҪҒBҠЗ—қҗlӮЕӮ ӮйҳaӢv“cӮӘӢCӮр—ҳӮ©Ӯ№ӮДҒAғfғbғLӮ©ӮзӮ·Ӯ®ӮМҸҠӮЙғLғғғ“ғv—pӮЖҺvӮнӮкӮйғeҒ[ғuғӢӮЖҲЦҺqӮрҸoӮөӮДӮӯӮкӮҪҒB
ғfғbғLӮМҸгӮЙғoҒ[ғxғLғ…Ғ[ғOғҠғӢӮӘ“сӮВҒAӮ»ӮМҺьӮиӮЙғҒғ“ғoӮМ”јҗ”ҒAғeҒ[ғuғӢӮМӮ Ӯй•ыӮЙҺcӮиӮӘӮўӮҪҒB
Ӯ»ӮМҺь•УӮЙӮўӮӯӮВӮ©ӮМүбҺжӮиҗьҚҒӮӘҗҶӮ©ӮкӮДӮўӮҪҒBӮұӮкӮНҸгү®•~—№ӮӘ—ҰҗжӮөӮДҚsӮБӮҪҒB
ҸкҸҠӮМҠЦҢWҸгғfғbғLӮМҸгӮЙӮўӮйғҒғ“ғoӮӘ’І—қӮвҒAҲщӮЭ•ЁӮрғLғbғ`ғ“ӮЙҺжӮиӮЙҚsӮӯ–р–ЪӮр•үӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒB
ғeҒ[ғuғӢӮМҺь•УӮЕӮН’NӮӘҺқӮБӮДӮ«ӮҪӮМӮ©үФүОӮрҺnӮЯӮДӮўӮйӮӘҒAӮЗӮҝӮзӮЙӮўӮДӮаӮұӮӨӮўӮӨҸкҚҮӮНӮ»ӮкӮИӮиӮЙ–К”’ӮўӮаӮМӮҫҒB–һүиӮНӮ»ӮӨҺvӮБӮҪҒB
ӮЗӮҝӮзӮӘғzғXғgӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮа–іӮўӮМӮҫҒB
–һүиӮНҒAҢҡ•ЁӮМ’ҶӮ©ӮзӮаӮкӮйҢхӮЙҸЖӮзӮіӮкӮҪ’фӮМүЎҠзӮрӮҝӮзӮиӮЖ“җӮЭҢ©ӮйҒB
ӮұӮсӮИӮЙӮаӢЯӮӯӮЙҠҙӮ¶ӮйҒBӮўӮВӮаӮЖ•Ё—қ“IӢ——ЈӮЙӮНҚ·ӮИӮсӮД–іӮўӮМӮҫӮӘҒAӮИӮсӮҫӮ©ӮўӮВӮаӮжӮиӮ©ӮаӮ·Ӯ®ӢЯӮӯӮЙӮўӮйӮжӮӨӮЙҠҙӮ¶ӮйӮМӮҫҒB
ӮұӮұӮӘҠOӮҫӮ©ӮзҒH
ҠX’ҶӮв‘еҠwӮ©Ӯз—ЈӮкӮДӮўӮйҒBҠi•КӮіӮкӮҪҗўҠEӮ©Ӯз—ЈӮкҒAүҪӮаӮИӮўғmҒ[ғ}ғӢӮИҒcҒcӮ»ӮӨҒAғvғҠғ~ғeғBғuӮИҸу‘ФӮЙӮўӮйӮ©ӮзҒH
ӮӨӮӨӮсҒAӮ«ӮБӮЖҗҢӮБӮДӮўӮйӮҫӮҜҒB
ӮұӮМҸуӢөӮЙҒAӮұӮМҗўҠEӮЙҒAҺ©•ӘҺ©җgӮЙҒB
ҒuӮ Ӯ ҒAӮаӮӨӮБҒIҒv
“Л”@ҒA“ҢҗқӮӘҺҶҺMӮр“ҠӮ°ҸoӮөӮД–\ӮкҺnӮЯӮҪҒB
ҒuӮӨӮнӮБҒAӮ ӮўӮВүҪӮвӮБӮДӮсӮМӮжҒvӮЖҳZаV—Ъ—һӮӘҢҷӮ»ӮӨӮИ•\ҸоӮрҢ©Ӯ№ӮйҒB
“ҢҗқӮНғeҒ[ғuғӢӮМӮ»ӮОӮЙӮўӮҪӮНӮёӮҫӮӘҒA—јҺиӮрҗUӮиүсӮөӮИӮӘӮзҢ©ӮҰӮИӮўүҪӮ©ӮЖҠi“¬ӮөӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМӮИӮсӮЖӮаҠҠҢmӮИ—xӮиӮрҢ©ӮДҚІҒX–ШӮН‘еҗәӮЕҸОӮўҺnӮЯӮйҒB
ҒuҗқҒIҒ@ӮИӮЙӮвӮБӮДӮсӮжҒHҒvҳZаV—Ъ—һӮӘ–\ӮкӮй“ҢҗқӮЙҗәӮрӮ©ӮҜӮйҒB
ҒuүбӮҫӮжҒIҒ@үбҒIҒv“ҢҗқӮНӮаӮӨӮҪӮЬӮзӮИӮўӮЖӮўӮБӮҪҠҙӮ¶ӮЕҗШҺАӮИ•\ҸоӮЕӢ©ӮФҒB
ҒuӮИӮЙӮжҒAӮ»ӮсӮИӮЙӮўӮИӮўӮЕӮөӮеҒB‘еӮ°ӮіӮИӮсӮҫӮ©ӮзҒcҒcҒv
ҒuҲбӮӨӮсӮҫӮБӮДӮОҒAүҪӮЕӮ©’mӮзӮИӮўӮҜӮЗ–lӮНҺhӮіӮкӮвӮ·ӮўӮсӮҫӮҹҒ[Ғ[Ғ[Ғv
“ҢҗқӮНӮ»ӮӨӮўӮӨӮЖүҪӮ©Ӯ©Ӯз“ҰӮ°ӮйӮжӮӨӮЙғXғEғFҒ[ӮрҢJӮи•ФӮ·ҒB
ҒuӮЗӮӨӮвӮзҒAӮЁ‘OӮжӮиӮ©ӮаӮӨӮЬӮўҢҢӮМҺқӮҝҺеӮӘӮўӮҪӮЭӮҪӮўӮҫӮИҒvӮ»ӮӨӮўӮўӮИӮӘӮз’фӮНҸОӮБӮҪҒB
ҒuӮ ӮМҒcҒcҒAҲщӮЭ•ЁӮ ӮиӮЬӮ·Ӯ©ҒHҒv
ӮЁӮБӮЖӮиӮЖӮөӮҪҗәӮЕҸ¬“№–ВӮӘ’фӮЖ–һүиӮЙҳbӮөӮ©ӮҜӮйҒB
ҒuӮ ҒA–ВҒBӮИӮЙҒAҲщӮЭ•ЁҒHҒ@ӮҝӮеӮБӮЖ‘ТӮБӮДӮЛҒv“сҗlӮМ‘гӮнӮиӮЙҳZаV—Ъ—һӮӘ“ҡӮҰӮйҒB
ҒuӮ ҒAӮ»ӮӨӮўӮҰӮОҸ¬“№ӮіӮсӮЖ“ҢҢNӮБӮД“ҜӮ¶ҠwүИӮИӮсӮҫӮБӮҜҒHҒv
ӮУӮЖ’фӮӘҺvӮўҸoӮ·ҒB
Ҹ¬“№–ВӮНҒAӮўӮВӮаӮНүәӮлӮөӮДӮўӮй”ҜӮМ–СӮр‘©ӮЛ’ZӮўғ|ғjҒ[ғeҒ[ғӢӮрҚмӮБӮДӮўӮйҒB”ЮҸ—ӮӘихӮӯӮЖӮ»ӮкӮӘ’өӮЛӮйӮжӮӨӮЙ—hӮкӮйҒB
ҒuӮНӮўҒA“ъ–{•¶ҠwүИӮЕҲкҸҸӮЕӮ·ҒvҸ¬“№–ВӮНҲӨӮзӮөӮӯҸОҠзӮрҚмӮйҒB
җlҢ`ӮМӮжӮӨҒAӮЖӮўӮӨҢҫ—tӮӘҺ—ҚҮӮӨӮЖӮНӮұӮМӮұӮЖӮҫӮлӮӨҒB
Ғu“ҢҢNӮБӮДҠwүИӮҫӮЖӮЗӮсӮИҠҙӮ¶ӮИӮМҒHҒv’фӮӘ•·ӮӯҒB
ҒuӮӨҒ[ӮсҒAӮЗӮӨӮБӮДҢҫӮнӮкӮДӮаҒcҒcҒvҸ¬“№–ВӮНҺсӮрӮРӮЛӮиҒAҸӯӮөҚlӮҰӮйӮжӮӨӮЙӮөӮДӮ©Ӯз“ҡӮҰӮҪҒBҒuӮЖӮБӮДӮаӮвӮіӮөӮўӮЕӮ·ӮжҒv
ҒuҒcҒcӮҰҒHҒv
ҺOҗlӮӘ“ҜӮ¶”ҪүһӮрҺжӮйҒB
ҺOҗlӮМ”ӯӮөӮҪҒwӮҰҒxӮЙӮН‘ч“_ӮӘ•tӮўӮДӮўӮДӮаӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB
Ғu–ВҒA•КӮЙӢCӮўҺgӮнӮИӮӯӮДӮаӮўӮўӮсӮҫӮжҒvҳZаV—Ъ—һӮНҸ¬“№–ВӮМҢЁӮЙӮ»ӮБӮЖҺиӮр’uӮӯҒBҒu“ҢӮҫӮжҒHҒ@“ҢҗқҒAӮ ӮўӮВӮӘҒcҒc—DӮөӮўҒHҒv
–ВӮНүҪӮӘҠФҲбӮБӮДӮўӮйӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮЖӮўӮӨӮжӮӨӮИҠзӮрӮ·ӮйҒB
Ғu—Ъ—һҒAҺ„үҪӮ©ӮЦӮсӮИҺ–ҢҫӮБӮҪҒHҒ@“ҢҢNӮўӮВӮаӮвӮіӮөӮўӮжҒv
ҸӯӮө—ЈӮкӮҪӮЖӮұӮлӮЕӮН“ҢҗқӮӘҠпҗәӮрҸгӮ°ӢуӮр”тӮФүбӮЖҠi“¬ӮрӮөӮДӮўӮйҒB
ӮаӮҝӮлӮсҚІҒX–ШӮН”ҡҸОӮр‘ұӮҜӮДӮўӮйҒB
ҒuӮөҒAҗMӮ¶ӮзӮкӮсҒcҒcҒvҳZаV—Ъ—һӮНӮЗӮӨҢ©ӮДӮа•ПҗlӮЙӮөӮ©Ң©ӮҰӮИӮў“ҢӮЙҺӢҗьӮрҢьӮҜӮйҒB
Ғu“ҜӮ¶ҺцӢЖӮЕҺ„ӮӘӢxӮсӮҫӮЖӮ«ӮЖӮ©ғmҒ[ғg‘ЭӮөӮДӮӯӮкӮҪӮиҒAҸoҗИғJҒ[ғhҸoӮөӮДӮЁӮўӮДӮӯӮкӮҪӮиҒA•ЧӢӯӮаӢіӮҰӮДӮӯӮкӮйӮөҒvҳZаV—Ъ—һӮ©ӮзҲщӮЭӮаӮМӮрҺуӮҜҺжӮиӮИӮӘӮзҸ¬“№–ВӮӘҳbӮ·ҒBҒuӮЁҠ©ӮЯӮМ–{ӮЖӮ©ҸРүоӮөӮДӮӯӮкӮҪӮиӮаӮ·ӮйӮжҒv
Ҹ¬“№–ВӮМ—lҺqӮ©ӮзӮөӮДүRӮЕӮНӮИӮўӮжӮӨӮҫӮөҒAүҪӮ©ӮМҠФҲбӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮаӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB
ӮВӮЬӮиҒA“ҢҗқӮНҸ¬“№–ВӮМ‘OӮЕӮНҸнҗlӮМӮжӮӨӮЙҗUӮй•‘ӮўҒAӮ»ӮкӮЗӮұӮлӮ©—DӮөӮіӮрӮаӮБӮДҗЪӮөӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮзӮөӮўҒB
ҒuӮӨҒ[ӮсҒv
ҺOҗlӮНҠzӮрҠсӮ№ҚҮӮБӮДҳrӮр‘gӮЮҒB
ҒuӮЗӮӨҺvӮўӮЬӮ·ӮЛҒA–һүиӮіӮсҒvӮЖ’фҒB
ҒuӮаӮөӮ©ӮөӮДҒHҒvӮЖ–һүиҒB
ӮіӮзӮЙҠzӮрӢЯӮГӮҜҸ¬җәӮЙӮИӮйҒB
ҒuҗMӮ¶ӮӘӮҪӮўӮұӮЖӮЕӮ·ӮӘҒcҒcҒvӮЖҳZаV—Ъ—һҒB
ҒuӮұӮкӮНҒcҒc—ц•зҒHҒv
Ӯ»ӮӨҢҫӮБӮҪ’фӮЙ“сҗlӮМҸ—җ«ӮМҺӢҗьӮӘҸWӮЬӮйҒB
ҒuүВ”\җ«ӮЖӮөӮДӮНҺOӮВҒBҲкҒAҢіҒXӮвӮіӮөӮіӮрҺқӮҝҚҮӮнӮ№ӮҪӮўӮў’jӮҫӮБӮҪҒB“сҒAӮҪӮҫӮМӢCӮЬӮ®ӮкҒBҺOҒA•aӢCҒv’фӮН“сҗlӮрҢрҢЭӮЙҢ©ӮйҒBҒuӮ Ӯ ҒAӮҝӮИӮЭӮЙҺOӮМӮН—цӮМӮБӮДҲУ–ЎӮЛҒv
ҺOҗlӮНҢіӮМ‘Мҗ§ӮЙ–ЯӮиҒAӮёӮБӮЖ•sҺvӢcӮ»ӮӨӮИ–ЪӮЕҢ©ӮДӮўӮҪ“VҺgӮМӮжӮӨӮИҸӯҸ—ҒAҸ¬“№–ВӮЦӮЖҢьӮ«’јӮйҒBӮ»ӮөӮДҒA•ПҗlӮЦӮЖҺӢҗьӮрҢьӮҜӮйҒB
ӮЬӮҪҒAҺOҗlӮН–ЪӮрҚҮӮнӮ№ӮйҒB
Ӯ»ӮөӮДҒAҗ\Ӯө–уӮИӮіӮ»ӮӨӮЙ–ЪӮрҲнӮзӮ·ҒB
ӮВӮЬӮиҒAҺOҗlӮМҲУҢ©ӮНҲк’vӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB
’фӮӘӮЪӮ»ӮиӮЖҢҫӮӨҒB
ҒuүһүҮӮөӮҪӮўӮМӮНҺRҒXӮҫӮӘҒcҒcҒv
Ғu’ЮӮиҚҮӮўӮЖӮўӮӨӮаӮМӮрҚlӮҰӮйӮЖӮЗӮӨӮаӮЛҒcҒcҒv
ҒuӮИӮсӮҫӮ©ӢғӮҜӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒcҒcҒv
ӮR
ғoҒ[ғxғLғ…Ғ[ӮМ•Р•tӮҜӮаӮ»ӮұӮ»ӮұӮЙҸIӮзӮ№ҒAҲк•”ӮМ•”ҲхӮҪӮҝӮНғҠғrғ“ғOӮЦӮЖҸWӮЬӮиӮ»ӮМӮЬӮЬ‘Дҗ«ӮЕғpҒ[ғeғBӮр‘ұӮҜӮДӮўӮҪҒB
’ӢӮМ”жӮкӮрӮаӮМӮЖӮаӮөӮИӮўӮМӮ©ҒAӮ»ӮМ”жӮкӮрүд–қӮөӮДӮЕӮаҺcӮиӮҪӮўӮМӮ©ӮНӮ»ӮкӮјӮкӮҫӮӘҲк”NӮЖ“Ў“c”ь‘ҒҲИҠOӮМ‘SҲхӮӘҺcӮБӮДӮўӮҪҒB
ғeҒ[ғuғӢӮМҸгӮЙӮНӮВӮЬӮЭӮЖғrҒ[ғӢӮӘ•АӮЧӮзӮкҚҮҸhӮЖӮўӮӨӮаӮМӮрҠ¬”\ӮөӮДӮўӮҪҒB
җВҺRҗГӮЖ’фҷy“№ҒAҗҙҸт–һүиҒAҸгү®•~—№ӮНүпҳbӮрӮөӮДӮўӮйҒB
Ҳк•ыӮЕӮНҗҢӮБӮҪҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮӘ“с”NӮрҸWӮЯӮДӢі•ЪӮЖӮўӮӨ–јӮМғeғҚӮрҚsӮБӮДӮўӮйҒBҚІҒX–ШӮМҺьӮиӮЙӮНғrҒ[ғӢӮМӢуӮ«ҠКӮӘӮўӮӯӮВӮа•АӮЧӮзӮкӮДӮўӮйҒB
ҒuӮұӮӨӮўӮӨҸуӢөӮБӮДӮўӮўӮжӮЛҒBӮўӮ©ӮЙӮаүҪӮ©ӢNӮұӮиӮ»ӮӨӮИҠҙӮ¶ӮЕӮіҒv
’фӮӘғrҒ[ғӢӮрӢуӮҜӮИӮӘӮзҢҫӮӨҒB
Ӯ·Ӯ©ӮіӮё–һүиӮӘҗVӮөӮўғrҒ[ғӢӮрҚ·ӮөҸoӮ·ҒB
ҒuҠmӮ©ӮЙӮЛҒBӮЬӮіӮөӮӯғ~ғXғeғҠҒ[Ҹ¬җаӮЖӮ©ҒcҒcӮ ҒAӮұӮМҢг“ҙҢAӮЕӮа”ӯҢ©Ӯ·ӮкӮОӮrӮeӮЙӮаӮИӮиӮ»ӮӨӮҫӮжӮЛҒvҗВҺRӮӘ“ҡӮҰӮйҒB
ҒuӮ»ӮкӮўӮўӮ©ӮаҒ[Ғv–һүиӮӘҠрӮөӮ»ӮӨӮЙ“ҡӮҰӮйҒB
ғWғғҒ[ғWҺpӮМ”ЮҸ—ӮНҗҢӮБ•ҘӮБӮДӮўӮйӮМӮ©ҠзӮӘҗФӮўҒB
ҒuҢ»ҺА“IӮ¶ӮбӮ ӮИӮўӮИҒBӮұӮұӮНӮвӮБӮПӮи’¬ӮЙӢAӮБӮДӮЭӮйӮЖҺАӮНӮЭӮсӮИ–^Қ‘ӮМҗN—ӘӮрҺуӮҜӮДӮДҒAүЖ‘°Ӯа‘ҖӮзӮкӮДӮўӮйҸу‘ФӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮаҒAҺ„ӮҪӮҝӮНӮ»ӮкӮЙӢCӮӘӮВӮ©ӮИӮўҒAӮЖӮ©Ғv
Ҹгү®•~—№ӮМ”ҜӮМ–СӮНүәӮлӮіӮкҒA”’ӮўғpғWғғғ}Ӯр’…ӮДӮўӮйҒB
ҒuӮҰӮҰӮБҒAҢ»ҺА“IӮЗӮұӮлӮ©ӢCӮӘӮВӮ©ӮИӮўӮсӮ¶ӮбҸ¬җаӮЙӮаӮИӮзӮИӮўӮ¶ӮбӮИӮўӮЕӮ·Ӯ©Ғv
’фӮӘҸОӮӨҒB
ҒuӮ»ӮӨҒHҒ@ҠFӮӘӢCӮӘӮВӮ©ӮИӮўӮЖӮұӮлӮӘҢ»ҺА“IӮ¶ӮбӮИӮӯӮБӮДҒv
ҺOҗlӮӘӮЁӮЁӮБӮЖҠҪҗәӮрҸгӮ°ӮйҒB
ҒuҠmӮ©ӮЙӮЛҒBӮіӮБӮ·ӮӘҺ„ӮМҢ©ҚһӮсӮҫҗж”yӮЕӮ·ҒIҒv
–һүиӮӘҸгү®•~—№ӮМҺиӮрӮЖӮиҢ©ҸгӮ°ӮйҒB
ҒuӮИӮсӮЕҒAӮЁ‘OӮӘҗж”yӮрҢ©ҚһӮЮӮсӮҫӮжҒB•Ғ’КӢtӮҫӮлҒv
–һүиӮНҠyӮөӮ»ӮӨӮЙ’фӮЙӮ Ӯ©ӮсӮЧҒ[ӮрӮ·ӮйҒB
ҒuӮЕӮаӮвӮБӮПӮұӮӨӮўӮӨҸуӢөӮНғQҒ[ғҖӮЙӮаӮ ӮйӮжӮЛҒBӮҰҒ[ӮЖҒcҒcғJғ}‘ӣӮ¬ӮМҒcҒcӮўӮвҒAғCғ^ғ`’BӮМҒcҒcӮИӮсӮҫӮБӮҜҒHҒv
’фӮӘҺиӮрӮ ӮІӮЙ“–ӮДҡXӮйҒB
ҒuӮ ӮйӮ ӮйҒIҒ@“~ӮМғyғ“ғVғҮғ“ӮЕ•ВӮ¶ҚһӮЯӮзӮкӮДҒAҺEҗl”ЖӮӘӮБӮДӮвӮВӮЕӮөӮеҒv–һүиӮӘ–ЪӮрӮ«ӮзӮ«ӮзӮіӮ№’фӮЙ‘МӮрҠсӮ№ӮйҒBҒuӮўӮўӮжӮЛҒAүӨ“№ӮБӮДӮўӮӨҠҙӮ¶ӮМғVғiғҠғIӮҫӮҜӮЗӮ»ӮкӮӘӮЬӮҪ”——НӮ ӮБӮДӮіҒv
–һүиӮНӮўӮВӮаӮжӮиӮ©Ӯа‘е’_ӮИҺ©•ӘӮЙӢCӮӘӮВӮ«ӮНӮ·ӮйӮаӮМӮМ•sҺvӢcӮҫӮЖӮНҠҙӮ¶ӮИӮўҒBҗҢӮБӮДӮўӮйӮ№ӮўӮЕҺьӮиӮӘҒAҢ©ӮҰӮДӮўӮИӮўӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮҜӮкӮЗӮұӮӨӮўӮӨҸкӮИӮзӮ»ӮкӮаӢ–ӮіӮкӮйӮҫӮлӮӨӮЖҺvӮӨӮМӮҫҒB
Ғu•ВҚҪ“IӢуҠФҒA‘жҲкӮМҺEҗlӮЙӮжӮБӮДӮЕӮ«Ӯй“БҲЩӮИҸуӢөҒAӮВӮЬӮи’NӮӘҺEҗlӮр”ЖӮөӮҪӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮұӮЖӮӘ’NӮаӮӘӢ^җSҲГӢSӮЙҺъӮнӮкӮйҒBӮ»ӮөӮДҒA”ЖҗlӮМ–Ъ“IӮМ“дҒv
Ҹгү®•~—№ӮМҺиӮЙӮНӮўӮВӮМҠФӮЙӮ©ғOғүғXӮӘҲ¬ӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮкӮрҲкҢыҲщӮЭҸОҠзӮЕӮЁӮўӮөӮўӮЖҷкӮӯҒB
Ғu–К”’ӮўӮЖҠҙӮ¶ӮйҸк–КӮНҗlӮ»ӮкӮјӮкӮҫӮлӮӨӮҜӮЗӮЛҒvҗВҺRӮӘҢҫӮӨҒB
ҒuүҙӮНӮвӮБӮПӮиҗSҸоӮМ•Пү»ӮӘҚDӮ«Ӯ©ӮИҒBғӮғүғӢӮМ•цүуӮЖӮ©Ӣ^җSҲГӢSӮЖӮ©ҒA‘z‘ңӮНӮ·ӮйӮҜӮЗҺАҚЫ‘МҢұӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮўӮаӮсӮЛҒBӮ»ӮкӮұӮ»җн‘ҲӮЖӮ©ӮЙӮИӮзӮИӮўӮЖӮИӮўӮҫӮлӮӨӮөҒv’фӮМҺӢҗьӮНҗВҺRӮЙҢьӮҜӮзӮкӮДӮўӮйҒBҒuӮИӮЙӮжӮиҒAӮ»ӮсӮИҸуӢөӮ¶ӮбӮ ҠyӮөӮЮӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮіӮ»ӮӨӮҫӮ©ӮзӮЛҒv
ҢҫӮўҸIӮнӮБӮДӮ©ӮзҠFӮЙҲУҢ©ӮрӢҒӮЯӮйӮжӮӨӮЙҢ©үсӮ·ҒB
ҒuүҙӮНғgғҠғbғNӮМ•ыӮ©ӮИҒBғgғҠғbғNӮБӮДҢҫӮБӮДӮа•ЎҺGӮИӮаӮМӮ¶ӮбӮИӮӯӮДӮўӮўӮсӮҫҒBӮўӮ©ӮЙ’PҸғӮИӮаӮМӮЙйxӮіӮкӮДӮөӮЬӮӨӮ©ӮӘ–К”’ӮўӮЖӮұӮлӮҫӮЖҺvӮӨӮжҒBҸ–ҸqғgғҠғbғNҠЬӮЯӮДӮЛҒv
ҒuӮ ӮҪӮөӮНҒcҒcҒv–һүиӮМҸЕ“_ӮНӮўӮЬӮўӮҝ’иӮЬӮБӮДӮўӮИӮўҒBҒu‘S•”ҒIҒv
ҒuӮЁ‘OҒA‘еҸд•vӮ©ҒHҒv
–һүиӮНӮҜӮҪӮҜӮҪӮЖҸОӮБӮДӮўӮйҒB
ҒuҗS”zҒHҒv
ҸОӮБӮДӮўӮҪӮНӮёӮМ–һүиӮӘӢ}ӮЙҠзӮрӢЯӮГӮҜӮДӮ«ӮҪӮМӮЕ’фӮНӢБӮӯҒB
–һүиӮ©ӮзӮНғVғғғ“ғvҒ[ӮМҠГӮўҚҒӮиӮӘӮөӮДӮўӮйҒB
Ғu’фҒA•”ү®ӮЙҳAӮкӮДҚsӮБӮДӮ Ӯ°ӮкӮОҒHҒvҗВҺRӮӘҢҫӮӨҒB
ҒuӮ ҒAӮ Ӯ ҒAӮ»ӮӨӮҫӮИҒv’фӮНихӮўӮД—§ӮҝҸгӮӘӮйҒBҒuӮЩӮзҒA–һүи—§ӮДӮйӮ©ҒHҒv
ӮУӮзӮУӮзӮЖ—НӮИӮӯ—§ӮҝҸгӮӘӮи’фӮЙӮаӮҪӮкӮ©Ӯ©ӮйӮжӮӨӮЙӮөӮД•аӮ«ҸoӮ·ҒB
ҒuӮаӮӨҒA–°ӮӯҒcҒcӮИӮсӮДӮИӮўӮжҒv
ӮФӮВӮФӮВӮЖ–һүиӮӘ•¶ӢеӮрҢҫӮӨӮӘ’фӮН–іҺӢӮөӮД•шӮҰӮйӮжӮӨӮЙӮөӮД“сҠKӮЦҢьӮ©ӮӨҒB
Ӯ»ӮсӮИӮЙҲщӮсӮЕӮўӮҪӢCӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮҜӮЗҒA‘Ҡ“–җҢӮБӮДӮйӮИҒB
ҲкҠKӮМҺу•t•tӢЯҒAҠK’iӮЖ“dӢCӮНҸБӮҰӮДӮўӮДҲГӮўҒB“сҠKӮМҳLүәӮҫӮҜӮНҢҺӮМ–ҫӮ©ӮиӮЕҸЖӮзӮіӮк‘«ҢіӮӘӮжӮӯҢ©ӮҰӮйҒBҳLүәӮрҸгӮиӮ«ӮиҚ¶ӮЦӢИӮӘӮйҒBӮQӮOӮRҚҶҺәӮНҠK’iӮрҸгӮБӮҪӮ·Ӯ®Қ¶ӮҫҒB
ҠmӮ©ҒA“Ў“c”ь‘ҒӮӘ•”ү®ӮЙӮўӮйӮНӮёӮҫҒBҸ¬“№–ВӮНӮЬӮҫҲкҠKӮЙӮўӮҪҒB
ҲкүһғmғbғNӮрӮөӮжӮӨӮЖҺvӮБӮҪӮӘҒA–һүиӮр•шӮҰӮИӮӘӮзӮ·ӮйӮЩӮЗӮМӮұӮЖӮЕӮаӮИӮўӮЖ”»’fӮөӮҪҒB
“Ў“c”ь‘ҒӮаӮаӮӨ–°ӮБӮДӮўӮйӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӮЩӮзҒAӮөӮБӮ©Ӯи—§ӮДӮжҒAӮаӮӨҒv
–һүиӮр•шӮҰӮИӮЁӮөӮДғhғAӮрҠJӮҜӮйҒB
ҒuӮ ӮБҒv
•”ү®ӮЙ“ьӮйӮЖҸ¬ӮіӮИҗәӮӘӮөӮҪҒB
“dӢCӮНҸБӮҰӮДӮўӮйӮӘҠOӮ©ӮзӮМҢхӮЕғxғbғhӮМҢ„ҠФӮ©ӮзҗlӮӘ—§ӮҝҸгӮӘӮйӮМӮӘӮнӮ©ӮйҒB
Ғ\Ғ\үҪӮрӮөӮДӮўӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒH
“Ў“c”ь‘ҒӮЕӮ ӮйҒB
ҒuӮҫӮкҒHҒv
”ь‘ҒӮ©ӮзӮНҠзӮЬӮЕӮНҢ©ӮҰӮИӮўӮзӮөӮўҒB
ҒuүҙӮҫӮжҒB’фҒv
ӮИӮәӮ©Ҹ¬җәӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮӘ’фӮӘ“ҡӮҰӮйҒB
ҒuүҪҒHҒv
”ь‘ҒӮӘ–іҲӨ‘zӮЙ“ҡӮҰӮйҒB
ӮЗӮӨӮа—lҺqӮӘӮЁӮ©ӮөӮўӮӘҒAӮўӮВӮаӮМӮұӮЖӮЖҠ„ӮиҗШӮйҒB
ҒuӮўӮвҒA–һүиӮӘҲщӮЭӮ·Ӯ¬ӮҪӮзӮөӮӯӮДҗҢӮБ•ҘӮБӮҝӮбӮБӮҪӮЭӮҪӮўӮИӮсӮҫҒv
Ғu’NӮЕӮаӮЁҺрӮрҲщӮЯӮОҗҢӮӨӮнӮжҒv
–іҲӨ‘zӮіӮЙ—ЦӮӘӮ©Ӯ©ӮйӮӘҲ«ҲУӮНӮИӮўӮМӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӮҰӮБӮЖҒAҗҢӮўӮ·Ӯ¬ӮҪҒcҒcӮ©ӮИҒA–һүиӮМғxғbғhӮНҒHҒv
–һүиӮНӮаӮӨҗQ‘§Ӯр—§ӮДӮНӮ¶ӮЯӮДӮўӮйҒB
”ь‘ҒӮӘҲк”ФғhғAӮЙӢЯӮўғxғbғhӮрҺwҚ·Ӯ·ҒB
’фӮН–һүиӮрғxғbғhӮЙӮИӮсӮЖӮ©җQӮ©Ӯ№ӮДӮвӮйҒBӮ»ӮМӮ ӮўӮҫ”ь‘ҒӮНӮёӮБӮЖҚЕҸүӮМҸкҸҠӮЕ—§ӮБӮҪӮЬӮЬ’фӮМӮұӮЖӮрҢ©ӮВӮЯӮДӮўӮҪҒB
Ғu’фҒv
’фӮӘӮ»ӮМӮЬӮЬүсӮкүEӮрӮөӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӮЖ”ь‘ҒӮӘҗәӮрӮ©ӮҜӮйҒB
ҒuӮ ӮсӮҪҒA–һүиӮМӮұӮЖҒcҒcӮНӮБӮ«ӮиӮөӮИӮіӮўӮжӮЛҒv
’фӮМ—\ҠъӮөӮДӮўӮИӮўҢҫ—tӮрҢҫӮнӮкӮйҒB
’фӮНӮЗӮӨӮөӮҪӮзӮўӮўӮ©ҚlӮҰӮйӮӘҢӢӢЗӮЖӮЪӮҜӮД•”ү®ӮрҸoӮйҒB
ҢҫӮнӮкӮҪӮұӮЖӮӘүҪӮ©ӮНӮжӮӯӮнӮ©ӮБӮДӮўӮйҒBүҙӮҫӮБӮД”nҺӯӮ¶ӮбӮИӮўӮсӮҫҒB”ь‘ҒӮЖ–һүиӮӘ’ҮӮӘӮўӮўӮұӮЖӮ©ӮзҚlӮҰӮйӮЖҒAӮ»ӮӨӮўӮБӮҪҳbӮрӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮа•ПӮЕӮНӮИӮўҒB
ӮўӮвҒA–һүиӮМҗ«ҠiӮ©ӮзҚlӮҰӮйӮЖ”ЮҸ—Ӯ©Ӯзҳb‘иӮрҗUӮйӮұӮЖӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨӮҜӮкӮЗҒA”ь‘ҒӮ©Ӯз–вӮўӢlӮЯӮзӮкӮйӮұӮЖӮНӮ ӮБӮҪӮҫӮлӮӨҒB
’mӮБӮДӮўӮйӮжҒB
–һүиӮӘүҙӮМӮұӮЖӮрҚDӮ«ӮИӮұӮЖӮӯӮзӮўӮНҒAӮұӮкӮҫӮҜ’·ӮўҠФҲкҸҸӮЙӮўӮйӮсӮҫҒB
ӢCӮӘӮВӮ©ӮИӮўӮЩӮӨӮӘӮЗӮӨӮ©ӮөӮДӮйӮҫӮлҒB
ӮЕӮаҒAӮНӮБӮ«ӮиӮ·ӮкӮОүуӮкӮДӮөӮЬӮӨӮұӮЖӮаӮ ӮйӮҫӮлӮӨҒH
Ӯ»ӮкӮНҠЦҢWӮӘӮ¶ӮбӮИӮўҒBҺ©•ӘӮӘүуӮкӮйӮұӮЖӮНӮИӮўӮҜӮкӮЗҒA–һүиӮНӮЗӮӨӮҫҒH
ҚЎӮМӮЬӮЬӮЕӮўӮўӮИӮзӮ»ӮкӮЕҒcҒcҒB
ӮS
ҠK’iӮрүәӮиӮйӮЖҗВҺRҗГӮЖ“ҢҗқҒAҸ¬“№–ВӮӘҢәҠЦӮ©ӮзҸoӮДҚsӮӯӮЖӮұӮлӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ ӮкҒAӮЗӮБӮ©ӮўӮӯӮМҒHҒv
ҒuӮўӮвҒA•—ӮЙӮ ӮҪӮиӮЙҚsӮӯӮҫӮҜӮҫӮжҒBӮ»ӮкӮЙҗҜӮаҢ©ӮДӮЁӮ«ӮҪӮўӮөӮЛҒvҗВҺRӮӘ“ҡӮҰӮйҒBҒuҸгү®•~җж”yӮӘҲкҗlӮҫӮ©ӮзҚsӮБӮДӮ Ӯ°ӮкӮОҒHҒv
Ҹ¬“№–ВӮЖ“ҢҗқӮН”жӮкӮҪ—lҺqӮҫҒBҚІҒX–Шҗж”yӮМ‘ҠҺиӮрӮөӮД‘М—НӮрҸБ–ХӮөӮҪӮЖӮұӮлӮрҗВҺRӮӘӢ~ӮўҸoӮөӮҪӮЖӮўӮБӮҪӮЖӮұӮлӮҫӮлӮӨҒB
’фӮН“ьӮиҢыӮМғhғAӮӘ•ВӮЬӮйӮМӮрҢ©“НӮҜӮДӮ©ӮзҒAғҠғrғ“ғOӮЦӮЖ–ЯӮйҒB
ҚІҒX–ШҚ„‘ҫӮН‘Ҡ•ПӮнӮзӮё‘еҗәӮЕүҪӮ©ҳbӮөӮДӮўӮйӮӘҒAҳZаV—Ъ—һӮӘӮ»ӮкӮЙӮВӮўӮДӮўӮБӮДӮўӮйӮМӮЙӮНӢБӮ«ӮҫҒB
Ҹгү®•~—№ӮН‘«ӮрҗFӮБӮЫӮӯ“ҠӮ°ҸoӮөҒAҺрӮМғrғ“ӮМғүғxғӢӮЙҸ‘Ӯ©ӮкӮҪ•¶ҺҡӮрӢ»–Ўҗ[Ӯ»ӮӨӮЙ“ЗӮсӮЕӮўӮйҒB
ҒuүҪӮ©–К”’ӮўӮұӮЖӮЕӮаҸ‘ӮўӮДӮ ӮиӮЬӮ·Ӯ©ҒHҒv
’фӮӘ”ЮҸ—ӮМ–ЪӮМ‘OӮЙҚҳӮрүәӮлӮ·ӮЖҠзӮрҸгӮ°ӮДҸОҠзӮрҚмӮйҒBӮ»ӮМҸОҠзӮЙӢ№ӮӘҲкӮВ‘еӮ«Ӯӯ‘ЕӮВҒB
ҒuӮ Ӯ ҒAӮИӮЙӮаӮИӮўӮжҒv
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒAүҪҢ©ӮДӮҪӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
ҒuҢ©ӮжӮӨӮЖӮНӮөӮҪӮҜӮЗҢ©ӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒBҺc”OӮҫҒvҸгү®•~—№ӮНғrғ“Ӯр’uӮ«ӮИӮӘӮз–{“–ӮЙҺc”OӮ»ӮӨӮЙӮөӮДӮўӮйҒBҒuӮ»ӮӨӮҫҒAҗҙҸтӮН‘еҸд•vӮҫӮБӮҪҒHҒv
ҒuӮҰӮҰҒAҚўӮБӮҪӮвӮВӮЕӮ·ӮжӮЛҒBҚЎ“ъӮНӮ»ӮсӮИӮЙҲщӮсӮЕӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮЖҺvӮБӮҪӮсӮЕӮ·ӮҜӮЗҒAӮ®ӮЕӮсӮ®ӮЕӮсӮЕӮөӮҪӮ©ӮзӮЛҒv
’фӮӘ“ҡӮҰӮйӮЖҸгү®•~—№ӮӘҸОӮӨҒB
ҒuӮ®ӮЕӮсӮ®ӮЕӮсӮБӮДӮўӮўӮЛҒv
Ғu—ЗӮӯӮИӮўӮЕӮ·ӮжҒIҒ@ӮвӮБӮПӮиӮұӮӨӮўӮБӮҪ•өҲНӢCӮӘӮўӮҜӮИӮ©ӮБӮҪӮсӮЕӮ·Ӯ©ӮЛҒv
ҒuғAғӢғRҒ[ғӢӮжӮиӮ©ӮаҗҢӮўӮвӮ·ӮўӮаӮМӮНӮИӮсӮЕӮөӮеӮӨҒHҒv
Ҹгү®•~—№ӮӘҗlҚ·ӮөҺwӮр—§ӮДӮйҒB
ҒuӮҰҒAғNғCғYӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv’фӮНғAғӢғRҒ[ғӢӮЕӮЪҒ[ӮЖӮ·Ӯй“ӘӮр“ӯӮ©Ӯ№ӮйҒBҒuӮҰҒ[ҒcҒcӮЖҒBҸd—НӮЖӮ©ҒA•Ё—қҢ»ҸЫӮЕӮаӮжӮўӮЬӮ·ӮжӮЛҒBҺ©•ӘӮМҺO”јӢKҠЗӮМ”FҺҜӮЖҺАҚЫӮМ“®Ӯ«ӮЙҢлҚ·ӮӘӮ ӮйҸкҚҮӮЖӮ©ҒcҒcҒv
Ҹгү®•~—№ӮӘҗOӮМ•Р•ыӮрӮр–Ј—Н“IӮЙҺқӮҝҸгӮ°”’ӮўҺ•ӮӘҢ©ӮҰӮйӮ©Ң©ӮҰӮИӮўӮ©ӮМӮЖӮұӮлӮЕҸОҠзӮрҚмӮйҒB
ҒuӮФӮБӮФҒ[Ғv
ӮЬӮҪҒAӮўӮҪӮёӮзӮБӮЫӮӯҢыӮМ‘OӮЙҗlҚ·ӮөҺwӮрҺқӮБӮДӮӯӮйҒB
’фӮНҺvӮӨҒBӮЗӮӨӮөӮДӮұӮМҗlӮНӮұӮсӮИӮЙӮа–Ј—Н“IӮИӮсӮҫӮлӮӨҒH
ҒuҗіүрӮН–ў—ҲӮЕӮөӮҪҒ[Ғv
”ЮҸ—ӮН’фӮӘ•sҺvӢcӮ»ӮӨӮИҠзӮрӮ·ӮйӮМӮрҢ©ӮДӮӯӮ·ӮӯӮ·ӮЖҸОӮӨҒB
ҒuӮИӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒAӮ»ӮкҒHҒv
Ҹгү®•~—№ӮӘӮ»ӮкӮЙ“ҡӮҰӮҪҒB
ҒuҗlӮӘӮИӮсӮЕҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮйӮЖҺvӮӨҒHҒ@ӮнӮ©ӮзӮИӮў–ў—ҲӮЙӮаүҪӮ©Һ©•ӘӮМ—қ‘z‘ңӮр•`ӮўӮДӮ»ӮМ–ў—ҲӮЙҗҢӮБӮДӮўӮйӮ©ӮзӮ¶ӮбӮИӮўҒHҒ@ӮұӮұӮЬӮЕ•Ё—қҢ»ҸЫӮӘүр–ҫӮіӮкӮДҺх–ҪӮв•aӢCӮИӮЗҺ©•ӘӮӘҺҖӮК—қ—RӮЬӮЕ•ӘӮ©ӮБӮҝӮбӮБӮДӮйҒBҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮДӮаүҪӮ©Ӯ ӮйӮнӮҜӮ¶ӮбӮИӮўӮұӮЖӮаӢCӮӘӮВӮўӮДӮўӮйҒBӮ»ӮкӮИӮМӮЙӮЗӮӨӮөӮДҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮзӮкӮйӮнӮҜҒHҒ@ӮаӮөӮ©ӮөӮДҒAҗ¶ӮЬӮкӮДҲУҺҜӮӘүиҗ¶ӮҰӮҪҺһӮ©ӮзҺ„ӮҪӮҝӮН–{“–ӮНҗҢӮў‘ұӮҜӮДӮйӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮөӮзҒBҗн‘ҲӮӘӢNӮұӮлӮӨӮӘҒAҺ–ҢМӮЕҺҖӮМӮӨӮӘҒAҗVӮөӮўғGғlғӢғMҒ[ӮӘ”ӯҢ©ӮіӮкӮҪӮЖӮөӮДӮаҒAӮ»ӮкӮӘӮИӮсӮҫӮЖӮўӮӨӮМҒHҒ@ҺРүпӮМҗ¬’·ҒHҒ@Ӯ»ӮсӮИӮаӮМӮЙӢҰ—НӮөӮДүҪӮӘ“ҫӮзӮкӮйӮМҒHҒ@Ӯ»ӮұӮЙҲУ–ЎӮр—^ӮҰӮйӮМӮНҢӢӢЗӮНҺ©ҲУҺҜӮЕӮөӮ©ӮИӮўҒBӮ»ӮкӮЙӮ·ӮзӢCӮӘӮВӮ©ӮИӮўҗlҠФӮ·ӮзӮўӮйӮнҒBӮҫӮ©ӮзҒAҗlӮНҠFҗҢӮБӮДӮўӮйӮМҒAҢАӮиӮИӮӯҠm’и“IӮЕ•sҠm’иӮИ–ў—ҲӮЙҒv
Ӯ»ӮМӮұӮЖӮрҠyӮөӮ»ӮӨӮЙҸqӮЧӮйҸгү®•~—№ӮЙ’фӮНҗщ—ҘӮрҠoӮҰӮйҒB
”ЮҸ—ӮН“ӘӮӘӮўӮўҢМӮЙҢӢҳ_Ӯр“ұӮ«ҸoӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮҫҒBӮЕӮаҒA”ЮҸ—ӮМ—lҺqӮ©Ӯз”ЯҠПӮНҺfӮҰӮИӮўӮЖӮұӮлӮрӮЭӮйӮЖӮ»ӮкӮӘ”ЮҸ—ӮМҢӨӢҶғeҒ[ғ}ӮЖӮИӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮйҒB
ҒuҸгү®•~ҒcҒcӮіӮсҒvӮИӮәӮ©җж”yӮЖӮўӮӨҢҫ—tӮрҺgӮўӮҪӮӯӮИӮ©ӮБӮҪҒBҒuӮжӮӯ–іҺ–ӮЕӮөӮҪӮЛҒv
Ҹгү®•~—№ӮНғOғүғXӮрӢуӮҜӮйҒB
ҒuӮЗӮӨӮ©ӮИҒA–іҺ–Ӯ¶ӮбӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮҪӮҫҒAӮ»ӮӨҒcҒcӮұӮкӮНғ~ғXғeғҠҒ[ӮҫӮИҒv
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ӮВӮГӮӯӮжҒIҒIҒI
|
|
|
|
| ҒuҒ@I ronyҒ@ҒvҒ@Ғ@Ғ@ҳAҚЪҺ®Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@’ҳҒ@Һl”Nҗ¶ҒFғWғFғoғ“ғjҒ@Ғi•ӣ•”’·Ғj |
|
|
|
Ғ@
Ғ@Ғ@Ғ@ғvғҚғҚҒ[ғO
Ғu”ьҚзҒA–lӮзӮНҚЎ“ъӮЕӮЁ•КӮкӮИӮсӮҫҒv
ҒuҒcҒcҒv
”ЮҸ—ӮНүҪӮа“ҡӮҰӮИӮўҒBӮҪӮҫӢ•ӮлӮИ–ЪӮЕӮЗӮұӮЖӮаӮВӮ©ӮИӮўҸкҸҠӮрҢ©ӮВӮЯӮДӮўӮйҒB
•УӮиӮНҲГӮўҒBӮіӮБӮ«ӮЬӮЕӮНӮөӮсӮөӮсӮЖҗбӮӘҚ~ӮБӮДӮўӮҪӮӘҒAҚЎӮЕӮНүJӮЙӮ©ӮнӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB–lӮНҺPӮаҚ·ӮіӮёҒA”ЮҸ—ӮМүҪӮаүfӮіӮИӮў“өӮрҢ©ӮВӮЯӮДҢҫ—tӮр–aӮўӮҫҒB
Ғu–lӮН”ьҚзӮЖӮНҲкҸҸӮЙҚsӮҜӮИӮўӮсӮҫҒBӮІӮЯӮсӮЛҒB–lӮНҲкҸҸӮЙ•йӮзӮөӮҪӮўӮсӮҫӮҜӮЗҒA”ьҚзӮНҚЎ“ъӮ©ӮзҲбӮӨҸҠӮЕ•йӮзӮіӮИӮ«ӮбӮўӮҜӮИӮўӮсӮҫҒv
ҒuҒcҒcҒv
•·ӮұӮҰӮДӮўӮйӮМӮ©ӮаӮнӮ©ӮзӮИӮўҒB
Ӯ»ӮкӮЕӮа–lӮНҳbӮө‘ұӮҜӮйҒB
ҚЎ“ъӮрӢ«ӮЙ•КӮкӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮў”ЮҸ—ӮЙҒB
Ғu”ьҚзӮНӮЛҒAҗSӮӘ•aӢCӮЙӮ©Ӯ©ӮБӮДӮйӮсӮҫҒBӮҫӮ©ӮзҒAӮұӮкӮ©ӮзӮНӮ»ӮМӮЁҲгҺТӮіӮс’BӮЖҲкҸҸӮЙ•йӮзӮ·ӮсӮҫӮжҒv
–lӮН•GӮрӮВӮ«ҒA”ЮҸ—ӮМҸқӮҫӮзӮҜӮМҗg‘МӮрӮ»ӮБӮЖ•шӮ«ҠсӮ№ӮДҢҫӮБӮҪҒB
”ьҚзҒB–lӮМ–…ҒB
ҚЎ”NӮЕӢгҚОӮЙӮИӮйӮЖӮўӮӨӮМӮЙҒAӮ»ӮМ”ӯҲзӮНҺА”N—оӮМӮ»ӮкӮжӮиӮаӮіӮзӮЙ—cӮўҒB
•кӮӘҗHҺ–Ӯр—^ӮҰӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮҫӮлӮӨҒBҗg‘МӮМҗ¬’·ӮӘ’xӮўӮМӮҫҒB
ҒuӮҫӮ©Ӯз”ьҚзҒA–lӮзӮНӮөӮОӮзӮӯҲ§ӮҰӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮсӮҫҒBҒ\Ғ\Ғ\ӮЕӮаҒAӮұӮкӮ©ӮзӮНӮ»ӮМҒcүЈӮзӮкӮҪӮиӮ·ӮйӮұӮЖӮа–іӮўӮөҒAҺьӮиӮН—DӮөӮўҗlӮОӮ©ӮиӮЙӮИӮйӮ©ӮзҒAӮ«ӮБӮЖ‘еҸд•vӮҫӮжӮЛҒHҒv
ҒuҒcҒcҒv
•ФҺ–ӮНӮЁӮлӮ©ҒAихӮӯӮұӮЖӮіӮҰӮөӮИӮўҒB”ЫҒAҸo—ҲӮИӮўӮМӮҫӮлӮӨҒB
–lӮӘҳbӮ·ӮМӮрҺ~ӮЯӮйӮЖҒA“r’[ӮЙҺьҲНӮМӮҙӮнӮЯӮ«ӮӘҺЁӮЙ“ьӮБӮДӮӯӮйҒB
ҒuҸoӮДҚsӮӯӮЭӮҪӮўӮЛҒBӮ ӮМҺqҒv
ҒuӮЁ•кӮіӮсӮЙҺhӮіӮкӮҪҺqӮЕӮөӮеӮӨҒHҒv
ҒuӮвӮБӮЖ–пүоҺТӮМҲкүЖӮӘӮўӮИӮӯӮИӮйӮМӮЛҒBӮЁҢZӮҝӮбӮсӮМ•ыӮаҸoӮДҚsӮӯӮсӮЕӮөӮеӮӨҒHҒv
Ғ@“ҜӮ¶ғAғpҒ[ғgӮЙҸZӮсӮЕӮўӮйҗlӮҪӮҝӮӘҒA–lӮзӮМү\ӮрӮөӮДӮўӮйӮЭӮҪӮўӮҫҒB
”wҢгӮЙӮ ӮйҢГӮСӮҪғgғ^ғ“ү®ҚӘӮМҸ¬ӮіӮИғAғpҒ[ғgӮМҲкҺәӮЙӮНҒAӮВӮўҲкҸTҠФ‘OӮЬӮЕ–lӮЖ–…ҒAӮ»ӮөӮД•кӮіӮсӮӘҸZӮсӮЕӮўӮҪҒB
ҲкүЖҒAӮЖҒA–lӮзӮНҢДӮОӮкӮҪӮҜӮкӮЗҒAӮ»ӮМҢҫ—tӮ©ӮзҠҙӮ¶ӮзӮкӮй—DӮөӮўҲУ–ЎҚҮӮўӮНҒA–lӮзҲкүЖӮЙӮН“–ӮДӮНӮЬӮзӮИӮўӮжӮӨӮЙҺvӮӨҒB
үЖӮЙӮўӮД•·ӮұӮҰӮДӮӯӮйӮМӮНӮўӮВӮа”ЮҸ—ӮМ”Я–ВӮЖҒA•кӮМ“{җәӮҫӮБӮҪҒB
–lӮМ–ј‘OӮНҚLҚ]җSҢмҒB
”ЮҸ—ӮМ–ј‘OӮНҚLҚ]”ьҚзҒBӢҢҗ©ӮрҺВҢҙ”ьҚзӮЖҢҫӮБӮҪҒB
–lӮЖ”ьҚзӮНҒA“сҗlӮ«ӮиӮМҢZ–…ӮЕӮНӮ ӮйӮҜӮкӮЗҒAҢҢӮНҢqӮӘӮБӮДӮўӮИӮўҒB
–lӮН•ғӮМҳAӮкҺqӮЕҒA”ьҚзӮН•кӮМҳAӮкҺqӮҫӮБӮҪҒB
•ғӮЖ•кӮН—јҺТӮЖӮаӮЙ—ЈҚҘ—пӮМӮ ӮйҒAғoғcғCғ`“ҜҺmӮЕҚДҚҘӮрӮөӮҪӮМӮҫҒB
”ьҚзӮӘҺOҚОҒA–lӮӘҸ\ҲкҚОӮМҺһӮЙҒB
ҚДҚҘӮөӮДӮөӮОӮзӮӯӮНҒAҚKӮ№ӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮЙҺvӮӨҒB
ӮҜӮкӮЗ•ғӮНҸ—җ«ӮЙӮҫӮзӮөӮМӮИӮўҗlӮЕҒAҚДҚҘҢгҒAҲк”NӮаӮөӮИӮўӮӨӮҝӮЙ‘јӮМҸ—ӮЖӮЗӮұӮ©ӮЦҚsӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB
Ӯ»ӮМӮ ӮҪӮиӮ©ӮзӮҫӮлӮӨӮ©ҒcҒcҒB•кӮӘүуӮкҺnӮЯӮҪӮМӮНҒB
•кӮН•ғӮӘҸoӮДҚsӮБӮДӮ©ӮзҒAҗlӮӘ•ПӮнӮБӮҪӮжӮӨӮЙҗГӮ©ӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮЬӮЕ–lӮӘҢ©ӮДӮ«ӮҪ•кӮНҒAүМӮӘҚDӮ«ӮЕҒA‘ҫ—zӮМӮжӮӨӮЙ–ҫӮйӮўҗlӮҫӮБӮҪӮМӮЙҒB
•кӮНҗHҺ–ӮрӮўӮВӮаҺlҗl•Ә—pҲУӮөӮҪҒB•ғӮӘӮўӮВӢAӮБӮДӮ«ӮДӮаӮўӮўӮжӮӨӮЙӮЖҒB
Ӯ»ӮөӮДӮўӮВӮа–й’xӮӯӮЬӮЕҒA•ғӮМӢAӮиӮр‘ТӮБӮДӮўӮҪҒB
–lӮЙӮНӮнӮ©ӮБӮДӮўӮҪҒB•ғӮН–lӮрӮұӮМҗlӮЙүҹӮө•tӮҜӮйӮҪӮЯӮЙҚДҚҘӮөӮҪӮМӮҫҒBӮҫӮ©ӮзҒAӮаӮӨӮ«ӮБӮЖ“с“xӮЖҒAӮұӮұӮЦӮНӢAӮБӮДӮұӮИӮўӮБӮДҒB
•ғӮӘҸoӮДҚsӮБӮҪӮ©Ӯз–lӮаӮұӮұӮЙӮНӮўӮзӮкӮИӮўӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪӮҜӮЗҒA•кӮНҢҢӮМҢqӮӘӮиӮМӮИӮў–lӮрҢ©ҺМӮДӮёӮЙҗўҳbӮөӮДӮӯӮкӮҪҒB
–lӮӘ’ҶҠwҚZӮЙ“ьӮБӮДҒA”wӮӘҗLӮСӮДӮӯӮйӮЖҒA•ғӮЙҺ—ӮДӮўӮйӮ©ӮзӮҫӮлӮӨӮ©ҒA•кӮН–lӮр“MҲӨӮөҒAӮ©ӮнӮиӮЙ”ьҚзӮрҺЧҢҜӮЙҲөӮӨӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒBӢs‘ТҒAғlғOғҢғNғgҒAҚрҚЎ’ҝӮөӮӯӮа–іӮў’PҢкӮҫӮӘҒA–lӮМүЖӮЕӮН–Ҳ“ъӮМӮжӮӨӮЙӮ»ӮМҠхӮЬӮнӮөӮўҚsҲЧӮӘҚsӮнӮкӮДӮўӮҪҒBӮЬӮҫ—cӮў–…ӮЙӮҫӮҜҒcҒcҒB
Ғu”ьҚзҒAҠҰӮӯӮИӮўҒHҒv
–lӮНӮұӮМҠҰӢуӮЙҚ~ӮйүJӮМ’ҶҒA”–’…ӮЕғRҒ[ғgӮа’…ӮёӮЙӮўӮй•п‘СӮҫӮзӮҜӮМ–…ӮЙҒA’…ӮДӮўӮҪғRҒ[ғgӮр’…Ӯ№ӮҪҒBүJӮЕ”GӮкӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮйӮөҒA”ьҚзӮаӮёӮФ”GӮкӮҫӮ©ӮзӮ ӮЬӮи–hҠҰ’…ӮЖӮөӮДӮМҢшүКӮН–]ӮЯӮИӮўӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮҜӮкӮЗ–lӮН”ьҚзӮЙғRҒ[ғgӮр’…Ӯ№ӮҪҒBӮҪӮҫүҪӮ©ӮөӮДӮ Ӯ°ӮҪӮ©ӮБӮҪҒBҲкҸҸӮЙҗ¶ҠҲӮөӮДӮўӮйҠФҒAҢZӮзӮөӮўӮұӮЖӮНүҪӮаӮөӮДӮвӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBҺзӮБӮДӮ Ӯ°ӮйӮұӮЖӮаҸo—ҲӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuҒcҒcҒv
–lӮЖ”ьҚзӮНҒAҢҢӮНҢqӮӘӮБӮДӮўӮИӮўӮҜӮкӮЗҒAӮ»ӮкӮЕӮаҢZ–…ӮЕҒAүЖ‘°ӮҫҒB•ғӮа•кӮаӮўӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮ©ӮзҒAҚЎӮНӮұӮМҗўӮЕӮҪӮБӮҪҲкҗlӮМүЖ‘°ӮҫҒB
ӮҜӮкӮЗҒA–ҫ“ъӮ©ӮзӮН•КҒXӮЙ•йӮзӮіӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒB
ҲкҸTҠФ‘OҒA–lӮӘҠwҚZӮ©ӮзӢAӮБӮДӮӯӮйӮЖҒA•кӮН”ьҚзӮМҳrӮр•п’ҡӮЕҺhӮөӮДӮўӮҪҒB
—Чҗl’BӮМү\’КӮиӮЙҒB
Ғu”ьҚзҒv
ҢДӮсӮЕӮа•ФҺ–ӮН–іӮўҒB
•ВӮ¶ӮзӮкӮҪҢыӮН•s“®ҒAҲГӮӯ’ҫӮсӮҫ–ЪӮӘ–lӮЖҚҮӮӨӮұӮЖӮНӮИӮўҒB
–lӮНӮҪӮЯ‘§ӮрӮВӮўӮҪҒB
Ғu”ьҚзҒcҒcҒv
–lӮНӮаӮӨҲк“xҒA”ьҚзӮМғKғҠғKғҠӮЕҸқӮҫӮзӮҜӮМҗg‘МӮрӮ»ӮБӮЖ•шӮўӮҪҒB
—НӮўӮБӮПӮў•шӮ«ӮөӮЯӮҪӮ©ӮБӮҪӮӘҒA”ьҚзӮМҗg‘МӮЙӮН’ЙҒXӮөӮўҸқӮӘ–іҗ”ӮЙӮ ӮйҒBӮ»ӮМ’ҶӮЙӮН•кӮЙҺhӮіӮкӮҪҸқӮаӮ ӮйӮМӮҫҒBӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮрӮ·ӮкӮОҸқӮӘҠJӮўӮДӮөӮЬӮӨӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB
ҒuҒcҒcҒv
—вӮҪӮўҒBӮёӮФ”GӮкӮҫӮ©ӮзӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮН–іӮўҒB
‘Мү·ӮӘҠҙӮ¶ӮзӮкӮИӮўҒBӮЬӮйӮЕ•XӮЕҸo—ҲӮҪҗlҢ`ӮЕӮа•шӮўӮДӮўӮйӮЭӮҪӮўӮҫӮБӮҪҒB
җSӮӘ“ҖӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮзҒAҗg‘МӮа“ҖӮБӮДӮөӮЬӮӨӮсӮҫӮлӮӨӮ©ҒH
–Ъ“ӘӮӘ”MӮўҒB–lӮНӢғӮўӮДӮўӮйӮсӮҫӮлӮӨҒB
ҸҒӮсӮҫ–ЪӮЕ”ЮҸ—ӮМ‘SҗgӮрҢ©ӮВӮЯӮҪҒB
•һӮЕҢ©ӮҰӮИӮўӮҜӮкӮЗҒA•sҢ’ҚNӮЙҚЧӮўҗg‘МӮН‘SҗgҸқӮҫӮзӮҜҒAҠзҗFӮаҲ«ӮўҒB
ӮұӮкӮӘ“ҜӮ¶ӢуҠФӮЙ•йӮзӮөӮДӮўӮИӮӘӮзҒA•кӮМ”ьҚзӮЙ‘ОӮ·ӮйӢs‘ТӮрҺ~ӮЯӮзӮкӮёҒA–TҠПӮ·ӮйӮҫӮҜӮҫӮБӮҪ–lӮМҗУ”CӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНҢҫӮӨӮЬӮЕӮаӮИӮўҒB
–lӮр“MҲӨӮөӮҪ•кҒB
–…ӮЦӮМӢs‘ТӮӘҺnӮЬӮБӮҪҚ ҒA–lӮӘҺ~ӮЯӮЙ“ьӮйӮЖӮ»ӮМҺһӮҫӮҜӮН–…ӮЦӮМ–\—НӮрҺ~ӮЯӮДӮӯӮкӮҪҒB
ӮҜӮкӮЗ•кӮНҒA–lӮЙ”ЭӮнӮкӮҪ–…ӮЙҺ№“iӮөӮДӮіӮзӮЙҚ“Ӯў–\—НӮрҗUӮйӮБӮҪҒB–lӮМҢ©ӮДӮўӮИӮўӮЖӮұӮлӮЕҒB
ӮЗӮӨӮөӮҪӮзӮўӮўӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮаӮҝӮлӮсҢцӮМӢ@ҠЦӮЙ—ҠӮБӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮБӮҪҒB
Ӯ»ӮкӮЕӮа•кӮМ–\—НӮНҺ~ӮЬӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB
–…ӮМ”Я–ВӮӘ•·ӮұӮҰӮй“xҒAҺЁӮрҚЗӮўӮҫҒB–ЪӮр•ВӮ¶ӮҪҒB
–lӮН•кӮЙӢtӮзӮнӮИӮ©ӮБӮҪҒB•кӮН–lӮЙӮН—DӮөӮ©ӮБӮҪӮөҒAүВҲЈ‘zӮИҗlӮҫӮБӮҪӮ©ӮзҒB
ӮўӮВӮөӮ©–lӮН–…ӮӘҸқӮВӮҜӮзӮкӮйӮМӮр–TҠПӮ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB
“–ӮҪӮи‘OӮМ“ъҸнӮЖӮөӮДҺуӮҜ“ьӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB
–…ӮИӮсӮДӮўӮИӮўӮаӮМӮҫӮЖӮіӮҰҺvӮБӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮйҒB
•кӮН–lӮЖ”ьҚзӮӘ’Ү—ЗӮӯӮөӮДӮўӮйӮМӮӘӢCӮЙ“ьӮзӮИӮўӮжӮӨӮҫӮБӮҪӮ©ӮзҒAӢЙ—НҒAҠЦӮнӮзӮИӮўӮжӮӨӮЙӮаӮөӮДӮўӮҪҒB
”ьҚзӮЙӮНҗhӮ©ӮБӮҪӮҫӮлӮӨҒB—BҲкҒAҺ©•ӘӮрҺзӮБӮДӮӯӮкӮҪҢZӮӘҒAҺ©•ӘӮрҢ©ҺМӮДӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒB
–lӮН–lӮЕӢкӮөӮ©ӮБӮҪӮҜӮкӮЗҒAӮ»ӮсӮИӮаӮМӮН”ьҚзӮМӢкӮөӮЭӮЙ”дӮЧӮкӮО”чҒXӮҪӮйӮаӮМӮҫҒB
ӮҜӮкӮЗҒAӮ»ӮсӮИ“ъҒXӮаҚЎ“ъӮЕҸIӮнӮйҒB
ҒuҗSҢмӮӯӮсҒAӮ»ӮлӮ»ӮлӮўӮўӮ©ӮўҒHҒv
ҺPӮрҚ·ӮөӮҪҒAғXҒ[ғcҺpӮМҗlӮМ—ЗӮіӮ»ӮӨӮИ’jӮӘ–lӮЙҗәӮрӮ©ӮҜӮҪҒB
Һҷ“¶‘Ҡ’kҸҠӮ©Ӯз”hҢӯӮіӮкӮДӮ«ӮҪҗlӮЕҒA–ј‘OӮНӢҙ–{ӮіӮсӮЖӮўӮӨӮзӮөӮўҒB
•кӮЖҢҲ•КӮөӮҪ–lӮзӮНҒAӮұӮкӮ©ӮзӮ»ӮкӮјӮкҗVӮөӮўҸкҸҠӮЕҒAҗVӮөӮўҗ¶ҠҲӮрҺnӮЯӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB
–lӮНӮұӮұӮр’ЗӮўҸoӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮ©ӮзҒAҚӮҚZӮЙ’КӮўӮИӮӘӮзҗVӮөӮўҸZӮЬӮўӮЕҲкҗl•йӮзӮөӮрӮ·ӮйҒB•”ү®ӮНӮаӮӨҢҲӮЬӮБӮДӮўӮйҒB
”ьҚзӮНӮЗӮұӮ©ү“ӮӯӮМ•aү@ӮЕҒAҗSӮМҺЎ—ГӮрӮ·ӮйҒB
ҲкҸTҠФ‘OӮМҺ–ҢҸӮМҢгҒA–ЪӮЬӮ®ӮйӮөӮӯ–lӮзӮрҺжӮиҠӘӮӯҠВӢ«ӮНҢғ•ПӮөӮҪҒB
ӮұӮкӮ©ӮзӮН•КҒXӮМӮЖӮұӮлӮЕҒAҲбӮӨҠВӢ«ӮЕҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB
ҒuӢҙ–{ӮіӮсҒAӮаӮӨҸӯӮөӮЕӮўӮўӮсӮЕӮ·ҒBӮ№ӮЯӮДҲкҢҫӮЕӮўӮўӮ©Ӯз”ьҚзӮМҒcҒcҒv
ҒuҗSҢмӮӯӮсҒAҚЎӮНҒc’ъӮЯӮИӮіӮўҒB”ьҚзӮҝӮбӮсӮНҗSӮр•ВӮҙӮөӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮйҒBҚЎӮНӮ»ӮМҲкҢҫӮҫӮБӮДӢк’ЙӮр”әӮӨӮсӮҫҒv
ҒuӮЕӮаҒv
ҒuҗSҢмӮӯӮсҒv
ҒuҒcҒcҒv
ӮнӮ©ӮБӮДӮўӮйӮсӮҫҒBӮЕӮаҒAҲкҢҫҒAҲкҢҫӮҫӮҜӮЕӮўӮўӮ©ӮзҒcҒcҒB
ҒuӮаӮӨӮ»ӮлӮ»Ӯл•aү@ӮЙҚsӮӯҺһҠФӮИӮсӮҫҒBӮ»ӮкӮЙүJӮаҚ“ӮўҒB“сҗlӮЖӮа•—ҺЧӮрӮРӮўӮДӮөӮЬӮӨӮжҒBҺPӮаҚ·ӮөӮДӮўӮИӮўӮсӮҫӮ©ӮзҒv
ҒuҒcҒcҒv
–lӮНҳлӮўӮҪҒBӢtӮзӮҰӮИӮўҢҫ—tӮҫӮБӮҪҒB
Ғu“с“xӮЖүпӮҰӮИӮўӮнӮҜӮ¶ӮбӮИӮўҒBӮҪӮҫҸӯӮөӮМҠФҒA•КҒXӮЙ•йӮзӮ·ӮҫӮҜӮҫӮжҒv
ҒuҸӯӮөӮБӮДҒcҒcҒBӮЗӮМӮӯӮзӮўӮИӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒcҒcҒHҒv
–lӮНҳлӮўӮҪӮЬӮЬӮЕ•·ӮўӮҪҒB
Ғu”ьҚзӮҝӮбӮсӮМ•aӢCӮӘҺЎӮйӮЬӮЕҒv
Ӣҙ–{ӮіӮсӮН–lӮМ–ЪӮрҗ^ӮБ’јӮ®ӮЙҢ©җҳӮҰӮДҢҫӮБӮҪҒB
ҒuҒcҒcҒv
–lӮНҺvӮБӮҪҒB
Ӯ»ӮсӮИӮаӮМҒAӮўӮВӮЙӮИӮйӮМӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўҒB
ӮЭӮсӮИӮӘ“ҜӮ¶ӮұӮЖӮрҢҫӮБӮҪҒB
ҲгҺТӮаҒAҢxҺ@ӮаҒAҗV•·ӮаҒB
–…ӮМҗSӮНүуӮкӮДӮўӮйӮЖҒB•кӮМ–\—НӮЕүуӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮҫӮЖҒB
ҺЎӮ·ӮЙӮН‘Ҫ‘еӮИҺһҠФӮӘӮ©Ӯ©ӮйӮсӮҫҒAӮЖҒB
ҒuӮіӮҹҒAӮаӮӨҚsӮ©ӮИӮўӮЖҒBҗSҢмӮӯӮсҒAӮЁ•КӮкӮрҒcҒcҒv
үчӮөӮіӮӘӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЙҺvӮӨҒB
ҚЎӮН–і—НӮИҺ©•ӘӮжӮиҒAӢҙ–{ӮіӮсӮвҒA–lӮМ’mӮзӮИӮў‘јҗlӮМ•ыӮӘ”ьҚзӮМ—НӮЙӮИӮкӮйӮұӮЖӮӘҒB
ӮЕӮаӮ»ӮкӮНҺd•ыӮМ–іӮўӮұӮЖӮҫҒB–lӮНӮЬӮҫҺqӢҹӮЕҒAҺРүп“IӮЙҺ©—§ӮөӮДӮаӮўӮИӮўҒB
үҪӮаҒcҒcҸo—ҲӮИӮўӮМӮҫҒB
Ғu”ьҚзҒv
ҒuҒcҒcҒv
ӮвӮНӮи“ҡӮҰӮДӮНӮӯӮкӮИӮўҒB
–lӮНҗ…ӮҪӮЬӮиӮМғAғXғtғ@ғӢғgӮЙ•GӮрӮВӮўӮДҒA”ьҚзӮрӮЬӮҪ•шӮ«ӮөӮЯӮҪҒBҸӯӮө’ЙӮ©ӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB
Ғu”ьҚзҒA•KӮёҒcҒcҢ}ӮҰӮЙҚsӮӯӮ©ӮзҒcҒc–lӮӘ‘еҗlӮЙӮИӮБӮДҒAҢNӮрҢмӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮзҒcҒcҒv
Ӯ»ӮкӮНҢҲҗSӮҫӮБӮҪҒB
•Ғ’КӮМҺqӢҹӮзӮөӮўҗ¶ҠҲҒAҚKӮ№ҒAҢ’ҚNӮИҗg‘МҒAӮ»ӮөӮДҢҫ—tӮЖҗSӮіӮҰӮа’DӮнӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪ”ЯӮөӮўҺqӢҹҒB–lӮЙӮНҢьӮҜӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪ•кӮМҠҙҸоӮрҲкҗlӮЕҲшӮ«ҺуӮҜӮДҒAүуӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҢZӮЕӮ Ӯй–lӮЙӮаҒAӮ»ӮкӮН•ӘӮҜ—^ӮҰӮзӮкӮйӮНӮёӮҫӮБӮҪӮМӮЙҒB
ҚЎӮМ–lӮНҒA”ЮҸ—ӮМӢ]җөӮМҸгӮЙӮ ӮйӮМӮҫҒB
Ҹ•ӮҜӮжӮӨӮЖҺvӮБӮҪҒBҸһӮЁӮӨӮЖҺvӮБӮҪҒBҲкҗ¶Ӯр“qӮҜӮДӮЕӮаҒA”ЮҸ—ӮМӮҪӮЯӮЙҒB
ҒuҢNӮМ•aӢCӮӘҺЎӮБӮҪӮзҒAӮЬӮҪҲкҸҸӮЙ•йӮзӮ»ӮӨҒv
ҢNӮН–lӮрҚҰӮсӮЕӮўӮйӮҫӮлӮӨҒBүҪӮаӮөӮИӮ©ӮБӮҪҢZӮрҒcҒcҒBүҪӮаҸo—ҲӮИӮ©ӮБӮҪ–lӮрҒcҒcҒB
Ғu•KӮёҒAҢ}ӮҰӮЙҚsӮӯӮ©ӮзҒcҒcҒv
ҚЎӮНүҪӮМ—НӮаӮИӮўҒAӮҪӮҫӮМҺqӢҹӮМ–lӮЙҒAҢNӮрҸ•ӮҜӮйҸpӮН–іӮўҒB
ӮҫӮҜӮЗ‘еҗlӮЙӮИӮБӮҪӮзҒAӮ«ӮБӮЖҚЎӮЬӮЕӮМ•sҚKӮр’ ҸБӮөӮЙҸo—ҲӮйӮӯӮзӮўӮМҚKӮ№ӮрҒA•KӮёҢNӮЙӮ Ӯ°ӮйӮ©ӮзҒcҒcҒBӮҫӮ©ӮзҒcҒcҒB
ҒuӮҫӮ©ӮзҚЎӮНҒcҒcҒBӮіӮжӮИӮзҒA”ьҚзҒcҒcҒv
ҒuҒcҒcҒv
”ьҚзӮНүҪӮаҢҫӮБӮДӮӯӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuҒcҒcҒv
–lӮНӮ»ӮкҲИҸгҒAүҪӮаҢҫӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ӢғӮўӮДӮўӮҪҒBҺvӮҰӮОүJӮӘҚ~ӮиҺnӮЯӮДӮ©ӮзӮНӮёӮБӮЖӢғӮўӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЙҺvӮӨҒB
ҒuӮ»ӮкӮ¶ӮбҒAҗSҢмӮӯӮсӮа•—ҺЧӮрӮРӮ©ӮИӮўӮжӮӨӮЙҒv
”ьҚзӮрҺФӮЙҸжӮ№ӮДҒAҺФӮЕ‘ТӮБӮДӮўӮҪҸ—җ«ӮЙ”ьҚзӮМ’…‘ЦӮҰӮр—ҠӮсӮҫҢгҒAӢҙ–{ӮіӮсӮН–lӮЙҢҫӮБӮҪҒB
Ғu‘еҸд•vӮҫӮжҒA•KӮёҺЎӮйҒBҺһҠФӮНӮ©Ӯ©ӮйӮҫӮлӮӨӮӘҒ\Ғ\ҒBҢNӮӘ‘еҗlӮЙӮИӮйҚ ӮЙӮНӮ«ӮБӮЖҺЎӮБӮДӮўӮйӮжҒBӮҫӮ©Ӯз”ьҚзӮҝӮбӮсӮМӮұӮЖӮНҗS”zӮөӮИӮўӮЕҒAҢNӮНҢNӮМҗS”zӮрӮөӮИӮіӮўҒBҢNӮҫӮБӮДҒAӮұӮкӮ©ӮзҗжӮН‘е•ПӮИӮсӮҫҒv
Ғu–lӮНҒcҒc‘еҸд•vӮЕӮ·ҒB”ьҚзӮӘҢмӮБӮДӮӯӮкӮҪӮ©ӮзҒB•KӮё—§”hӮИ‘еҗlӮЙӮИӮБӮДҒA”ьҚзӮрҢ}ӮҰӮЙҚsӮ«ӮЬӮ·Ӯ©ӮзҒAӮ»ӮкӮЬӮЕҒcҒcҒAӮ»ӮкӮЬӮЕ”ьҚзӮрӮЁҠиӮўӮөӮЬӮ·Ғv
ҒuӮнӮ©ӮБӮҪҒBҠж’ЈӮйӮсӮҫӮжҒv
Ғ@Ӣҙ–{ӮіӮсӮНӮёӮФ”GӮкӮМ–lӮМ“ӘӮр•ҸӮЕӮҪҒB–lӮЙӮН–іӮўҒA‘еҗlӮМҺиӮӘӮ»ӮұӮЙӮ ӮБӮҪҒB
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒAӮаӮӨҚsӮӯӮжҒv
ҒuӮНӮўҒv
Ғ@Ӣҙ–{ӮіӮсӮНҺФӮЙҸжӮйӮЖҒA‘ӢӮрҠJӮҜӮД–lӮЙҢҫӮБӮҪҒB
ҒuғRҒ[ғgӮНӮўӮўӮМҒHҒv
ҒuӮўӮўӮсӮЕӮ·ҒB”ьҚзӮЙӮаӮБӮДӮўӮБӮДӮаӮзӮўӮҪӮўӮМӮЕҒcҒcҒv
–lӮНҢҷӮнӮкӮДӮўӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮҜӮЗҒAҚҰӮсӮЕӮӯӮкӮДӮаӮўӮўӮҜӮЗҒA–YӮкӮйӮұӮЖӮҫӮҜӮНӮөӮИӮўӮЕ—~ӮөӮўӮ©ӮзҒcҒcҒB
ҒuӮ»ӮӨҒAӮ»ӮкӮ¶ӮбӮЁ•КӮкӮҫҒAҗSҢмӮӯӮсҒv
ҒuҒcҒcӮНӮўҒv
–lӮН‘ӢӮМҠOӮ©Ӯз”ьҚзӮрҢ©ӮҪҒBҚЎ“ъӮрӢ«ӮЙӮөӮОӮзӮӯҲ§ӮҰӮИӮӯӮИӮйҚЕҢгӮМүЖ‘°ӮрҒA–ЪӮЙҸДӮ«•tӮҜӮйӮжӮӨӮЙҒB
ҺФӮӘӮдӮБӮӯӮиӮЖ‘–ӮиҸoӮөӮҪҒB
Ғu”ьҚзҒIҒv
ү“ӮҙӮ©ӮБӮДӮўӮӯҺФӮЙҒA–lӮНӢ©ӮсӮҫҒB
үJӮӘҗәӮрӮ©Ӯ«ҸБӮөӮҪҒB
ӮўӮВӮМҠФӮЙӮұӮсӮИӮЙӢӯӮӯӮИӮБӮҪӮМӮ©ҒAӮПӮзӮПӮзӮЖҸ¬Қ~ӮиӮҫӮБӮҪүJӮӘҚЎӮЕӮНӮЗӮөӮбҚ~ӮиӮҫҒB
—вӮҪӮўҒA—вӮҪӮўӮҜӮкӮЗҒAӮұӮМүJӮЕӮіӮҰҒA–lӮЙӮН’gӮ©ӮӯҠҙӮ¶ӮзӮкӮҪҒB
•XӮМӮжӮӨӮЙ—вӮҪӮ©ӮБӮҪ”ьҚзӮМҗg‘МӮЙ”дӮЧӮҪӮзҒAӮұӮсӮИӮаӮМӮН”M“’ӮЙӮіӮҰҠҙӮ¶ӮзӮкӮйҒB
җВӮ ӮҙӮМҠзҒAҹzӮзӮкӮҪ”ҜҒAӢ•ӮлӮИ“өҒB
–lӮНӮ»ӮкӮзӮр–ьӮ·‘SӮДӮр‘јҗlӮЙ”CӮ№ӮҪӮМӮҫҒB
ҸоӮҜӮИӮўҒB
Ӯ»ӮсӮИ–lӮӘҒA•КӮкӮрҚҗӮ°ӮҪҢгӮЙҒA”ЮҸ—ӮЙүҪӮрҢҫӮЁӮӨӮЖӮўӮӨӮМӮҫӮлӮӨҒB
Ғ@–lӮНӮөӮОӮзӮӯӮ»ӮкӮрҚlӮҰӮДӮўӮҪҒB”ьҚзӮрҸжӮ№ӮҪҺФӮӘҢ©ӮҰӮИӮӯӮИӮБӮДӮаҒAӮёӮБӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪҒB“ҡӮҰӮНҸoӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ғu•KӮёӮЬӮҪҒcҒcҲкҸҸӮЙ•йӮзӮ»ӮӨҒc”ьҚзҒv
Ғ@ҷкӮўӮДҒA”ьҚзӮӘӢҺӮБӮДӮўӮБӮҪ“№ӮЙ”wӮрҢьӮҜӮҪҒB
Ӯ»ӮӨӮөӮД–lӮзӮМ“№ӮН•КӮкӮҪҒB
ҚӮҚZ“с”NҒA“~ӮаҸIӮнӮиӮМӮұӮЖӮҫӮБӮҪҒB
Ғ@Ғ@ӮP
•Ҫ“ъӮМҗ^’ӢҠФҒAҚg’ғӮМӮЁӮўӮөӮўӮұӮЖӮЕ—L–јӮИӢi’ғ“XӮЕҒAӮ»ӮнӮ»ӮнӮЖ—ҺӮҝ’…Ӯ©ӮИӮў—lҺqӮЕғRҒ[ғүӮИӮсӮ©ӮрҲщӮсӮЕӮўӮйҒAӮИӮсӮЖӮаҸкӮрӮнӮ«ӮЬӮҰӮИӮў’jӮӘӮўӮҪҒB
Ӯ»ӮкӮӘ–lҒAҚLҚ]җSҢмӮҫҒB
Ӯ ӮкӮ©ӮзҳZ”NҒB–lӮН“сҸ\ҺOҚОӮЙӮИӮиҒAҺРүпҗlӮЖӮөӮД“ӯӮўӮДӮўӮҪҒB
ҺdҺ–ӮН—LӢxӮрӮЖӮБӮҪҒBӮИӮәӮИӮзҚЎ“ъӮН–…ӮМ”ьҚзӮӘҺ{җЭӮрҸoӮД–lӮЙүпӮўӮЙӮӯӮйӮ©ӮзӮҫҒB
”ьҚзӮЙүпӮӨӮМӮНҺАӮЙҳZ”NӮФӮиӮМӮұӮЖӮҫҒBҳZ”N‘OӮМӮ ӮМ“ъҒA”ьҚзӮЖ•КӮкӮДӮ©Ӯз–lӮНҲк“xӮа”ьҚзӮЙүпӮнӮ№ӮДӮНӮаӮзӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒBҺ–ҢҸӮМ“–Һ–ҺТӮЖӮМҗЪҗGӮН”рӮҜӮйӮЧӮ«ӮЖҚlӮҰӮҪҺw“ұҲхӮЖҲгҺtӮМ”»’fӮҫӮ»ӮӨӮҫҒBӮаӮҝӮлӮсҺ•бyӮӯҺvӮБӮҪӮӘҒAҢӢүК“IӮЙӮНӮ»ӮкӮЕӮжӮ©ӮБӮҪӮМӮҫӮЖҺvӮБӮДӮўӮйҒB”ьҚзӮЙҲ§ӮҰӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ–lӮМҲУҺvӮрӮжӮиӢӯҢЕӮИӮаӮМӮЙӮөӮДӮӯӮкӮҪӮжӮӨӮИӢCӮӘӮ·ӮйӮ©ӮзӮҫҒB
ӮұӮМҳZ”NҠФӮНҒAҢҲӮөӮД•Ҫ’RӮИӮаӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮкӮЕӮаӮұӮӨӮөӮДҢoҚП“IӮЙҺ©—§ӮөӮДҒA”ьҚзӮрҲшӮ«ҺжӮйӮұӮЖӮр”FӮЯӮДӮаӮзӮҰӮйӮЖӮұӮлӮЬӮЕӮұӮзӮкӮҪӮМӮН•ОӮЙҒA”ьҚзӮрҚЎ“xӮұӮ»ҚKӮ№ӮЙӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ–Ъ“IӮӘӮ ӮБӮҪӮ©ӮзӮҫҒB
ҒuӮұӮұҒAӮўӮўӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
ҺбӮўӮМӮЙғXҒ[ғcӮЙ’…ӮзӮкӮйӮұӮЖӮИӮӯҢ©Һ–ӮЙ’…ӮкӮДӮўӮйҒAҺdҺ–ӮМҸo—ҲӮ»ӮӨӮИ”ьҸ—ӮӘ–lӮЙҗәӮрӮ©ӮҜӮҪҒBҢьӮ©ӮўӮМҗИӮЙҚАӮиӮҪӮўӮжӮӨӮҫҒB
ҒuӮ ҒAӮ Ӯ ҒAӮ·ӮЭӮЬӮ№ӮсҒBҳAӮкӮӘ—ҲӮйӮсӮЕҒ\Ғ\ӮБӮДҒA—Rҗ^Ӯ©ҒcҒcҒv
ҳZ”NӮФӮиӮЙ”ьҚзӮЙҲ§ӮҰӮйӮ©ӮзӮ©ҒAҚЎӮМ–lӮЙӮН—ҺӮҝ’…Ӯ«ӮЖӮўӮӨӮаӮМӮӘӮИӮўҒBӮВӮўӮЕӮЙҗіҸнӮИ”»’f—НӮаҺёӮӯӮөӮДӮўӮйӮзӮөӮўҒB‘ТӮҝҚҮӮнӮ№ӮрӮөӮДӮўӮҪӢҢӮў—FҗlӮМҺpӮаҒAҢyӮўҲ«ӮУӮҙӮҜӮаҢ©”ІӮҜӮИӮўӮЩӮЗӮЙҒB
ҒuӮІӮЯӮсӮЛҒA‘ТӮҪӮөӮҪҒHҒv
’ҶҠwҺһ‘гӮ©ӮзӮМ•tӮ«ҚҮӮўӮЕӮ Ӯй—FҗlҒAӢЯҚ]—Rҗ^ӮНӮ»ӮӨҢҫӮӨӮЖ–lӮМҢьӮ©ӮўӮЙҚАӮБӮҪҒB
ҒuӮўӮвҒAӮЗӮӨӮҫӮлҒAҸ\•ӘӮӯӮзӮўӮН‘ТӮБӮҪӮМӮ©ӮИҒHҒv
ӮұӮұӮЙ—ҲӮДӮ©ӮзӮЗӮМӮӯӮзӮўҺһҠФӮӘҢoӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮнӮ©ӮзӮИӮўҒB“һ’…ӮөӮҪӮМӮНҸ\Һһ”јҚ ӮҫӮБӮҪӮЖҺvӮӨҒB‘ТӮҝҚҮӮнӮ№ӮМҺһҠФӮНҗіҢЯӮҫҒBҺһҢvӮЙ–ЪӮрӮвӮйӮЖҢ»ҚЭҺһҚҸӮНҗіҢЯҢЬ•Ә‘OӮҫӮБӮҪҒB
ҒuүҪӮ»ӮкҒHҒ@‘еҸд•vҒHҒ@“ӘҒAүсӮБӮДӮйҒHҒv
ҒuӮ ҒAӮўӮвҒA‘Ҫ•ӘҒcҒcүсӮБӮДӮИӮўҒv
ҒuӮ»ӮсӮИӮЙӢЩ’ЈӮөӮДӮсӮМҒHҒ@Қр“ъӮҝӮбӮсӮЖҗQӮкӮҪҒHҒv
ҒuӮ ӮсӮЬӮиҗQӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒv
ҒuӮЕӮөӮеӮӨӮЛҒAҗSҢмҒAғKғ`ғKғ`ӮжҒHҒ@ҚЎҒv
Ӯ»ӮӨӮИӮМӮҫҒB–lӮНҚЎғKғ`ғKғ`ӮЙӢЩ’ЈӮөӮДӮўӮйҒB“–‘RӮҫҒB’ӢӮМ“сҺһҒAӮВӮЬӮиӮ ӮЖ“сҺһҠФҢгӮЙӮН”ьҚзӮЖҳZ”NӮФӮиӮМҚДүпӮҫҒBҢZ–…ӮЖӮНӮўӮҰӢЩ’ЈӮөӮИӮўӮнӮҜӮН–іӮўҒBӮ»ӮкӮЙҚЎ“ъӮН”ьҚзӮӘ–lӮЖ•йӮзӮ·ӮұӮЖӮЙ“ҜҲУӮөӮДӮӯӮкӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮӘӮ©Ӯ©ӮБӮДӮўӮй‘еҺ–ӮИ“ъӮИӮМӮҫҒBӢҙ–{ӮіӮсӮрҠЬӮЮҺҷ“¶•ҹҺғҠЦҢWӮМҗlӮҪӮҝӮНҒAҚЎӮМ–lӮЙӮИӮз”ьҚзӮрҲшӮ«ҺжӮйҺ‘ҠiӮӘӮ ӮйӮЖ”FӮЯӮДӮӯӮкӮҪӮӘҒA”ьҚзӮН–lӮӘҚЎӮЗӮсӮИ•—ӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮ©ҒAҗіҠmӮИӮЖӮұӮлӮр’mӮзӮИӮўҒBӮҫӮ©ӮзҚЎ“ъӮН”ьҚзӮӘ–lӮр”FӮЯӮДӮӯӮкӮйӮ©ҒA–lӮӘ•ЫҢмҺТӮЙӮИӮйӮұӮЖӮрӢ–ӮөӮДӮӯӮкӮйӮ©ӮӘӮ©Ӯ©ӮБӮҪ‘еҺ–ӮИ“ъӮИӮМӮҫҒB–lӮМҳZ”NҠФӮМ”ј•ӘӮНӮұӮМ“ъӮМӮҪӮЯӮЙӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮБӮДӮаүЯҢҫӮЕӮНӮИӮўҒB
ҒuӮ»ҒAӮ»ӮӨӮИӮсӮҫҒB–lҒAҚЎҒAӮ©ӮИӮи•s–ЎӮўӮсӮҫҒBӮИӮсӮ©—ҺӮҝ’…Ӯ©ӮИӮӯӮДҒcҒcҒv
ҒuӮЬӮ ҒAҳZ”NӮФӮиӮҫӮаӮсӮЛҒB“–ӮҪӮи‘OӮ©Ғv
ҒuӮӨӮсҒv
Ғu”ьҚзӮҝӮбӮсҒAӮаӮӨӮ·Ӯ®ҚӮҚZҗ¶Ӯ©Ғv
”ьҚзӮНҺlҢҺӮ©ӮзҚӮҚZҗ¶ӮЙӮИӮйҒBҗ”“ъ‘OҒA’ҶҠwӮЕӮН‘ІӢЖҺ®ӮӘӮ ӮиҒAҚЎҒA”ьҚзӮНҸtӢxӮЭӮҫҒB
ҺlҢҺҒA’ҶҠwӮМҗіҠmӮИ‘ІӢЖӮНҺOҢҺӮМ––“ъӮҫҒBҺlҢҺҲк“ъӮрӮаӮБӮДҒA”ьҚзӮНҚӮҚZҗ¶ӮЙӮИӮйҒBӮ»ӮөӮДҒA’ҶҠwӮМ‘ІӢЖӮЖ“ҜҺһӮЙ–…ӮМҸZҸҠӮН–lӮЖ“ҜӮ¶ӮЙӮИӮйҒ\Ғ\—\’иӮҫҒB”ьҚзӮӘҚЎ“ъ–lӮр”FӮЯӮДӮӯӮкӮкӮОӮМҳbҒAӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒB
Ғu”ьҚзӮҝӮбӮсҒAҚӮҚZҗ¶ӮЙӮИӮйӮБӮДӮұӮЖӮНҒAӮаӮӨ‘еҸд•vӮИӮсӮЕӮөӮеҒHҒv
—Rҗ^ӮӘҢҫӮБӮДӮўӮйӮМӮН”ьҚзӮМҗSӮМӮұӮЖӮҫҒB—Rҗ^ӮН–l’BҢZ–…ӮМҗlӮЙҢҫӮўӮГӮзӮўүЯӢҺӮр’mӮБӮДӮўӮйҒB–lӮзӮМҺ–ҢҸӮНӮ ӮМ“–ҺһҒAӮ©ӮИӮиҗўҠФӮр‘ӣӮӘӮ№ӮҪҒBғҒғfғBғAӮЙ–ј‘OӮұӮ»ҸoӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮаӮМӮМҒAӢЯҸҠӮЙҸZӮсӮЕӮўӮҪҗlҒXӮНӮЭӮсӮИ’mӮБӮДӮўӮҪӮөҒAҚӮҚZӮЕӮНҳb‘иӮЙӮИӮиӮ·Ӯ¬ӮДӮ»ӮкӮИӮиӮЙҗhӮў–ЪӮЙӮаӮ ӮБӮҪӮаӮМӮҫҒBҺ–ҢҸӮ©ӮзӮөӮОӮзӮӯӮМҠФҒAғ}ғXғRғ~ӮН–Ҳ“ъӮМӮжӮӨӮЙ–lӮМҸҠӮЙ—ҲӮҪҒB–lӮНүҪӮа’қӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮҜӮкӮЗҒAҺ–ҢҸӮМӮұӮЖӮр•·Ӯ©ӮкӮйӮҪӮСӮЙ–lӮМҗSӮН”ж•ҫӮөӮДӮўӮБӮҪҒBӮ»ӮсӮИҺһҒA–lӮрҺxӮҰӮДӮӯӮкӮҪӮМӮН”ЮҸ—ӮрҠЬӮЮҗ”җlӮМ—Fҗl’BӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ Ӯ ҒAҺw“ұҲхӮіӮсӮМҳbӮҫӮЖҒAӮ·ӮБӮ©Ӯи–ҫӮйӮӯӮИӮБӮҪӮзӮөӮўҒv
ҒuӮЦӮҘҒAӮ ӮМ”ьҚзӮҝӮбӮсӮӘӮЛӮҘҒv
ӮЙӮнӮ©ӮЙӮНҗMӮ¶“пӮўӮұӮЖӮҫӮБӮҪҒB–lӮМ’mӮБӮДӮўӮй”ьҚзӮНӮўӮВӮаӮСӮӯӮСӮӯӮөӮДӮўӮДҒAҲшӮБҚһӮЭҺvҲДӮЕҒAҸОӮБӮҪӮұӮЖӮИӮсӮДӮЩӮсӮМҗ”үсӮөӮ©Ң©ӮҪҺ–ӮӘ–іӮўҒBӮ»ӮсӮИҺqӢҹӮҫӮБӮҪҒBҗ«ҠiӮӘ–ҫӮйӮӯӮИӮБӮҪӮИӮсӮД‘z‘ңӮаӮВӮ©ӮИӮўҒBүҪӮжӮи•КӮкҚЫӮМӮ ӮМҗ¶ӢCӮМ–іӮўҠзӮОӮ©ӮиӮӘӢӯӮӯҲуҸЫӮЙҺcӮБӮДӮўӮй–lӮЙӮЖӮБӮДҒAӮ»ӮсӮИ”ьҚзӮМҺpӮр‘z‘ңӮ·ӮйӮұӮЖҺ©‘МӮӘ–і—қӮИҳbӮҫҒB
ӮҜӮкӮЗҒAӮ»ӮМҺpӮНӮ«ӮБӮЖҒA–lӮӘҗШ–]ӮөӮДӮвӮЬӮИӮўӮаӮМӮИӮсӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӮЖӮұӮлӮЕҗSҢмҒAҺ„ӮаүҪӮ©—ҠӮсӮЕӮўӮўҒHҒv
—Rҗ^ӮӘғҒғjғ…Ғ[ӮрҢ©ӮИӮӘӮзҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ Ӯ ҒAӮўӮўӮжҒv
ҒuӮ ӮсӮҪӮМҡшӮиӮжҒHҒ@Һ„ӮҫӮБӮД–ZӮөӮўӮМӮЙҒA–…ӮЙүпӮӨ‘OӮМҚЕҸIғ`ғFғbғNӮМӮҪӮЯӮҫӮҜӮЙҢДӮСҸoӮөӮҪӮсӮҫӮ©ӮзҒAӮ»ӮМӮӯӮзӮўӮН“–‘RӮжӮЛҒHҒv
ҒuӮӨӮсҒAӮўӮўӮҜӮЗҒBӮБӮДҸAҗEӮөӮДӮ©ӮзӮНӮўӮВӮа–lӮМҡшӮиӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒBӮ»ӮӨӮўӮӨӮМӮНҲк“xӮЕӮаҺ©•ӘӮЕ•ҘӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮ Ӯй“zӮӘҢҫӮӨӮсӮҫҒv
ҒuӮўӮўӮ¶ӮбӮИӮўҒBҲк—¬ҠйӢЖӮЙӢОӮЯҒAҠ”ӮЕӮН‘е–ЧӮҜҒAӮіӮзӮЙӮНғ}ғ“ғVғҮғ“ӮЬӮЕӮЁҺқӮҝӮМҗSҢмғTғ}ӮЙӮН‘еӮөӮҪҸo”пӮ¶ӮбӮИӮўӮЕӮөӮеҒHҒv
ҒuҒcҒcҺ©•ӘӮҫӮБӮД‘Ҡ“–үТӮўӮЕӮйӮӯӮ№ӮЙҒcҒcҒv
–lӮНҚҰӮЭӮӘӮЬӮөӮӯҢҫӮБӮҪҒB
”ьҚзӮЖ•КӮкӮДӮ©ӮзӮМ–lӮНҒAӮЖӮЙӮ©ӮӯӮЁӢаӮрүТӮ®ӮұӮЖӮЙҺ·’…ӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮЬӮЕҚӮҚZҗ¶ӮЖӮөӮДӮ»ӮкӮИӮиӮЙҠж’ЈӮБӮДӮўӮҪ•”ҠҲ“®ӮвҒA—Fҗl’BӮЖ—VӮФҺһҠФӮаҗЙӮөӮсӮЕғAғӢғoғCғgӮЙ—гӮсӮҫҒBҺ©•ӘӮМҗ¶ҠҲӮвҗiҠwӮМӮҪӮЯӮЙӮЁӢаӮӘ•K—vӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮаӮ ӮБӮҪӮӘҒAҲк”ФӮМ—қ—RӮН”ьҚзӮМӮҪӮЯҒA”ьҚзӮМ•aӢCӮӘҺЎӮБӮДҺ{җЭӮрҸoӮҪӮЖӮ«ҒAӮЬӮҪҲкҸҸӮЙ•йӮзӮ·ӮҪӮЯӮЙҒA–lӮНӮ Ӯй’ц“xӮМҚаӮрҺқӮБӮДӮўӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒBӮ»ӮМӮҪӮЯӮЙҒAҚӮҚZҗ¶ӮМӮӨӮҝӮ©Ӯз’ҷ’~ӮЙ—гӮсӮЕӮўӮҪӮМӮҫҒB
ӮаӮҝӮлӮсӮ»ӮкӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBӮўӮӯӮзӮЁӢаӮр’ҷӮЯӮҪӮБӮДҒAғAғӢғoғCғgӮЕүТӮ°ӮйӮЁӢаӮИӮсӮДӮҪӮ©ӮӘ’mӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮкӮЙӢҙ–{ӮіӮсӮЖ–с‘©ӮөӮҪӮМӮҫҒB
•KӮё—§”hӮИ‘еҗlӮЙӮИӮБӮДҒA”ьҚзӮрҢ}ӮҰӮЙҚsӮӯҒAӮЖҒB
•КӮЙӮ»ӮМҢАӮиӮ¶ӮбӮИӮўӮӘҒA“–ҺһӮМ–lӮӘҚlӮҰӮй—§”hӮИ‘еҗlӮЖӮўӮӨӮМӮНҒAӮвӮНӮиҲк—¬ӮМ‘еҠwӮрҸoӮДҒAҲк—¬ҠйӢЖӮЙӢОӮЯӮДҒAҺРүп“IӮИҗM—pӮрҺқӮБӮДӮўӮДҒA•iҚs•ыҗіӮИҗlӮМӮұӮЖӮҫӮБӮҪҒB
ӮҫӮ©Ӯз–lӮН•ЧӢӯӮаҠж’ЈӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮ©ӮўӮ ӮБӮДҒAҚ‘—§‘еҠwӮМҸ§Ҡwҗ¶ӮЖӮөӮДҒAӮіӮөӮҪӮйӢа‘K“I•ү’SӮа–іӮӯ‘еҠwӮЙҗiҠwӮөҒAҸAҗEҠҲ“®ӮЙӮаҗ¬ҢчӮөҒA–іҺ–‘ІӢЖӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮҪҒB
–lӮНҢoҚПҠw•”ӮЙҗРӮр’uӮўӮДӮўӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮБӮДҒAҠ”ӮЙӮаҠЦҗSӮрҺқӮБӮДӮўӮҪҒBҠ”ӮЕ‘еӢаҺқӮҝӮЙӮИӮлӮӨӮИӮсӮДҚlӮҰӮНҺқӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒA–{—Ҳ‘еҠwӮМҠw”пӮЙ“–ӮДӮйӮВӮаӮиӮҫӮБӮҪӮЁӢаӮӘҸ§ҠwӢаҗ§“xӮр—ҳ—pӮөӮҪӮұӮЖӮЕ•ӮӮўӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕҒiӮаӮҝӮлӮсҢгӮЕ•ФӮ·ӮМӮҫӮӘҒjҒAӮ»ӮМ’ҶӮЕҺёӮӯӮөӮДӮа’ЙӮӯӮИӮў’ц“xӮМӢаҠzӮЕҒAӢCӮЬӮ®ӮкӮЙҠ”Ӯр”ғӮБӮДӮЭӮҪӮМӮҫҒBӮаӮҝӮлӮсӮ»ӮкӮИӮиӮЙ•ЧӢӯӮаӮөӮҪӮөҒAӮ»ӮкӮИӮиӮЙ—L–]ӮИҠ”ӮЙ–ЪӮрӮВӮҜӮД”ғӮБӮҪӮМӮҫӮҜӮкӮЗҒAӮЬӮіӮ©–{“–ӮЙҒcҒcҒB–lӮМ”ғӮБӮҪ–^ӮhӮsҠйӢЖӮМҠ”үҝӮН”ҡ”ӯ“IӮЙӢ}ҸгҸёӮөҒAҚЕҚӮ’lӮМҺһӮЙ–lӮНӮ»ӮкӮр”„ӢpӮөҒA“сҸ\ҲкҚОӮЙӮөӮДҲкҚаҺYҚмӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮЁӢаӮЕӮЬӮҪҠ”Ӯр”ғӮўҒAҸҮ’ІӮЙҚsӮБӮҪҢӢүКҒA–lӮНӮұӮМ“xҒA“сҸ\ҺOҚОӮЙӮөӮД“s“аӮМ—З•ЁҢҸғ}ғ“ғVғҮғ“ӮМҲкҺәӮр”ғӮӨӮЖӮўӮӨ–\Ӣ“ӮЙӮЕӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒB
Ҡ”ӮИӮсӮ©ӮЙ—ҠӮзӮИӮўҢҳҺАӮИҢvүжӮЕӮНғ}ғ“ғVғҮғ“Ӯр”ғӮБӮҪӮиӮ·ӮйӮМӮНӮЬӮҫҸӯӮөҗжӮЙӮИӮйӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪӮӘҒAү^ӮаӮ ӮБӮҪӮсӮҫӮЖҺvӮӨҒBӮаӮөӮӯӮНҗ_ӮМҢbӮЭӮӘ—^ӮҰӮзӮкӮҪӮМӮҫҒB”ьҚзӮЖ–lӮӘҗVӮөӮўҗ¶ҠҲӮр•аӮЮӮМӮЙҚЕҚӮӮМғ^ғCғ~ғ“ғOҒBҗ_ӮЖҠ”Һ®ҺsҸкӮЙҠҙҺУӮөӮДӮЁӮӯӮЧӮ«ӮҫӮЖҺvӮӨҒB
ҒuҺ„ӮНӮ ӮсӮҪӮЩӮЗүТӮўӮЕ–іӮўӮнӮжҒv
ҒuүRӮОӮБӮ©ҒAҺРүпҗlҲк”N–ЪӮЕҠOҺФҸжӮиүсӮөӮДӮйӮМӮИӮсӮ©—Rҗ^ӮӯӮзӮўӮҫӮжҒv
Ғu’ҶҢГӮжҒAӮ ӮкҒBӮЬӮ ӮЕӮаҲк”К“IӮИ“ъ–{ҺФӮМҗVҺФ”ғӮӨӮжӮиӮНҚӮӮ©ӮБӮҪӮҜӮЗҒv
ҒuӮЩӮзҒAӮвӮБӮПӮиҒv
ҒuӮЬӮҹӮЛҒAҸmӢЖҠEӮНҗlӢCӮЖҺиҳrҺҹ‘жӮЕӢӢ—ҝҸгӮӘӮБӮҪӮиӮ·ӮйӮ©ӮзҒBӮЩӮзҒAҺ„ӮБӮДҗ¶“kӮЙҗlӢCӮ ӮйӮөҒҷҒv
ҒuҒcҒcӮ»ӮӨҒAӮжӮ©ӮБӮҪӮЛҒv
ҒuҗMӮ¶ӮДӮИӮўӮЕӮөӮеҒHҒv
ҒuӮЬӮҹӮЛҒv
ҒuҺбӮӯӮД”ьҗlӮЕ‘Ҹ–ҫӮИҸ—ӢіҺtҒAӢЯҚ]—Rҗ^ҒIҒ@ғRғҢӮЕҗlӢCӮЕӮИӮўӮЩӮӨӮӘӮЁӮ©ӮөӮӯӮИӮўҒHҒv
ҒuҒcҒcҒv
—Rҗ^ӮНҠmӮ©ӮЙгY—нӮҫҒBҠXӮрҢ©үсӮөӮДӮаӮұӮМғҢғxғӢӮНӮҝӮеӮБӮЖӮўӮИӮўҒBҠwҗ¶Һһ‘гӮНӮ·ӮІӮӯғӮғeӮДӮўӮҪҒB—Rҗ^ӮНҺ©•ӘӮӘ”ьҗlӮҫӮЖ’mӮБӮДӮўӮйӮ©ӮзҒAҠёӮҰӮДү“—¶Ӯ№ӮёӮЙӮ»ӮӨӮўӮӨӮұӮЖӮрҢҫӮӨҒB—Rҗ^һHӮӯҒAҒu’NӮӘҢ©ӮҪӮБӮДӮ»ӮӨҺvӮӨӮсӮҫӮ©ӮзҒAҢӘ‘»ӮөӮҪӮзӢtӮЙӮўӮвӮзӮөӮўҒvӮзӮөӮўҒB
ҒuӮұӮзҒAӮИӮсӮЕ–ЩӮйҒHҒ@Ӯ»ӮкӮЖӮаӮ»ӮМ’ҫ–ЩӮНҗMӮ¶ӮҪӮЖҺуӮҜҺжӮБӮДӮўӮўӮМҒHҒv
ҒuӮЬӮҹҒAӮ»ӮкӮЕӮўӮўӮжҒv
ҒuӮсӮУӮУҒAӮжӮлӮөӮўҒv
—Rҗ^ӮНҸгӢ@ҢҷӮЕҚДӮСғҒғjғ…Ғ[ӮЙ–ЪӮр—ҺӮЖӮ·ӮЖҒAғEғFғCғgғҢғXӮрҢДӮсӮЕғ_Ғ[ғWғҠғ“ғeғBҒ[ӮЖғNғүғuғnғEғXғTғ“ғhӮр’Қ•¶ӮөӮҪҒB
’Қ•¶ӮөӮҪӮаӮМӮӘ—ҲӮйӮЬӮЕӮМҠФҒA–lӮзӮНӮЁҢЭӮўӮМӢЯӢөӮр•сҚҗӮөҚҮӮБӮҪҒB
–lӮМ•ыӮНҒAҺdҺ–ӮНӮ»ӮкӮИӮиӮЙҸҮ’ІӮЕӮ ӮйӮұӮЖҒAҗжҸTӮ©Ӯз”ғӮБӮҪғ}ғ“ғVғҮғ“ӮЙҸZӮЭҺnӮЯӮҪӮұӮЖҒAғ}ғ“ғVғҮғ“ӮМ‘ӢӮ©ӮзҢ©ӮҰӮй—[—zӮӘгY—нӮЕӮ ӮйӮұӮЖҒB
—Rҗ^ӮМӮЩӮӨӮНҒAҠwҸKҸmӮН–йӮӘғҒғCғ“ӮМӮҪӮЯҒA’ӢҠФӮН“БӮЙүҪӮа–іӮҜӮкӮОүЙӮҫӮБӮҪӮиӮ·ӮйӮұӮЖҒAҗ¶“kӮӘҗ¶ҲУӢCӮИӮұӮЖҒA“Ҝ—»ӮЙғCғPғҒғ“ӮӘӮўӮИӮўӮұӮЖӮИӮЗҒAӮЩӮЖӮсӮЗӮўӮВӮаӮМӢр’sӮҫӮБӮҪӮҜӮкӮЗҒAӮ»ӮМӮЁӮ©Ӯ°ӮЕ–lӮНҢЁӮМ—НӮӘ”ІӮҜӮҪҒBӮвӮБӮПӮи”ьҚзӮЙҲ§ӮӨ‘OӮЙ—Rҗ^ӮЙҲ§ӮБӮДӮЁӮўӮДӮжӮ©ӮБӮҪҒB
”ЮҸ—ӮЖӮўӮйӮЖҒA–lӮН—ҺӮҝ’…ӮӯӮМӮҫҒB
ҒuӮЁ‘ТӮҪӮ№ӮўӮҪӮөӮЬӮөӮҪҒv
ғEғFғCғgғҢғXӮӘ—ҝ—қӮЖҚg’ғӮрү^ӮсӮЕӮӯӮйӮЖ—Rҗ^ӮНҒA
ҒuғCғ^ғ_ғLғ}ғXҒIҒ@ҺАӮН’©ӮІ”СӮЬӮҫӮҫӮБӮҪӮМҒBӮЩӮзҒAҺ„ӮўӮВӮаӢNӮ«ӮйӮМӮЁ’ӢүЯӮ¬ӮҫӮ©ӮзҒv
ӮЖҒAӮўӮ©ӮЙӮаҺ©•ӘӮНӮ ӮИӮҪӮМӮҪӮЯӮЙ‘ҒӢNӮ«ӮөӮДҗHӮӨӮаӮМӮаҗHӮнӮёӮЙӮұӮұӮЙ—ҲӮЬӮөӮҪҒBӮЖҒAҢҫӮнӮсӮОӮ©ӮиӮМү¶’…Ӯ№ӮӘӮЬӮөӮў”ӯҢҫӮрӮөӮҪҒB
ҒuҒcҒcӮ»ӮиӮбҲ«Ӯ©ӮБӮҪӮЛҒv
ҒuӮсҒAӢCӮЙӮөӮИӮӯӮДӮўӮўӮжҒBӮЬӮҪҚЎ“xӮЁӮІӮБӮДӮӯӮкӮкӮОӮўӮўӮ©ӮзҒv
ҸОҠзӮЕҢҫӮӨӮЖҒA—Rҗ^ӮНғNғүғuғnғEғXғTғ“ғhӮрҢыӮЙү^ӮсӮҫҒBӮЖӮДӮаӮЁӮўӮөӮ»ӮӨӮҫӮБӮҪҒB
—Rҗ^ӮМҗHҺ–ӮӘҸIӮнӮйӮЖҒA–lӮН–{‘иӮЙ“ьӮБӮҪҒB
Ғu“Л‘RҲУ–ЎӮнӮ©ӮсӮИӮўӮЖҺvӮӨӮсӮҫӮҜӮЗҒA—Rҗ^ҒA–lӮН—Rҗ^Ӯ©ӮзҢ©ӮДӮЗӮӨҒHҒv
ҒuӮЗӮӨӮБӮДҒHҒv
ӮвӮНӮиҲУ–ЎӮӘӮнӮ©ӮзӮИӮўҒAӮЖӮўӮБӮҪҠҙӮ¶ӮЙ•·Ӯ«•ФӮөӮДӮ«ӮҪҒBӮЬӮҹҒAӮ»ӮкӮаӮ»ӮӨӮ©ҒB
Ғu”ьҚзӮМҗM—pӮр“ҫӮзӮкӮйӮӯӮзӮўҒA—§”hӮИ‘еҗlӮЙӮИӮкӮДӮўӮйӮ©ӮИӮБӮДӮұӮЖҒv
Ӯ»ӮӨҒAӮЪӮӯӮНӮ»ӮкӮр•·Ӯ«ӮҪӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒBҺ©•ӘӮЕӮНӮ»ӮкӮИӮиӮМҗlҠФӮЙӮИӮкӮҪӮВӮаӮиӮЕӮўӮйҒBӮҜӮкӮЗҺ©•ӘӮМҢ©үрӮҫӮҜӮЕӮН•sҲАӮИӮМӮҫҒB‘јҗlӮ©ӮзӮа“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙҢ©ӮҰӮйӮ©ҒAӮ»ӮкӮӘӢCӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮ»ӮсӮИӮМӮнӮҙӮнӮҙҢДӮСҸoӮіӮИӮӯӮҪӮБӮД“dҳbӮЕ•·ӮҜӮОӮўӮўӮМӮЙҒAӮЖӮНҺ©•ӘӮЕӮаҺvӮӨҒBӮҜӮкӮЗӮвӮБӮПӮи–КӮЖҢьӮ©ӮБӮДҢҫӮБӮДӮЩӮөӮўӮМӮҫҒB–lӮМҗМӮр’mӮБӮДӮўӮй—Rҗ^ӮЙҒB
ҒuӮ»ӮӨӮЛҒAҺ„Ӯ©ӮзҢ©ӮҪӮзӮЬӮҫӮЬӮҫҺҠӮзӮИӮўҸҠӮОӮБӮ©ӮиӮҫӮҜӮЗҒcҒcҒv
ҒuӮ»ӮӨҒcҒcҒv
ҒuӮЕӮаҒA”ьҚзӮҝӮбӮсӮМӮҪӮЯӮЙ“w—НӮөӮДҒAӮұӮұӮЬӮЕ—ҲӮҪҗSҢмҒAҺ„ӮН—§”hӮҫӮЖҺvӮӨҒv
Ғu—Rҗ^ҒcҒcҒv
ҒuӮҫӮ©ӮзҒAҺ©җMӮаӮБӮДҚsӮБӮД—ҲӮўҒIҒ@ҚLҚ]җSҢмҒIҒv
ҒuӮӨӮсҒv
ҒuӮБӮДӮўӮӨӮжӮӨӮИӮұӮЖӮрҢҫӮБӮДӮЩӮөӮўӮМҒHҒv
ҒuӮЁӮўҒIҒv
ӮЬӮБӮҪӮӯҒAғxғ^ӮИӮұӮЖӮрҒcҒcҒB
ҒuӮЕӮаҒA–{“–ӮЙ—§”hӮҫӮЖӮНҺvӮБӮДӮйӮжҒBӮҝӮеӮБӮЖӮ»ӮМҺ–ӮЙ“ЛӮБ‘–ӮиӮ·Ӯ¬ӮДҒA‘јӮМҺ–Ӯр’uӮ«–YӮкӮД—ҲӮҝӮбӮБӮДӮйӮжӮӨӮЙӮаҺvӮӨӮҜӮЗҒv
—Rҗ^ӮНҗ^–К–ЪӮИҠзӮЕҢҫӮБӮҪҒB
ҒuҗSҢмҒA”ьҚзӮҝӮбӮсӮМӮұӮЖӮОӮБӮ©ӮиӮЕҒAҺ©•ӘӮМӮұӮЖҒAҗFҒX’ъӮЯӮҪӮЕӮөӮеӮӨҒHҒv
–lӮЙӮН—Rҗ^ӮӘүҪӮрҢҫӮўӮҪӮўӮМӮ©ӮнӮ©ӮБӮДӮўӮҪҒB
Ғu—ӨҸгӮМӮұӮЖӮИӮзӮўӮўӮсӮҫӮжҒBӮЗӮӨӮ№‘ұӮҜӮДӮҪӮБӮДҒAҲк”ФӮЙӮНӮИӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮжҒv
ҒuүRҒB’mӮБӮДӮйӮжҒAҺ„ҒB‘IҺиҢ“ғ}ғlҒ[ғWғғҒ[ӮҫӮаӮсҒBҗSҢмӮМ1500ӮҚӮМҺ©ҢИғxғXғgҒAӮ ӮМ”NӮМ‘SҚ‘—DҸҹҺТӮМғ^ғCғҖӮЖҒwӮЩӮЖӮсӮЗҒx“ҜӮ¶ӮҫӮБӮҪӮЕӮөӮеҒv
—ӨҸгӮрӮвӮБӮДӮўӮйҗlҠФӮИӮзӮ»ӮМҒwӮЩӮЖӮсӮЗҒxӮӘҸҮҲКӮЙӮЗӮкӮҫӮҜ‘еӮ«ӮўҚ·ӮрӮаӮҪӮзӮ·Ӯ©ӮНӮнӮ©ӮБӮДӮўӮйӮНӮёӮҫҒB—Rҗ^ӮНӮ»ӮкӮрӮнӮ©ӮБӮҪҸгӮЕҢҫӮБӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҒwӮЩӮЖӮсӮЗҒxӮрҺgӮӨӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮН“–‘R–lӮМғ^ғCғҖӮН—DҸҹҺТӮжӮиӮнӮёӮ©ӮЙ—тӮБӮДӮўӮйӮМӮҫҒB
Ғu—ыҸKӮМғxғXғgӮЖ‘еүпӮНҲбӮӨӮжҒBӮЮӮөӮл‘еүпӮЕҺ©ҢИғxғXғgӮМғ^ғCғҖӮӘҸoӮ№Ӯй‘IҺиӮИӮсӮДӢHӮИӮсӮҫҒBӮҫӮ©ӮзҲк”ФӮН–і—қӮҫӮжҒv
‘еүпӮЕҺ©ҢИғxғXғgӮрҚXҗVӮ·ӮйӮұӮЖӮН“пӮөӮўҒBӮұӮкӮНҲк”КӮЙҢҫӮнӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮЕҒA–lӮаҲЩҳ_ӮН–іӮўҒBӮИӮәӮИӮз–lӮН‘еүпӮЕҲк“xӮҫӮБӮД—ыҸKӮжӮиӮўӮўғ^ғCғҖӮрҸoӮөӮҪӮұӮЖӮӘ–іӮўӮ©ӮзӮҫҒBӮЬӮҪҒAӮұӮкӮӘ“–ӮҪӮи‘OӮЖӮ·ӮйӮИӮзҒAҢҸӮМ‘еүпӮЕ—DҸҹӮөӮҪ‘IҺиӮН—ыҸKӮЕӮНӮаӮБӮЖӮўӮўғ^ғCғҖӮрҺқӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB—НӮрҸoӮөҗШӮкӮёӮЙ‘–ӮБӮД–lӮМҺ©ҢИғxғXғgӮЖ“ҜӮ¶ӮИӮз–lӮЙҸҹӮДӮй“№—қӮНӮИӮўҒB—Rҗ^ӮҫӮБӮДӮаӮҝӮлӮсӮ»ӮкӮНӮнӮ©ӮБӮДӮўӮйӮМӮҫҒB
ҒuӮ»ӮӨӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮҜӮЗҒAӮЕӮаҒAҺ„ӮН‘–ӮБӮДӮЩӮөӮ©ӮБӮҪҒv
ҒuҒcҒcҒv
—Rҗ^ӮМҢҫӮӨӮЖӮЁӮиҒA–lӮНҚӮҚZҺһ‘гҒA—ӨҸг•”ӮЙҸҠ‘®ӮөӮД’·Ӣ——ЈӮрӮвӮБӮДӮўӮҪҒB”wӮМҚӮӮў–lӮЙ’·Ӣ——ЈӮНҢьӮ©ӮИӮўӮЖҢҫӮнӮкӮДӮНӮўӮҪӮҜӮкӮЗӮ»ӮкӮН‘еӮөӮҪ–в‘иӮЙӮНӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ӯ»ӮкӮИӮиӮЙ‘¬ӮӯӮДҒAҲк”Nҗ¶ӮМӮӨӮҝӮ©Ӯз‘SҚ‘‘еүпӮЙҸoӮҪӮиӮөӮДҒAӮ»ӮкӮИӮиӮЙҠҲ–фӮөӮДӮўӮҪҒB
“с”Nҗ¶ӮМҚ ӮЙӮН‘SҚ‘ӮЕӮа–ј‘OӮӘ’mӮзӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮДҒAҺO”Nҗ¶ӮМҚ ӮЙӮН—ӨҸг•”ӮрҺ«ӮЯӮДӮўӮҪҒB
Ӯ ӮМҺ–ҢҸӮӘӮ ӮБӮДҒA–lӮрҺжӮиҠӘӮӯҠВӢ«ӮӘ•ПӮнӮБӮДҒAғAғӢғoғCғgӮрҺnӮЯӮҪӮ©ӮзӮҫҒB
—ӨҸг•”ӮМ‘IҺиҢ“ғ}ғlҒ[ғWғғҒ[ӮЕҒAӮўӮВӮа–lӮрүһүҮӮөӮДӮӯӮкӮҪ—Rҗ^ӮЙӮНҗ\Ӯө–уӮИӮ©ӮБӮҪӮҜӮкӮЗҒA–lӮНҲкүһӮМ–ІӮЖ—Rҗ^ӮМҠъ‘ТӮр— җШӮБӮҪӮМӮҫҒB
ҒuӮБӮДҒAҚЎҚXӮҫӮИҒ[ҒAӮвӮЯӮжӮБӮ©ҒBҚЎӮНӮ»ӮӨӮЬӮЕӮөӮДӮвӮБӮЖҺжӮи–ЯӮөӮ©ӮҜӮҪҗSҢмӮМ‘еҺ–ӮИ–…ӮіӮсӮМӮұӮЖӮрҚlӮҰӮжӮӨҒv
ҒuҒcҒcӮӨӮсҒv
җі’јҒAӮЁӮаӮөӮлӮўҳb‘иӮЕӮНӮИӮўҒB–lӮМ’ҶӮЕӮНӮаӮӨҸIӮнӮБӮДӮўӮйҳbӮИӮМӮҫҒBҚlӮҰӮДӮЭӮкӮО–lӮӘӮ»ӮсӮИ•—ӮЙҒA•Ғ’КӮМҚӮҚZҗ¶ӮзӮөӮўҺһҠФӮрҗ¶Ӯ«ӮзӮкӮҪӮұӮЖӮҫӮБӮДҒA”ьҚзӮӘӢ]җөӮЙӮИӮБӮДӮӯӮкӮҪӮЁӮ©Ӯ°ӮИӮМӮҫҒB”ьҚзӮЙӮНүҪӮаӮіӮ№ӮИӮ©ӮБӮҪ•ӘҒA•кӮН–lӮЙӮНүҪӮЕӮаӮвӮзӮ№ӮҪҒB—ӨҸгӮаӮ»ӮсӮИ’ҶӮМҲкӮВӮҫӮБӮҪҒB•”ҠҲ“®ӮЖҢҫӮӨӮМӮНҒA“БӮЙү^“®•”ӮНӮЁӢаӮӘӮ©Ӯ©ӮйӮаӮМӮҫҒB•кҗeҲкҗlӮМүТӮ¬ӮЕ•йӮзӮөӮДӮўӮҪ“–ҺһӮМ–l’BӮЙӮНҒAҢҲӮөӮД–іҺӢӮЕӮ«ӮИӮў•ү’SӮҫӮБӮҪӮлӮӨҒBӮ»ӮкӮЕӮа•кӮіӮсӮН–lӮӘӢЈӢZ—pӮМғXғpғCғNӮр—~ӮөӮўӮЖҢҫӮҰӮОҗҰӮӯҚӮӮў•ЁӮр”ғӮБӮДӮӯӮкӮҪҒB
Ғu–в‘иӮНӮЗӮӨӮвӮБӮДҗM—ҠӮр“ҫӮйӮ©ӮжӮЛҒv
ҒuӮӨӮсҒv
ҒuӮЖӮиӮ ӮҰӮёғfҒ[ғgғRҒ[ғXӮНӮұӮМҺҶӮЙҸ‘ӮўӮДӮЁӮўӮҪҒv
Ӯ»ӮӨҢҫӮБӮД—Rҗ^ӮНғoғbғOӮ©ӮзғҒғӮ’ ӮрҺжӮиҸoӮөӮДҒAғfҒ[ғgғRҒ[ғXҒiҒHҒjӮМҸ‘Ӯ©ӮкӮҪғyҒ[ғWӮр”jӮБӮДӮжӮұӮөӮҪҒBӮ»ӮсӮИӮұӮЖ—ҠӮсӮЕӮўӮИӮўӮМӮҫӮӘҒA—Rҗ^ӮНӢCӮӘӮ«ӮӯҒB–lӮӘӮ»ӮӨӮўӮӨӮұӮЖӮЙ‘aӮўӮМӮр’mӮБӮДӮўӮйӮ©ӮзҒAҚlӮҰӮДӮ«ӮДӮӯӮкӮҪӮМӮҫҒB
ҒuӮЕҒAғfҒ[ғgғRҒ[ғXӮБӮДҒcҒcҒv
ҒuғҒҒ[ғӢӮЕӮаӮжӮ©ӮБӮҪӮсӮҫӮҜӮЗӮЛҒAҺиҸ‘Ӯ«ӮМӮЩӮӨӮӘҠyӮҫӮөҒv
ҠyҒAӮЖӮўӮӨҠ„ӮЙӮНӮЁ“XӮМ“Б’ҘӮв•өҲНӢCӮЬӮЕӮнӮ©ӮиӮвӮ·ӮӯҸ‘ӮўӮДӮӯӮкӮДӮўӮйҒBӮ«ӮБӮЖ”ьҚзӮМӮҪӮЯӮЙ—Rҗ^ӮаҠж’ЈӮБӮДӮӯӮкӮҪӮсӮҫӮлӮӨҒBӮ»ӮкӮЙӮөӮДӮағfҒ[ғgӮБӮДҒcҒcҒBҢZ–…ӮЕҠXӮр•аӮӯӮұӮЖӮағfҒ[ғgӮБӮДҢҫӮӨӮсӮҫӮлӮӨӮ©ҒH
Ғu”ьҚзӮҝӮбӮсҒAӮёӮБӮЖ•aү@ӮЖ—{ҢмҺ{җЭӮҫӮБӮҪӮсӮЕӮөӮеҒHҒ@Ӯ»ӮкӮИӮзҠOӮЕҠyӮөӮӯ—VӮсӮҫҢoҢұӮИӮсӮДӮ»ӮсӮИӮЙ–іӮўӮЖҺvӮӨҒBӮҫӮ©ӮзӮөӮБӮ©ӮиҚӢ—VӮіӮ№ӮДӮвӮйӮұӮЖҒv
ҒuҚӢ—VӮБӮДҒcҒcҒv
ҒuӮўӮўӮМӮжҒA”ьҚзӮҝӮбӮсӮЙӮНӮнӮӘӮЬӮЬӮаҢҫӮнӮ№ӮДӮ Ӯ°ӮДҒAҺvӮўӮБӮ«ӮижТ‘тӮіӮ№ӮДӮвӮйӮМҒB—ҠӮкӮй‘еҗlӮМҸрҢҸӮМҲкӮВӮЙӮНӢаҒIҒ@ӮұӮкӮа‘еҺ–ӮИӮсӮҫӮ©ӮзҒAӮ»ӮкӮрҢҷ–ЎӮЙӮИӮзӮИӮў’ц“xӮЙҢ©Ӯ№•tӮҜӮВӮВҒA•п—e—НӮБӮДӮўӮӨӮ©ҒAүщӮМҗ[ӮіӮрғAғsҒ[ғӢӮ·ӮйӮМӮжҒv
Ӯ»ӮкӮНӮ»ӮӨӮҫӮлӮӨӮӘҒA—Rҗ^ӮӘҢҫӮӨӮЖүҪӮ©‘ЕҺZ“IӮИҠҙӮ¶ӮӘӮөӮДҺбҠұҢҷӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮЬӮҹҒAҠж’ЈӮБӮДӮЭӮйӮжҒv
ҒuӮЖӮЙӮ©ӮӯҠо–{ӮНӮ»ӮМҺҶӮЙҸ‘ӮўӮДӮ Ӯй’КӮиӮЕӮўӮўӮЖҺvӮӨҒB’n—қӮНӮнӮ©ӮйӮЕӮөӮеҒHҒv
ҒuӮӨӮсҒv
‘еҸд•vҒAӮ»ӮкӮИӮиӮЙ“y’nҠЁӮНӮ ӮйҒB
ҒuӮ ӮЖӮН”ьҚзӮҝӮбӮсӮМҠу–]ӮЙүҲӮБӮДғAғhғҠғuӮЕүҪӮЖӮ©ӮөӮИӮіӮўҒBӮ ҒAӮ ӮЖҒAӮ»ӮМҺҶҒAҲГӢLӮөӮИӮіӮўҒB–YӮкӮҪӮзҢ©ӮДӮаӮўӮўӮҜӮЗ”ьҚзӮҝӮбӮсӮЙҢ©ӮзӮкӮҝӮбғ_ғҒӮҫӮ©ӮзӮЛҒv
ӮЬӮ ҒA“–ӮҪӮи‘OӮ©ҒBғAғhғҠғuӮа‘еҸд•vӮҫӮЖҺvӮӨҒB–lӮҫӮБӮДүҪ“ъӮа‘OӮ©ӮзӮұӮМ“ъӮМӮҪӮЯӮЙҗFҒXҚlӮҰӮДӮ«ӮҪӮМӮҫҒB
“ҜӮ¶Ҹ—җ«ӮЕӮ Ӯй—Rҗ^ӮМ‘gӮсӮЕӮӯӮкӮҪғvғүғ“Ӯр—DҗжӮөӮДҒAҢгӮН”ьҚзӮМҠу–]ӮЕҚDӮ«ӮИҸҠӮЙҳAӮкӮДҚsӮБӮДӮ Ӯ°ӮйҒBӮ»ӮсӮИӮЖӮұӮлӮЙҳbӮН—ҺӮҝ’…ӮўӮҪҒB
ҒuӮӨӮсҒAӮ ӮиӮӘӮЖҒA—Rҗ^Ғv
–lӮНӮўӮВӮаҗўҳbӮрҸДӮўӮДӮӯӮкӮйӢҢ—FӮЙҠҙҺУӮМӢCҺқӮҝӮрҚһӮЯӮДӮЁ—зӮрҢҫӮБӮҪҒB”ЮҸ—ӮЙӮНҗМӮ©ӮзҗўҳbӮЙӮИӮиӮБӮПӮИӮөӮҫҒB
ҒuӮЬӮҪ‘ЭӮөӮӘ‘қӮҰӮҪӮЛҒBҚЎ“xӮНүЖӮЕӮа”ғӮБӮДӮаӮзӮЁӮӨӮ©ӮИҒv
ҒuӮҝӮеҒAӮ»ӮкӮНҒcҒcҒv
Ҹз’kӮрҢрӮҰӮВӮВҒA–lӮзӮНҚДӮСҺG’kӮЙ–ЯӮБӮҪҒB
ҒuӮіӮДҒAӮ»ӮлӮ»ӮлҚsӮӯӮжҒv
ҺһҢvӮНҲкҺһ”јӮрҚҸӮсӮЕӮўӮҪҒB‘ТӮҝҚҮӮнӮ№ҸкҸҠӮНӮұӮұӮ©Ӯз“k•аӮЕҸ\•ӘӮӯӮзӮўӮМғfғpҒ[ғgӮМ•ЗӮЙӮНӮЯҚһӮЬӮкӮҪ‘еҢ^ғfғBғXғvғҢғCӮМ‘OӮҫҒBӮұӮМ•УӮиӮЕӮН–Ъ—§ӮВҸкҸҠӮҫӮҜӮЙ‘ТӮҝҚҮӮнӮ№ӮЙҺgӮӨҗlӮа‘ҪӮўҒB
ҒuӮӨӮсҒv
—§ӮҝҸгӮӘӮБӮД–lӮН—Rҗ^ӮЙ•·ӮўӮҪҒB
Ғu–lҒAӮұӮМғXҒ[ғcҒA•ПӮ¶ӮбӮИӮўӮжӮЛҒHҒv
ҒuӮӨӮсҒA‘еҸд•vҒv
ҒuҠзӮЖӮ©”ҜӮЖӮ©‘еҸд•vҒHҗQ•s‘«‘ұӮ«ӮҫӮ©Ӯз–ЪӮЙғNғ}ӮЖӮ©Ӯ ӮйӮ©ӮаҒv
Ғu‘еҸд•vҒAӮўӮВӮа’КӮиӮМ”ьҢ`ӮжҒv
–lӮМҠзӮНҲк”К“IӮЙҢ©ӮйӮЖӮўӮнӮдӮй”ьҢ`ӮзӮөӮўҒBӢLүҜӮЙӮ Ӯй•ғӮаҒAӮ»ӮӨӮўӮҰӮОҗ®ӮБӮҪҠз—§ӮҝӮрӮөӮДӮўӮҪҒBӮҫӮ©ӮзӮұӮ»ӮМҸ—ӮБӮҪӮзӮөӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒB–lӮН•ғӮЙҺ—ӮҪҺ©•ӘӮМҠзӮӘӮ ӮЬӮиҚDӮ«ӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuүҪӮ©•ПӮИӮЖӮұӮИӮўӮжӮЛҒHҒv
ҒuӮаӮӨҒIҒ@ӮөӮВӮұӮўҒIҒ@Ҹ—ҺqҚӮҗ¶Ӯ©Ӯ ӮсӮҪӮНҒIҒ@‘еҸд•vӮБӮДӮўӮБӮҪӮз‘еҸд•vӮжҒIҒv
ҒuӮІҒAӮІӮЯӮсҒv
ӮжӮөҒA—Rҗ^ӮӘӮ»ӮӨҢҫӮӨӮИӮз‘еҸд•vҒB
үпҢvӮрҚПӮЬӮ№ӮД“XӮрҸoӮйӮЖҒA—Rҗ^ӮӘ–lӮЙҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮвӮБӮЖӮҫӮЛҒAҗSҢмҒv
ҒuӮӨӮсҒv
’·Ӯ©ӮБӮҪҒBӮұӮұӮЬӮЕ—ҲӮйӮМӮНҒB
ҒuӮжӮ©ӮБӮҪӮЛҒv
ҒuӮӨӮсҒv
Ӯ»ӮӨҒA–lӮНӮвӮБӮЖ”ьҚзӮЙҲ§ӮҰӮйҒB
ҒuӮ»ӮкӮ¶ӮбҒAҚsӮБӮДӮзӮБӮөӮбӮўҒBғwғ}Ӯ·ӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮнӮжҒv
”ьҚзӮН–lӮрӢ–ӮөӮДӮӯӮкӮДӮўӮйӮҫӮлӮӨӮ©ҒBӮ»ӮсӮИӮнӮҜӮН–іӮўӮЖ“аҗSӮЕӮНӮнӮ©ӮБӮДӮўӮйҒBҺvӮҰӮО–lӮН—cӮў”ьҚзӮЙӮНҢҷӮнӮкӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЙӮаҺvӮӨҒB”ј’[ӮЙҢмӮиҒAҲк“xӮНҢ©ҺМӮДҒAҺжӮи–ЯӮ»ӮӨӮЖӮөӮҪӮЖӮ«ӮЙӮН’xӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮсӮИҢZӮҫҒBҢҷӮнӮкӮДӮўӮДӮаҺd•ыӮИӮўҒBӮ»ӮкӮЕӮа”ьҚзӮНҚЎ“ъ–lӮЙҲ§ӮӨӮұӮЖӮрҸі‘шӮөӮДӮӯӮкӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒAӮЗӮсӮИҠҙҸоӮЕӮ ӮБӮДӮа–lӮЙҺvӮӨӮЖӮұӮлӮӘӮ ӮйӮМӮҫӮлӮӨҒB–lӮН“{ӮзӮкӮДӮаӮўӮўҒBҚҰӮЭҢҫӮрҢҫӮнӮкӮДӮаӮўӮўҒBүЈӮзӮкӮҪӮБӮДҚ\ӮнӮИӮўҒBҺуӮҜ“ьӮкӮДӮЭӮ№ӮйҒB
–lӮНҚЎ“ъҒAӮвӮБӮЖҢNӮЙҲ§ӮҰӮйӮсӮҫӮ©ӮзҒB
ҒuӮӨӮсҒAҚsӮБӮДӮ«ӮЬӮ·ҒB—Rҗ^ӮаҺdҺ–ҒAҠж’ЈӮБӮДҒv
—Rҗ^ӮЙҺиӮрҗUӮБӮД–lӮН•аӮ«ҸoӮөӮҪҒB”ьҚзӮЙҢqӮӘӮй“№ӮҫҒBҚЎ“xӮНҢ©‘—ӮйӮҫӮҜӮ¶ӮбӮИӮўҒB–lӮӘҢ}ӮҰӮЙҚsӮӯӮсӮҫҒB
ӮўӮВӮа’КӮй“№ӮҫӮҜӮкӮЗҒA–lӮНӮөӮБӮ©ӮиӮЖ“ҘӮЭӮөӮЯӮйӮжӮӨӮЙ•аӮўӮҪҒBҳZ”NҠФӮЕ’nӮЙ‘«ӮрӮВӮҜӮҪ–lӮӘ”w’ҶӮрүҹӮөӮДӮӯӮкӮДӮўӮҪҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ӮQ
ҲкӮВ–в‘иӮӘӮ ӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB–lӮНӮұӮМҗlӮІӮЭӮМ’ҶӮ©Ӯз”ьҚзӮрҢ©ӮВӮҜӮзӮкӮйӮМӮ©ҒH
”ьҚзӮЙӮН–lӮМҺКҗ^ӮМ“ьӮБӮҪҺиҺҶӮрүҪ“xӮаҸoӮөӮДӮўӮйӮ©ӮзҒA–lӮМӮұӮЖӮНӮнӮ©ӮйӮЖҺvӮӨҒB
ӮҜӮкӮЗ–lӮНӮұӮМҳZ”NҠФӮЕҗ¬’·ӮөӮҪ”ьҚзӮМҺpӮрҲк“xӮҫӮБӮДҢ©ӮДӮўӮИӮўҒB–lӮМҸoӮөӮҪҺиҺҶӮН•ФҺ–ӮрӢҒӮЯӮйӮжӮӨӮИ“а—eӮЙӮНӮИӮБӮДӮўӮИӮўҒBӮҪӮҫү“—¶ӮөӮДӮўӮҪӮБӮДӮнӮҜӮ¶ӮбӮИӮўҒB•ФҺ–ӮрӢҒӮЯӮйӮМӮӘ•|Ӯ©ӮБӮҪӮМӮҫҒB”ьҚзӮНӮ«ӮБӮЖ–lӮрҢҷӮБӮДӮўӮйҒBҺАҚЫӮНӮЗӮӨӮИӮМӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўӮҜӮкӮЗҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮа–lӮНӮ»ӮӨҺvӮБӮДӮўӮйҒBҺиҺҶӮМ•ФҺ–ӮрӢҒӮЯӮДӮ»ӮкӮӘ•ФӮБӮДӮұӮИӮ©ӮБӮҪӮзҒAӮ»ӮкӮН”ьҚзӮӘ–lӮрӢ–ӮөӮДӮўӮИӮўҒAҢҷӮБӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮрғҠғAғӢӮЙӮВӮ«ӮВӮҜӮзӮкӮҪӮжӮӨӮИӮаӮМӮҫҒB–lӮНӮ»ӮкӮӘ•|Ӯ©ӮБӮҪҒBҠoҢеӮНӮөӮДӮўӮйӮВӮаӮиӮҫӮӘӮвӮБӮПӮи•|Ӯ©ӮБӮҪӮМӮҫҒB
Ғi‘еҸд•vҒAӮ«ӮБӮЖӮнӮ©ӮйӮіҒj
Ӯ»ӮкӮЙҚlӮҰӮДӮЭӮкӮОҒA–lӮЙ”ьҚзӮӘӮнӮ©ӮзӮИӮӯӮДӮаҒA”ьҚзӮӘ–lӮрҢ©ӮВӮҜӮДҗәӮрӮ©ӮҜӮДӮӯӮкӮкӮОӮўӮўӮҫӮҜӮҫҒB‘еӮөӮҪӮұӮЖӮ¶ӮбӮИӮўҒB
ҒiӮҜӮЗҒAҳZ”NӮФӮиӮЖӮНӮўӮҰӮұӮкӮ©Ӯз•ЫҢмҺТӮЙӮИӮлӮӨӮБӮДӮўӮӨҢZӮӘ–…ӮЙӢCӮГӮҜӮИӮ©ӮБӮҪӮзҒA”ьҚзӮН“{ӮйҒAӮЖӮўӮӨӮ©Һё–]Ӯ·ӮйӮҫӮлӮӨӮ©ҒcҒcҒj
Ӯ»ӮсӮИ•—ӮЙ–lӮӘҚlӮҰҒAүҪӮЖӮ©ӮөӮД”ьҚзӮМҳZ”N‘OӮМҺpӮ©ӮзҚЎӮМ”ьҚзӮр‘z‘ңӮөӮДӮЭӮжӮӨӮЖ“w—НӮөҺnӮЯӮҪҚ ҒAүwӮМӢЯӮӯӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAҗl’КӮиӮМҢғӮөӮўӮұӮМҸкҸҠӮЕ“Л‘RҗlӮІӮЭӮӘҠ„ӮкӮҪҒB
ӮұӮМҸкӮЙӮўӮйӮ·ӮЧӮДӮМҗlӮӘҒw”ЮҸ—ҒxӮрҢ©ӮҪҒB‘ТӮҝҚҮӮнӮ№ӮрӮөӮДӮўӮҪҗlӮаҒA’КӮиӮ·ӮӘӮБӮҪӮҫӮҜӮМҗlӮаҒBӮаӮҝӮлӮс–lӮаҒB
ӢPӮӯӮжӮӨӮИ”ьҸӯҸ—ҒBӮ»ӮӨ•\Ң»Ӯ·ӮйӮМӮӘӮўӮўӮЖҺvӮӨҒB—eҺpӮҫӮҜӮ¶ӮбӮИӮўҒBӮ»ӮМ•\ҸоӮЙӮаӮИӮЙӮ©Һ©җMӮМӮжӮӨӮИӮаӮМӮӘҠҙӮ¶ӮзӮкӮйҒB
Ғw”ЮҸ—ҒxӮН”GӮкӮДӮўӮйӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮӨӮЩӮЗүҗӮвӮ©ӮИ’·ӮўҚ•”ҜӮрӮИӮСӮ©Ӯ№ӮД•аӮӯҒB
ҒiгY—нӮИҸ—ӮМҺqӮҫӮИҒj
–lӮН‘f’јӮЙӮ»ӮӨҺvӮБӮҪҒBҺбӮўҚ ӮМ—Rҗ^ӮЭӮҪӮўӮҫҒAӮИӮсӮДҢҫӮБӮҪӮз—Rҗ^ӮНҒuӮЬӮҫҺбӮўҒIҒ@ӮФӮБҺEӮ·ӮжҒIҒvӮЖӮ©ҢҫӮБӮД“{ӮиӮ»ӮӨӮҫҒBӮЕӮаҒAӮўӮйӮаӮсӮИӮсӮҫӮИӮҹҒAӮұӮӨӮўӮӨҺqҒAӮЖҺvӮБӮҪҒB
ӮҜӮкӮЗҚЎӮМ–lӮЙӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮНҚұҺ–ӮҫҒB—ЗӮў–ЪӮМ•Ы—{ӮЙӮИӮБӮҪҒAӮЖҒw”ЮҸ—ҒxӮМӮұӮЖӮНҺvҚlӮ©ӮзҗШӮиҺМӮДҒAҚДӮС”ьҚзӮМӮұӮЖӮрҚlӮҰӮйҒB
ҺһҚҸӮН“сҺһҺO•ӘҒB‘ТӮҝҚҮӮнӮ№ӮМҺһҠФӮНүЯӮ¬ӮДӮўӮйҒBҢg‘С“dҳbӮрҺжӮиҸoӮөӮДӮЭӮйҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМҚs“®ӮЙҲУ–ЎӮН–іӮўҒBҚЎҺһӮМ’ҶҠwҗ¶ӮИӮзҢg‘СӮӯӮзӮўҺқӮБӮДӮўӮйҺqӮМ•ыӮӘ‘ҪӮўӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮҜӮкӮЗ”ьҚзӮНҢg‘С“dҳbӮИӮсӮДҺқӮБӮДӮўӮИӮўҒB“–‘RӮҫҒBҺ{җЭӮЕҗ¶ҠҲӮөӮДӮўӮй”ьҚзӮӘҢg‘СӮИӮсӮДҺқӮБӮДӮўӮйӮНӮёӮӘ–іӮўҒB
ҢӢӢЗҒA–lӮНҺ©•ӘӮМҳrҺһҢvӮЖҢg‘С“dҳbӮМҺһҢvӮМҺһҚҸӮМғYғҢӮрҠm”FӮөӮҪӮҫӮҜӮЕӮ·Ӯ®ӮЙғXҒ[ғcӮМғ|ғPғbғgӮЙӮ»ӮкӮрӮөӮЬӮБӮҪҒBғYғҢӮНҺө•bӮҫӮБӮҪҒB
•УӮиӮрҢ©үсӮөӮДӮЭӮйҒBҺьҲНӮМҗlҒXӮН‘Ҡ•ПӮнӮзӮёҒw”ЮҸ—ҒxӮЙҺӢҗьӮр“B•tӮҜӮЙӮіӮкӮДӮўӮйӮЭӮҪӮўӮҫӮҜӮЗҒA–lӮЙӮНӮ»ӮкӮНҠЦҢWӮИӮўҒB•S”ӘҸ\ғZғ“ғ`Ңг”јӮМҒAҗl•АӮЭӮжӮиҚӮӮўҺӢ“_ӮЕ”ьҚзӮзӮөӮ«җl•ЁӮр’TӮ·ҒB“ҜӮ¶”NҚ ӮМҺqӮИӮзӮҪӮӯӮіӮсӮўӮйҒBӮҜӮкӮЗӮЗӮМҺqӮа–lӮМ‘z‘ңӮ·Ӯй”ьҚзӮЖӮНҸdӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ӯ·Ӯ®—ЧӮЕҗlӮр‘ТӮБӮДӮўӮйӮзӮөӮў’jӮЖ–ЪӮӘҚҮӮБӮҪҒBҺӢҗьӮрӮ»ӮзӮөӮҪҗжӮЕҚЎ“xӮНҢўӮрҳAӮкӮҪӮЁӮ¶ӮіӮсӮЖ–ЪӮӘҚҮӮБӮҪҒBӮЖӮўӮӨӮ©ҒAӢCӮӘ•tӮӯӮЖӮЭӮсӮИӮӘ–lӮрҢ©ӮДӮўӮҪҒBҢ»‘г“ъ–{ӮН“ҢӢһӮЕҗlӮрӢГҺӢӮ·ӮйӮЖӮН’ҝӮөӮўҒBӮӨҒ[ӮЮҒAӮЗӮӨӮөӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӮұӮсӮЙӮҝӮНҒv
“Л‘RҒAүВҲӨӮзӮөӮўҸ—ӮМҺqӮМҗәӮЕӮЗӮұӮ©ӮзӮ©ҲҘҺAӮрӮіӮкӮҪҒB
ҒuӮҰҒHҒ@Ӯ ҒAӮНӮўҒAӮұӮсӮЙӮҝӮНҒv
ӮЖҒAӮВӮў”ҪҺЛ“IӮЙҒAғ}ғkғPӮЙ•ФӮөӮДӮНӮЭӮҪӮаӮМӮМҒA–lӮН’NӮЙҲҘҺAӮрӮіӮкӮҪӮМӮ©ӮнӮ©ӮзӮёҒA•УӮиӮрғLғҮғҚғLғҮғҚӮЖҢ©үсӮ·ҒB’NӮҫӮлӮӨҒHҒ@Ӯ»ӮкӮзӮөӮўҗlӮНҢ©“–ӮҪӮзӮИӮўҒB
ҒuӮҝӮеӮБӮЖҒAүәҒAӮаӮӨӮҝӮеӮўүәҒv
үәҒAӮЖҢҫӮнӮкӮДүәӮрҢ©ӮДӮЭӮйӮЖҒ\Ғ\ҒB
‘еҸOӮМҺӢҗьӮр“B•tӮҜӮЙӮөӮДӮўӮҪҒw”ЮҸ—ҒxӮӘӮ»ӮұӮЙӮўӮҪҒB–lӮН”wӮӘҚӮӮўӮМӮЕҒAҗg’·ӮМ’бӮўҒw”ЮҸ—ҒxӮНҺӢҠEӮЙ“ьӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒB
ҒuӮұӮсӮЙӮҝӮНҒv
–lӮЖ–ЪӮӘҚҮӮӨӮЖҒw”ЮҸ—ҒxӮНҚДӮСҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮҰҒHҒ@Ӯ ҒAӮНӮўҒAӮұӮсӮЙӮҝӮНҒv
җжӮЩӮЗӮМҸДӮ«‘қӮөӮҫҒBӮ Ӯ ҒAӮИӮйӮЩӮЗҒAӮұӮМҺqӮӘ–lӮМӢЯӮӯӮЙӮўӮҪӮ©ӮзӮЭӮсӮИ–lӮМ•ыӮрҢ©ӮДӮўӮҪӮМӮ©ҒBӮЕӮаҒAӮұӮМҺqӮНүҪӮЕ–lӮЙҲҘҺAӮрҒHҒ@ӮұӮсӮИгY—нӮИҺqӮӘ–lӮЙүҪӮМ—pӮӘӮ ӮйӮсӮҫӮлӮӨҒHҒ@ӮЬӮіӮ©ғiғ“ғpӮЕӮаӮИӮўӮҫӮлӮӨӮөҒB
ҒuүҪӮ©ҢҫӮӨӮұӮЖӮНӮИӮўӮМҒHҒv
Ғw”ЮҸ—ҒxӮӘ”ј–ЪӮЕ–lӮрбЙӮЭӮИӮӘӮзҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮҰҒAӮ ӮМҒAӮҰҒ[ӮЖҒAӮЖӮиӮ ӮҰӮёӮІӮЯӮсӮИӮіӮўҒv
ҺУӮБӮДӮЭӮҪҒB
ҒuӮИӮсӮЕӮжҒIҒ@ғoғJҒIҒv
“{ӮзӮкӮҪҒI
Ҳк‘МӮИӮсӮҫӮЖӮўӮӨӮМӮҫӮлӮӨҒBүҪӮ©ҢҫӮӨӮұӮЖӮНҒHҒ@ӮЖҢҫӮнӮкӮДӮаҒA“Л‘RҢ©’mӮзӮКҗlӮЙҲҘҺAӮіӮкӮДүҪӮрҢҫӮҰӮЖҢҫӮӨӮсӮҫӮлӮӨҒH
ҒuӮаӮӨҒIҒ@ӮИӮсӮЕӮнӮ©ӮсӮИӮўӮМӮжҒIҒv
ӮИӮсӮ©“{ӮБӮДӮйҒI
ҒuӮІҒAӮІӮЯӮсҒAӮЕӮа–lҒAҢNӮӘүҪӮрҢҫӮБӮДӮйӮМӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўӮсӮҫҒcҒcҒv
җі’јӮЙҢҫӮБӮДӮЭӮҪҒB
ҒuӮНӮҹҒHҒ@ҢкҠw—НӮИӮўӮМҒHҒ@“ъ–{ҢкӮжҒHҒ@Ӯ»ӮсӮИӮсӮЕӮжӮӯҚ‘—§‘еӮЙ“ьӮкӮҪӮнӮЛҒv
Ғ\Ғ\ҒBӮИӮсӮЕӮұӮМҺqӮНӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮр’mӮБӮДӮўӮйӮМӮ©ҒHҒ@ӮЖҚlӮҰӮҪӮЖӮұӮлӮЕӮжӮӨӮвӮӯ–lӮНӢCӮӘӮВӮўӮҪҒB
ҒuҢNҒA”ьҚзҒHҒv
ӮЬӮіӮ©ҒAӮЖӮўӮӨҺvӮўҚ¬Ӯ¶ӮиӮЙ•·ӮўӮДӮЭӮйҒBҲшӮ«ӮВӮБӮҪӮжӮӨӮИҸОҠзӮЕҒB
Ғw”ЮҸ—ҒxӮН‘еӮ«ӮӯӮҪӮЯ‘§ӮрӮВӮўӮДӮ©ӮзҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ»ӮӨӮжҒAӢvӮөӮФӮиӮЛҒAӮЁҢZӮҝӮбӮсҒv
ҒuҒIҒIҒIҒv
ғ}ғWӮЕӮ·Ӯ©ҒAӮ»ӮӨӮЕӮ·Ӯ©ҒA–lӮНӮ ӮИӮҪӮМӮЁҢZӮҝӮбӮсӮЕӮөӮҪӮ©ҒB
ғrғVғbҒAӮЖү№Ӯр—§ӮДӮД–lӮМҲшӮ«ӮВӮБӮҪҸОҠзӮН“ҖӮиӮВӮўӮҪҒAӮжӮӨӮИӢCӮӘӮ·ӮйҒB
“ҖӮиӮВӮўӮҪӮМӮЙӮНҺOӮВӮМ—қ—RӮӘӮ ӮйҒBӮЬӮёҚЎӮМ”ьҚзӮӘ–lӮМ‘z‘ңӮЖӮ©ӮҜ—ЈӮкӮ·Ӯ¬ӮДӮўӮҪӮұӮЖҒBӮ»ӮиӮбӮұӮсӮИӮЙгY—нӮЙӮИӮБӮДҒAӮөӮ©ӮаӮЁ“]”kӮ»ӮӨӮЕҒcҒcҒBӢҙ–{ӮіӮсӮ©Ӯз–ҫӮйӮӯӮИӮБӮҪӮЖ•·ӮўӮДӮўӮҪӮЖӮНӮўӮҰҒAӮұӮкӮ¶ӮбӮ –lӮМӢLүҜӮЖҸdӮИӮйӮнӮҜӮӘ–іӮўҒB“сӮВ–ЪӮН”ьҚзӮӘӮҝӮеӮБӮЖҢыӮӘҲ«ӮӯҲзӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮұӮЖҒBӢҙ–{ӮіӮсҒcҒcӮ ӮИӮҪӮЙ”CӮ№ӮҪӮМӮНҠФҲбӮўӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©Ғ\Ғ\ҒBҺOӮВ–ЪӮН–lӮӘ”ьҚзӮЙӮ·Ӯ®ӮЙӢCӮГӮҜӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖҒBҠлңңӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖӮЕӮНӮ ӮБӮҪӮҜӮкӮЗҒAҺАӮНҢ©ӮкӮОӮнӮ©ӮйӮЖӮўӮӨҺ©җMӮӘӮ ӮБӮҪӮҫӮҜӮЙӮЬӮБӮҪӮӯӮнӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪғVғҮғbғNӮН‘еӮ«ӮўҒBӮіӮзӮЙ—\‘z’КӮиҒA”ьҚзӮр“{ӮзӮ№ӮҪҸгӮЙҺё–]ӮіӮ№ӮҪҠҙӮӘӮ ӮйҒBӮұӮкӮӘҲк”Ф‘еӮ«ӮўҒB
Ӯ Ӯ ҒAӮИӮсӮЖӮўӮӨҚДүпҒB‘sҗвӮИӮвӮБӮҝӮбӮБӮҪҠҙӮӘ–lӮр‘ЕӮҝӮМӮЯӮөӮДӮўӮӯҒB
Ӯ»ӮкӮЙӮИӮсӮДӮўӮӨӮ©ҒAӮаӮБӮЖҒwҠҙ“®ӮМҚДүпҒIҒxӮЭӮҪӮўӮИӮМӮрҠъ‘ТӮөӮДӮҪӮМӮЙӮИӮҹҒB
ҒuӮРҒAӢvӮөӮФӮиҒA”ьҚзҒv
ӮЖӮНӮўӮҰҒA‘ТӮҝӮЙ‘ТӮБӮҪҸuҠФӮҫҒBҠрӮөӮіӮӘҚһӮЭҸгӮ°ӮДӮ«ӮДҸӯӮөӢғӮ«Ӯ»ӮӨӮҫҒBӮБӮДӮўӮӨӮ©ӮаӮӨӢғӮўӮДӮўӮўӮЕӮ·Ӯ©ӮЛҒHҒ@ӮҝӮеӮБӮЖғ}ғWӮЕҒB
ҒuӮҝӮеҒAӮЁҢZӮҝӮбӮсҒHҒ@ӮИӮсӮЕӢғӮӯӮМҒHҒ@ӮвӮЯӮДҒIҒ@’pӮёӮ©ӮөӮўҒIҒv
ҒuӮІҒAӮІӮЯӮсҒAӮЕӮаҒA”ьҚзҒcҒcҒA–lӮНҳZ”NӮаҒcҒcҒv
Ӯ Ӯ ҒAҠiҚDҲ«ӮўӮЖӮұӮлӮИӮсӮДҢ©Ӯ№ӮҝӮбӮўӮҜӮИӮўӮМӮЙҒAӮЕӮаүд–қӮЕӮ«ӮИӮўҒB
ҒuӮ Ғ[ҒIҒ@ӮаӮӨҒIҒ@ҚsӮӯӮжҒIҒ@ӮЁҢZӮҝӮбӮсҒIҒ@ӮЩӮзҒIҒ@•аӮўӮДҒIҒv
”ьҚзӮӘҚQӮДӮҪ—lҺqӮЕ–lӮМҺиӮрҢЎӮўӮД•аӮ«ҸoӮөӮҪҒBҺьӮиӮМҗlӮӘ–lӮзӮр—lҒXӮИ–ЪӮЕҢ©ӮДӮўӮйҒB
ҒuӮнӮҹҒA”ьҢ`ҢZ–…ҒvҒuӮўӮўӮИӮҹҒAӮ ӮсӮИӮЁҢZӮҝӮбӮсҒvҒuӮИӮсӮҫҒAҢZӢMӮҫӮБӮҪӮМӮ©ҒA”ЮҺҒӮҫӮБӮҪӮзҺфӮўҺEӮ·ӮЖӮұӮҫӮБӮҪҒvҒuӮ ӮсӮИүВҲӨӮў–…ӮӘӮўӮҪӮзҒcҒcғnғ@ғnғ@ҒvҒuӮЖӮұӮлӮЕӮИӮсӮЕӮ ӮМҗlӢғӮўӮДӮйӮМҒHҒvҒuӮіӮҹҒHҒ@–…ӮЙүХӮЯӮзӮкӮҪӮсӮ¶ӮбӮИӮўҒHҒv
җFҒXӮИӮұӮЖӮрҢҫӮнӮкӮДӮўӮйӮҜӮкӮЗҒA”ьҚзӮМ—eҺpӮр–JӮЯӮДӮМӮұӮЖӮНӮИӮсӮҫӮ©–ӯӮЙҠрӮөӮ©ӮБӮҪҒBҺ©•ӘӮр–JӮЯӮзӮкӮйӮжӮиҒAүҪ”{ӮаҒB
ҒuӮЕӮаҒA”ьҚзӮНӮжӮӯ–lӮӘӮ·Ӯ®ӮЙӮнӮ©ӮБӮҪӮЛҒv
ҒuӮӨӮсҒAҺКҗ^ӮаҢ©ӮҪӮөҒAӮЁҢZӮҝӮбӮсҒA•ПӮнӮБӮДӮИӮўӮаӮМҒv
җі’јӮИӮЖӮұӮлҒA–lӮНӮіӮБӮ«ӮЬӮЕғhғLғhғLӮөӮДӮўӮҪҒB”ьҚзӮЖҲ§ӮБӮҪӮзӮЗӮсӮИӮұӮЖӮрҳbӮ»ӮӨҒAҗFҒXҚlӮҰӮДӮНӮ«ӮҪӮҜӮЗҺһҢvӮМҗjӮӘ“сҺһӮЙӢЯ•tӮӯӮІӮЖӮЙӢЩ’ЈӮӘ‘қӮөӮДӮўӮБӮДҳbӮМғlғ^Ӯр–YӮкӮҪҒBӮ»ӮаӮ»ӮаӮұӮсӮИӮЙғhғLғhғLӮөӮДӮўӮҪӮзҗәӮӘ— •ФӮБӮДүпҳbӮаҸo—ҲӮИӮўӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮМӮ©ҒHҒ@–{ӢCӮЕӮ»ӮсӮИ•—ӮЙҺvӮБӮҪҒBҺ–‘OӮЙ—Rҗ^ӮЙүпӮБӮДӮўӮИӮҜӮкӮОӮаӮӨ”ӯӢ¶ӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮ»ӮкӮӯӮзӮў–lӮМӢЩ’ЈӮМғpғүғҒҒ[ғ^Ғ[ӮНӮlӮ`ӮwӮЙӢЯӮГӮўӮДӮўӮҪӮМӮҫҒB
ӮҜӮкӮЗҒAӮұӮМғ_ғҒӮИҚДүпӮНҢӢүК“IӮЙӮНӮжӮ©ӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB–lӮМӢЩ’ЈӮНҚЕҸүӮМҺё”sӮЕӮўӮўҠҙӮ¶ӮЙүрӮҜӮДҒAҚЎӮЕӮНӮұӮсӮИ•—ӮЙүпҳbӮаҸo—ҲӮйҒB
ҒuӮ»ӮӨӮ©ӮИӮҹҒAӮЬӮ Ӯ»ӮкӮаӮ»ӮӨӮ©ҒA–lӮНӮ ӮМҺһҚӮ“сӮҫӮөҒAҢ©ӮҪ–ЪӮЙӮ»ӮӨ•Пү»ӮНӮИӮўӮ©ӮИҒv
ҒuӮ»ӮӨӮЛҒAӮҝӮеӮБӮЖғoғJӮБӮЫӮўӮЖӮұӮаӮЛҒv
Ғuғ\Ғ[ғfғXғJҒv
Ғuғ\Ғ[ғfғXғҲҒҷҒv
”ьҚзӮНҸОҠзӮЕҢҫӮБӮҪҒB
ғqғhғCӮИӮҹҒAҠmӮ©ӮЙӮ ӮМҚ ӮМ–lӮНғoғJӮИӮұӮЖӮаӮвӮБӮДӮўӮҪӮҜӮкӮЗҒA–lӮҫӮБӮДӮ ӮкӮ©ӮзӮ»ӮкӮИӮиӮЙҠж’ЈӮБӮҪӮВӮаӮиӮҫҒBӮЬӮҹҒAӮ»ӮкӮЕ”ьҚзӮӘҸОӮБӮДӮӯӮкӮйӮИӮзҒA‘S‘RӮўӮўӮсӮҫӮҜӮЗҒB
ҒuӮЕӮаҒA”ьҚзӮНӮ©ӮИӮи•ПӮнӮБӮҪӮЛҒAӮИӮсӮДӮўӮӨӮ©ӮұӮӨҒAгY—нӮЙӮИӮБӮҪҒBӮаӮө”ьҚзӮӘҳbӮөӮ©ӮҜӮДӮӯӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮзҒAҗв‘ОӢCӮГӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒv
ҒuӮЁҒAӮЁҗўҺ«ӮЕҢл–Ӯү»Ӯ»ӮӨӮЖӮөӮҪӮБӮДҒ\Ғ\Ғ\Ғv
ҸӯӮөҸЖӮкӢC–ЎӮЙҢҫӮБӮҪ”ьҚзӮМҢҫ—tӮрҺХӮБӮД–lӮНҗі’јӮЙҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮЁҗўҺ«Ӯ¶ӮбӮИӮӯӮДҒAғzғ“ғgҒB–lҒAҚЎӮМ”ьҚзӮӯӮзӮўүВҲӨӮўҺqҒAӮ ӮсӮЬӮиҢ©ӮҪӮұӮЖ–іӮўӮжҒHҒv
—Rҗ^ӮЖӮўӮӨ—бҠOӮӘӮўӮйӮҜӮЗӮЛҒB
ҒuӮЩҒA–JӮЯӮҪӮБӮДҺ„ҒAүҪӮЙӮаҸo—ҲӮИӮўӮжҒIҒv
ҸЖӮкӮДӮ»ӮБӮЫӮрҢьӮўӮҪ”ьҚзӮрҢ©ӮДҒA–lӮНҚKӮ№ӮрҺАҠҙӮөӮҪҒB–ІӮЙӮЬӮЕӮЭӮҪҢхҢiӮҫҒBҺ©‘RӮЖҠзӮӘҠЙӮсӮЕӮөӮЬӮӨҒB
ҒuүҪғjғ„ғjғ„ӮөӮДӮйӮМӮжҒIҒ@ӮаӮӨҒIҒv
”ьҚзӮН‘Ғ‘«ӮЕ•аӮ«ҸoӮөӮҪҒB
ӮЬӮБӮҪӮӯҒAӮЗӮұӮЙҚsӮӯӮМӮ©ӮнӮ©ӮБӮДӮйӮМӮ©ҒB–lӮа‘Ғ‘«ӮЕ”ьҚзӮр’ЗӮБӮҪҒB
ҒuӮЖӮұӮлӮЕ”ьҚзҒAӮ№ӮБӮ©ӮӯҸгӢһӮөӮД—ҲӮҪӮсӮҫӮөҒAүҪӮ©—~ӮөӮў•ЁӮЖӮ©ӮИӮўӮМҒHҒv
Ғu—~ӮөӮўӮаӮМҒcҒcҒAҺФҒIҒv
ҒuҒcҒcӮЬӮёӮН–ЖӢ–ӮрҺжӮлӮӨӮЛҒv
ҺФӮЛҒAӮЬӮ ”ьҚзӮӘҺФӮЙҸжӮйҚОӮЙӮИӮБӮҪӮз”ғӮБӮДӮ Ӯ°ӮДӮаӮўӮўӮҜӮЗҒB
ҒuӮ»ӮӨӮўӮҰӮОӮЁҢZӮҝӮбӮсӮБӮДҺФҺқӮБӮДӮйӮМҒHҒv
ҒuӮсҒHҒ@Ӯ Ӯ ҒAӮ ӮйӮҜӮЗҒcҒc•аӮӯӮМ”жӮкӮҪҒHҒv
ҒuӮӨӮӨӮсҒAӮҪӮҫ•·ӮўӮДӮЭӮҪӮҫӮҜҒv
ӮЬӮҹ—Rҗ^ӮМҸжӮБӮДӮйӮжӮӨӮИҗҰӮўӮМӮЕӮНӮИӮўӮҜӮЗӮЛҒB
ҒuӮНӮНҒAҚЎ“ъӮНҠX’ҶӮрҗFҒXүсӮйӮВӮаӮиӮҫӮБӮҪӮ©ӮзҒAҺФӮҫӮЖҗFҒX•s•ЦӮИӮсӮҫҒBӮІӮЯӮсӮЛҒB”жӮкӮҪӮИӮзӮЗӮұӮ©ӮЁ“XӮЙҒ\Ғ\Ғv
ҒuӮ ҒAӮ ӮкӮ©ӮнӮўӮўҒv
”ьҚзӮіӮсҒAҗlӮМҳb•·ӮұӮӨӮжҒcҒcҒBӮЬӮҹҒAӮўӮўӮсӮҫӮҜӮЗӮЛҒA•КӮЙҒB
”ьҚзӮНҸ—•ЁӮМ•һү®ӮМғVғҮғEғEғBғ“ғhғEӮЙ’ЈӮи•tӮўӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҚЎ“ъӮН’иӢx“ъӮИӮМӮ©ӮЁ“XӮМ“ьӮиҢыӮЙӮНӮbӮkӮnӮrӮdӮcӮМҺDӮӘүәӮӘӮБӮДӮўӮҪҒBғVғҮғEғEғBғ“ғhғEӮМ•һҒA”ғӮБӮДӮ Ӯ°ӮҪӮўӮҜӮЗҒAӮЬӮҹҒA•һү®ӮН•Ҫ“ъӢxӮЭӮӘ•Ғ’КӮҫӮөӮЛҒBӮөӮеӮӨӮӘӮИӮўҒB
Ғu”ьҚзҒA•һҒA—~ӮөӮўӮМҒHҒv
ҚlӮҰӮДӮЭӮкӮО”ьҚзӮНҺ{җЭ•йӮзӮөӮҫҒBҺ„•һӮИӮсӮДӮ ӮсӮЬӮиҺқӮБӮДӮўӮИӮўӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮҫӮлӮӨӮ©ҒHҒ@”NҚ ӮМҸ—ӮМҺqӮИӮсӮҫӮөҒAӮвӮБӮПӮиғIғVғғғҢӮЙӮНӢ»–ЎӮ ӮйӮЖҺvӮӨӮсӮҫӮҜӮЗҒB
ҒuӮҰҒAӮЧҒA•КӮЙӮўӮзӮИӮўӮҜӮЗҒHҒv
–ЪӮрҚҮӮнӮ№ӮжӮӨӮЖӮөӮИӮўҒBҸ—ӮМҺqӮНүRӮрӮВӮӯӮЖӮ«ӮН‘ҠҺиӮМ–ЪӮрӮөӮБӮ©ӮиҢ©ӮйӮЖӮўӮӨӮҜӮЗҒA”ьҚзӮНӮЬӮҫӮ»ӮкӮӘҸo—ҲӮИӮўӮжӮӨӮҫҒBӮ»ӮкӮЙ–ҫӮзӮ©ӮЙ–ЪӮӘғVғҮғEғEғBғ“ғhғEӮЙӮўӮБӮДӮйӮөҒB
Ӯ»ӮӨӮўӮҰӮО—Rҗ^ӮМғfҒ[ғgғRҒ[ғXғҒғӮӮЙӮаүw‘OӮМғfғpҒ[ғg“аӮЙӮ Ӯй•һү®ӮЙҚsӮҜӮБӮДҸ‘ӮўӮДӮ ӮБӮҪҒBӮ Ӯ»ӮұӮН—FҗlӮӘӢОӮЯӮДӮўӮйӮ©Ӯз–lӮаӮжӮӯ‘«Ӯрү^ӮФҒAӮЖӮўӮӨӮ©ҒAҚЕӢЯӮЕӮН–lӮМ•һӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮ»ӮұӮЕ”ғӮБӮДӮўӮйҒBӮ Ӯ»ӮұӮИӮзҸ—ӮМҺqӮМ•ЁӮаӮҪӮӯӮіӮс’uӮўӮДӮ ӮйӮөҒA”ьҚзӮаӮ«ӮБӮЖӢCӮЙ“ьӮйӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӮЛӮҘ”ьҚзҒA•һӮӘ—~ӮөӮўӮИӮзүw‘OӮМғfғpҒ[ғgӮЙ–lӮМ—F’BӮӘӢОӮЯӮДӮўӮй•һү®ӮіӮсӮӘӮ ӮйӮсӮҫӮҜӮЗҒAҚsӮБӮДӮЭӮйҒHҒv
ҒuӮҰҒAӮҫҒAӮҫӮ©ӮзӮўӮзӮИӮўӮБӮДҒcҒcҒv
ҒuӮӨӮсҒAӮЕӮа–lҒAӮ»ӮлӮ»ӮлҸt•ЁӮМ•һӮр”ғӮўӮҪӮўӮЖҺvӮБӮДӮҪӮсӮҫҒBӮ№ӮБӮ©ӮӯҗVҸhӮЬӮЕ—ҲӮДӮйӮсӮҫӮөҒAӮВӮўӮЕӮҫӮ©Ӯз”ғӮБӮДӮўӮұӮӨӮЖҺvӮБӮДҒBҲ«ӮўӮҜӮЗҒA•tӮ«ҚҮӮБӮДӮӯӮкӮйҒHҒv
–lӮНҸt•ЁӮМ•һӮИӮсӮДҒAҗМ—Rҗ^’BӮЙҸa’JӮвҢҙҸhӮрҳAӮкӮЬӮнӮіӮкӮҪӮЖӮ«ҒAҢьӮұӮӨүҪ”NӮаҸt•һӮЙӮНҚўӮзӮИӮўӮӯӮзӮў”ғӮнӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮҫӮ©ӮзӮұӮкӮН”ьҚзӮрғfғpҒ[ғgӮЙҳAӮкӮДҚsӮӯӮҪӮЯӮМүRӮҫҒB”ьҚзӮЙӮаӮ»ӮкӮНӮнӮ©ӮБӮДӮўӮйӮҫӮлӮӨҒBӮЕӮаҒAӮұӮӨӮўӮӨҢҫӮў•ыӮрӮ·ӮкӮОҒ\Ғ\ҒB
ҒuӮ»ҒAӮ»ӮкӮИӮзӮўӮўӮҜӮЗҒcҒcҒv
”ьҚзӮНҸaҒXӮИӮӘӮз“ҜҲУӮөӮДӮӯӮкӮҪҒB
ҒuӮЁҒ[ҒAҗSҢмҒA‘ТӮБӮДӮҪӮжҒ[Ғv
ӮЁ“XӮЙ“ьӮйӮИӮиҒAӮўӮ©ӮЙӮаҒuҺdҺ–ӮН•һҸьҠЦҢWӮЕӮ·ҒIҒvӮЖӮўӮБӮҪҠҙӮ¶ӮМғIғVғғғҢӮИ’jӮӘ–lӮЙҗәӮрӮ©ӮҜӮДӮ«ӮҪҒB—FҗlӮМҚ]ҚиҲІӮҫҒB
ҒuҲІҒAӢvӮөӮФӮиҒB‘ТӮБӮДӮҪӮБӮДҒHҒv
ҒuӮўӮвӮҹҒA—Rҗ^ӮҝӮбӮсӮ©Ӯз“dҳbӮӘӮ ӮБӮДӮіҒAҚЎ“ъҗSҢмӮӘ”ьҚзӮҝӮбӮсӮрҳAӮкӮДҒ\Ғ\ӮБӮДӮӨӮ§Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ ғbҒIҒv
ҒuӮЗҒAӮЗӮӨӮөӮҪ!?Ғv
ҲІӮӘҳbӮМ“r’ҶҒA”ьҚзӮЙ–ЪӮрӮвӮБӮҪҸuҠФӢ©ӮСӮҫӮөӮҪҒB”ьҚзӮНғrғbғNғҠӮөӮД–lӮМҢгӮлӮЙүBӮкӮДғXҒ[ғcӮМ‘іӮр’НӮсӮҫҒB
ҒuӮҰҒIҒ@ӮұӮМҺq”ьҚзӮҝӮбӮсҒHҒ@Ҹ«—Ҳ”ьҗlӮЙӮИӮйӮЖӮНҺvӮБӮДӮҪӮҜӮЗғ}ғWҒHҒ@ӮЛӮҘғ}ғWӮИӮМӮЁҢZӮіӮсҒHҒ@’ҙ”ьҸӯҸ—Ӯ¶ӮбӮсҒIҒ@ӮЗӮсӮҫӮҜӮҘҒ[ҒIҒv
Ӯ Ӯ ҒAӮИӮйӮЩӮЗҒBҲІӮӘӮұӮӨӮИӮйӮМӮаӮнӮ©ӮйҒBҲІӮН”ьҸ—ӮрҢ©ӮйӮЖғeғ“ғVғҮғ“ӮӘҸгӮӘӮйӮМӮҫҒB
ҒuӮўӮвӮҹҒAӮСӮБӮӯӮиӮөӮҪҒBӮІӮЯӮсӮЛ”ьҚзӮҝӮбӮсҒAӢБӮ©Ӯ№ӮДҒv
ҒuӮўҒAӮўӮҰҒA•КӮЙҒcҒcҒv
”ьҚзӮНҺбҠұ‘ЮӮўӮДӮўӮйҒB
ҒuӮҰҒ[ӮЖҒAҲкүһҺ©ҢИҸРүоӮрӮөӮДӮЁӮұӮӨӮ©ҒBүҙӮНҚ]ҚиҲІҒBҗSҢмӮЖӮН’Ҷ–VӮМҺһӮ©ӮзӮМ•tӮ«ҚҮӮўӮЕҒA”ьҚзӮҝӮбӮсӮЖӮаүҪ“xӮ©үпӮБӮҪӮұӮЖӮ ӮйӮҜӮЗҒA”ьҚзӮҝӮбӮсӮНӮЬӮҫҸ¬ӮіӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзҠoӮҰӮДӮИӮўӮжӮЛҒHҒv
ҒuӮҰӮЖҒAӮ ӮМҒAӮНӮўҒAҠoӮҰӮДӮИӮўӮЕӮ·ҒcҒcҒv
ҒuӮ ӮБӮНӮБӮНӮБӮНӮБҒIҒ@•КӮЙӮўӮўӮсӮҫӮжҠoӮҰӮДӮИӮӯӮДӮаҒIҒ@ӮұӮкӮ©ӮзӮжӮлӮөӮӯӮЛҒIҒv
ҒuӮНӮўҒAӮжӮлӮөӮӯӮЁҠиӮўӮөӮЬӮ·Ғv
ҒuӮӨӮсҒAӮ¶ӮбӮ үҙӮҝӮеӮБӮЖҳbӮ·ӮұӮЖӮӘӮ ӮйӮ©ӮзӮЁҢZӮіӮсҺШӮиӮйӮжҒHҒ@ӮҝӮеӮБӮЖӮМҠФҒA•һӮЕӮаҢ©ӮДӮДҒHҒv
ҒuӮ ҒAӮНӮўҒBӮ¶ӮбӮ ӮЁҢZӮҝӮбӮсҒAӮҝӮеӮБӮЖҢ©ӮДӮӯӮйҒv
”ьҚзӮНғҢғfғBҒ[ғXӮМғRҒ[ғiҒ[ӮЙҢьӮ©ӮБӮДӮўӮБӮҪҒB
ҲІӮН”ьҚзӮЦӮМҲҘҺAӮрҚПӮЬӮ·ӮЖ–lӮЙҢьӮ«’јӮБӮҪҒB
ҒuӮўӮвӮҹӢБӮўӮҪҒB—Rҗ^ӮҝӮбӮсӮЙҸҹӮйӮЖӮа—тӮзӮИӮў”ьҸ—ӮӘӮЬӮҪүҙӮМ‘OӮЙҢ»ӮкӮҪҒBӮұӮкӮНҚЕ‘Ғү^–ҪӮЖҢДӮФӮЧӮ«Ӯ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮЛҒHҒ@ӮЁӢ`ҢZӮіӮсҒHҒv
Ғu’NӮӘӮЁӢ`ҢZӮіӮсӮҫҒHҒ@ӮУӮҙӮҜӮҪӮұӮЖҢҫӮБӮДӮйӮЖӮФӮБҺEӮ·ӮжҒHҒv
–lӮН—вӮҪӮўҸОҠзӮЖ“ҖӮБӮҪ“өӮЕҲІӮрбЙӮЭӮВӮҜӮҪҒB
ҒuӮӨӮнӮБҒAӢ°ғbҒIҒ@Ҹз’kӮЕӮ·ӮжҒ`ӮЁҢZӮіӮсҒv
ҒuӮУӮсҒAӮЕҒHҒ@ӮіӮБӮ«—Rҗ^ӮӘӮЗӮӨӮЖӮ©ҢҫӮБӮДӮИӮ©ӮБӮҪҒHҒv
ҒuӮ Ӯ ҒAҲкҚр“ъ—Rҗ^ӮҝӮбӮсӮ©Ӯз“dҳbӮӘӮ ӮБӮДӮіҒAҒw”ьҚзӮҝӮбӮсӮНӮ«ӮБӮЖ”ьҗlӮЙӮИӮБӮДӮйӮ©ӮзҒAӮ ӮМ”NҚ ӮМҸ—ӮМҺqӮЙҺ—ҚҮӮўӮ»ӮӨӮИғ„ғcӮўӮӯӮВӮ©ғsғbғNғAғbғvӮөӮЖӮўӮДҒB’l’iӮНҢӢҚ\’ЈӮБӮДӮаӮўӮўӮЖҺvӮӨҒBӮЮӮөӮлҗSҢмӮМҚа•zӮрғJғүӮЙӮ·ӮйҗЁӮўӮЕҚӮӮў•Ё‘IӮсӮ¶ӮбӮБӮДӮўӮўӮ©ӮзҒxӮБӮДҒBӮҫӮ©ӮзӮўӮӯӮВӮ©ӮаӮӨ‘IӮсӮЗӮўӮҪӮсӮҫӮҜӮЗҒcҒcҒv
ӮіӮ·ӮӘ—Rҗ^ӮҫҒBҺиүсӮөӮӘ‘fҗ°ӮзӮөӮўҒBӮБӮДӮўӮӨӮ©ғzғ“ғgҒAӮўӮӯӮзҠҙҺУӮөӮДӮаӮө‘«ӮиӮИӮўӮЕӮ·ҒBғnғCҒB
–lӮНӮаӮӨҲкҗ¶”ЮҸ—ӮЙ‘«ӮрҢьӮҜӮДҗQӮзӮкӮИӮўӢCӮӘӮ·ӮйҒB
ҒuӮ»ӮБӮ©ҒAӮ ӮиӮӘӮЖҒBҲІҒv
ҒuӮ Ӯ ҒAӮўӮўӮжҒBӮұӮБӮҝӮНҸӨ”„”Йҗ·ӮҫӮөҒBӮЁ’l’iӮМ•ыӮНӮЁ‘OӮМҚа•zӮӘ•sңаӮЕӮИӮзӮИӮўӮжҒHҒv
ҒuӮҰҒAӮ»ӮсӮИӮЙҒHҒv
ҒuӮЬӮҹҒAҢӢҚ\җFӮсӮИғuғүғ“ғhӮЕ‘өӮҰӮҪӮ©ӮзӮЛӮҘҒBӮӨӮҝӮМ“XӮМғIғҠғWғiғӢӮҫӮҜӮБӮДӮМӮағAғҠӮҫӮБӮҪӮсӮҫӮҜӮЗҒAӮЁ‘OӮМҚа•zғJғүӮЙӮөӮДӮўӮўӮБӮДҢҫӮнӮкӮҪӮ©ӮзҚӮӮўӮМӮаү“—¶ӮИӮӯ‘IӮОӮ№ӮДӮўӮҪӮҫӮўӮҪҒҷҒv
бҝӮөӮўҸОҠзӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ»ҒAӮ»ӮӨҒAӮЬҒAӮЬӮҹӮўӮўӮҜӮЗӮЛҒB”ьҚзӮӘҠмӮсӮЕӮӯӮкӮкӮОҒA–lӮНӮ»ӮкӮЕӮўӮўӮөҒcҒcҒv
ҒuӮЁҒ[—§”hӮҫӮЛӮҘӮЁҢZӮіӮсҒBӮЁ’l’iӮН–сҸ\Һl–ңӮЩӮЗӮЙӮИӮиӮЬӮ·ӮӘӮжӮлӮөӮўӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHҒv
ҒuӮ¶ӮгҒAӮ¶ӮгӮӨӮжҒIҒ@ҒcҒcӮ©ҒAғJҒ[ғhӮЕӮўӮўҒHҒv
Ҹ\Һl–ңү~ҒcҒcҒBҚЎ“ъӮН”ьҚзӮМӮҪӮЯӮЙӮИӮзӮўӮӯӮзҺgӮБӮДӮаӮўӮўӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪӮҜӮкӮЗҒAӮўӮ«ӮИӮиҸ\–ң’PҲКӮМ”ғӮў•ЁӮЙӮИӮйӮЖӮНҒcҒcҒBҲкүһҚа•zӮМ’ҶӮЙӮНӮ»ӮкӮӯӮзӮў“ьӮБӮДӮўӮйӮҜӮЗҒAӮұӮМҢгҗHҺ–ӮЙӮаҚsӮӯӮҫӮлӮӨӮөҒA”ьҚзӮрҗFӮсӮИҸҠӮЙҳAӮкӮДҚsӮБӮДӮ Ӯ°ӮҪӮўҒBӮҫӮ©ӮзҢ»ӢаӮНҺgӮнӮёҒAғJҒ[ғhӮЕҺx•ҘӮӨӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒB
Ғu–Ҳ“xӮ ӮиҒ`ҒIӮЖҒAӮўӮўӮҪӮўӮЖӮұӮҫӮҜӮЗҒAӮЬӮёӮН”ьҚзӮҝӮбӮсӮЙҺҺ’…ӮөӮДӮаӮзӮнӮИӮўӮЖҒBӮ ӮМғӢғbғNғXӮҫӮөҒAүҪ’…ӮДӮаҺ—ҚҮӮӨӮМӮНҠmҺАӮҫӮҜӮЗҒAғTғCғYӮМӮұӮЖӮаӮ ӮйӮөҒAӮЖӮиӮ ӮҰӮё’…ӮДӮаӮзӮнӮИӮўӮЖҒAӮИҒHҒv
ҒuӮ·ӮІӮБҒIҒ@ҺGҺҸӮЙҚЪӮБӮДӮйғ„ғcӮҫҒIҒ@Ӯ«ӮбҒ[ҒIҒv
ғҢғfғBҒ[ғXӮМғRҒ[ғiҒ[ӮЙ—ҲӮйӮЖ”ьҚзӮӘҸ—җ«“XҲхӮЖ‘еӮНӮөӮбӮ¬ӮЕ•һӮрҺҺ’…ӮөӮЬӮӯӮБӮДӮўӮҪҒB
“XҲхӮіӮсӮа‘fҚЮӮМӮўӮў”ьҚзӮЙҗFҒX’…Ӯ№ӮДҠyӮөӮсӮЕӮўӮйӮжӮӨӮҫҒB
”ьҚзӮӘҠyӮөӮ»ӮӨӮҫҒBҗМӮМҸОӮӨӮұӮЖӮМӮИӮ©ӮБӮҪ”ЮҸ—Ӯ©ӮзӮНҚlӮҰӮзӮкӮИӮўҒB–lӮН”ьҚзӮМӮұӮсӮИҠзӮӘҢ©ӮзӮкӮй“ъӮр‘ТӮҝ–]ӮсӮЕӮўӮҪҒBҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮДӮжӮ©ӮБӮҪҒB‘еҢUҚҫӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮҜӮЗӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮЬӮЕҚlӮҰӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB
ҒuӮЁҺoӮіӮсҒIҒ@ӮұӮк’…ӮДӮЭӮДӮаӮўӮўӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
ҒuӮ ҒAӮ»ӮкӮЕӮөӮҪӮзӮұӮБӮҝӮМғvғҠҒ[ғcғXғJҒ[ғgӮЖӮ ӮнӮ№ӮДӮЭӮДӮНӮўӮ©ӮӘӮЕӮөӮеӮӨҒHҒv
ҒuӮ ҒAүВҲӨӮўӮ©ӮаҒIҒv
”ьҚзӮЖ“XҲхӮіӮсӮНӮИӮсӮЖӮўӮӨӮ©ҒAҸ—ӮМҺqӮМүпҳbӮЙ–І’ҶӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒB”ьҚзӮӘҠyӮөӮ»ӮӨӮЙҗlӮЖҳbӮөӮДӮўӮйӮМӮрҢ©ӮйӮМӮНҸүӮЯӮДӮҫҒB–lӮНҠрӮөӮӯӮИӮБӮҪҒB
–lӮН”ьҚзӮЙ—F’BӮӘӮўӮйӮМӮ©ӮЗӮӨӮ©Ӯ·Ӯз’mӮзӮИӮўҒBӮ»ӮкӮНҚЎӮаӮ»ӮӨӮҫӮҜӮкӮЗҒAҗМӮ©ӮзӮҫҒBҗМҒAӮЬӮҫ–lӮЖ”ьҚзӮӘ“sҺs•УүҸӮМғAғpҒ[ғgӮЙҲкҸҸӮЙҸZӮсӮЕӮўӮҪҚ ҒA–lӮН”ьҚзӮЙ–іҠЦҗSӮҫӮБӮҪҒBӮЖӮўӮӨӮжӮиҒAӢCӮЙӮ©ӮҜӮДӮНӮўӮҜӮИӮўӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪҒBӮҫӮ©Ӯз”ЮҸ—ӮӘҠwҚZӮЕӮЗӮсӮИ•—ӮЙҗ¶ҠҲӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮИӮсӮДӮнӮ©ӮзӮИӮўҒB–lӮМ’mӮБӮДӮўӮй”ьҚзӮНӮҪӮҫ•”ү®ӮМӢчӮМ•ыӮЕғKғ^ғKғ^ӮЖҗkӮҰӮДӮўӮйӮҫӮҜҒBӮўӮВӮа•кӮіӮсӮЙӢҜӮҰӮДӮўӮйҒAӮ»ӮсӮИӮЖӮұӮлӮөӮ©ҠoӮҰӮДӮўӮИӮўҒB
–lӮНҗМӮрҺvӮўҸoӮ·“xҒAҺ©•ӘӮрҺфӮБӮҪҒB–іҠЦҗSӮЕӮўӮҪҺ©•ӘӮӘӢ–Ӯ№ӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒiӮ»ӮсӮИӮұӮЖҢҫӮБӮҪӮБӮДҒAҺd•ыӮИӮўӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒB–lӮӘ”ьҚзӮр”ЭӮБӮҪӮзҒA”ьҚзӮНӮаӮБӮЖҚ“Ӯў–ЪӮЙӮ ӮӨӮсӮҫӮ©ӮзҒj
Ӯ»ӮсӮИҢҫӮў–уӮӘӮ·Ӯ®ҢыӮрӮВӮўӮДҸoӮйӮМӮаӢ–Ӯ№ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮ¶ӮбӮИӮўҒBҚЎӮИӮзӮнӮ©ӮйҒBӮҪӮЖӮҰӮ»ӮМҸкҢАӮиӮЕӮаҒAҺ©•ӘӮр”ЭӮБӮДӮӯӮкӮҪҗlӮӘӮўӮйӮЖӮўӮӨӮҫӮҜӮЕӮ»ӮкӮНҺxӮҰӮЙӮИӮйҒBӮаӮө–lӮӘ”ьҚзӮрҢ©ҺМӮДӮИӮ©ӮБӮҪӮзҒA”ьҚзӮМҗSӮНүуӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮсӮҫҒB
ҒuӮЁҒAӮЁҢZӮҝӮбӮсҒIҒv
”ьҚзӮӘ–lӮЙӢCӮӘ•tӮўӮҪӮжӮӨӮҫҒB
Ғu”ьҚзҒAҠyӮөӮ»ӮӨӮҫӮЛҒBӢCӮЙ“ьӮБӮҪӮМӮ ӮБӮҪҒHҒv
–lӮНүAҹTӮИҺvҚlӮрҗШӮиҸгӮ°ӮДҸОҠзӮЕҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮҪҒAҠyӮөӮўӮжҒA’…ӮйӮҫӮҜӮИӮзғ^ғ_ӮҫӮөҒcҒcҒv
ҒuӮНӮНҒAӢCӮЙ“ьӮБӮҪӮМӮӘӮ ӮБӮҪӮИӮзҒA”ғӮБӮДӮ Ӯ°ӮйӮжҒv
ҒuӮўҒAӮўӮўӮжҒBҚӮӮўӮөҒA•һӮИӮсӮД•КӮЙ’…ӮкӮкӮОӮИӮсӮҫӮБӮДҒcҒcҒv
ӮвӮБӮПӮиӮ©ҒB”ьҚзӮН’l’iӮрӢCӮЙӮөӮДӮўӮйӮЭӮҪӮўӮҫҒBҠmӮ©ӮЙӮұӮМӮЁ“XӮНҢ|”\җlӮа‘«Ӯрү^ӮФӮжӮӨӮИӮЁ“XӮҫҒB’l’iӮНӮЗӮкӮаҸҺ–ҜӮМҠҙҠoӮжӮиӮНҚӮӮЯӮЙҗЭ’иӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮкӮЙ”ьҚзӮНҺ{җЭ•йӮзӮөӮӘ’·ӮўӮөҒAӮӨӮҝӮНҢіҒX—T•ҹӮ¶ӮбӮИӮ©ӮБӮҪҒBӢа‘KҠҙҠoӮНҸҺ–ҜӮМӮ»ӮкӮжӮиӮіӮзӮЙғVғrғAӮИӮсӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӮНӮБӮНӮБӮНӮБӮНӮБҒA”ьҚзӮҝӮбӮсҒAӢаӮИӮзӢCӮЙӮөӮИӮӯӮДӮўӮўӮжҒv
ҲІӮӘҢыӮрӢІӮсӮҫҒBҲІӮЯҒAӮ»ӮкӮН–lӮМғZғҠғtӮҫҒB
ҒuҗSҢмӮМғ„ғcҒAҚЎӮв”тӮФ’№ӮрӮіӮзӮЙ”тӮОӮ·җЁӮўӮЕӢаҺқӮҝҠX“№Ӯр”ҡҗi’ҶӮҫӮ©ӮзӮіҒҷҒ@ӮўӮӯӮзҺgӮБӮДӮа—Nҗ…ӮМӮІӮЖӮӯ—NӮ«Ӯ ӮӘӮБӮДӮӯӮйӮсӮҫӮжҒIҒ@ӮИӮҹҒHҒ@җSҢмҒHҒv
ӮИӮсӮҫӮ»ӮкӮНҒcҒcҒBҠmӮ©ӮЙ“Ҝҗў‘гӮМүТӮ¬ӮМ•ҪӢПӮжӮиӮНҸгӮҫӮЖҺvӮӨӮҜӮЗҒAӮ»ӮкӮНҢҫӮўӮ·Ӯ¬ӮҫӮжҒAҲІҒBӮЁӢаӮБӮДҒA’ҷӮЯӮйӮМӮН‘е•ПӮҫӮҜӮЗҒAҺgӮӨӮЖӮ·Ӯ®–іӮӯӮИӮйӮсӮҫҒB
ӮЕӮаҒAҚЎ“ъӮН”ьҚзӮМӮҪӮЯӮЙӮИӮзӮўӮӯӮзҺgӮБӮДӮаӮўӮўҒBҚЕҸүӮ©ӮзӮ»ӮӨӮўӮӨӮВӮаӮиӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ»ӮсӮИӮнӮҜӮИӮўӮҫӮлҒAғoғJҲІҒBҒ\Ғ\ӮЕӮаҒA”ьҚзӮЙӮҝӮеӮБӮЖғuғүғ“ғh•ЁӮМ•һӮр”ғӮБӮДӮ Ӯ°ӮйӮӯӮзӮўӮМ—]—TӮНӮ ӮйӮВӮаӮиӮҫӮжҒv
–lӮНӮіӮБӮ«Ӯ©ӮзҺиӮЙҺқӮБӮҪ•һӮрғ`ғүғ`ғүҢ©ӮИӮӘӮзӢ““®•sҗRӮИ”ьҚзӮЙҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮЕҒAӮЕӮаҒcҒcҒv
ӮЮҒAӮИӮ©ӮИӮ©ӢӯҸоӮҫҒBӮЕӮаӮаӮӨҲкүҹӮөӮИҠҙӮ¶ӮЕӮНӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮИӮзҒ\Ғ\ҒB
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒA’ҶҠwӮМ‘ІӢЖҸjӮўӮБӮДӮұӮЖӮЕӮЗӮӨҒHҒ@–lӮНӮЬӮҫ”ьҚзӮЙүҪӮаӮ Ӯ°ӮДӮИӮўӮөҒBӮ»ӮкӮИӮзӮўӮўӮЕӮөӮеҒHҒv
”ьҚзӮН–lӮЖҺиӮЙҺқӮБӮҪғҸғ“ғsҒ[ғXӮрҢрҢЭӮЙҢ©ӮДҒAӮЁӮёӮЁӮёӮЖҢыӮрҠJӮўӮҪҒB
Ғuғzғ“ғgӮЙҒcҒcӮўӮўӮМҒHҒv
ӮЎӮжӮөӮБҒI—ҺӮҝӮҪҒI
ҒuӮӨӮсҒA‘IӮсӮЕӮЁӮўӮЕҒv
ҒuӮ¶ӮбҒAӮ¶ӮбӮ Ҳк’…ӮҫӮҜҒcҒcҒv
”ғӮӨӮЖҢҲӮЬӮйӮЖ”ьҚзӮНӮӯӮйӮӯӮйӮЖҗFӮсӮИ•һӮрҢ©ӮДҒAҺиӮЙҺқӮБӮҪ”’ӮўғҸғ“ғsҒ[ғXӮЖҢ©”дӮЧӮДӮўӮҪҒB
ҒuӮ ӮБӮҝӮМӮаӮўӮўӮөҒ`ҒAӮұӮБӮҝӮМӮаҒ`ҒAӮ Ғ`ӮЕӮаӮвӮБӮПӮиӮұӮкӮӘӮўӮўӮ©ӮИӮҹҒ`ҒAӮвҒAӮЕӮаӮвӮБӮПӮиҒ`Ғv
–АӮБӮДӮйӮИӮҹҒB•КӮЙҲк’…ӮҫӮҜӮ¶ӮбӮИӮӯӮДӮаӮўӮўӮсӮҫӮҜӮЗҒB
–ЪӮЬӮ®ӮйӮөӮӯ•ПӮнӮй”ьҚзӮМ•\ҸоӮНҢ©ӮДӮўӮД–OӮ«ӮИӮўҒB
җМҒAӢ°•|ӮЙҲшӮ«ӮВӮБӮҪҠзӮЕӢғӮўӮДӮўӮйӮОӮ©ӮиӮҫӮБӮҪ”ЮҸ—Ӯ©ӮзӮН‘z‘ңӮЕӮ«ӮИӮўҒBӮҪӮҫ•һӮр”ғӮӨӮҫӮҜӮЕӮ ӮсӮИӮЙ–АӮБӮДүEүқҚ¶үқӮ·ӮйҺpӮНӮЗӮұӮ©ӮзӮЗӮӨҢ©ӮДӮа•Ғ’КӮМҸ—ӮМҺqӮМӮ»ӮкӮҫҒB
ҒuӮ Ғ`ӮвӮБӮПӮиӮұӮкӮ©ӮИӮҹҒv
ӮЗӮӨӮвӮзҢҲӮЬӮБӮҪӮзӮөӮўҒBӮ»ӮұӮЙҲІӮӘ—Rҗ^ӮМ—ҠӮЭӮЕғsғbғNғAғbғvӮөӮДӮЁӮўӮҪ•һӮМҲк‘өӮўӮрҺқӮБӮДӮўӮБӮҪҒBӮЗӮӨӮвӮзҺҺ’…ӮіӮ№ӮйӮЭӮҪӮўӮҫҒB
ӮөӮ©ӮөҒAӮИӮ©ӮИӮ©ҺиӮІӮнӮ©ӮБӮҪӮИҒBҢZӮӘ–…ӮЙ•һӮр”ғӮБӮДӮ Ӯ°ӮйӮӯӮзӮў•Ғ’КӮМӮұӮЖӮҫӮЖҺvӮӨӮсӮҫӮҜӮЗҒcҒcҒBү“—¶ӮіӮкӮЬӮӯӮиҒBӮвӮБӮПӮиҒAӮЬӮҫү“ӮўӮМӮ©ӮИҒcҒcҒB
ҒuҒcҒcҒv
•sҠoӮЙӮаҢ©ҚӣӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҲІӮНҠпҗәӮрҸгӮ°ӮДӮўӮҪҒB
ҺҺ’…ҺәӮ©ӮзҸoӮДӮ«ӮҪ”ьҚзӮН–lӮӘғҢғfғBҒ[ғXӮМғRҒ[ғiҒ[ӮЙ—ҲӮҪ“–ҸүӮ©ӮзҺқӮБӮДӮўӮҪ”’ӮўғmҒ[ғXғҠҒ[ғuӮМғҸғ“ғsҒ[ғXӮр’…ӮДӮўӮҪҒB
ҒuҗҰӮўӮИҒA”ьҚзӮҝӮбӮсҒAҗF”’ӮўӮөҒAҚЧӮўӮ©ӮзғSғVғbғNҢnӮағCғPӮйӮсӮ¶ӮбӮЛҒHҒv
ҒuӮ ҒIҒ@ӮўӮўӮЛҒA’…Ӯ№ӮжӮӨ’…Ӯ№ӮжӮӨҒIҒv
ҲІӮЖ“XҲхӮіӮсӮӘҠyӮөӮ»ӮӨӮЙ•һӮр‘IӮСӮЙӮўӮБӮҪҒB
ҒuӮЁҢZӮҝӮбӮсҒHҒv
ҚӣӮҜӮДӮўӮҪ–lӮЙ”ьҚзӮӘҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮҰҒAӮИҒAӮИӮЙҒHҒv
–lӮНҚQӮДӮД•ФҺ–ӮрӮөӮҪҒB
ҒuӮЗӮӨҒHҒ@Һ—ҚҮӮӨҒHҒv
”ьҚзӮӘӮРӮзӮиӮЖүсӮБӮДҢ©Ӯ№ӮҪҒBӮ»ӮМҺһ–lӮМ–ЪӮН”ьҚзӮМҳrӮЙӮ ӮМҸқӮрҢ©ӮВӮҜӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB•кӮіӮсӮЙҺhӮіӮкӮҪҸқӮҫҒB
ҒiҚӯҒAӮвӮБӮПӮиҺcӮБӮҝӮбӮБӮҪӮсӮҫҒj
”ьҚзӮМ”’Ӯў”§ӮЙҒAӮ»ӮкҲИҠOӮМҸқӮНҢ©“–ӮҪӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB‘јӮМ–\ҚsӮЕӮВӮҜӮзӮкӮҪб{ӮвҸқӮНгY—нӮЙҸБӮҰӮҪӮЭӮҪӮўӮҫҒBӮ ӮМҺhӮөҸқӮЙӮөӮҪӮБӮДҒAӮаӮӨҳZ”NӮа‘OӮМӮаӮМӮҫҒBҚӯӮӘӮ ӮйӮЖӮўӮБӮДӮаӮ»ӮсӮИӮЙ–Ъ—§ӮҪӮИӮўҒB–lӮӘӮ ӮМҸқӮр’TӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮ©ӮзӢCӮӘ•tӮўӮҪӮҫӮҜӮҫҒB
ҒuӮӨҒAӮӨӮсҒAүВҲӨӮўҒBӮ·ӮІӮӯҒBӮҝӮеӮБӮЖҢ©ҚӣӮкӮҝӮбӮБӮҪӮжҒv
ҸқӮЙӮНӢCӮӘ•tӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪғtғҠӮрӮөӮД–lӮН”ьҚзӮр–JӮЯӮҪҒBҸЖӮкӮҪӮжӮӨӮИүүӢZӮЕҒB
ҸқӮрҢ©ӮДҢҷӮИӮұӮЖӮрҺvӮўҸoӮөӮ»ӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮҜӮкӮЗҒA•\ҸоӮЙӮНҸoӮіӮИӮ©ӮБӮҪҒB–lӮНғ|Ғ[ғJҒ[ғtғFғCғXӮЙӮНҺ©җMӮӘӮ ӮйӮМӮҫҒB
ҒuӮ»ӮӨҒAӮ©ӮИҒHҒv
”ьҚзӮаҸӯӮөҸЖӮкӮҪӮжӮӨӮЙҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒAҺҹӮНҲІӮіӮсӮӘ‘IӮсӮЕӮӯӮкӮҪӮМ’…ӮДӮЭӮйӮЛҒv
ҢҫӮӨӮЖ”ьҚзӮНӮЬӮҪҺҺ’…ҺәӮЙҲшӮБҚһӮсӮЕӮўӮБӮҪҒB
•@үМӮЬӮ¶ӮиӮЙ’…‘ЦӮҰӮДӮўӮйҒB”ьҚзӮНҸгӢ@ҢҷӮИӮжӮӨӮҫҒB
–lӮНӮЖӮўӮҰӮОҒAғҢғfғBҒ[ғXӮМғRҒ[ғiҒ[ӮЙӮ ӮйҺҺ’…ҺәӮМ‘OӮЙ’jҲкҗlӮЕӮўӮйӮЖӮўӮӨ‘ПӮҰ“пӮўӢк’ЙӮЙүХӮЬӮкӮДӮўӮҪҒB
ӮөӮОӮзӮӯӮ·ӮйӮЖҲІӮЖ“XҲхӮіӮсӮӘҠyӮөӮ»ӮӨӮЙ–ЯӮБӮДӮ«ӮҪҒBҲІӮМҺиӮЙӮНүҪӮҫӮ©Ҡп”ІӮИғfғUғCғ“ӮМғtғҸғtғҸӮөӮҪ•һӮӘҲк‘өӮўҒ\Ғ\ҒB
ҒuҲІҒAӮ»ӮкҒAғrғWғ…ғAғӢҢnӮБӮДӮвӮВҒHҒv
ҒuҲбӮӨҒIҒ@ғSғVғbғNғҚғҠҒ[ғ^—ӘӮөӮДғSғXғҚғҠӮ¶ӮбҒIҒ@ӢрӮ©ҺТӮЯҒIҒ@ӮўӮўӮ©ҒHҒ@ғSғXғҚғҠӮБӮДӮНӮ»ӮаӮ»ӮаҒ\Ғ\Ғv
ҲІӮӘғSғXғҚғҠӮЙӮВӮўӮДӮМҚuӢ`ӮрҺnӮЯӮҪҒBӮұӮӨӮИӮйӮЖ’·ӮўҒB
–lӮН•һӮЙҠЦӮөӮДӮН–еҠOҠҝӮҫҒB’…ӮДӮўӮй•һӮНӮЩӮЖӮсӮЗҲІӮӘ‘IӮсӮЕӮӯӮкӮҪӮаӮМӮҫӮөҒB
Ӣ»–ЎӮӘ–іӮўӮБӮДӮнӮҜӮ¶ӮбӮИӮўӮҜӮЗҒA–lӮНҺdҺ–ӮағXҒ[ғcӮҫӮөҒAӢx“ъӮҫӮБӮД—Rҗ^ӮвҲІӮЙҳAӮкҸoӮіӮкӮИӮўҢАӮиӮНғXҒ[ғpҒ[ӮЙ”ғӮў•ЁӮЙҚsӮӯӮӯӮзӮўӮөӮ©ҠOҸoӮНӮөӮИӮўҒBӮҫӮ©ӮзҺ„•һӮНӮ»ӮсӮИӮЙӮұӮҫӮнӮй•K—vӮӘӮИӮўӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪҒBӮҜӮЗҒAӮұӮкӮ©ӮзӮНҒA”ьҚзӮЖҲкҸҸӮЙ•йӮзӮ·ӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮзҒA“сҗlӮЕӮЗӮұӮ©ӮЙҸoӮ©ӮҜӮйӮұӮЖӮҫӮБӮДӮ ӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB
Ғi–lӮаҸӯӮөӮӯӮзӮўӮН•һӮЙӢCӮрҺgӮБӮДӮЭӮжӮӨӮ©ӮИҒj
Ӯ»ӮсӮИӮұӮЖӮрҺvӮБӮҪҒB
ҒuҒ\Ғ\Ғ\ӮБӮДӮўӮӨҠҙӮ¶ӮЙӮИӮйӮнӮҜӮҫҒBӮұӮұӮЕ‘еҗШӮИӮМӮНғSғXғҚғҠӮЖҠГғҚғҠӮМҲбӮўӮЙӮВӮўӮДӮҫҒBҢлӮБӮДғsғ“ғNӮМғuғүғEғXӮИӮсӮ©’…ӮҪ“ъӮЙӮНҒ\Ғ\ӮБӮДҗSҢмҒIҒ@•·ӮўӮДӮсӮМӮ©ҒHҒv
ҒuӮ ҒAӮІӮЯӮсҒB•·ӮўӮДӮИӮ©ӮБӮҪҒv
ҒuғeғҒғFҒIҒ@ғIғӮғeҸoӮлҒIҒ@ӢM—lӮМ‘МӮЙүҙ—lӮМғEғHғVғғғҢҗ^ҢқӮМүңӢZӮр’@Ӯ«ҚһӮсҒ\Ғ\Ғv
ғJғ`ғғҒAӮЖҺҺ’…ҺәӮМғhғAӮӘҠJӮўӮҪҒBӮҝӮИӮЭӮЙӮұӮМҺҺ’…ҺәҒAғJҒ[ғeғ“ӮЕҺdҗШӮзӮкӮҪӮҫӮҜӮМҠИ‘fӮИӮаӮМӮЕӮНӮИӮӯҒAғhғAӮНӮИӮсӮҫӮ©ҺпӮМӮ Ӯй–Шҗ»•iӮЕҒA–і‘КӮЙҚӮӢүҠҙӮӘӮ ӮйҒB—¬җОӮНҢ|”\җlҢд—p’BӮЖӮўӮБӮҪӮЖӮұӮлӮИӮМӮ©ӮИҒBҠЦҢWӮ ӮйӮ©ӮНӮнӮ©ӮзӮИӮўӮҜӮЗҒB
ҒuҒ\Ғ\ӮЕӮвҒcҒcӮйҒv
ҲІӮМҺӢҠEӮЙҺҺ’…ҺәӮ©ӮзҸoӮДӮ«ӮҪ”ьҚзӮӘ“ьӮБӮҪҸuҠФҒAҲІӮМ“®Ӯ«ӮӘҺ~ӮЬӮБӮҪҒB“XҲхӮіӮсӮаҒAӮ»ӮөӮД–lӮа“®Ӯ«ӮрҺ~ӮЯӮҪҒBӮўӮвҒAҺ~ӮЯӮҪӮсӮ¶ӮбӮИӮўҒBҺ~ӮЬӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮсӮҫҒB
ҒuӮИҒAӮИӮЙҒHҒ@ӮЗӮӨӮөӮДҢЕӮЬӮБӮДӮйӮМҒHҒv
”ьҚзӮӘҚўҳfӮөӮҪ•\ҸоӮЕҢҫӮБӮҪҒB
ҲІӮӘ“Л‘RҸ°ӮЙҚАӮиҚһӮсӮҫҒBӮ»ӮөӮДҒA
Ғuғuғүғ”ғHғIғIғIғIғIғIғIғIғIғbҒIҒv
Ӣ©ӮСӮИӮӘӮзҒAҚАӮБӮҪӮЬӮЬӮМҺpҗЁӮЕғWғғғ“ғvҒI
үҪӮҫӮ©җFҒXҠФҲбӮБӮДӮйӢCӮӘӮ·ӮйӮҜӮЗҲІӮМӢCҺқӮҝӮНӮнӮ©ӮиӮЬӮ·ҒBӮ·ӮІӮӯӮнӮ©ӮиӮЬӮ·ӮЖӮаҒI
–lӮӘ–^Қ‘ӮМҚHҚмҲхӮИӮзҠФҲбӮўӮИӮӯ”ьҚзӮрқf’vӮиӮЬӮ·ҒIҒ@ӮНӮўҒI
ҒuӮНӮҹҒAӮНӮҹҒAӮЬҒAӮЬӮіӮ©ӮұӮұӮЬӮЕҺ—ҚҮӮӨӮЖӮНҒcҒcҚ]ҚиҲІҒAҗlҗ¶ҚЕҚӮӮМҺdҺ–ҒIҒv
ҒuӮЁҒAӢ°ӮлӮөӮўҺqҒIҒv
ҲІӮЖ“XҲхӮіӮсӮН—lҒXӮИғҠғAғNғVғҮғ“ӮЕ”ьҚзӮр•]үҝӮөӮҪҒB
Ғu”ьҚзҒAҗҰӮўҒIҒv
‘өӮўӮЕҸ\Һl–ңү~ӮаӮ·ӮйӮжӮӨӮИ•һӮҫҒBғfғUғCғ““IӮЙӮағXғ^ғCғӢӮӘ—ЗӮӯӮИӮҜӮкӮОҺ—ҚҮӮнӮИӮўҒA•Ғ’КӮМҸ—ӮМҺqӮИӮз•һӮЙ’…ӮзӮкӮДӮөӮЬӮӨӮжӮӨӮИ•һӮрҢ©Һ–ӮЙ’…ӮұӮИӮөӮДӮўӮйҒBҺGҺҸӮМғӮғfғӢҠз•үӮҜӮҫҒB–lӮНҺvӮнӮё‘МҲзүпҢnӮМғmғҠӮЕ”ьҚзӮМҢЁӮр’НӮсӮЕғҶғTғҶғTӮЖҗUӮБӮҪҒB
ҒuӮ ӮнӮнҒAӮвӮЯӮДӮжҒAӮЁҢZӮҝӮбӮсҒA’ЙӮў’ЙӮўҒv
–lӮНҷтҡlӮЙҺиӮр—ЈӮөӮҪҒB
ҒuӮ ҒAӮІҒAӮІӮЯӮсҒv
ӮөӮ©ӮаҺУӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҺё”sӮҫҒBҸОӮўӮИӮӘӮзҺиӮр—ЈӮ·ӮМӮӘҗіүрӮҫҒB
ҒuӮаӮӨӮБҒIҒ@•һӮЙғVғҸӮӘӮВӮӯӮ¶ӮбӮИӮўҒIҒv
”ьҚзӮМ•Ф“ҡӮНӮ ӮиӮӘӮҪӮ©ӮБӮҪҒBүЯӢҺӮЙӢCӮрҺgӮБӮДӮўӮйӮЖҺvӮнӮкӮҪӮӯӮИӮўӮ©ӮзҒB
’ЙӮўҒAӮЖӮўӮӨҢҫ—tӮЙ–lӮНүЯ•qӮЙ”ҪүһӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮМҢҫ—tӮӘҗМӮМ”ЮҸ—Ӯ©ӮзӮНӮўӮВӮаӢ©ӮОӮкӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮҫҒBӮұӮМ’ц“xӮМҗGӮкҚҮӮўӮН“ъҸнҗ¶ҠҲӮЕӮНӮ ӮБӮД“–ӮҪӮи‘OӮЕҒA–lӮа‘ҠҺиӮӘ”ьҚзӮ¶ӮбӮИӮҜӮкӮОүҪӮаҺvӮнӮИӮўҒBӮҜӮЗҒA”ьҚзӮ©ӮзӮ»ӮМҢҫ—tӮр•·ӮӯӮМӮНҢҷӮҫӮБӮҪҒBӮаӮӨ“с“xӮЖ•·Ӯ«ӮҪӮӯӮИӮўӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪҒB
ҒiӮЕӮаҒAҗМӮЖӮНҲбӮӨҒB“ҜӮ¶Ғw’ЙӮўҒxӮЕӮаҒA’gӮ©ӮіӮМӮ ӮйҒw’ЙӮўҒxӮҫҒBӮұӮсӮИӮұӮЖҒAӮўӮҝӮўӮҝӢCӮЙӮөӮҝӮбғ_ғҒӮҫҒj
‘еҸд•vҒAҲкҸҸӮЙ•йӮзӮ·ӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮзҒAӮ·Ӯ®ҠөӮкӮйӮіҒB
Ғ@
Ӯ»ӮкӮ©Ӯз”ьҚзӮНҲІ’BӮӘҺқӮБӮДӮ«ӮҪғtғҸғtғҸӮөӮҪғSғXғҚғҠӮМ•һӮр’…Ӯ№ӮзӮкӮД’pӮёӮ©ӮөӮ»ӮӨӮЙӮөӮДӮўӮҪҒBҲІӮНӮ»ӮкӮрҢ©ӮД•@ҢҢӮр•¬ҸoӮөҒA“XҲхӮіӮсӮНүВҲӨӮіӮМӮ ӮЬӮи”ьҚзӮр—UүыӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕ–ЕӮЪӮіӮ№ӮДӮаӮзӮБӮҪҒBҢӢӢЗҒAғSғXғҚғҠӮН”ғӮнӮёҒAҲІӮМ‘IӮсӮЕӮӯӮкӮҪӮаӮМӮЖ”ьҚзӮМ‘IӮсӮҫ”’ӮўғҸғ“ғsҒ[ғXҒAӮ»ӮкӮЙҚҮӮнӮ№ӮйғWғғғPғbғgҒAӮ»ӮөӮДӮұӮұӮЙ—ҲӮйҢыҺАӮЙҺgӮБӮҪҸt•ЁӮМғVғғғcӮрҲк–ҮӮҫӮҜ”ғӮӨӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒB”ьҚзӮН–{“–ӮЙҲк’…ӮҫӮҜ”ғӮБӮДӮаӮзӮӨӮВӮаӮиӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮЕҗа“ҫӮЙӢкҳJӮөӮҪҒB
Һx•ҘӮўӮМҺһҒAҲІӮӘҢҫӮБӮҪҒB
Ғu”ьҚзӮҝӮбӮсҒAғXғQҒ[Һ—ҚҮӮБӮДӮҪҒIҒ@ӮЗӮкӮ©ҚЎӮ©Ӯз’…ӮДӮБӮҪӮзҒHҒv
ҒuӮҰҒAӮЕӮаҒcҒcҒv
ҒuӮўӮўӮМӮўӮўӮМҒBҢӢҚ\‘е—КӮҫӮ©ӮзӮЛҒB•пӮЮӮМӮЖүпҢvӮЙӮҝӮеӮБӮЖҺһҠФӮ©Ӯ©ӮйӮ©Ӯз’…‘ЦӮҰӮДӮЁӮўӮЕҒBҗSҢмӮаӮіӮБӮ«ӮМ•һӮМ•ыӮӘӮўӮўӮжӮИҒHҒv
ҠmӮ©ӮЙҒA”ьҚзӮӘҚЎ’…ӮДӮўӮй•һӮНҠXӮЙӮўӮй“Ҝ”N‘гӮМҸ—ӮМҺqӮМӮаӮМӮЙ”дӮЧӮДҸӯӮө’n–ЎӮҫҒB–lӮЖӮөӮДӮН”ьҚзӮЙ•Ғ’КӮМҺqӮЖ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮИҠiҚDӮрӮөӮДӮаӮзӮўӮҪӮўҒB–lӮН•һ‘•ӮИӮсӮДӮЗӮӨӮҫӮБӮДӮўӮўӮЖӮНҺvӮБӮДӮўӮйӮҜӮЗҒAӮіӮБӮ«ӮМ—lҺqӮрҢ©ӮйӮЙҒA”ьҚзӮН—¬ҚsӮМ•һӮр’…ӮД•аӮ«ӮҪӮўӮНӮёӮҫҒB
ҒuӮӨӮсҒAӮЬӮҹҒAӮ©ҒAүВҲӨӮ©ӮБӮҪӮөҒv
”ьҚзӮМҠзӮӘҗФӮӯӮИӮБӮҪҒB
ҒuӮ¶ӮбҒAӮ¶ӮбӮ ҒcҒcӮҝӮеӮБӮЖ’…‘ЦӮҰӮДӮӯӮйҒv
”ьҚзӮӘ”’ӮМғҸғ“ғsҒ[ғXӮЖғWғғғPғbғgӮрҺқӮБӮДҺҺ’…ҺәӮЙ“ьӮБӮДӮўӮБӮҪӮМӮрҢ©ҢvӮзӮБӮДҒAҲІӮӘҢҫӮБӮҪҒB
ҒuҚЎ“ъҒAүҙӮМҡшӮиӮЕӮўҒ[ӮнҒv
ҒuӮНӮҹ!?Ғ@үҪҒAӮўӮ«ӮИӮиҒHҒv
–lӮН–{ӢCӮЕӢБӮўӮҪҒBҸ\–ңӮр’ҙӮҰӮй‘еӢаӮрҡшӮйҒHҒ@ҲІӮНӮЗӮұӮ©ӮЁӮ©ӮөӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒAӮИӮсӮД–{ӢCӮЕҚlӮҰӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB
ҒuҗәӮЕӮҜҒ[ӮжҒAӮұӮМӮұӮЖ—Rҗ^ӮҝӮбӮсӮЖ”ьҚзӮҝӮбӮсӮЙӮН”й–§ӮИҒv
ҒuӮИҒcҒcҒv
Ғu–ІӮҫӮБӮҪӮсӮҫӮлҒHҒ@”ьҚзӮҝӮбӮсӮЖ•йӮзӮ·ӮМҒv
ҒuӮИҒAӮИӮсӮҫӮжӮўӮ«ӮИӮиҒBӮ»ӮиӮбӮ»ӮӨӮҫӮҜӮЗҒAӮ»ӮкӮӘүҪӮМҠЦҢWӮӘҒ\Ғ\Ғv
Ғu‘OҸjҒHҒ@ӮЭӮҪӮўӮИғӮғ“ӮҫӮжҒBӮўӮўӮ¶ӮбӮсҒAӮұӮкӮӯӮзӮўӮөӮҪӮБӮДҒv
ҒuӮҜҒAӮҜӮЗҒAҸ\–ңҲИҸгӮ·ӮйӮсӮҫӮжҒHҒ@Ӯ»ӮсӮИӮМҡшӮБӮДӮаӮзӮӨӮнӮҜӮЙӮНҒ\Ғ\ҒBӮ»ӮкӮЙ–lҒAӮЁӢаӮИӮзӮ»ӮкӮИӮиӮЙҒ\Ғ\Ғv
ҒuӢCҺқӮҝӮҫӮжҒAӢCҺқӮҝҒBӢҢӮўҳAӮкӮМ–ІӮӘҠҗӮӨӮ©ӮаӮБӮДӮЖӮ«ӮҫӮөҒAӮұӮМӮӯӮзӮўӮМӮұӮЖӮНӮіӮ№ӮДӮӯӮкӮДӮаӮўӮўӮ¶ӮбӮсҒv
ҒuҲІҒcҒcҒv
–lӮЙӮЖӮБӮДӮНҲІӮӘ”ьҚзӮМӮҪӮЯӮЙ•һӮр‘IӮсӮЕӮӯӮкӮҪӮҫӮҜӮЕҸ\•ӘӮҫӮБӮҪҒB
Ғu•йӮзӮ№ӮйӮЖӮўӮўӮИҒAҲкҸҸӮЙҒv
ҒuҒcҒcӮӨӮсҒv
—Rҗ^ӮаӮ»ӮӨӮҫӮҜӮЗҒA–lӮН–{“–ӮЙ—FҗlӮЙҢbӮЬӮкӮДӮўӮйӮЖҺvӮӨҒB
ҒuӮ»ӮӨӮөӮДӮӯӮкӮИӮўӮЖҒAүҙӮӘ”ьҚзӮҝӮбӮсӮЙӮаӮӨүпӮҰӮИӮӯӮИӮБӮҝӮбӮӨӮ©ӮзҒҷҒ@Ӯ ҒA”ьҚзӮҝӮбӮсӮБӮДғPҒ[ғ^ғCҺқӮБӮДӮйҒHҒ@ҺқӮБӮДӮйӮсӮҫӮБӮҪӮз”ФҚҶӮЖғAғhӢіӮҰӮДӮӯӮсӮЛҒHҒv
ӮўӮвӮҹҒAғRғCғc“GҒBғGғlғ~Ғ[ҒB
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ӮВӮГӮӯӮжҒIҒIҒI
|
|
|
|
| ҒuҒ@”ФҠi“сҸd‘tҒ@ҒvҒ@Ғ@Ғ@ҳAҚЪҺ®ҒHҒ@ҒiҒuҠ@ҒIҒHҒ@җM’·ҠwүҖҒIҒIҒvғXғsғ“ғIғtҚм•iҒjҒ@Ғ@Ғ@’ҳҒ@Һl”Nҗ¶ҒFғWғFғoғ“ғjҒ@Ғi•ӣ•”’·Ғj |
|
|
|
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ғvғҚғҚҒ[ғO
Ғu“VүәӮжҒIҒ@’jӮИӮзӮДӮБӮШӮсӮр–ЪҺwӮ№ҒIҒ@Ӯ»ӮкӮӘ’jӮБӮДӮаӮсӮҫӮлӮӨҒIҒv
ҒuӮЁӮӨӮжҒIҒ@ғIғҢӮНӮвӮйӮәҒIҒ@ғIғҢӮӘӮаӮӨҲк“xҒAӮұӮМ“ҝҗмӮЙ“VүәӮрҒIҒv
ҒuӮ»ӮӨӮ©ӮҹҒIҒ@ӮіӮ·ӮӘӮНүҙӮМ‘§ҺqӮҫҒIҒ@ӮИӮзӮОүҙӮН‘S—НӮЕӮЁ‘OӮрүһүҮӮ·ӮйӮјҒIҒv
Ғu•ғӮҝӮбӮсҒIҒv
Ғu“VүәӮҹҒIҒv
Ғ@ғKғVғbӮЖ•шӮ«ҚҮӮӨғAғcӮўҗeҺqӮӘ–lӮМ–ЪӮМ‘OӮЕӮИӮЙӮвӮзҗҫӮўӮ ӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒB
Ғ@ӮЬӮБӮҪӮӯҸӢӢкӮөӮўҒBҺlҢҺӮЖӮўӮӨҸӢӮӯӮаҠҰӮӯӮаӮИӮўүЯӮІӮөӮвӮ·ӮўӢGҗЯӮҫӮЖӮўӮӨӮМӮЙҒAӮұӮұҺ„—§“ҝҗмҚӮҚZӮМ•”Һә“ғӮМҲкҺәҒA”ФҠi•”ӮМ•”ү®ӮҫӮҜӮНҗ^үДӮЙ—в–[Ӯа“ьӮкӮёӮЙ‘ӢӮр•ВӮЯҗШӮБӮҪҺlҸфҠФӮМӮжӮӨӮЙҸӢӢкӮөӮӯҠҙӮ¶ӮзӮкӮЬӮ·ҒB
Ӯ»ӮкӮЖӮўӮӨӮМӮаҒAҚЎ–lӮМ–ЪӮМ‘OӮЕүдӮӘҚZӮМ—қҺ–’·ӮЕӮ ӮйӮНӮёӮМ’jӮӘҺ©•ӘӮМҺqӮЙҢьӮ©ӮБӮД’jӮМ“№ӮЙӮВӮўӮД”MӮӯҢкӮиҒA“–ӮМҺqӮаӮ»ӮкӮЙҢҢӢШ’КӮиӮМ”MҢҢӮЕүһӮҰӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB
”ЮӮзӮӘҚмӮиҸoӮ·ҲЩӢуҠФӮЙӮНҠөӮкӮДӮўӮйӮаӮМӮМҒAӮвӮНӮиӮұӮӨҠФӢЯӮЕӮвӮзӮкӮйӮЖ‘ПӮҰ“пӮўҒB
Ғu“VүәӮҹӮҹӮҹӮҹӮҹӮҹӮҹӮҹғbҒIҒv
Ғu•ғӮҝӮбӮҹӮҹӮҹӮҹӮҹӮҹӮҹӮсҒIҒv
Ғ@Ғ\Ғ\ӮНӮҹҒAӮ»ӮлӮ»ӮлӮ©ӮИҒB
Ғ@ӮұӮМҗeҺqӮН•ъӮБӮДӮЁӮӯӮЖҚЫҢАӮИӮӯ”RӮҰҸгӮӘӮйӮМӮЕҒA–lӮНӮўӮВӮаӮМҺ©•ӘӮМҺdҺ–ӮрӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮөӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@Ӯ·ӮИӮнӮҝҒA”RӮҰҗ·ӮйүОӮрҸБӮ·ҸБ–hҺmҒBүpҢкӮЕҢҫӮӨӮЖғtғ@ғCғAҒ[ғ}ғ“ҒBӮұӮкӮҫӮЖӮИӮсӮ©–lӮӘ”RӮҰӮДӮйӮжӮӨӮИӢCӮӘӮөӮЬӮ·ӮЛҒBӮЖҒAӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮНӮЗӮӨӮЕӮаӮўӮўӮвҒAӮіӮДҒB
‘еӮ«Ӯӯ‘§ӮрӢzӮБӮДҒ\Ғ\ҒB
Ғu—қҺ–’·ҒA“VүәӮНҸ—ӮМҺqӮЕӮ·ҒIҒ@ӮўӮўүБҢё‘§ҺqҲөӮўӮ·ӮйӮМӮНӮвӮЯӮДӮӯӮҫӮіӮўҒIҒ@Ӯ ӮсӮҪ‘§ҺqӮМҸ«—ҲҚlӮҰӮҪӮұӮЖӮ ӮйӮсӮЕӮ·Ӯ©ҒIҒ@ӮұӮсӮИҸ—ӮМҺqҗв‘ОҸAҗEӮЙӢкҳJӮөӮЬӮ·ӮжҒIҒv
Ғ@ҲꑧӮЕҢҫӮўҗШӮиӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@Ӯ»ӮӨӮИӮМӮЕӮ·ҒBҚЎ–lӮМ–ЪӮМ‘OӮЙӮўӮй“сҗlӮМӮӨӮҝӮМҲкҗlҒAүҗӮвӮ©ӮИ’·ӮўҚ•”ҜӮрҢгӮлӮЕ“ZӮЯӮҪғ|ғjҒ[ғeҒ[ғӢӮӘҲуҸЫ“IҒA‘SҗgӮӘғuғJғuғJӮЕ•sҺ©‘RӮЙҸдӮМ’·Ӯўүь‘ўҗ§•һҒA‘ӯӮЙ’·ғүғ“ӮЖҢДӮОӮкӮйӮаӮМӮрүВҲӨӮзӮөӮӯ’…ӮұӮИӮөӮДӮўӮйҒi’…ӮзӮкӮДӮўӮйҒHҒjӮМӮН–lӮМ—c“йҗхӮЭҒA“ҝҗм“VүәҒB’jҢҫ—tӮрҺgӮўҒA’j‘•ӮрҚDӮЮ•ПҗlӮҫӮҜӮкӮЗҒAҠФҲбӮўӮИӮӯҸ—ӮМҺqӮЕҒAӮЁӮЬӮҜӮЙ”ьҸӯҸ—ӮЕӮ·ҒB
Ӯ»ӮсӮИ”ЮҸ—ӮЖ—c“йҗхӮЭӮИ–lӮНҒAӮ«ӮБӮЖ“Б•КӮИ‘¶ҚЭӮИӮсӮҫӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB
ӮҰӮҰҒAғzғ“ғgӮЙҒA“Б•КҒw•sҚKҒxӮИӮсӮҫӮЖҒB
ӮҫӮБӮДӮ»ӮӨӮНҺvӮўӮЬӮ№ӮсӮ©ҒHҒ@
•Р‘zӮўӮМ‘ҠҺиӮӘӮұӮсӮИҒA’j‘•ӮЕҢыӮӘҲ«ӮӯӮД”MҢҢҒAгY—нӮИ’·Ӯў”ҜӮрғXғ|Ғ[ғcҺлӮиӮЙӮЕӮаӮөӮДӮөӮЬӮҰӮОӮаӮӨҠ®‘SӮЙҒwҸ—ҠзӮМ’jӮМҺqҒxӮИҸӯҸ—ӮИӮМӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒB
Ғ@ӮНӮҹҒAҸ¬ҠwҚZӮМҚ ҒAӮЬӮҫ—cӮў–lӮӘҺvӮў•`ӮўӮДӮўӮҪ–ІӮМҲкӮВӮЙӮұӮсӮИӮаӮМӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB
Ғ\Ғ\ҚӮҚZҗ¶ӮЙӮИӮБӮҪӮзҒAҗ§•һҒ\Ғ\ӮаӮҝӮлӮсҸ—ҺqӮМӮЛҒ\Ғ\Ӯр’…ӮҪүВҲӨӮўҒ\Ғ\ӮұӮұҒAҸd—vӮЛҒ\Ғ\Ҹ—ӮМҺqӮЖҒ\Ғ\ӮБӮДӮўӮӨӮ©“VүәӮЖҒ\Ғ\ҲкҸҸӮЙ“oүәҚZӮ·ӮйҒI
ӮУӮУҒAҚЎӮЖӮИӮБӮДӮН–{“–ӮЙ–ІӮЕӮ·ӮЛҒBӮҫӮБӮД”ЮҸ—ҒA“VүәӮНӮұӮМ“ҝҗмҚӮҚZӮЙ“ьҠwӮөӮДӮ©ӮзҲк”NҠФҒAҲк“xӮҫӮБӮДҺw’иӮМҗ§•һӮр’…ӮДӮ«ӮҪӮұӮЖӮНӮИӮўӮМӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒB
ӮаӮӨҠ®‘SӮЙғҒғ“ғYӮЕӮ·ӮжӮЛҒB
Ғ@җ§•һӮр’…ӮҪҚDӮ«ӮИҸ—ӮМҺqӮЖ“oүәҚZӮ·ӮйҒB’jҺqӮИӮз’NӮЕӮаҲк“xӮНҺvӮў•`Ӯ«ҒA“w—НҺҹ‘жӮЕӮНҠҗӮӨӮ©ӮаӮөӮкӮИӮў–ІӮрҢ©ӮйӮұӮЖӮіӮҰ–lӮЙӮНӮЕӮ«ӮИӮўӮЖӮўӮӨӮМӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒA–lӮН•sҚKӮҫӮЖҢҫӮҰӮйӮЕӮөӮеӮӨҒB
Ӯ Ӯ ҒAӮИӮсӮДӮ©ӮнӮўӮ»ӮӨӮИ–lҒB
ҒuӮӨӮнӮ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ ӮсҒIҒ@җD“cӮМҺҹ’j–VӮЙ“{ӮзӮкӮҪӮҹҒIҒv
Ғ@Ӯ ӮлӮӨӮұӮЖӮ©ӢғӮ«ҸoӮөӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBғIғbғTғ“ӮМ•ыӮӘҒBӢғӮ«ӮҪӮўӮМӮН–lӮМ•ыӮҫҒB
ҒuӮўӮўҚОӮөӮҪғIғbғTғ“ӮӘӢғӮ©ӮИӮўӮЕӮӯӮҫӮіӮўӮжҒIҒ@ӢCҺқӮҝҲ«ӮўҒIҒv
ҒuӮұӮз“V”nҒIҒ@•ғӮҝӮбӮсӮрӮўӮ¶ӮЯӮйӮИҒIҒ@ӮўӮўӮ©ҒHҒ@ӮўӮ¶ӮЯӮНҚЕ’бӮҫӮјҒIҒ@ғJғbғRҲ«ӮўӮсӮҫӮјҒIҒ@ӮЬӮБӮҪӮӯҒIҒ@үдӮӘҚZӮМ— ”Ф’·ӮЖӮаӮ ӮлӮӨҺТӮӘҸоӮҜӮИӮўӮЖҺvӮнӮИӮўӮМӮ©ҒIҒv
ҒuӮўӮ¶ӮЯӮ¶ӮбӮИӮӯӮДҗаӢіӮҫӮжҒIҒ@ӮЮӮөӮлҺlҸ\үЯӮ¬ӮДҚӮҚZҗ¶ӮЙҗаӢіӮіӮкӮДӢғӮӯӮЩӮӨӮӘҸоӮҜӮИӮўӮнҒIҒ@Ӯ»ӮаӮ»ӮаҚӮҚZҗ¶ӮЙҗаӢіӮіӮкӮйӮұӮЖҺ©‘МӮЗӮӨӮ©ӮөӮДӮйӮнҒIҒv
ҒuғoғJ–мҳYҒIҒ@ӮнӮ©ӮзӮИӮўӮМӮ©ҒHҒ@Ӯ»ӮұӮӘ•ғӮҝӮбӮсӮМғiғEӮўӮЖӮұӮлӮИӮсӮҫӮжҒIҒv
ҒuӮнӮ©ӮйӮ©ӮұӮМғtғ@ғUғRғ“ҒIҒ@ӮБӮДӮ©ғiғEӮўӮБӮДҢNҒAғzғ“ғgӮЙ•Ҫҗ¬җ¶ӮЬӮкӮМҸ—ҺqҚӮҗ¶Ӯ©ҒH
ӮўӮВӮМҺһ‘гӮМғcғbғpғҠӮҫӮжҒIҒv
ҒuӮИӮсӮҫӮЖҒA“V”nӮМӮӯӮ№ӮЙҒIҒ@ҢҫӮБӮДӮЁӮӯӮӘғIғҢӮН•ғӮҝӮбӮсӮжӮи•кӮҝӮбӮсӮМ•ыӮӘҚDӮ«ӮҫӮјҒIҒ@ӮЮӮөӮлғ}ғUғRғ“ӮҫҒIҒv
ҒuҗHӮўӮВӮӯӮЖӮұӮ»ӮұӮ©ӮжҒIҒv
ҒuӮҰӮҰҒHҒ@Ӯ»ӮсӮИҒcҒc“VүәҒA•ғӮҝӮбӮсӮжӮи•кӮҝӮбӮсӮМ•ыӮӘӮўӮўӮБӮДҢҫӮӨӮМӮ©ӮўҒHҒv
ҒuӮ Ӯ ҒIҒ@ӮІӮЯӮс•ғӮҝӮбӮсҒIҒ@ӮВӮўҒ\Ғ\Ғv
ҒuӮВӮў–{ү№ӮӘҸoӮҝӮЬӮБӮҪӮБӮДҢҫӮӨӮсӮҫӮИҒHҒ@ӮҝҒA’{җ¶ҒA•кӮҝӮбӮсӮЯӮҘӮҘӮҘҒcҒcҒv
ҒuӮ ӮнӮнҒAӮЗӮӨӮөӮжӮӨ“V”nҒIҒ@ӮЁ‘OӮЖғIғҢӮМӮ№ӮўӮЕ“ҝҗмүЖӮӘ—ЈҚҘӮМҠлӢ@ӮҫӮјҒIҒv
ҒuҢNӮҫӮҜӮМӮ№ӮўӮҫӮлӮӨӮӘҒIҒv
“ҝҗмүЖӮМүЖ‘°Ҡi•tӮҜғүғ“ғLғ“ғOӮӘҠ_ҠФҢ©ӮҰӮДӮөӮЬӮӨғSғ^ғSғ^ӮөӮҪүпҳbӮрӮөӮДӮўӮйӮЖҒA“Л‘R•”ҺәӮМғhғAӮӘҗЁӮўӮжӮӯҠJӮ©ӮкӮЬӮөӮҪҒB
Ғu“GҸPҒIҒv
Ғ@ӮўӮ«ӮИӮиҢ»ӮкӮДӮ»ӮӨӢ©ӮсӮҫҗlүeӮЙҢьӮ©ӮБӮД–lӮзӮН‘өӮБӮДҒA
ҒwғCғPғҒғ“ҒIҒx
Ғ@ғCғPғҒғ“ҒAӮЖӮўӮӨӮМӮН“ьӮБӮДӮ«ӮҪ’jӮМӮ Ӯҫ–јӮИӮМӮЕӮ·ҒB
Ғ@”ЮӮМ–јӮН’r–Л‘ҫҳYҒB“ЗӮЭӮНғCғPҒEғҒғ“ғ^ғҚғEӮЕӮ·ҒBҚЎ”N“ьҠwӮөӮДҒAҗж“ъ“ь•”ӮөӮҪӮОӮ©ӮиӮМҲк”Nҗ¶ӮЕҒA–lӮзӮМҢг”yӮЙ“–ӮҪӮиӮЬӮ·ҒBҺАҚЫ”ьҢ`ӮЕӮ ӮйӮҪӮЯҒAғCғPғҒғ“ӮЖҢДӮсӮЕӮаҚ·ӮөҺxӮҰӮИӮўӮМӮЕӮ»ӮӨҢДӮФӮұӮЖӮЙӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB
Ғu”Ф’·ҒAҢZӢMҒAӮДӮҘӮЦӮсӮҫҒIҒ@Ӯ·Ӯ®ҚZ’лӮЙ—ҲӮДӮӯӮкҒIҒ@–С—ҳҠwү@ӮМ“zӮзӮӘғJғ`ҚһӮсӮЕ—ҲӮвӮӘӮБӮҪӮсӮҫҒIҒv
Ғ@”Ф’·ҒAӮ»ӮӨҢДӮОӮкӮҪӮМӮН–ЪӮМ‘OӮМ”MҢҢ”ьҸӯҸ—ҒA“ҝҗм“VүәҒBҢҫӮӨӮЬӮЕӮаӮИӮӯҒAҢZӢMӮН–lҒAҗD“c“V”nҒB
Ғ@ӮЗӮӨӮвӮзӢЯ—ЧӮМ–С—ҳҠwү@ҚӮҚZӮМ”ФҠi•”ӮӘҒA–lӮҪӮҝ“ҝҗмҚӮҚZ”ФҠi•”ӮЙҗн‘ҲӮрҺdҠ|ӮҜӮДӮ«ӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒB
ҒuӮЁӮаӮөӮкӮҘҒAҸг“ҷӮ¶ӮбӮЛӮҘӮ©ҒIҒ@ҚsӮӯӮј“V”nҒIҒv
Ғ@“VүәӮН–lӮМҺиӮрҺжӮБӮДӢмӮҜҸoӮ»ӮӨӮЖӮөӮЬӮ·ҒB
ҒuӮҰӮҰҒAӮҝӮеҒAӮ»ӮсӮИӢ}ӮЙғPғ“ғJӮИӮсӮДҒcҒcҒB—қҺ–’·ҒAҺ~ӮЯӮДӮӯӮҫӮіӮўӮжҒIҒv
Ғ@–lӮН“VүәӮЙҲшӮ«ӮёӮзӮкӮИӮӘӮзӮұӮМ“ҝҗмҚӮҚZӮМӢіҲзҺТӮМғgғbғvӮЙҸ•ӮҜӮрӢҒӮЯӮЬӮ·ҒB
ҒuғqғғғbғzғHғHғHғEҒIҒ@җнӮ¶ӮбҗнӮ¶ӮбӮ ҒIҒ@Ҡж’ЈӮкӮжӮ§“VүәҒIҒ@•ғӮҝӮбӮсӮЁ‘OӮМ—YҺpӮрӮөӮБӮ©ӮиғrғfғIӮЙҺBӮБӮДӮвӮйӮ©ӮзӮИҒIҒv
ҒuӮҝӮБӮӘӮӨӮҫӮлӮ§Ӯ§Ӯ§ҒIҒ@Ӯ ӮсӮҪҗS”zӮ¶ӮбӮИӮўӮМ!?Ғv
ҒuӮИӮсӮҫӮжӮӨӮйӮ№Ғ[ӮИҒAҗS”zӮөӮИӮӯӮДӮаӮҝӮбӮсӮЖҢNӮаүfӮөӮДӮвӮйӮөғ_ғrғ“ғOӮаӮөӮДӮвӮйӮжӮ§ҒBӮ ҒAӮӨӮҝҚЕӢЯғuғӢҒ[ғҢғCӮЙӮөӮҪӮсӮҫӮҜӮЗҒAҢNӮМүЖҒAҚДҗ¶ӮЕӮ«ӮйғnҒ[ғhӮ ӮйҒHҒv
ҒuӮ»ӮӨӮ¶ӮбӮЛӮҰӮҰӮҰӮҰӮҰӮҰӮҰӮҰӮҰӮҰӮҰғbҒIҒ@ҸӯӮөӮН–әӮМҗS”zӮөӮлӮжҒIҒv
Ғ@ғ_ғҒӮҫғRғCғcҒBӮЗӮӨӮөӮжӮӨӮаӮИӮӯғ_ғҒӮИ‘еҗlӮҫҒB
ҒuӮөӮ©ӮөҒAӮИӮйӮЩӮЗҒ\Ғ\ҒB–С—ҳӮМҳA’ҶӮНҸүҗнӮЙӮӨӮҝӮр‘IӮсӮҫӮ©Ғv
Ғ@—қҺ–’·ӮНғjғqғӢӮИҸОӮЭӮр•ӮӮ©ӮЧӮД•sҗёғqғQӮрҗGӮиӮИӮӘӮзихӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМҺpӮНӮіӮИӮӘӮзҗ”‘ҪӮӯӮМҗн—җӮрҗ¶Ӯ«ү„ӮСӮДӮ«ӮҪ—рҗнӮМ—b•әӮрғzғEғtғcӮЖӮіӮ№ӮЬӮөӮҪӮӘӮұӮМҗeғoғJӮӘӮвӮБӮҪӮЖӮұӮлӮЕҸӯӮөӮаҠiҚDӮжӮӯӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB
Ғu—қҺ–’·ҒIҒ@–С—ҳӮИӮсӮҙҒAҢZӢMӮЙӮ©Ӯ©ӮиӮб“с•ӘӮЕғAғEғVғ…ғ”ғBғbғcӮЕӮіӮҹҒIҒv
ғCғPғҒғ“ҒAӮ»ӮкҢҫӮўүЯӮ¬ҒAӮ»ӮөӮД•sӢЮҗTҒB
ҒuӮ ӮҹӮсҒHҒ@Ҹ¬‘mҒAӮӨӮҝӮМ“VүәӮӘҗD“cӮМҺҹ’j–VӮЙ—тӮйӮБӮДӮМӮ©ӮҹҒHҒv
Ғ@ҚӮҚZҲк”Nҗ¶Ӯр‘ҠҺиӮЙӮаӮМӮ·ӮІӮўғҒғ“ғ`ӮрҗШӮйғIғbғTғ“ҒB
ҒuӮ ӮсӮҪ‘еҗlӢCӮИӮўӮжҒIҒv
Ғ@Ӯ»ӮӨӮұӮӨӮөӮДӮўӮйҠФӮЙӮа–lӮН•”ҺәӮМҸoҢыӮЬӮЕҲшӮ«ӮёӮзӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB
Ғu•ғӮҝӮбӮсҒIҒ@ҚsӮБӮД—ҲӮйӮәҒIҒv
Ғ@“VүәӮН—қҺ–’·ӮЙҢьӮ©ӮБӮДҗeҺwӮр—§ӮДӮЬӮ·ҒB
ҒuӮЁӮӨӮжҒIҒ@ӮўӮБӮҝӮеӮ©ӮЬӮөӮД—ҲӮўҒIҒv
Ғ@ғoғJҗe•ғӮаҗeҺwӮр—§ӮДӮДүһӮҰӮЬӮ·ҒB
Ғ@Ӯ Ӯ ҒAғ_ғҒӮҫҒBӮнӮ©ӮБӮДӮНӮўӮҪӮҜӮЗ—қҺ–’·ӮНғNғ\ӮМ–рӮЙӮа—§ӮҪӮИӮўҒB
Ғu‘ТӮҪӮ№ӮҪӮИҒA–мҳYӮЗӮаҒIҒ@ӢCҚҮӮН“ьӮБӮДӮйӮ©ҒIҒv
Ғwүҹ”EғbҒIҒx
Ғ@”Ф’·ҒA“ҝҗм“VүәӮМҗәӮЙҒA•”Һә“ғӮМӮ·Ӯ®ҠOӮЙҸWӮБӮДӮўӮҪүдӮӘҚZӮӘҢЦӮйғcғbғpғҠӮМҗёүsӮҪӮҝҸ\—]–јӮӘ—НӢӯӮў•ФҺ–ӮрӮөӮЬӮ·ҒB
Ғu–ЪҺwӮ·‘SҚ‘җ§”eӮМӮҪӮЯӮМҸүҗнӮҫҒIҒ@Ҡ®•ҶӮИӮ«ӮЬӮЕӮЙ–С—ҳӮМеv’ҺӮЗӮаӮр’@Ӯ«’ЧӮ·ӮјҒIҒ@Ӯ»ӮөӮД“zӮзӮІҺ©–қӮМҺO–{ӮМ–оӮЖӮвӮзӮаҒA“zӮзӮМ–ЪӮМ‘OӮЕҗeҺwӮЖҗlҚ·ӮөҺwӮҫӮҜӮЕӮЦӮөҗЬӮБӮДӮвӮйҒIҒ@Ӯ»ӮсӮЕҢҫӮБӮДӮвӮйӮсӮҫҒIҒ@ҚЧӮӯӮДҗЖӮў–оӮНҲк–{ӮИӮзҠИ’PӮЙҗЬӮкӮйҒAӮЕӮаҺO–{ӮИӮзҗЬӮкӮИӮўҒAӮҫӮБӮДҒHҒ@ғIғҢӮИӮзҺO–{ӮЕӮаҠИ’PӮЙҗЬӮкӮйӮБӮВҒ[ӮМӮБӮДӮИҒIҒ@Ӯ ӮНӮНҒA–С—ҳӮМғAғzӮЗӮаӮМүчӮөӮ»ӮӨӮИҠзӮӘ–ЪӮЙ•ӮӮ©ӮФӮжӮӨӮҫҒIҒ@ӮЗӮӨӮҫӮЁ‘OӮзӮҹҒIҒ@ҠyӮөӮ»ӮӨӮҫӮлӮ§ҒIҒv
ҒwғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғIғbҒIҒx
ҸкӮМӢуӢCӮӘ–ТҺТӮҪӮҝӮМ”MӢCӮЙ“–ӮДӮзӮкӮД–cӮкҸгӮӘӮБӮДӮўӮӯӮМӮӘӮнӮ©ӮиӮЬӮ·ҒB‘ТӮҝҺуӮҜӮйҢҲ“¬Ӯр‘OӮЙ”ЮӮзӮМғeғ“ғVғҮғ“ӮНғ}ғbғNғXӮЙҒI
ҒuӮУӮРӮРҒAӮіӮ·ӮӘ“ҝҗм”Ф’·ҒAӮҰӮ°ӮВӮИӮўӮәҒIҒ@–GӮҰӮДӮ«ӮҪӮҹҒIҒv
ҒuӮЬӮБӮҪӮӯӮҫҒA”ьҸӯҸ—ӮИӮМӮЙӢS’{ӮЙӮаӮЩӮЗӮӘӮ ӮйӮәҒBӮҫӮӘӮ»ӮкӮӘӮўӮўҒIҒv
ҒuӮҪӮЬӮсӮЛҒ[ӮИҒIҒ@ғIғҢҒAӮ ӮМҗlӮрҢ©Ӯй“xҒA”ФҠi•”ӮЙ“ьӮБӮДҗіүрӮҫӮБӮҪӮИӮБӮДҺvӮӨӮсӮҫҒv
ҒuӮ ҒAӮвӮБӮПӮиҒHҒ@үҙӮаҒv
Ғ@ӮИӮсӮЖӮўӮӨӮ©ҒA“VүәӮНӮ»ӮМ‘e–\ҒAӮЖӮўӮӨӮ©”j“VҚrӮИҗ«ҠiӮЖӮжӮӯғOғүғrғAӮИӮсӮ©ӮЕҲА”„ӮиӮіӮкӮй”ьҸӯҸ—ӮЖӮН”дӮЧ•ЁӮЙӮИӮзӮИӮўҒAғzғ“ғӮғmӮМ”ьҸӯҸ—ӮЖӮўӮБӮҪ—e–eӮр’j‘•ӮЕ‘д–іӮөӮЙӮөӮДӮўӮйӮаӮБӮҪӮўӮИӮўӮЖӮұӮлӮӘӢtӮЙғCғCҒIҒ@ӮЖӮ©ӮИӮсӮЖӮ©ӮўӮӨӮжӮӯӮнӮ©ӮзӮИӮў—қ—RӮЕ”ФҠi•”ӮНӮЁӮлӮ©ҒAҠwҚZ’ҶӮМҗ¶“kӮ©Ӯз‘еҗlӢCӮЕӮ·ҒBӮЬӮБӮҪӮӯҒAӮӨӮҝӮМҠwҚZӮМҳA’ҶӮНғ}ғjғAғbғNӮЕҢӢҚ\ӮИӮұӮЖӮЕӮ·ҒB
Ғ@Ӯ ӮМүЯҢғӮИ”ӯҢҫӮа–lӮЖӮөӮДӮНӢЮӮсӮЕӮаӮзӮўӮҪӮўӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮұӮкӮ©ӮзҢҲ“¬ӮЙҚsӮӯӮМӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒAҺmӢCӮӘҚӮӮЬӮйӮМӮН—ЗӮўӮұӮЖӮЕӮ·ҒB
ҒuғCғPғӢҒIҒ@”Ф’·ӮМӮҪӮЯӮИӮзүҙӮНҺҖӮКӮЩӮЗӢШғgғҢӮөӮДғKғ`ғҖғ`ӮЙӮҫӮБӮДӮИӮБӮДӮвӮйҒIҒv
ҒuӮ¶ӮбӮ үҙӮНҗЕ—қҺmӮЙӮИӮйҒIҒv
ҒuӮ¶ӮбӮ –lӮНҢxҺ@ҠҜӮҫҒIҒv
ҒuӮ¶ӮбӮ ӮнӮҪӮөӮНғEғFғfғBғ“ғOғvғүғ“ғiҒ[ҒIҒv
Ғ@ӮИӮсӮМғRғ}Ғ[ғVғғғӢӮҫӮжҒAӮЬӮБӮҪӮӯҒB
ҒuӮНӮҹҒcҒcҒv
Ғ@ҺьҲНӮӘҗ·ӮиҸгӮӘӮй’ҶӮЕ–lӮНҲкҗlҒAӮҪӮЯ‘§ӮрӮВӮ«ӮЬӮөӮҪҒB
Ғ@ӮўӮӯӮз•”ҠҲӮЖӮНӮўӮҰ‘јҚZӮЖҢҲ“¬ӮҫӮИӮсӮДҒA–{“–ӮН“VүәӮЙӮНӮ»ӮсӮИҠлӮИӮўӮұӮЖӮрӮөӮД—~ӮөӮӯӮНӮИӮўӮМӮЕӮ·ҒcҒcҒBҸ—ӮМҺqӮӘғPғ“ғJӮИӮсӮДӮНӮөӮҪӮИӮўӮөҒAүҪӮжӮиҠлӮИӮўӮөҒB
Ғ\Ғ\ӮвӮБӮПӮи–lӮӘ“VүәӮрҺзӮзӮИӮ«ӮбҒ\Ғ\ҒB
Ғ@ҚrҺ–ӮӘӮ Ӯй“xӮЙӮ»ӮӨҢҲҲУӮ·ӮйӮаӮМӮМҒA–lӮӘ“VүәӮрҺзӮзӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҸуӢөӮЙӮИӮсӮ©ӮЬӮёӮИӮзӮИӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮрҒA–lӮНӮнӮ©ӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB
Ғ\Ғ\ӮҫӮБӮДҒA“VүәӮНӢӯӮўҒBӮ»ӮкӮаҗlӮМҲжӮрҲн’EӮөӮДӮўӮйӮЖҺvӮҰӮйӮЩӮЗҒB“VүәӮНӮ»ӮұӮҫӮҜӮbӮfӮЕҸo—ҲӮДӮўӮйӮЖӮаӮБӮПӮзӮМғEғҸғTӮЕӮ·ҒB
җМӮ©Ӯз“ӘӮаү^“®җ_ҢoӮа—ЗӮ©ӮБӮҪӮҜӮкӮЗҒAӮ»ӮкӮЕӮа•WҸҖӮМҲжӮрҸoӮйӮЩӮЗӮ¶ӮбӮИӮ©ӮБӮҪӮөҒAҸ¬ӮіӮўҚ ӮМ“VүәӮН•һ‘•ӮаҢҫ—tҢӯӮўӮаӮаӮБӮЖҸ—ӮМҺqӮзӮөӮ©ӮБӮҪҒB
ӮўӮБӮҪӮў”ЮҸ—ӮЙүҪӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮ©ҒAӮёӮБӮЖҗМӮ©ӮзҲкҸҸӮЙӮўӮй–lӮЙӮаӮнӮ©ӮзӮИӮўҒB
ҒuҚsӮӯӮјӮ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§ғbҒIҒv
Ғ@Ӣ©ӮФӮЖ“VүәӮН“GӮМ‘ТӮВҚZ’лӮЙҢьӮ©ӮБӮД‘–ӮиҸoӮөӮЬӮөӮҪҒB
Ӯ»ӮМӮжӮӯ“§ӮйҚӮӮўӮМӮЙ—ҺӮҝ’…ӮўӮҪӢ©ӮСӮЙҒA–ТҺТӮҪӮҝӮӘ—YӢ©ӮСӮрҸгӮ°ӮДҢгӮЙ‘ұӮ«ӮЬӮ·ҒB
–lӮНӢCҸжӮиӮөӮИӮўӮЬӮЬӮЕӮөӮҪӮӘҚЕҢг”цӮЙӮВӮ«ӮЬӮөӮҪҒB
”ФҠi•”ӮМ•ӣ•”’·ҒAӮ·ӮИӮнӮҝҒA“ҝҚӮӮМ— ”Ф’·ӮЖӮөӮДӮМ’иҲК’uҒAӮўӮнӮдӮйҒwғPғcҺқӮҝҒxӮЕӮ·ҒB
Ғu—ҲӮҪӮнҒIҒ@”ФҠi•”ӮжҒIҒv
Ғ@Ӯ ӮйҸ—җ¶“kӮМҚbҚӮӮўҗәӮрҚҮҗ}ӮЙҒAҚZҺЙӮМ‘ӢӮ©ӮзғLғғҒ[ғLғғҒ[ӮЖү©җFӮўҗәӮӘӮ ӮӘӮиӮЬӮ·ҒB
ҒuӮ«ӮбҒ[ҒIҒ@Ӯ©ӮБӮұӮўӮўҒIҒ@ҒiӮ ӮиӮӘӮЖӮӨҒIҒjҒv
Ғu•үӮҜӮсӮИӮжӮ§ҒIҒ@”ФҠi•”ҒIҒ@ҒiҠж’ЈӮиӮЬӮ·ҒIҒjҒv
ҒuӮнӮ«ӮбҒ[ҒIҒ@“ҝҗмӮӯӮЈӮсҒIҒ@Ҡж’ЈӮБӮДӮҘҒIҒ@Ғi“VүәӮНҸ—ӮҫӮјҒIҒjҒv
Ғu“ҝҗмӮҹҒIҒ@ҲӨӮөӮДӮйӮјӮ§ҒIҒ@ҒiӮ»ӮкӮН–lӮЙ‘ОӮ·Ӯй’§җнӮИӮсӮҫӮЛҒHҒjҒv
Ғu— ”ФӮаҠж’ЈӮкӮжӮ§ҒIҒ@Ғi— ”ФӮБӮДӮўӮӨӮ©•ӣ•”’·ӮИӮсӮҫӮҜӮЗӮЛҒjҒv
Ғu“VүәӮіӮсҠж’ЈӮБӮДӮҘҒIҒ@ӮЁҢZӮҝӮбӮсӮағPғKӮөӮИӮўӮЕӮЛӮҘҒIҒ@ҒiӮ ӮиӮӘӮЖӮӨҒA–…ӮжҒBӮЁҢZӮҝӮбӮсҠж’ЈӮйӮжҒjҒv
Ғu“V”nӮҹҒAӮЁ‘O–ЯӮБӮДӮұӮИӮўӮЖҺvӮБӮДҠчӮМҸгӮЙ’uӮўӮДӮ ӮБӮҪғAғbғvғӢғeғBҒ[ҲщӮсӮ¶ӮбӮБӮҪӮјӮ§ҒIҒ@ӮІӮЯӮсӮИӮҹҒIҒ@ҒiӮФӮБҺEӮ·ӮјғeғҒғFғFғFғFғbҒIҒ@ғAғbғvғӢғCғYғ}ғCғ\ғEғӢҒIҒjҒv
Ғu’rӮӯӮсҒAүцүдӮөӮИӮўӮЕӮЛҒIҒ@“БӮЙҠзҒIҒ@ҒiӮ ӮкҒHҒ@’jӮМҗәӮИӮсӮҫӮҜӮЗҒcҒcҒjҒv
ҒuғCғPғҒғ“ӮНҺҖӮЛӮҘҒIҒ@ҒiҗlӮрҺфӮнӮОҢҠ“сӮВҒcҒcҒjҒv
ҒuҲ·ӮіӮсӮМғJғ~ғ\ғҠҺJӮ«ҒA–С—ҳӮМ“zӮзӮЙҢ©Ӯ№ӮДӮвӮБӮДӮӯӮҫӮ№ӮҘҒIҒ@ҒiғJғ~ғ\ғҠӮНҠлӮЛӮҘҒIҒjҒv
ҒuӮЭӮсӮИҠж’ЈӮкӮжҒIҒ@җжҗ¶ҒAӮЁ‘OӮҪӮҝӮЙҢЬҗзү~“qӮҜӮДӮйӮсӮҫӮ©ӮзӮИҒIҒ@ӮөӮБӮ©ӮиүһүҮӮ·ӮйӮ©Ӯзҗв‘ОҸҹӮДӮжҒIҒ@ҒiӮұӮұӮМӢіҲх‘еҸд•vҒHҒjҒv
Ғ@‘ҪҺн‘Ҫ—lӮИҗәүҮӮЙҒA–Ъ—§ӮҝӮҪӮӘӮиӮМ“VүәӮН‘еҺиӮрҗUӮБӮДҒAғCғPғҒғ“Ӯв‘јӮМ•”Ҳх’BӮНӮФӮБӮ«ӮзӮЪӮӨӮИӮӘӮзҢyӮӯҺиӮрҸгӮ°ӮйӮИӮЗӮөӮДүһӮҰӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ғ@Ғ\Ғ\Ӯ Ӯ ҒAӮөӮ©ӮөҒAӮўӮВӮаӮИӮӘӮз•sүВҺvӢcӮИҢхҢiӮҫҒB
Ғ@ӮЗӮӨӮөӮДҠw“аӮЙ‘јҚZӮМҗ¶“kӮӘҗN“ьӮ·ӮйӮұӮЖӮаҒAӮ»ӮкӮЖҗ¶“kӮӘғPғ“ғJӮрӮ·ӮйӮұӮЖӮа—e”FӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮйӮМӮ©Ғ\Ғ\ҒB
Ғ@ӮЬӮБӮҪӮӯҒAӮ ӮсӮИ“ӘӮМӮЁӮ©ӮөӮў“Б‘[–@ӮіӮҰӮИӮҜӮкӮОҒAӮұӮсӮИӮұӮЖӮЙӮНӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЙҒB
Ғ@Ғ\Ғ\ҚЎӮр‘kӮйӮұӮЖ“с”N‘OҒAҗј—пӮQӮOӮOӮU”NҒB
Ғ@ҸӯҺqү»ӮӘӢ©ӮОӮкӮйҺһ‘гӮЙӮ ӮБӮДҸ®ҒAҸӯ”N”ЖҚЯӮН‘қүБӮМҲк“rӮр’HӮиҒAӮ»ӮМҺиҢыӮНӢЙҲ«ӮрӢЙӮЯҒAҠwҗ¶ӮҪӮҝӮМ“к’ЈӮи‘ҲӮўӮЕӢNӮ«ӮйғPғ“ғJӮНҢгӮрҗвӮҪӮИӮ©ӮБӮҪҒB
‘ОүһӮЙ’ЗӮнӮкӮҪҠwҚZҒAҢxҺ@ҒAҗӯ•{ӮН”жӮкүКӮДӮДӮўӮҪҒBӮИӮЙӮөӮлӮЗӮсӮИ‘ОҚфҲДӮрҸoӮ»ӮӨӮЖӮаҒA’ҶҒXҢшүКӮӘҸгӮӘӮзӮИӮўӮМӮҫҒBҗlҠФӮН–і‘КӮИӮұӮЖӮрӮ·ӮйӮЖҗёҗ_ӮЙ’ЙҺиӮӘӮӯӮйғCғLғӮғmӮҫҒB”жӮкӮН—ӯӮЬӮйҲк•ыӮҫӮБӮҪҒB
Ӯ»ӮсӮИӮ Ӯй“ъҒ\Ғ\ҒB
үҪ“x–ЪӮ©ӮаӮнӮ©ӮзӮИӮўӮЩӮЗҢJӮи•ФӮіӮкӮҪ‘ОҚфүпӢcӮЕҒAӮ·ӮБӮ©ӮиңЬңӘӮөӮҪҗӯҺЎүЖӮМҲкҗlӮӘ“VҢ[ӮӘүәӮБӮҪӮ©ӮМӮжӮӨӮЙ“Л‘R—§ӮҝҸгӮӘӮБӮДӮұӮӨҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ»ӮӨӮҫҒIҒ@Ӯ»ӮсӮИӮЙҢіӢCӮӘ—LӮи—]ӮБӮДӮйӮИӮзҒAӮаӮӨғPғ“ғJӮр•”ҠҲӮЙӮөӮҝӮбӮЁӮӨҒIҒv
Ғ@Ӯ»ӮкӮр•·ӮўӮҪҺьҲНӮМҺТ’BӮНӮұӮјӮБӮДҢҫӮБӮҪҒB
ҒwӮЁ‘OҒA“VҚЛӮ¶ӮбӮЛҒHҒx
Ғ@Ғ\Ғ\ҢгӮЙ–ј•tӮҜӮзӮкӮйҒwҠwҗ¶җнҚ‘Һһ‘гҒxӮМ–ӢҠJӮҜӮЕӮ ӮйҒB
‘SҚ‘Ҡe’nӮМҠeҠwҚZӮЙҲкҗlҒA”Ф’·Ӯр—pҲУӮіӮ№ҒA”Ф’·ӮЙҸ]ӮӨӮаӮМӮрҸWӮЯӮД•”ҠҲ“®ӮЖӮ·ӮйҒB
Ӯ»ӮМ–јӮаҒw”ФҠi•”ҒxӮЕӮ ӮйҒB
”ЮӮзӮМҠҲ“®ӮН‘јҚZӮМ”ФҠi•”ӮЖғPғ“ғJӮрӮ·ӮйӮМӮӘҺеӮҫҒB”ФҠi•”ӮМ–јӮМүәӮЙҚsӮнӮкӮйғPғ“ғJӮНғPғ“ғJӮЕӮНӮИӮӯҒAҺҺҚҮӮЖҢДӮОӮкӮйӮМӮҫӮӘҒAҺҺҚҮӮЖӮўӮӨӮ©ӮзӮЙӮН‘еүпӮӘӮ ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB
–Ҳ”NӮМүДӮЙҒw”ФҠiҚbҺqүҖҒxӮЖӮўӮӨҒw“ъ–{ҚЕӢӯҒxӮМҠwҗ¶ӮҪӮҝӮрҢҲӮЯӮйӮЖӮўӮӨҒAҺбҺТӮИӮзӮОҺ©‘RӮЖҢҢ•ҰӮ«“ч–фӮй‘SҚ‘‘еүпӮӘҠJҚГӮіӮкӮйҒB
ҺбҺТӮЙӮЖӮБӮДҒAҚЕӢӯӮЖӮўӮӨҢҫ—tӮНӮ»ӮкӮҫӮҜӮЕӮұӮМҸгӮИӮӯ–Ј—Н“IӮИӮаӮМӮҫҒB
”ФҠi•”ӮНӮЭӮйӮЭӮйӮӨӮҝӮЙҗlҗ”Ӯр‘қӮвӮөҒA”ФҠiҚbҺqүҖӮМғeғҢғr’ҶҢpӮМҺӢ’®—ҰӮНҚЎӮвҒAҚӮҚZ–мӢ…ӮМҚbҺqүҖ’ҶҢpӮр’ЗӮў”ІӮўӮДӮўӮйҒB
“Б‘[–@Һ{ҚsӮ©ӮзҺO”NҒA•Ҫҗ¬ӮМҗўӮНҢҢӮМӢCӮМ‘ҪӮўҠwҗ¶’BӮӘҢҢӮЕҢҢӮрҗфӮӨҗнҚ‘Һһ‘гӮЖү»ӮөӮДӮўӮҪҒB
ӮҫӮӘҺЎҲАӮӘҲ«ӮўӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒB
“ъ–{ӮМҺбҺТӮН”RӮҰӮДӮўӮйӮМӮҫҒBӮ»ӮӨҒAҚЎҒAҠwҗ¶’BӮНҒ\Ғ\ҒB
Ғ@Ғ\Ғ\Ҡwҗ¶’BӮНҚЎҒAҗӯ•{Ңц”FӮМғPғ“ғJӮЙ–ҫӮҜ•йӮкӮДӮўӮйҒI
җј—пӮQӮOӮOӮW”NҒAҺlҢҺҸ\ҢЬ“ъҒA‘ҫ—zҢn‘жҺOҳfҗҜ’nӢ…ӮН“ъ–{Қ‘ӮМҲӨ’mҢ§–^ҺsҒA”ФҠiҚbҺqүҖ—DҸҹӮр–ЪҺwӮ·үдӮз“ҝҗмҚӮҚZӮМҸүҗнҒA‘О–С—ҳҠwү@ҚӮҚZҗнӮМ–ӢӮӘҚ~ӮиӮжӮӨӮЖӮөӮДӮўӮҪҒB
ҺlҢҺ’ҶҸ{Ӯ©ӮзҳZҢҺ––ӮМҠФӮЙҢ§“аӮМ”ФҠi•”“ҜҺmӮЕҚ‘ҺжӮиҒAӮаӮЖӮўҒAҠwҚZҺжӮиҚҮҗнҒiғSғҚҲ«ӮўҒjӮрҚsӮўҒAҚЕҢгӮЬӮЕҺcӮБӮДӮўӮҪҒAӮаӮөӮӯӮНҠъ“ъӮЬӮЕӮЙҺx”zӮөӮҪҠwҚZҗ”ӮӘҚЕӮа‘ҪӮ©ӮБӮҪҠwҚZӮМ”ФҠi•”ӮӘ‘SҚ‘‘еүпҸoҸкӮМҗШ•„ӮрҺиӮЙ“ьӮкӮйҒBҺҺҚҮӮЙӮНҢҲӮЬӮБӮҪ“ъ’цӮНӮИӮӯҒAӮҪӮҫҢҲӮЯӮзӮкӮҪҠъҠФ“аӮЕҺ©—RӮЙ’ЧӮөӮ ӮӨӮМӮЭӮҫҒB
Ӯ»ӮМӮҪӮЯ–С—ҳҠwү@ҚӮҚZӮН—\‘IҠJҺnӮМҚЎ“ъҒAҚЕӮаӢЯӮӯӮЙӮ ӮБӮҪүдӮӘ“ҝҗмҚӮҚZӮЙҸҹ•үӮр’§ӮсӮЕӮ«ӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒ\Ғ\ҒB
Қ•ӮМҠwҗ¶•һӮЙҗgӮр•пӮсӮҫҠwҗ¶’BӮӘ—җ“¬ӮрҢJӮиҚLӮ°ӮҪҗнҸкҗХ’nҒi“ҝҗмҚӮҚZҚZ’лҒjҒAҺҖҺr—ЭҒXҒAӮҪӮБӮҪҲкҗlӮМҸӯҸ—ӮӘҚмӮиҸгӮ°ӮҪҺҖ‘МҒiҗ¶Ӯ«ӮДӮЬӮ·ӮжҒIҒjӮМӢuӮМ’ёҸгӮЕҒA—[—zӮр”wӮЙӮөӮҪғ|ғjҒ[ғeҒ[ғӢӮӘҲкҗlҒA—HӢSӮМӮІӮЖӮӯ—§ӮБӮДӮўӮйҒB
ҒuӮУӮУҒA–С—ҳҠwү@ҒAӮаӮӨҸӯӮөҚңӮӘӮ ӮйӮ©ӮЖҺvӮБӮДӮўӮҪӮӘҒAҢыӮЩӮЗӮЙӮаӮИӮ©ӮБӮҪӮИҒv
Ғ@ӮұӮұҒAҲӨ’mӮМӮ ӮйҸкҸҠӮЕҒA“ъ–{ӮМҒA”ЫҒAҗўҠEӮМ”Ф’·ӮЖӮИӮйӮЧӮ«ҠнӮМҺТӮӘҒAҸҷҒXӮЙҒAӮөӮ©ӮөҠmҺАӮЙ”eүӨӮЦӮМ“№Ӯр•аӮЭҺnӮЯӮДӮўӮҪҒB
Ғ\Ғ\ӮұӮМ•ЁҢкӮНҒA‘SҚ‘җ§”eӮр–ЪҺwӮ·ҸӯҸ—ҒAҺһ‘гӮӘҗ¶ӮсӮҫ•Ҫҗ¬ӮМ•—ү_ҺҷҒiҒHҒjҒA“ҝҗм“VүәӮЖҒA”ЮҸ—ӮМ–Ј—НҒiҒHҒjӮЙҲшӮ«ҚһӮЬӮкӮҪҒiҠӘӮ«ҚһӮЬӮкӮҪҒHҒjҗlҒXӮМҒA“җӮсӮҫғoғCғNӮЕғJғb”тӮОӮөӮДӮөӮЬӮӨӮжӮӨӮИҺбӮіӮЖҒA”MӮ«җнӮўӮЖҒAӮ»ӮөӮДӢ№Ӯр“ЛӮӯӮжӮӨӮИҗШӮИӮў—цӮМ•ЁҢкҒ\Ғ\ӮзӮөӮўӮЕӮ·ӮжҒH
•”‘ҘӮ»ӮМҲкҒ@Ғw”ФҠiӮҪӮйҺТҒA”ьӮөӮӯӮ ӮкҒIҒx
ҒuӮЁӮўҒAӮЩӮсӮЖӮЙғ„ғӢӢCӮИӮМӮ©ҒHҒv
ҒuӮ Ӯ ҒAүҙӮН–{ӢCӮҫҒv
Ғ@ӮӨӮзӮзӮ©ӮИ—zҢхҚ·ӮөҚһӮЮ’ӢӢxӮЭӮМӢіҺәҒA–lӮМҺҝ–вӮЙҗ^Ң•ӮИ–КҺқӮҝӮЕ“ҡӮҰӮҪғNғүғXғҒғCғgӮЙӮөӮД•”—FӮЕӮ Ӯй‘O“cҢcҲкҳYӮрҲНӮсӮҫ–lӮЖ“VүәӮНӮИӮсӮЖӮНӮИӮөӮЙҒAӢіҺәӮМ“ьҢы•tӢЯӮЕ—F’BӮЖ—§ӮҝҳbӮрӮөӮДӮўӮйӢ№ӮМӮУӮӯӮжӮ©ӮИҸ—ӮМҺqҒAҗО“cӮіӮсӮЙ–ЪӮрҢьӮҜӮЬӮөӮҪҒB
Ғu–{“–ӮЙҗО“cӮіӮсӮрҒHҒv
ҒuӮЁӮӨҒAӮаӮӨүд–қӮИӮзӮсҒAүҙӮНҗО“cӮМ“ыӮрқҶӮЮӮјҒIҒv
Ғ@“ҜӮ¶”ФҠi•”ҲхӮЕӮ Ӯй‘O“cҢcҲкҳYҒAӮұӮўӮВӮӘ“Л”ҸҺqӮа–іӮўӮұӮЖӮрҢҫӮўҸoӮ·ӮМӮН•КӮЙ’ҝӮөӮўӮұӮЖӮЕӮНӮИӮўӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҚЎүсӮНӮ»ӮМ“Л”ҸҺqӮМ–іӮіӮӘҸнӮМҺO”{ӮНӮ ӮБӮҪӮМӮЕ–lӮЖ“VүәӮНҸӯӮөҚўӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒB
ҒuҺQҚlӮЬӮЕӮЙҲкӮВ•·Ӯ«ӮҪӮўҒBӮИӮЙӮӘӮЁ‘OӮрӮ»ӮұӮЬӮЕҒ\Ғ\Ғv
ҒuүҪҢМӮЖ–вӮӨӮ©ҒAҗD“cӮжҒBӮИӮзӮО“ҡӮҰӮжӮӨҒv
Ғ@‘O“cӮН‘ӢҚЫӮЙ—§ӮБӮДҚ·ӮөҚһӮЮ“ъӮр”wӮЙӮөҒAҢқӮр“VҚӮӮӯ“ЛӮ«ҸгӮ°ҒAӮ»ӮөӮДӢ©ӮсӮҫҒB
ҒuӮ»ӮұӮЙ“сӮВӮМҺRҒAӮаӮЖӮўҒA“ыӮӘӮ ӮйӮ©ӮзӮҫҒIҒv
Ғ@ӮІӮЯӮсҒAҚЎӮМӮЁ‘OҒAӮҝӮеӮБӮЖӮ©ӮБӮұӮўӮўӮжҒBӮ©ӮФӮ«ҺТӮМӢЙӮЭӮҫӮжҒB
Ғ\Ғ\ӮЕӮа“ҜҺһӮЙӮнӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒB‘O“cҒAӮЁ‘OғAғzӮҫӮлҒB
ҒuӮҫӮўӮҪӮўүҙӮНҸнҒXҺvӮБӮДӮўӮҪҒIҒ@үҪҢМӮ ӮМҸ—ӮНҺ©җgӮӘғZғNғnғү‘е–Ӯҗ_ӮИӮМӮЙүҙӮҪӮҝӮӘҺd•ФӮөӮЙҗGӮлӮӨӮЖӮ·ӮйӮЖҢҷӮӘӮйӮсӮҫҒIҒv
ҒuӮ»ӮкӮНҸ—җ«ӮЖӮөӮД“–‘RӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЛҒHҒ@‘O“cӢЁҒv
Ғ@•”—FӮӘүдӮр–YӮкӮ»ӮӨӮИӮМӮЙ‘ОӮөҒA–lӮН—вҗГӮЙҗШӮи•ФӮөӮЬӮөӮҪҒB
ҒuүҪӮрӮЁӮБӮөӮбӮйҒAҗD“c”ҢҺЭҒIҒ@”ЮҸ—ӮЙҸ—җ«ӮЖӮөӮДӮМ’pӮ¶ӮзӮўӮвҗЯ“xӮӘӮ ӮйӮЖӮЕӮаҒHҒ@ӮЁӮ©ӮөӮўӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒA”ЮҸ—ӮНҚZ’лӮЙғGғҚ–{ӮӘ—ҺӮҝӮДӮўӮйӮМӮрҢ©ӮВӮҜӮкӮОҺцӢЖ’ҶӮЕӮа“БҺк•”‘аӮМ“®Ӯ«ӮЕ‘ӢӮ©Ӯз”тӮСҸoӮөӮДӮўӮӯӮөҒAҗј“ғҺOҠKӮМҸ—ҺqҚXҲЯҺәӮЕҸ—ҺqӮӘ’…‘ЦӮҰӮДӮўӮкӮО–ШӮЙ“oӮиҒAғIғyғүғOғүғXӮрҺgӮБӮДӮЕӮа”`ӮӯғZғNғVғғғҠғXғgӮҫҒBӮ»ӮөӮДҺ„Ӯа“ҜӮ¶ӮҫҒBҺ„ӮЖӮДҚZ’лӮЙғGғҚғrғfғIӮӘ—ҺӮҝӮДӮўӮҪӮзҺцӢЖ’ҶӮҫӮлӮӨӮӘҠъ––ғeғXғg’ҶӮҫӮлӮӨӮӘ–АӮнӮё”тӮСҸoӮөӮД–ІӮрғQғbғgӮ·ӮйҒiӮ«ӮБӮЖ‘еҠw“ьҺҺӮМҚЕ’ҶӮЕӮ·ӮзҺ„ӮН–ІӮр’ЗӮӨӮМӮҫӮлӮӨҒjӮ»ӮөӮДҸ—ҺqҚXҲЯҺә”`Ӯ«ӮНӮаӮҝӮлӮсҒAҺ„ӮНғXғJҒ[ғgӮМ’ZӮўҸ—ҺqӮӘҠK’iӮр“oӮБӮДӮўӮҪӮҫӮҜӮЕӮа–АӮнӮё”`ӮҜӮйғXғ|ғbғgӮЙ“җ—ЫӮМ“ҫҲУӮИҚbҺqүҖӢ…ҺҷӮОӮиӮМғwғbғhғXғүғCғfғBғ“ғOӮрҠёҚsӮ·ӮйӮЩӮЗӮМӢӯ•әӮҫҒBӮ»ӮМҲУ–ЎӮЕҒAғGғҚғXӮрӢЙӮЯӮсӮЖӮ·ӮйҺ„ӮЖ”ЮҸ—ӮН“Ҝ‘°ҒBӮаӮБӮЖ“ч‘М“IғXғLғ“ғVғbғvӮрҗ}ӮБӮДӮаӮўӮўӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒHҒv
Ғ@ӮўӮ©ӮсҒAӮұӮўӮВӮН‘е•ПӮҫҒBӮҪӮўӮЦӮсӮИӮЦӮсӮҪӮўӮҫҒB
ҒuӮ»ҒAӮ»ӮкӮНҒAӮ»ӮӨӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮсӮӘҒAӮЁ‘OӮМ•ЁҢҫӮўӮЕӮНӮЁ‘OӮМӮЩӮӨӮӘ•П‘ФӮЙ•·ӮұӮҰӮйӮӘҒv
Ғu–іҳ_ҒAүҙӮН•П‘ФӮҫҒBҺ©ҠoӮаӮ ӮйӮөҢЦӮиӮаӮ ӮйҒv
ҺқӮВӮИӮжҒAӮ»ӮсӮИҢЦӮиҒcҒcҒB
ҒuӮИӮМӮЙӮИӮә”ЮҸ—ӮНүҙӮр”рӮҜӮйҒIҒ@үҙӮҫӮБӮДҺцӢЖ’ҶӮНҸ\•bӮЙҲк“xғGғҚғCӮұӮЖӮрҚlӮҰӮДӮўӮйғGғҚғ\ғҖғҠғGӮҫҒIҒ@“Л‘RӢіҺtӮЙҺw–јӮіӮкҒA—§ӮҝҸгӮӘӮБӮД”ӯ•\Ӯ·ӮйӮЖӮ«ӮИӮЗӮжӮӯ‘OӮ©ӮӘӮЭӮЙӮИӮйӮЁ’ғ–ЪӮіӮсӮҫҒIҒ@ӮИӮМӮЙӮИӮә”ЮҸ—ӮН“Ҝ‘°ӮМүҙӮр”рӮҜӮйӮМӮҫҒIҒ@үҪҢМӮ ӮМ“ыӮНүҙӮМӮаӮМӮЙӮИӮзӮсҒIҒ@ӮаӮӨүд–қӮЕӮ«ӮсҒIҒ@үҙӮНҒAүҙӮНҒ\Ғ\үp—YӮЙӮИӮйҒIҒv
Ғu‘O“cҒAӮЁ‘OҒ\Ғ\Ғv
Ғ@ӮұӮМ’jҒAғ}ғWӮҫҒB
Ғ@–lӮЙӮНӮұӮМ’jӮрҺ~ӮЯӮйӮМӮН–і—қӮ»ӮӨӮИӮМӮЕҒAҚЕӢӯ”Ф’¬ӮМ“VүәӮЙҸ•ӮҜӮрӢҒӮЯӮЬӮ·ҒB
Ғu“VүәҒAҺ~ӮЯӮИӮўӮМӮ©ҒHҒ@“ҜӮ¶Ҹ—ӮМҺqӮӘғZғNғnғүӮіӮкӮ»ӮӨӮИӮсӮҫӮјҒHҒv
ҒuӮӨҒ[ӮсҒAӮ»ӮӨӮИӮсӮҫӮҜӮЗӮИӮҹҒAҗО“cӮЙӮНғIғҢӮа–Ҳ“ъӮМӮжӮӨӮЙғZғNғnғүӮіӮкӮДӮйӮ©ӮзҒA”нҠQҺТӮМӢCҺқӮҝӮр’mӮБӮДӮаӮзӮӨӮўӮўӢ@үпӮҫӮЖҺvӮБӮДҒv
ҒuӮ»ӮӨӮҫӮБӮҪӮИҒAӮ»ӮӨӮўӮҰӮОҒv
Ғ@ҲУҠOӮЙӮа“VүәӮМӮЁӢ–ӮөӮӘҸoӮЕӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBӮЖӮИӮкӮОҒAҚӮҚZ“с”Nҗ¶ӮМҢ’ҚN“IӮИ’jҺqӮЕӮ Ӯй–lӮаҗgӮМҗUӮи•ыӮр•ПӮҰӮЛӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒB“–‘RҒAҺжӮй‘I‘рҺҲӮНҲкӮВҒ\Ғ\ҒB
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒAӮ¶ӮбӮ –lӮаӮЁӮБӮПӮўӮЕҒIҒv
Ӣ©ӮФӮИӮи–lӮЖ‘O“cӮНӢіҺәӮМ“ьӮиҢыӮЦӮЖ–ТҗiҒI
ҒuӮҰҒIҒ@“V”nҒAӮЁ‘OӮаӮ©ҒHҒ@Ӯ»ҒAӮ»ӮкӮНӮвӮЯӮҪӮЩӮӨӮӘӮўӮўӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒHҒv
Ғ@“VүәӮӘӮ ӮнӮДӮДӮўӮЬӮ·ҒB
ҒuӮҫӮӘ’fӮйҒIҒIҒv
–lӮНӮ»ӮӨҢҫӮў•ъӮВӮЖҒAӮаӮНӮвҢгӮлҸИӮЭӮёҒA“аӮИӮйҸC—…ӮЙҗgӮр”CӮ№ӮДӮРӮҪ‘–ӮиӮЬӮөӮҪҒI
җжӮрҚsӮӯ‘O“cӮӘӮ»ӮМ‘ҒӢмӮҜӮЕ“GӮМ‘oашӮЙ“һ’BҒIҒI
“GӮНҗN“ьӮрӢ–ӮөӮҪӮұӮЖӮЙӢC•tӮўӮДӮўӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB‘O“cӮНӮЙҠпҸPҗ¬ҢчҒIҒI
Ғu“V”nҒIҒ@ҢгӮЙ‘ұӮҜӮҘҒIҒIҒv
ҒuӮЁӮӨӮжҒIҒ@“с”Ф‘„ҒIҒ@җD“c“V”nҺQҸгғbҒIҒIҒ@ӢЮӮсӮЕӮЁ‘ҠҺиӮўӮҪҒAғCғ^ҒAғCғ^ғ^ҒA’ЙӮўҒI“VүәӮвӮЯӮДҒIҺЁҲшӮБ’ЈӮсӮИӮўӮЕҒIҒIҒv
•·ӮўӮДӮМӮЖӮЁӮи–lӮН“VүәӮЙҺ~ӮЯӮзӮкӮЬӮөӮҪӮӘҒA‘O“cӮМүEҺиӮНүhҢхӮрҺиӮЙӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB
ҸҷҒXӮЙҗО“cӮіӮсӮМ–jӮӘҚg’ӘӮөӮДӮўӮ«Ғ\Ғ\
ҒuӮ«ӮбӮ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ Ӯ ғbҒIҒv
җО“cӮіӮсӮӘҺЁӮрӮВӮсӮҙӮӯӮжӮӨӮЙ”Я–ВӮрҸгӮ°ӮЬӮ·ҒB
ҒuӮвҒAӮвӮБӮҪҒcҒcҒBӮвӮБӮҪӮјӮ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§Ӯ§ҒIҒv
Ғ@Ӯ»ӮӨӢ©ӮсӮҫ‘O“cӮНҠҙӢЙӮЬӮБӮД—ЬӮр—¬ӮөӮЬӮөӮҪҒB’jӢғӮ«ӮЖӮўӮӨӮвӮВӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒB
Ғ@ӢіҺә“аӮӘӮҙӮнӮЯӮ«ҺnӮЯӮЬӮ·ҒB
ҒuӮЁӮўҒAӢғӮўӮҪӮјҒIҒ@Ӯ ӮМ‘O“cӮӘҒIҒ@Ҹ¬ҠwҚZӮМӮұӮл‘g‘М‘ҖӮЕғnғuӮЙӮіӮкӮДҗжҗ¶ӮЖ‘gӮЬӮіӮкӮДӮаӢғӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪӮ ӮМ‘O“cӮӘҒIҒiҲЙ“ЎҒjҒv
Ғuғzғ“ғgӮҫҒAӢғӮўӮДӮйҒIҒ@’ҶҠwҺһ‘гҒAҗg‘М‘Ә’иӮМ“ъӮЙҠФҲбӮҰӮДҗe•ғӮМ”’ғuғҠҒ[ғtӮрӮНӮўӮДӮ«ӮДӮ»ӮкӮр”nҺӯӮЙӮіӮкӮДӮаӢғӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪӮ ӮМ‘O“cӮӘҒIҒi‘OҢҙҒjҒv
ҒuҸoүпӮўҢnғTғCғgӮЕ’mӮиҚҮӮБӮҪҸ—җ«ӮӘҸ¬ҠwҚZӮМӮұӮлӮМү¶ҺtӮҫӮБӮҪӮЖӮ«ӮаӢғӮ©ӮёӮЙ‘ПӮҰӮҪӮ ӮМ‘O“cӮӘҒIҒi•җ“cҒjҒv
ҒwҒ\Ғ\ӢғӮўӮДӮўӮйҒIҒx
Ғ@
ҒuӮЁ‘OӮзӮҹҒIҒv
Ғ@үдӮӘҚZӮМ–ј•Ё•—ӢIҲПҲх’·ӮӘ—җ“ьӮөӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒBғZҒ[ғүҒ[•һӮМҺ—ҚҮӮӨ”ьҗlӮЕӮ·ҒB”ЮҸ—ӮН“VүәӮЙүHҢрӮўҚiӮЯӮЙӮіӮкӮДӮўӮй–lӮрҢ©ӮДҢҫӮўӮЬӮөӮҪҒB
ҒuҗD“cҒIҒ@ӮЁ‘OӮЬӮЕҒcҒcҒBӮӯғbҒA”nҺӯӮОӮБӮ©ӮиӮМ”ФҠi•”ӮЕӮН—BҲкӮЬӮЖӮаӮИ“zӮҫӮЖҺvӮБӮДӮҪӮМӮЙҒ\Ғ\ҒBӮҜӮөӮ©ӮзӮсҒIҒ@ӮЩҒAӮЩӮЩҒA•ъүЫҢгӮҝӮеӮБӮЖ•tӮ«ҚҮӮҰҒIҒv
Ғ@Ӯ ӮйӮҘҒ[ҒHҒ@ӮИӮсӮҫӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўӮҜӮЗғfҒ[ғgӮМӮЁ—UӮўҒHҒiӢғҒj
Ғ@ӮўӮвӮҹҒAғӮғeӮйӮБӮДҗhӮўӮИӮҹҒB‘AӮЬӮөӮўӮ©ӮзӮБӮД–ј‘OӮрҸ‘Ӯ©ӮкӮҪӮзӮ»ӮМҗlӮӘҺҖӮсӮЕӮөӮЬӮӨғmҒ[ғgӮЙ–lӮМ–ј‘OӮрҸ‘Ӯ©ӮИӮўӮЕӮӯӮҫӮіӮўӮЛҒH
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@–і–@“VӮЙ’КӮёҒIҒIҒ@ӮЬӮҫӮЬӮҫ‘ұӮӯӮјғHҒIҒIҒI
|
|
|
|
| ҒuҸpҺmҒvҒ@Ғ@ҳAҚЪҺ® Ғ@’ҳҒ@Ғ@“с”Nҗ¶ҒFҒ@Ito |
|
|
|
Ғ@“ъ–{ӮЙӮНҒAҢҲӮөӮД—рҺjӮЙ“oҸкӮ·ӮйӮұӮЖӮМӮИӮўҲк‘°ӮӘ“сӮВ‘¶ҚЭӮ·ӮйҒB—рҺjӮМ— ӮЙҸнӮЙүо“ьӮө‘ұӮҜҒAӮҜӮкӮЗҺjҺАӮЙ–јӮӘӢLӮіӮкӮйӮұӮЖӮНӮИӮўҒB
Ғ@ҲкӮВӮНҒwҺҶҸpҺtҒxҒAӮ»ӮөӮДӮаӮӨҲкӮВӮНҒw–aҸpҺtҒxҒBҢИӮӘҺқӮВ—НӮр‘ҖӮй”}үоӮ©ӮзҒAӮ»ӮӨҢДӮсӮЕӮўӮҪҒB
Ғ@“ъ–{ҺjӮМҸгӮЕүҪӮ©‘ҲӮўӮӘӮ ӮйҺһҒAӮ»ӮкӮН“сӮВӮМҲк‘°ӮӘүҪӮзӮ©ӮМ—ҳҢ ӮрӢҒӮЯӮй‘ҲӮўӮҫӮБӮҪҒBӢӯ‘еӮИ—НӮрҺқӮҝҒAҢҢӮМҢӢ‘©ӮрҲИӮБӮДҗўӮр“nӮБӮҪҒBӮ ӮйҺһӮНҢ —НҺТӮрүщҸ_ӮөҒAӮ ӮйҺһӮН–ҜҸOӮрҗо“®ӮөҒAӮ ӮйҺһӮН‘SӮӯҺpӮрҸБӮөӮҪҒBӮ»ӮӨӮөӮДҸнӮЙҲЕӮМ’ҶӮ©ӮзҒA“ъ–{Ӯр‘ҖӮи‘ұӮҜӮҪҲк‘°ҒBӮ»ӮМ‘¶ҚЭӮНҚLӮӯ’mӮзӮкӮйӮұӮЖӮНӮИӮӯҒAӮЬӮҪҒA–јӮр’mӮйҺТӮӘҠF–іӮЖӮИӮйӮұӮЖӮаӮИӮӯҒAҺһӮрүәӮБӮҪҒB
Ғ@Һһ‘гӮН•ПӮнӮиҒAҢ —НӮаҺҹ‘жӮЙҺpӮр•ПӮҰӮҪҒBҢ —НҺТӮрүщҸ_ӮөӮДӮаҒA“ҫӮзӮкӮй—ҳүvӮНҢёӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҢ©җШӮиӮрӮВӮҜӮҪ“сӮВӮМҲк‘°ӮНҒA—рҺjӮМ— ‘ӨӮ©ӮзӮ·ӮзӮаҺpӮрҸБӮөӮҪҒBӮҪӮҫӮМ–}—fӮИҗlҠФӮЙҚ¬Ӯ¶ӮБӮДҗ¶Ӯ«ӮйӮұӮЖӮрҒA”ЮӮзӮН‘I‘рӮ·ӮйҗUӮиӮрӮөӮҪӮМӮҫҒB
Ғ@ҲА“gӮөӮДӮўӮҪӮМӮНҒA”ЮӮзӮрҺжӮиҚһӮЮӮұӮЖӮЙҺё”sӮөӮҪҺТҒBӢtӮЙӢ°•|ӮрҠoӮҰӮҪӮМӮНҒA”ЮӮзӮр—ҳ—pӮөӮжӮӨӮЖӮөӮД—ҳ—pӮіӮкӮДӮўӮҪҺТҒB•\ӮЙӮНҢҲӮөӮД’mӮзӮкӮйӮұӮЖӮМӮИӮўҚ¬—җӮӘҒA”ЮӮзӮрҸPӮБӮҪҒB
Ғ@ӮҫӮӘҒAӮ»ӮкӮ©ӮзүҪ”NӮаҒwҸpҺtҒxӮН—рҺjӮЙҢ»ӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBҢ —НӮЙӮЁӮаӮЛӮйӮұӮЖӮаҒA–ҜҸOӮрҗо“®Ӯ·ӮйӮұӮЖӮаӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB‘¶ҚЭӮр’mӮйҺТӮаҒAҺҹ‘жӮЙҢёӮБӮҪҒBҲк‘°ӮН–Е–SӮөӮҪӮМӮҫӮЖҚlӮҰӮйҺТӮаӮўӮҪҒBҲҪӮўӮНҒAҒwҸpҺtҒxӮМ—НӮрҺёӮБӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҚlӮҰӮйҺТӮаӮўӮҪҒBҒ\Ғ\ӮЗӮҝӮзӮаҒAүјҗаӮМҲжӮрҸoӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ғ@Ӯ»ӮӨӮөӮДҒwҸpҺtҒxӮМ‘¶ҚЭӮНҒA”јӮО“`җаӮЖү»ӮөӮҪҒB‘¶ҚЭӮр’mӮйҺТӮНӮўӮДӮаҒAҺАҚЫӮЙүпӮБӮҪӮұӮЖӮМӮ ӮйҺТӮНӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ғ@ӮҫӮӘҒA–Е–SӮөӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўҒBӮҪӮҫ‘§ӮрҗцӮЯӮДӮўӮҪӮҫӮҜӮЕҒAҲк‘°ӮНҲк‘°ӮЖӮөӮД‘¶ҚЭӮрӮВӮГӮҜӮДӮўӮҪӮМӮҫҒB
Ғ@–nӮрӮ·Ӯйү№ҒAӮіӮзӮіӮзӮЖ•MӮМҠҠӮйү№Ғ\Ғ\ҺЁӮЙҠөӮкӮҪү№Ӯр•·Ӯ«ӮИӮӘӮзҒAӢгҸр –цӮа•MӮрҺжӮБӮҪҒBҸTӮЙ“сүсӮМ•”ҠҲӮНҒAҠwҚZӮМҸ‘“№ҺәӮЕҚsӮнӮкӮйҒB•MӮӘҺиӮЙ“йҗхӮсӮҫӮЖҺvӮӨӮМӮНҒA•MҗжӮӘ”јҺҶӮЙҗGӮкӮҪҺһҒA–nӮӘҺҶӮЙ—ҺӮҝӮДҒAҸүӮЯӮД•MӮЖҲк‘МӮЙӮИӮБӮҪӮжӮӨӮИҠҙҠoӮӘҗ¶ӮЬӮкӮйҒBҲкӢCӮЙҸ‘Ӯ«ҸгӮ°ҒA•MӮр’uӮўӮҪҒB
ҒuӮ ӮзӢгҸрӮіӮсҒA“°ҒXӮЖӮөӮҪҺҡӮЛҒv
Ғ@–цӮӘҸ‘Ӯ«ҸгӮ°ӮҪҺҡӮрҢ©ӮДҒAҸъ‘хӢі—@ӮНҗәӮрӮ©ӮҜӮйҒBҲк•”ӮЕӮН—L–јӮИҸ‘“№үЖӮзӮөӮўӮМӮ©ӮӘҒAӮИӮәӮ»ӮсӮИҗlӮӘҺгҸ¬Ҹ‘“№•”ӮМҺw“ұӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮ©ҒcҒc“дӮЕӮ ӮйҒBӮҝӮИӮЭӮЙҒAҚм•iӮН”„ӮкӮДӮўӮйӮМӮЕҗ¶ҠҲӮЙҚўӮБӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨ–уӮЕӮаӮИӮўӮзӮөӮўҒBҒcҒcӮвӮНӮи“дӮҫҒB
ҒuӮ ӮиӮӘӮЖӮӨӮІӮҙӮўӮЬӮ·Ғv
ҒuӮ ҒAӮ»ӮӨӮ»ӮӨҒB—ҲҢҺӮМғRғ“ғNҒ[ғӢҒAӢгҸрӮіӮсҸoӮіӮИӮўҒHҒv
ҒuӮНӮ ҒcҒcҒv
Ғ@Һ©–қӮЕӮНӮИӮўӮӘҒAҺАӮН–цӮНҲк•”ӮЕҒiӮұӮкӮаҲк•”ӮҫҒj—L–јӮИӮМӮҫҒB‘SҚ‘ӢK–НӮМғRғ“ғNҒ[ғӢӮЕӢаҸЬӮЖҺжӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮйӮМӮЕҒiҚӮҚZҗ¶ӮМ•”ӮҫӮБӮҪӮӘҒjҒA–ј‘OӮҫӮҜӮН’mӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮсӮИӮұӮсӮИӮЕҒAӮұӮӨӮөӮДӮЩӮўӮЩӮўҚм•iӮрҸoӮ·ғnғҒӮЙӮИӮйӮМӮҫӮӘҒB
ҒuӮЕҒAӮЗӮБӮҝӮЙҸoӮ·ҒHҒ@үЫ‘иҒHҒ@Ӯ»ӮкӮЖӮаҺ©—RүЫ‘иҒHҒv
ҒuҒcҒcҒcҒcҒv
Ғ@‘К–ЪӮҫҒBҠ®‘SӮЙҸoӮ·ӮұӮЖӮӘҢҲ’иӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮӨӮИӮйӮЖүҪӮрҢҫӮБӮДӮа–і‘КӮИӮМӮНҒA–цӮаӮжҒ\Ғ\ӮБӮӯ’mӮБӮДӮўӮҪҒB
ҒuҒcҒcүЫ‘иӮЕҒv
ҒuӮ Ӯз’ҝӮөӮўҒBӮўӮВӮаӮИӮзӢгҸрӮіӮсӮНҺ©—RүЫ‘иӮИӮМӮЙҒBҒv
ҒuӮҰӮҰҒAӮЬӮ Ғv
Ғ@ҠmӮ©ӮЙҒAҺ©•ӘӮЕҺҡӮрҚlӮҰӮйҒA•S•аҸчӮБӮДӮа•Ўҗ”ӮМүЫ‘иӮ©Ӯз‘IӮФ•ыӮӘҚDӮ«ӮҫӮБӮҪҒBӮҫӮӘҒAҚЎӮНӮ»ӮӨӮаҢҫӮБӮДӮзӮкӮИӮўҒB
ҒuӮҝӮеӮБӮЖҚЎҒAҗFҒX–ZӮөӮўӮМӮЕҒv
ҒuӮ»ӮӨӮҫӮБӮҪӮМҒv
ҒiӮ»ӮӨӮҫӮБӮҪӮсӮЕӮ·Ғj
Ғ@“аҗSӮЕ•ФҺ–ӮрӮөҒAӮВӮўӮЕӮЙҗ[ҒXӮЖ—ӯӮЯ‘§ӮрӮВӮ«ӮҪӮӯӮИӮБӮҪҒB
Ғ@ҲкҸTҠФӮЩӮЗ‘OӮҫӮБӮҪӮ©ҒAӮвӮНӮи•”ҠҲӮМӢAӮиӮМӮұӮЖӮҫҒBҲкҗlӮЕҚZ–еӮрҸoӮйӮЖҒAҲкҗlӮМ’jӮӘ—§ӮБӮДӮўӮҪҒB•sҗRӢЙӮЬӮиӮИӮўӮМӮЕҒA–іҺӢӮөӮД’КӮиүЯӮ¬ӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒBҒcҒcӮӘҒB
ҒuҒcҒcӮЁ‘OҒAҒwҸpҺtҒxӮҫӮИҒv
ҒuӮҰҒHҒv
Ғ@үҪӮ©ҷкӮ©ӮкҒAҺvӮнӮёҗUӮи•ФӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB
ҒuҒ\Ғ\ҒwҺҶҸpҺtҒxӮ©Ғv
Ғ@үҪӮрҢҫӮнӮкӮДӮўӮйӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒB“ъ–{ҢкӮр’қӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮНҠmҺАӮИӮМӮҫӮӘҒAӮ»ӮкӮЙӮөӮДӮаҲУ–ЎӮӘ’КӮ¶ӮИӮўӮМӮҫҒB
ҒuҸӯҒXҺиӮұӮёӮБӮҪӮӘҒAҢ©ӮВӮ©ӮБӮҪӮҫӮҜғ}ғVӮҫҒv
Ғ@Ғ\Ғ\җgӮМҠлҢҜӮрҠҙӮ¶ӮҪҒB‘ҠҺиӮӘүцӮөӮӯҒAҢҫӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮаҲУ–Ў•s–ҫҒAҚXӮЙҺ©•ӘӮр’TӮөӮДӮўӮҪӮзӮөӮўҒBӮұӮұӮЬӮЕ‘өӮҰӮОҒAӮҪӮЖӮҰӢ©ӮсӮЕӮа“ҰӮ°ҸoӮөӮДӮа•sҗRӮЕӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB
Ғ@–цӮӘ‘IӮсӮҫӮМӮНҒA“ҰӮ°ҸoӮ·•ыӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮЁӮў‘ТӮДҒBүцӮөӮўҺТӮ¶ӮбӮИӮўҒv
ҒuӮ»ӮкҢҫӮБӮДӮйҺһ“_ӮЕҒAҗв‘ОүцӮөӮўҒIҒIҒv
Ғ@Ӣ©ӮОӮИӮҜӮкӮО—]ҢvӮИ‘М—НӮрҺgӮнӮёӮЙҚПӮЮӮМӮҫӮӘҒAӢ©ӮСӮЕӮаӮөӮИӮўӮЖӮвӮБӮДӮзӮкӮИӮўӮМӮҫӮБӮҪҒB
Ғ@ӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҒA–цӮН‘«ӮӘӮ ӮЬӮи‘ҒӮӯӮИӮўҒBӮЖӮўӮӨӮ©ҒAӮНӮБӮ«ӮиҢҫӮБӮД’xӮўҒB‘«ӮӘ’xӮўӮ©ӮзҸ‘“№•”ӮЙӮўӮйӮМӮ©ҒAҸ‘“№•”ӮЙӮўӮйӮ©Ӯз‘«ӮӘ’xӮўӮМӮ©ҒBҒ\Ғ\ӮЖӮўӮӨ–уӮЕҒBӮ ӮБӮіӮиүсӮиҚһӮЬӮкҒA“№ӮрҚЗӮӘӮкӮҪҒBӮұӮұӮЕҚXӮЙ“ҰӮ°ӮзӮкӮйӮЩӮЗҒAҺқӢv—НӮаӮИӮўҒB
Ғu—ҠӮЭӮҪӮўӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒv
ҒuҒcҒcүҪҒHҒv
Ғ@Ҡ“ӮрҲ¬Ӯи’чӮЯ–вӮў•ФӮ·ҒBҸүӮЯӮДӮЬӮЖӮаӮЙҢ©ӮҪ‘ҠҺиӮНҒAӮвӮНӮиүҪ“xҢ©ӮДӮа•sҗRӮҫӮБӮҪҒB’·җgӮЖ’·”ҜӮНӮіӮДӮЁӮ«ҒiүцӮөӮіӮр”{‘қӮіӮ№ӮДӮўӮйӮұӮЖӮН”Ы’иӮөӮИӮўӮӘҒjҒAүҪӮжӮиүцӮөӮўӮМӮН‘SҗgҚ•ӮёӮӯӮЯӮЖӮўӮӨ•һ‘•ӮҫӮлӮӨҒBҗ§•һӮМҲЯ‘ЦӮҰӮӘ‘ТӮҝү“ӮөӮўӮұӮМӢGҗЯҒAҸӢӮӯӮИӮўӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
ҒuҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮр’TӮөҸoӮөҒA••ҲуӮөӮДӮЩӮөӮўҒv
Ғ@ӮЬӮҪҒAҲУ–ЎӮМ•ӘӮ©ӮзӮИӮўҢҫ—tӮӘҸoӮДӮ«ӮҪҒB
ҒuӮ»ӮсӮИӮаӮМҒA’mӮиӮЬӮ№ӮсҒv
Ғu’mӮзӮИӮӯӮД“–‘RӮҫҒBӮЮӮөӮл’mӮБӮДӮўӮҪӮзҒAӮұӮҝӮзӮӘӢБӮўӮҪҒv
Ғ@йGҒXӮЖҢҫӮўҒAҚXӮЙҢҫ—tӮр‘ұӮҜӮйҒB
ҒuӮҫӮӘҒAүјӮЙӮаҒwҸpҺtҒxӮМ’[ӮӯӮкӮИӮзҒAӢҰ—НӮөӮДӮаӮзӮнӮИӮӯӮДӮНҚўӮйҒv
ҒuҒcҒcҺ„ӮНҒAӮ»ӮМҒwҸpҺtҒxӮЖӮвӮзӮ¶ӮбӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB‘јӮр“–ӮҪӮБӮДүәӮіӮўҒv
Ғu”nҺӯӮИҒv
Ғ@•@ӮЕҸОӮнӮкӮДӮөӮЬӮў• ӮӘ—§ӮБӮҪӮӘҒA’mӮзӮИӮўӮаӮМӮН’mӮзӮИӮўӮөҒAҲбӮӨӮаӮМӮНҲбӮӨӮМӮҫҒBӮ»ӮаӮ»ӮаҢҫ—tӮр•·ӮўӮҪӮМӮӘҸүӮЯӮДӮИӮМӮҫӮ©ӮзҒAҺd•ыӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB
ҒuҺгӮўӮжӮӨӮҫӮӘҒAҒwҺҶҸpҺtҒxӮЖӮөӮДӮМ—НӮрҺқӮБӮДӮўӮйӮҫӮлӮӨҒv
ҒuӮҫӮ©ӮзҒA’mӮзӮИӮўӮЖҢҫӮБӮДҒ\Ғ\Ғv
ҒuҢ©ӮҪӮўӮ©ҒHҒv
Ғ@–цӮМҢҫ—tӮрҺХӮиҒA’jӮНҺwҗжӮрҢьӮҜӮДӮ«ӮҪҒBӮ»ӮМүsӮіӮЙҒA–цӮНҢгӮёӮіӮйҒB
ҒuҢ©ӮИӮӯӮДӮНҗMӮ¶ӮзӮкӮИӮўӮИӮзҒAҢ©Ӯ№Ӯй•ы–@ӮаӮ ӮйҒv
ҒuҒcҒcӮ ӮИӮҪҒAүҪҺТҒHҒv
Ғ@ӮұӮМҗўӮЙӮНҗlӮМ’mҺҜӮМӢyӮОӮИӮўӮұӮЖӮӘӮ ӮйӮЖҒA–цӮа•ӘӮ©ӮБӮДӮўӮйҒB—H—мӮв—dүцӮӘӮўӮҪӮБӮДӮўӮўҒBӮҜӮкӮЗҒAӢӨ‘¶ӮЕӮ«ӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮН•КӮМҳbӮҫӮлӮӨҒBҗlӮМҗўҠEҒA—H—мӮМҗўҠEҒA—dүцӮМҗўҠEӮНҒAҢрӮнӮзӮИӮў•ыӮӘӮўӮўӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBүҪӮ©ӮМ”ҸҺqӮЙҢрӮнӮБӮДӮөӮЬӮӨ’ц“xӮМ•ыӮӘҒAҢЭӮўӮМӮҪӮЯӮЙӮўӮўӢCӮӘӮ·ӮйҒB
Ғ@Ӯ»ӮкӮНӮіӮДӮЁӮ«ҒAӮ»ӮМҒuҗlӮЕӮНӮИӮўӮаӮМҒvӮӘ–цӮЖүҪӮМҠЦҢWӮӘӮ ӮйӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBӮўӮвҒAүәҺиӮрӮ·ӮйӮЖ–цӮаҒuҗlӮЕӮНӮИӮўӮаӮМҒvӮЙҠЬӮЬӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮИҢы’ІӮЕӮ ӮйҒB
ҒuҺ„ӮаҒAҒwҸpҺtҒxӮМҲкҗlӮҫҒv
Ғ@• ӮӘ—§ӮВӮӯӮзӮўҠИҢүӮИ•ФҺ–ӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒwҸpҺtҒxӮБӮДүҪҒHҒv
ҒuҢГ‘гӮ©Ӯз‘ұӮӯҲЩ”\ӮМҲк‘°ӮҫҒBҢіӮНӣЮҸ—Ӯр”rҸoӮөӮҪҲк‘°ӮҫӮБӮҪӮсӮҫӮлӮӨӮӘҒAҺҹ‘жӮЙ—НӮрҺқӮВҺТӮӘ‘қӮҰҒAҢ —НӮрҲ¬ӮйӮұӮЖӮаӮ ӮБӮҪҒv
Ғ@ҲЩ”\ӮрҺқӮВӮҪӮЯҒAҺһ‘гӮЙӮжӮБӮДӮН”—ҠQӮМ‘ОҸЫӮЖӮаӮИӮиӮ©ӮЛӮИӮўҒBӮ»ӮМӮҪӮЯӮМҺ©ҢИ–hүqҚфӮҫҒBӮөӮ©ӮөҺһӮЖӢӨӮЙҚ‘Ӯа•ПӮнӮиҒAҲк‘°ӮН—рҺjӮМ— ‘ӨӮ©ӮзҺpӮрҸБӮөӮҪҒB
Ғ@ҢӢҳ_ӮрҢҫӮҰӮОҒAҒwҸpҺtҒxӮН‘§ӮрҗцӮЯӮҪӮҫӮҜӮҫӮБӮҪҒBҢ»‘гӮЙӮЁӮўӮДӮаҲк‘°ӮН‘¶ҚЭӮөҒA‘ұӮўӮДӮўӮйҒBӮаӮБӮЖӮаҒA‘SҲк‘°Ӯр‘©ӮЛӮйӮЩӮЗӮМ—НӮНӮИӮўҒB—НӮМӢӯӮў’Ҷҗ•ӮМӮЭӮр‘©ӮЛҒA—НӮМҺгӮўҺТӮНҗlӮЙҚ¬Ӯ¶ӮБӮДҗ¶ҠҲӮөӮДӮўӮйҒBҗlӮЙҚ¬Ӯ¶ӮБӮДҗ¶Ӯ«ӮйҺТӮЙӮНҒAҺ©ӮзӮӘҒwҸpҺtҒxӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮр–YӮкӮҪҺТӮа‘ҪӮўӮЖӮўӮӨҒB
ҒuӮЁ‘OӮаҒAӮ»ӮМҲкҗlӮҫӮИҒv
Ғ@‘еӮ«ӮИӮЁҗўҳbӮҫҒBӮөӮ©ӮөҒuҲк‘°ҒvӮЖӮўӮӨӮИӮзӮОҒAҢҢӢШӮЕҺуӮҜҢpӮӘӮкӮйӮНӮёӮҫҒB–цӮМҸкҚҮӮЙӮа“–ӮДӮНӮЬӮйӮИӮзӮОҒA—јҗeӮЗӮҝӮзӮ©ӮӘҒwҸpҺtҒxӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB
ҒuӮ»ӮкӮЕҒAҺ„ӮНҒwҺҶҸpҺtҒxӮИӮМҒHҒv
ҒuӮ»ӮӨӮҫҒBҺҶӮр”}үоӮЖӮөҒA—НӮрҺgӮӨҒv
Ғ@ӮЬӮҫ”јҗM”јӢ^ӮҫӮБӮҪӮӘҒAҠ®‘SӮЙүRӮЖӮаҺvӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮұӮЬӮЕҳbӮрҚмӮйҺиҠФӮрҚlӮҰӮйӮЖҒAӮ ӮЬӮиӮЙӮаҠ„ӮМҲ«ӮўғTғMӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©Ӯа‘ҠҺиӮНҚӮҚZҗ¶ӮҫҒB
ҒuҺ„ӮЙүҪӮрӮөӮДӮЩӮөӮўӮМҒHҒv
ҒuҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮр’TӮөҸoӮөҒA••ҲуӮөӮДӮЩӮөӮўҒv
Ғ@Ӯ»ӮкӮНүҪӮ©ӮЖҗqӮЛӮйӮЖҒAҚДӮСҠИҢүӮИ“ҡӮҰӮӘ•ФӮБӮДӮӯӮйҒB
ҒuҒwҠCӮМҗв‘ОӮМүБҢмӮр“ҫӮйӮаӮМҒxӮҫҒv
Ғ@ҒcҒc‘SӮӯ–уӮӘ•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒB’nҗ}ӮЖӮўӮӨӮаӮМӮҫӮ©ӮзҒwҺҶҸpҺtҒxӮЖӮўӮӨ”ӯ‘zӮН—қүрӮЕӮ«ӮйӮӘҒAҠCӮМ’nҗ}ӮЕӮНҠCҗ}ӮҫӮлӮӨҒB
ҒuҠCҗ}ӮМӮұӮЖҒHҒv
ҒuӮўӮвҒB•Ё—қ“IӮЙүҪӮ©Ӯр“ҫӮзӮкӮйӮаӮМӮЕӮНӮИӮўҒBҠCҗ_ӮМ—НӮрҺШӮиҒAҠCӮ»ӮМӮаӮМӮр‘ҖӮй”}үоӮҫҒv
Ғu•Ё—қ“IӮЕӮаӮИӮўӮМӮЙҒAӮЗӮӨӮвӮБӮДҠCӮр‘ҖӮйӮМӮжҒBҒv
Ғ@үҪӮӘҢҫӮўӮҪӮўӮМӮ©ҒAӮвӮНӮи•ӘӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBҠCӮр‘ҖӮйӮЖӮўӮӨӮМӮИӮзҒAүҪӮ©•K—vӮИӮМӮЕӮНӮИӮўӮМӮ©ҒB
ҒuҠmӮ©ӮЙҺҶӮЙҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮ»ӮкӮНҺnӮЯӮҫӮҜӮҫҒBҺҶӮЙҚһӮЯӮзӮкӮҪ—НӮрҺжӮиҚһӮЯӮОҒAӮҪӮҫӮМҺҶӮЙӮИӮйҒBҒv
ҒuӮ»ӮкӮНҒAҒwҸpҺtҒxӮ¶ӮбӮИӮӯӮДӮаҺgӮҰӮйӮаӮМҒHҒv
ҒuҺgӮӨӮҫӮҜӮИӮзӮИҒBӮҫӮӘҒA••ҲуӮ·ӮйӮЙӮНҒwҸpҺtҒxӮМ—НӮӘӮўӮйҒBҒv
Ғ@ӮвӮвӮұӮөӮўҚмӮиӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮаӮМӮҫҒBӮЗӮӨӮ№ӮИӮзҺgӮӨӮҫӮҜӮЕӮаҒwҸpҺtҒxӮМ—НӮЖӮвӮзӮӘ•K—vӮИӮзӮО—ЗӮ©ӮБӮҪӮМӮЙӮЖҒAҺvӮнӮёӮЙӮНӮўӮзӮкӮИӮўҒB
Ғ@ӮөӮ©ӮөӮ»ӮМ‘OӮЙҒAӮ ӮБӮіӮиӮЖ”ҡ’eӮӘ—ҺӮҝӮҪҒB
ҒuҗўҠEӮМ•цүуӮЙүБ’SӮөӮҪӮӯӮИӮҜӮкӮОҒAӢҰ—НӮөӮДӮЁӮўӮҪ•ыӮӘҗіүрӮҫӮЖҺvӮӨӮӘӮИҒBҒv
ҒuӮҝӮеҒAүҪӮ»ӮМҒw–ҫ“ъӮНүJӮӘҚ~ӮиӮЬӮ·Ғx“IӮИҢы’ІӮЕҢҫӮӨ‘„ӮМҚ~ӮиӮ»ӮӨӮИ“VӢC—\•сӮНҒIҒHҒv
ҒuҒcҒcӮЗӮӨӮўӮӨҲУ–ЎӮҫӮ©•ӘӮ©ӮзӮсҒv
Ғ@Ғ\Ғ\•КӮЙ•ӘӮ©ӮБӮДӮаӮзӮЁӮӨӮЖӮНҺvӮнӮИӮўӮМӮҫӮӘҒA”ыҠФӮЙб°ӮрҠсӮ№ӮДҢҫӮнӮИӮӯӮДӮаӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӮЖӮЙӮ©ӮӯҒAӮ»ӮкӮҫӮҜҠлҢҜӮИӮаӮМӮҫҒBҢВҗlӮМҺиӮЙӮН—]ӮйҒv
ҒuҢВҗlӮМҺиӮЙ—]ӮйӮаӮМӮӘҒAӮЗӮӨӮөӮД–м•ъӮөӮИӮМӮжҒv
Ғu••ҲуӮӯӮзӮўҒAӮөӮДӮ ӮБӮҪӮіҒv
Ғ@•@ӮЕҸОӮўӮ©ӮЛӮИӮўҢы’ІӮЕҢҫӮў•ъӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө••ҲуӮөӮДӮ ӮБӮҪӮНӮёӮМӮаӮМӮрҒAӮИӮә••ҲуӮөӮИӮӯӮДӮНӮИӮзӮИӮўӮМӮ©ҒBӮ»ӮаӮ»ӮаҒAӮИӮәӮ»ӮМҲЛ—ҠӮр–цӮЙ—ҠӮЮӮМӮ©ҒB‘јӮЙӮаҒwҸpҺtҒxӮНӮўӮйӮҫӮлӮӨҒBӮ«ӮҝӮсӮЖҒwҸpҺtҒxӮЖӮөӮДӮМҺ©ҠoӮрҺқӮҝҒA–цӮжӮиӮаӢӯӮў—НӮрҺқӮБӮҪҒwҸpҺtҒxӮӘҒB
ҒuӮҪӮҫҒAӮ»ӮұӮзӮМҲў•рӮӘ‘_ӮБӮДӮўӮйӮзӮөӮӯҒAҚЎӮЬӮЕӮМ••ҲуӮЕӮНҢ©ӮВӮ©ӮйүВ”\җ«ӮӘӮ ӮйҒBҚXӮЙӢӯ—НӮИ••ҲуӮрҺ{Ӯ·Ӯ©ҒAӮўӮБӮ»ҸБ–ЕӮіӮ№ӮйӮМӮаҺиӮҫӮИҒv
Ғ@үҪӮЕӮаӮўӮўӮ©ӮзҒA‘јӮр“–ӮҪӮБӮДӮЩӮөӮ©ӮБӮҪҒBӮ ӮЬӮиӮЙӮа“r•ыӮаӮИӮўҳbӮЕҒAӮ»ӮкӮұӮ»–цӮМҺиӮЙӮН—]ӮйҒBӮЖӮўӮӨӮ©ҒAүҪӮа’mӮзӮИӮўҸу‘ФӮЕ•ъӮиҚһӮЬӮкӮДӮаҚўӮйӮМӮҫҒBүҪӮЖӮ©ҸуӢөӮр”cҲ¬ӮөӮВӮВӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮЗӮӨӮ·ӮкӮОӮўӮўӮМӮ©ӮН‘SӮӯ•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒBӮ»ӮаӮ»ӮаҒwҸpҺtҒxӮМ—НӮНӮЗӮӨӮвӮБӮДҺgӮӨӮМӮ©ҒB
ӮЬӮҪҒAӮұӮМ’jӮӘүҪҺТӮИӮМӮ©Ӯа–ўӮҫӮЙ“дӮМӮЬӮЬӮҫҒBүцӮөӮўӮЖҺvӮӨӮМӮа”nҺӯӮзӮөӮӯӮИӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮЕӮаҲк”КҗlӮЖҺvӮӨӮМӮНҲк”КҗlӮЙҺё—зӮЕӮ ӮйҒB–цҺ©җgҒAӮЕӮ«ӮкӮО“ҜӮ¶җlҺнӮЙҠҮӮзӮкӮҪӮӯӮНӮИӮўҒBӮЖӮўӮӨӮ©ҒAҗв‘ОӮЙҢҷӮҫҒB
ҒuӮЬӮ ҒAӮ»ӮМ•УӮНӮўӮўӮнҒBӮЗӮӨӮ№•·ӮўӮДӮа•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮөҒv
Ғ@—қүрӮ·ӮйӮұӮЖӮр‘ҒҒXӮЙ•ъҠьӮөҒA–цӮНҺиӮрҗUӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮжӮиӮаҒA–ј‘OӮ·Ӯз’mӮзӮИӮўҢ»ҸуӮМ•ыӮӘ–в‘иӮҫҒB
ҒuӮЖӮұӮлӮЕҒA–ј‘O•·ӮўӮДӮаӮўӮўҒHҒv
Ғu–ј‘OҒHҒv
Ғ@үцжbӮИҠзӮрӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮ»ӮсӮИӮЙ•ПӮИӮұӮЖӮр•·ӮўӮҪӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
ҒuғҠғҮғEҒAӮҫҒv
ҒuғҠғҮғEҒHҒv
Ғ@ҠҝҺҡӮӘ“–ӮДӮНӮЯӮзӮкӮИӮў–ј‘OӮҫӮБӮҪҒBҸӯӮөҚlӮҰӮйӮҫӮҜӮЕҒAӮўӮӯӮВӮаҠҝҺҡӮӘ•ӮӮ©ӮсӮЕӮөӮЬӮӨҒB
ҒuҠҝҺҡӮНҒAӮИӮўҒB•Рүј–јӮҫӮЖӮЕӮаҺvӮБӮДӮўӮкӮОӮўӮўӮҫӮлӮӨҒv
Ғ@ҠҝҺҡӮӘӮИӮўӮЖӮНҒAҗҸ•ӘӮЖ•ПӮнӮБӮҪ–ј‘OӮҫҒBӮўӮвҒA“ъ–{җlӮЕӮаҠҝҺҡӮЕӮНӮИӮў–ј‘OӮНӮ ӮйӮӘҒAӮ»ӮкӮЙӮөӮДӮа•Рүј–јӮЖӮН•ПӮнӮБӮДӮўӮйҒB
Ғ@ӮҜӮкӮЗҒAӮ»ӮұӮНҗ[Ӯӯ’ЗӢyӮөӮИӮўӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒB–ј‘OӮЙӮНӮ»ӮМҗlӮМҢВҗ«ӮӘ•\ӮкӮйҒBӮұӮМҗlӮЙҢАӮБӮД•Рүј–јӮЖӮўӮӨӮМӮаҒAӮ»ӮкӮИӮиӮЙҺ—ҚҮӮБӮДӮйҒcҒcӮжӮӨӮЙҢ©ӮҰӮйҒB
ҒuҺ„ӮНӢгҸр–цҒBӮжӮлӮөӮӯҒAғҠғҮғEҒv
Ғ@Ӯ»ӮсӮИӮұӮсӮИӮЕҒA–цӮНҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮМ••ҲуӮр—ҠӮЬӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮҫӮБӮҪҒBүҪӮҫӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮИӮӘӮзҒAӮЖӮЙӮ©ӮӯҒwҸpҺtҒxӮЙҠЦӮ·ӮйӮұӮЖӮрҗFҒXӮЖ•·Ӯ©ӮіӮкӮДӮўӮйҚЕ’ҶӮЕӮ ӮйҒB
Ғ@Ӯ»ӮӨӮўӮҰӮОҒAҒwҸpҺtҒxӮМ—НӮрҺқӮБӮДӮўӮҪӮМӮН•кҗeӮМ•ыӮҫӮБӮҪҒB•·ӮўӮДӮНӮўӮИӮўӮӘҒAүҪӮЖӮИӮӯ“ҜӮ¶ӮаӮМӮрҠҙӮ¶ҺжӮБӮҪӮМӮҫҒBӮ»ӮкӮН•кҗeӮа“ҜӮ¶ӮИӮМӮ©ҒA–цӮӘӢC•tӮўӮҪ“ъӮЙҺ©Ӯз–ҫӮ©ӮөӮДӮ«ӮҪҒB’mӮзӮИӮўӮЬӮЬӮИӮзҒAӮ»ӮкӮЕҚПӮЬӮ№ӮйӮВӮаӮиӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўҒBҺ©•ӘӮӘҒwҸpҺtҒxӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮр”й–§ӮЙӮөӮДҒA•кӮНҚЎӮЬӮЕҗ¶Ӯ«ӮДӮ«ӮҪҒB•ғӮа’mӮзӮИӮўӮзӮөӮўҒB
Ғ@’mӮзӮ№ӮИӮӯӮДӮаӮўӮўӮЖҒA–цӮНҺvӮБӮҪҒB’mӮзӮ№ӮДӮаҺьӮиӮӘӮЕӮ«ӮйӮұӮЖӮИӮЗӮИӮўӮЖҒA’јҠП“IӮЙҺvӮБӮҪӮ©ӮзҒBӮ»ӮкӮжӮиӮаҒA–цӮМ—НӮӘӮЖӮМ’ц“xӮМӮаӮМӮИӮМӮ©ӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮМ•ыӮӘҸd—vӮҫӮБӮҪҒB
—НӮӘҺгӮўӮЖҒAғҠғҮғEӮНҢҫӮБӮҪҒB•кӮаҒAҢҲӮөӮДӢӯӮў—НӮрҺқӮБӮДӮўӮй–уӮЕӮНӮИӮўҒBӮЮӮөӮл—НӮӘҺгӮўӮ©ӮзӮұӮ»ҒA•Ғ’КӮМҗlӮЖӮөӮДҗ¶ҠҲӮЕӮ«ӮДӮўӮҪӮМӮҫҒB–әӮМ–цӮӘҒAӢӯӮў—НӮрҺқӮВӮНӮёӮӘӮИӮўҒBӮ ӮЬӮиӮЙ—НӮӘӢӯӮҜӮкӮО••ҲуӮ·ӮйӮұӮЖӮаӮ ӮйӮзӮөӮўӮӘҒAӮ»ӮМ•K—vӮӘӮИӮў’ц“xӮМ—НӮөӮ©ҺқӮҪӮИӮўӮМӮҫҒB
ҺҶӮрҲИӮБӮДҗўӮр“nӮБӮҪҲк‘°ӮМ––ебҒB
Ӯ»ӮсӮИ–ј‘OӮр”w•үӮўҒA–цӮНӮұӮМҗжӮрҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮӯӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҗlӮЙӮН—қүрӮіӮкӮёҒA’mӮзӮкӮйӮұӮЖӮ·ӮзӮИӮў—НӮрҺқӮБӮДҒB
Ӯ»ӮӨҺvӮӨӮЖҒAҗжӮӘҺvӮўӮвӮзӮкӮйӮжӮӨӮИӢCӮЙӮИӮБӮҪҒB
•MҗжӮӘ”јҺҶӮЙҗGӮкӮҪҺһӮМҠҙҠoӮНҒAҒwҸpҺtҒxӮҫӮ©ӮзӮұӮ»ӮМҠҙҠoӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮЖҺvӮБӮҪҒBҺҶӮЖҲк‘МӮЙӮИӮйӮИӮЗҒA•Ғ’КӮЕӮНҚlӮҰӮзӮкӮИӮўҒB
ҒiӮЕӮаҒAӮЗӮӨӮвӮБӮД—НӮрҺgӮӨӮБӮДӮМӮжҒj
Ғ@ғҠғҮғEӮЙӮНҒwҸpҺtҒxӮЖӮөӮДӮМ—НӮӘӮ ӮйӮЖҢҫӮнӮкӮҪӮӘҒAӮЗӮӨӮвӮБӮДҺgӮӨӮМӮ©ӮНӢіӮҰӮДӮӯӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB–цӮМҸкҚҮӮЙҢАӮзӮёӮЖӮаҒA•Ғ’КӮНӮЗӮӨӮвӮБӮД—НӮрҺgӮӨӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBӮҝӮИӮЭӮЙҒA•кҗeӮН—НӮрҺgӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕ‘SӮӯҺQҚlӮЙӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮаӮ»ӮаҺgӮЁӮӨӮЖӮаҺvӮнӮИӮ©ӮБӮҪӮзӮөӮўӮМӮЕҒAӢЙӮЯӮДҚKӮ№ӮИҗlӮЕӮ ӮйҒB
ҒiӮЖӮЙӮ©ӮӯҒAӮұӮМӮЬӮЬӮ¶ӮбҚўӮйӮМӮжҒj
Ғ@—ӯӮЯ‘§ӮрӮВӮ«ӮҪӮўӢC•ӘӮЕ•MӮрҠҠӮзӮ№ӮҪҒBҸ‘ӮўӮДӮўӮ镶ҺҡӮНҒuӢCүҠ–ңҸдҒvҒAҗж“ъҢҫӮнӮкӮҪғRғ“ғNҒ[ғӢӮЙҸo“WӮ·Ӯй—\’иӮМүЫ‘иӮЕӮ ӮйҒBүҪ–ҮҸ‘ӮўӮДӮаҒAҗі’јҒAүҪӮЖӮаҺvӮнӮИӮўҒBҸгҺиӮўӮЖӮаүәҺиӮЖӮаҒA–{җlӮЙӮН•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮЖӮўӮӨӮМӮӘ–цӮМҠҙ‘zӮҫӮБӮҪӮиӮ·ӮйҒB
Ғu–цҒA‘еҸд•vҒHҒv
ҒuҒcҒcӮ ӮсӮЬӮиҒv
Ғ@ӮөӮ©Ӯө“ҜӢүҗ¶ӮЙӮаҗS”zӮіӮкӮйӮЩӮЗҒA•¶ҺҡӮЙүeӢҝӮӘҸoӮДӮўӮйӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒB
ҒuӮЕӮаҒAҚЎ“ъӮНҸIӮнӮиӮҫӮБӮДҒv
ҒuӮҰҒAүҪӮЕҒHҒ@ӮЬӮҫҺһҠФӮЙӮН‘ҒӮўӮМӮЙҒv
Ғ@ҺһҢvӮрҢ©ӮҪӮӘҒAӮўӮВӮаӮжӮиҺOҸ\•ӘӮН‘ҒӮўҒBӮўӮВӮаӮИӮзҺһҠФӮўӮБӮПӮўӮЬӮЕ—ыҸKӮіӮ№Ӯйҗжҗ¶ӮӘҒAҚЎ“ъӮЙҢАӮБӮДӮЗӮӨӮөӮҪӮұӮЖӮ©ҒB
ҒuүҪӮҫӮ©—pҺ–ӮӘӮ ӮйӮсӮҫӮБӮДҒBӮБӮДӮўӮӨӮ©ҒAӮўӮВӮаӮӘүЙӮ·Ӯ¬ӮйӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮМҒAӮ ӮМҗжҗ¶Ғv
ҒuҒcҒcҒcҒcҒv
Ғ@ҺvӮнӮёҗ[ҒXӮЖ”[“ҫӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮ»ӮұӮ»Ӯұ—L–јӮИӮМӮЙҒAӮ ӮЬӮи–ZӮөӮўҗlӮЙӮНҢ©ӮҰӮИӮўҒBҺсӮрҢXӮ°ӮҪӮӯӮИӮйҒuҸъ‘хӢі—@ӮМҺө•sҺvӢcҒvӮЕӮ ӮйҒBҒcҒcӮаӮБӮЖӮаҒA‘јӮМҳZӮВӮНӮИӮўӮМӮҫӮӘҒB
ҒuӮ¶ӮбҒAҺ„Ӯа•Р•tӮҜӮИӮ«ӮбҒv
ҒuӮ ҒAӮӨӮсҒv
Ғ@ҢҘӮрҺқӮҝҸгӮ°ҒA–nӮрҺМӮДӮйҒBҺUӮзӮОӮБӮДӮўӮҪ”јҺҶӮрӮЬӮЖӮЯҒAҠ“ӮЙӢІӮЭҚһӮсӮҫҒB•Р•tӮҜӮрҸIӮҰҒAҲкҗlӮЕҸ‘“№ҺәӮрҢгӮЙӮ·ӮйҒBӮЖӮўӮӨӮ©ҒA–цӮӘҚЕҢгӮҫӮБӮҪҒB‘јӮМ•”ҲхӮН–цӮӘ•рӮҜӮДӮўӮйҠФӮЙҒA•Р•tӮҜӮрҸIӮҰӮДӮўӮҪӮзӮөӮўҒBҒcҒcӮаӮБӮЖ‘ҒӮӯҗәӮрӮ©ӮҜӮДӮЩӮөӮ©ӮБӮҪҒB
Ғ@ҚZ–еӮрӮӯӮ®ӮиҒA•аӮ«ҸoӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAҢгӮлӮр•аӮӯҗlүeӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮЬӮіӮ©ҢгӮрӮВӮҜӮДӮўӮй–уӮЕӮаӮИӮўӮҫӮлӮӨӮӘҒAӮ ӮЬӮиӮўӮўӢC•ӘӮЕӮНӮИӮўҒBӮ©ӮЖӮўӮБӮДҗжӮрҸчӮБӮДӮаҒAҚЎ“xӮНӢtӮЙҺ©•ӘӮӘҢгӮр’ЗӮӨ‘ӨӮЙӮИӮиӮ©ӮЛӮИӮўҒB
ҒiӮЗӮӨӮ№ӮИӮзҒAҗжӮЙҚsӮБӮДӮЩӮөӮўӮнҒj
Ғ@ӮўӮБӮ»•аӮӯ‘¬ӮіӮӘҺvӮўӮ«ӮиҲбӮҰӮОӮжӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮӨӮ·ӮкӮОӢ——ЈӮӘҠJӮӯӮҫӮлӮӨҒBӮөӮ©ӮөҒAӮЩӮЖӮсӮЗ“ҜӮ¶‘¬“xӮЕҢгӮлӮр•аӮўӮДӮўӮйҒB
ҒiҒcҒcӮЬӮіӮ©ҒAӮЛҒj
Ғ@ӮўӮвҒAӮҪӮЬӮҪӮЬ“ҜӮ¶•ыҢьӮЙҢьӮ©ӮӨӮҫӮҜӮМҳbӮҫӮлӮӨҒBӮЖӮўӮӨӮ©ҒAӮ¶ӮбӮИӮўӮЖ•|ӮўҒBҗж“ъӮМғҠғҮғEӮЖӮўӮўҚЎ“ъӮЖӮўӮўҒAӮЗӮӨӮөӮД•ПӮИҳbӮЙҠӘӮ«ҚһӮЬӮкӮДӮўӮйӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
Ғ@ӮаӮБӮЖӮаҒA‘–ӮиҸoӮіӮИӮў’ц“xӮМҠwҸKӮНӮөӮДӮўӮҪҒBӮЗӮӨӮ№Ӯ·Ӯ®ӮЙ’ЗӮўӮВӮ©ӮкӮйӮМӮӘғIғ`ӮҫҒBҒ\Ғ\ӮӘҒB
ҒuҺё—зҒAӮ»ӮұӮМӮЁҸчӮіӮсҒv
ҒiҢҷҒ\Ғ\ӮБҒIҒIҒj
Ғ@ҺvӮўҗШӮи•Ғ’КӮЙҗәӮрӮ©ӮҜӮзӮкӮҪҒBӮЖӮБӮіӮЙҒwҗXӮМҢFӮіӮсҒxӮрҺvӮўҸoӮөӮДӮөӮЬӮӨ•УӮиҒAүҪӮ©ҲбӮӨӢCӮаӮ·ӮйӮМӮҫӮӘҒB
ҒuӮ»ӮұӮМҗ§•һӮМӮЁҸчӮіӮсҒv
Ғ@ӮнӮҙӮнӮҙҢҫӮў’јӮіӮИӮӯӮДӮаҒA–цӮМ‘јӮЙҗlӮНӮўӮИӮўҒBӮЬӮіӮ©ӮЖӮНҺvӮӨӮӘҒAҺ©•ӘӮр•sҗRҺТӮҫӮЖҺ©ҠoӮөӮДӮўӮИӮўӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBҒcҒcғҠғҮғEӮЖӮўӮўӮұӮМҸӯ”NӮЖӮўӮўҒA•ПӮИҗўӮМ’ҶӮЙӮИӮБӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB
ҒuӮИҒAүҪӮЕӮөӮеӮӨҒHҒv
Ғ@ӮЖӮНӮўӮҰҒA“с“xӮаҢДӮОӮкӮД–іҺӢӮЕӮ«ӮйӮЩӮЗ‘е•ЁӮЕӮНӮИӮўҒBӮ©ӮИӮи•sҺ©‘RӮИ“®Ӯ«ӮИӮӘӮзӮаҗUӮи•ФӮБӮҪҒB
Ғ@Ӯ»ӮұӮЙӮўӮҪӮМӮНҒAҺ©•ӘӮЖ“ҜӮ¶ӮӯӮзӮўӮМ”NӮМҸӯ”NҒBӮөӮ©ӮөғҠғҮғEӮЖӮН‘ОҸЖ“IӮЙҒA‘S‘М“IӮЙҗF‘fӮӘ”–ӮўҲуҸЫӮрҺуӮҜӮҪҒB
ҒuӢMҸ—ҒAҒwҸpҺtҒxӮЕӮ·ӮЛҒHҒv
ҒuӮБҒIҒHҒv
Ғ@ӮИӮәӮ»ӮкӮр’mӮБӮДӮўӮйӮМӮ©ӮЖӢБңұӮөӮҪҒBҒwҸpҺtҒxӮМӮұӮЖӮНҒwҸpҺtҒxӮөӮ©’mӮзӮИӮўӮНӮёӮҫӮЖғҠғҮғEӮЙҢҫӮнӮкӮДӮўӮҪҒBҒ\Ғ\’mӮБӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНҒAӮұӮМҸӯ”NӮаҒwҸpҺtҒxӮМҠЦҢWҺТҒB
ҒuӮ»ӮкӮаҒAҒwҺҶҸpҺtҒxӮҫҒv
ҒuҒcҒcӢM•ыҒAүҪҺТҒHҒv
Ғ@–цӮМҢгӮрӮВӮҜӮДӮўӮҪӮЖӮөӮ©ҺvӮҰӮИӮўҒA“дӮМҸӯ”NҒBӮҜӮкӮЗҒAҒwҸpҺtҒxӮМ‘¶ҚЭӮр’mӮБӮДӮўӮйҒB
Ғuғ{ғNӮаҒwҸpҺtҒxӮМҲк‘°ӮИӮсӮЕӮ·ӮжҒBӮЬӮ —НӮ»ӮМӮаӮМӮНҒAӮіӮЩӮЗӢӯӮӯӮИӮўӮЕӮ·ӮҜӮЗҒv
ҒuӮ»ӮкӮЕҒAҺ„ӮЙүҪӮ©—pҒHҒv
Ғ@үҪҺТӮ©ӮНҒAӮ Ӯй’ц“xӮМ—\‘ӘӮӘӮЕӮ«ӮДӮўӮҪҒBӮҫӮ©ӮзҒAӮ»ӮкӮНӮЗӮӨӮЕӮаӮўӮўҒB–в‘иӮИӮМӮНҒAӮИӮә–цӮЙҗәӮрӮ©ӮҜӮҪӮМӮ©ҒB
ҒuӮЗӮӨӮвӮзҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮр••ҲуӮ·ӮйӮжӮӨӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮкӮрҺ~ӮЯӮЙӮЛҒv
Ғ@–цӮНӮЖӮБӮіӮЙҗgҚ\ӮҰӮҪҒBӮИӮәӮИӮМӮ©ӮН•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒBӮЁӮ»ӮзӮӯ–{”\“IӮИ”ҪүһӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӢMҸ—ӮӘүҪӮрҺvӮБӮД••ҲуӮөӮжӮӨӮЖҚlӮҰӮҪӮМӮ©ӮН’mӮиӮЬӮ№ӮсӮӘҒA‘¶ҚЭӮөӮДӮўӮИӮӯӮДӮНӮИӮзӮИӮўӮаӮМӮЖӮўӮӨӮМӮаҒAҗўӮМ’ҶӮЙӮНӮ ӮйӮЕӮөӮеӮӨҒHҒv
ҒuҒcҒcӮ»ӮМ’ҶӮЙҒAҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮа“ьӮБӮДӮйӮБӮДӮұӮЖҒHҒv
Ғ@үҪӮрҗMӮ¶ӮДӮўӮўӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮӯӮИӮБӮДӮ«ӮҪҒBғҠғҮғEӮН••ҲуӮМҲЛ—ҠӮрӮөӮЙ—ҲӮҪӮөҒAӮұӮМҸӯ”NӮН••ҲуӮөӮИӮў•ыӮӘӮўӮўӮЖҢҫӮӨҒB’ZӮўҠФӮЙ—јӢЙ’[ӮИӮұӮЖӮрҢҫӮнӮкӮҪӮМӮЕӮНҒAҚ¬—җӮөӮДӮөӮЬӮӨӮМӮӘ•Ғ’КӮҫӮлӮӨҒB
ҒuӮ»ӮМ’КӮиӮЕӮ·ҒBӮИӮӯӮДӮНҚўӮйҒv
Ғ@ӮИӮәӮ©ҒAӮұӮМҸӯ”NӮӘҗіӮөӮўӮМӮҫӮЖҺvӮБӮҪҒBүҪӮМҚӘӢ’ӮаӮИӮӯҒAӮҪӮҫ”ҷ‘RӮЖҒBҚЕҸүӮЙғҠғҮғEӮрҗMӮ¶ӮҪӮМӮНҒAҠФҲбӮўӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮЖҒBҠИ’PӮЙҗMӮ¶ӮДӮөӮЬӮБӮҪҺ©•ӘӮНҒAҗуӮНӮ©ӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒAӮұӮМӮЬӮЬ•ъӮБӮДӮЁӮўӮД‘еҸд•vӮИӮМӮЛҒHҒv
ҒuӮҰӮҰҒAӮаӮҝӮлӮсӮЕӮ·ҒB••ҲуӮіӮкӮИӮӯӮДҸ•Ӯ©ӮиӮЬӮөӮҪҒv
Ғ@ҺЧӢCӮМӮИӮўҸОӮЭӮрҢьӮҜӮзӮкҒA–цӮНҢЛҳfӮБӮҪҒBүҪӮаӮөӮДӮўӮИӮўӮМӮЙҒAӮ»ӮкӮӘ—ЗӮ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮөӮЬӮӨӮЖ”ҪүһӮЙҚўӮйҒB
ҒuҒcҒcӮвӮНӮиҢ»ӮкӮҪӮ©Ғv
Ғ@ӮөӮ©ӮөҒAҺХӮБӮҪӮМӮН’бӮўҗәӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮЬӮ ҒA—\‘zӮНӮөӮДӮўӮҪӮӘҒv
Ғ@җUӮи•ФӮйӮЖҒAӮ»ӮұӮЙӮНғҠғҮғEӮӘ—§ӮБӮДӮўӮҪҒB‘Ҡ•ПӮнӮзӮё•\ҸоӮН–RӮөӮўӮӘҒAӮ»ӮкӮЕӮаӢ@ҢҷӮӘҲ«ӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮҫӮҜӮН•ӘӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuӢvӮөҗUӮиӮҫӮЛҒBӮўӮВӮЬӮЕғ{ғNӮМҺЧ–ӮӮрӮ·ӮйӮВӮаӮиӮҫӮўҒHҒv
ҒuӮЁҢЭӮў—lӮҫӮлӮӨӮӘҒB‘Ҡ•ПӮнӮзӮё–ӯӮИҲкҗlҸМӮрҺgӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮҫӮИҲў•рҒv
Ғ@ӮЗӮӨӮвӮз“сҗlӮН’mӮиҚҮӮўӮзӮөӮўҒBҒcҒcӮ»ӮкӮЙӮөӮДӮНҒAҢҫ—tӮМ’[ҒXӮЙҺhӮӘҚ¬Ӯ¶ӮБӮДӮўӮйӢCӮӘӮ·ӮйӮӘҒB
ҒuӮўӮўӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҲкҗlҸМӮИӮсӮДүҪӮЕӮаҒBғ{ғNӮНғ{ғNӮӘӢCӮЙ“ьӮБӮДӮйӮ©ӮзӮўӮўӮсӮҫӮжҒv
ҒuӮвӮвӮұӮөӮўҠOҢ©ӮрӮөӮДӮўӮйӮсӮҫҒAӮЗӮБӮҝӮ©ӮЙ“қҲкӮөӮДӮЁӮҜҒv
ҒuҢNӮЩӮЗӮвӮвӮұӮөӮӯӮИӮўӮжҒB‘е‘МӮЛҒAүҪӮ»ӮМҠiҚDҒBҸӢӮӯӮИӮўӮМҒHҒv
Ғ@–цӮӘ“ЛӮБҚһӮЯӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮрҒAӮ ӮБӮіӮиӮЖҢҫӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBүҪҺТӮИӮМӮ©ӮНҗUӮиҸoӮөӮЙ–ЯӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮӘҒAүҪӮЙӮ№Ӯж‘е•ЁӮЕӮ ӮйҒB
Ғ@ӮұӮұӮЬӮЕ•·ӮўӮДӮўӮД•ӘӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮЖҢҫӮҰӮОҒAӮ№ӮўӮәӮўҠOҢ©ӮЖҗ«•КӮӘҲк’vӮөӮДӮўӮИӮўҒiӮзӮөӮўҒjӮұӮЖӮӯӮзӮўӮҫҒB’jӮЙҢ©ӮҰӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНҒAҺАӮНҸ—ӮИӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
ҒuӮ»ӮсӮИӮсӮЕ•аӮўӮДӮҪӮз•sҗRӢЙӮЬӮиӮИӮўӮжҒBӮ»ӮұӮЕ–Ъ—§ӮБӮДӮЗӮӨӮ·ӮйӮМӮіҒv
ҒuӮ»ӮаӮ»ӮаҠOӮЙҸoӮИӮўӮ©Ӯз–в‘иӮИӮўӮИҒv
ҒuӮӨӮнҒAӮ»ӮкҲшӮ«ӮұӮаӮиӮҫӮжҒBҠOӮНӮўӮўӮжҒAҠyӮөӮўӮ©ӮзӮЛҒv
ҒuӮЁ‘OӮЖҲкҸҸӮЙӮ·ӮйӮИҒBӮ»ӮаӮ»ӮаҒwҸpҺtҒxӮӘҠOӮЙӮЕӮДӮЗӮӨӮ·ӮйҒv
Ғ@Ғ\Ғ\ӮИӮәӮ©ҒAҚЫҢАӮИӮӯғRғ“ғgӮЙ•·ӮұӮҰӮДӮ«ӮҪҒBҗ^–К–ЪӮЙҳbӮ·ӢCӮӘӮИӮўӮМӮИӮзҒA•ъӮБӮДӮЁӮўӮДӢAӮлӮӨӮ©ҒBҸҹҺиӮЙҢҲ’…ӮрӮВӮҜҒAӮ»ӮМҸгӮЕ–цӮМҸҠӮЙҺқӮҝҚһӮсӮЕӮЩӮөӮўҒB–цӮЙӮН•ӘӮ©ӮзӮИӮўҺҹҢіӮМҳbӮМӮжӮӨӮҫҒB
ҒuҒcҒcҺ„ҒAҗжӮЙӢAӮйӮнҒv
Ғ@ғ{ғ\ғҠӮЖҷкӮ«ҒAӮіӮБӮіӮЖ”wӮрҢьӮҜӮҪҒB
ҒuӮ ҒAӮҝӮеӮБӮЖӮЁҸчӮіӮсҒBӮЩӮзҒAҢNӮӘ•|ӮўӮ©Ӯз“ҰӮ°ҸoӮөӮҪӮ¶ӮбӮИӮўӮ©Ғv
ҒuҒcҒcҲбӮӨӮҫӮлӮӨҒv
Ғ@ӮұӮМҸкҚҮӮЙӮМӮЭҒAғҠғҮғEӮМҷкӮ«ӮНҗіӮөӮўҒB•КӮЙғҠғҮғEӮӘ•|ӮўӮЖӮ©ӮўӮӨҳbӮЕӮНӮИӮўӮМӮҫҒBӮҫӮӘҒA–{җl’BӮЙҺ©ҠoӮНҠF–іӮзӮөӮўҒBҚўӮБӮҪӮаӮМӮҫҒB
ҒuӮҰҒAҲбӮӨӮМҒHҒv
ҒuӮҰӮҰҒAӮЬӮ ҒcҒcҒv
Ғ@үҪӮЖ“ҡӮҰӮДӮўӮўӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮёҒAһB–ҶӮЙихӮўӮҪҒB
ҒuӮ ҒAӮ»ӮӨҒBҒ\Ғ\ӮЕӮаӮЛҒv
Ғ@ӮУӮЖҒA‘ҠҺиӮМ•\ҸоӮӘҗШӮи‘ЦӮнӮйҒB”wӢШӮЙ—вӮҪӮўӮаӮМӮӘ‘–ӮйӮМӮрҒA–цӮНҠmӮ©ӮЙҠҙӮ¶ҺжӮБӮҪҒB
ҒuҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxҒA••ҲуӮіӮкӮйӮЖҚўӮйӮсӮҫӮжӮИӮҹҒv
Ғ@ӢC”—ӮЙ“ЫӮЬӮкҒA’mӮзӮёҢгӮёӮіӮйҒBҗж’цӮЬӮЕӮМҢy”–ӮіӮНҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮа•\–КӮҫӮҜӮМӮаӮМӮҫҒB–{—ҲӮМҗ«ҠiӮНҒAӮұӮұӮЙӮ ӮйҒB
Ғuғ{ғNӮНӮЛҒAӮЁҸчӮіӮсҒBӮЁҸчӮіӮсӮМ“GӮЙ“–ӮҪӮйҗlҠФӮИӮсӮҫӮжҒBҒ\Ғ\ҲкүһӮЛҒv
Ғ@ҢyӮвӮ©ӮЙҸОӮЭӮр•ӮӮ©ӮЧҒAҗі”Ҫ‘ОӮМҢҫ—tӮр–aӮ®ҒBӮ»ӮМҢғӮөӮўҲбҳaҠҙӮЙҒAӢ°•|Ӯ·ӮзҠoӮҰӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB
ҒuӮЕӮаҒA“GӮҫӮ©ӮзӮБӮДҺEӮ»ӮӨӮЖӮ©ӮНҚlӮҰӮДӮИӮўӮжҒBҢ©ӮҪӮЖӮұҒA‘еӮөӮҪ—НӮаҺқӮБӮДӮИӮўӮжӮӨӮҫӮөӮЛҒBӮҪӮҫҒ\Ғ\Ғv
Ғ@ҲкҸuӮЕҒA•ӮӮ©ӮЧӮДӮўӮҪҸОӮЭӮ·ӮзӮаҸБӮҰӮҪҒB
ҒuҺЧ–ӮӮрӮ·ӮйӮИӮзҒA—eҺНӮНӮөӮИӮўҒv
ҒuҺЧ–ӮӮИӮзӮОҒAӮіӮ№ӮДӮаӮзӮӨҒv
Ғ@Ңҫ—tӮрҺёӮБӮҪ–цӮЙ‘гӮнӮиҒAғҠғҮғEӮӘҺХӮБӮҪҒB
ҒuҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮНҒA•KӮё••ҲуӮ·ӮйҒBӮ ӮкӮНҒAӮ ӮБӮДӮНӮИӮзӮИӮўӮаӮМӮҫҒv
ҒuӮУҒ[ӮсҒHҒ@ҢNӮӘҚмӮБӮҪӮМӮЙҒHҒv
Ғ@•@ӮЕҸОӮБӮД•ФӮіӮкӮҪҢҫ—tӮЙҒA–цӮНӢБңұӮөӮҪҒBҚЎҒAүҪӮЖҢҫӮБӮҪҒH
ҒuӮ»ӮкҒAӮЗӮӨӮўӮӨҒcҒcҒHҒv
ҒuӮ ӮкҒA’mӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒHҒ@Ӯ»ӮкӮНҲ«ӮўӮұӮЖӮөӮҪӮ©ӮИҒv
Ғ@”чҗoӮаҲ«ӮўӮЖҺvӮБӮДӮўӮИӮўӮМӮНҒAҢы’ІӮв•\ҸоӮ©Ӯз–ҫӮзӮ©ӮҫҒBӮөӮ©ӮөҒA–цӮӘ’mӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮЙҠЦӮөӮДӮНҲУҠOӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўҒB
ҒuӮЁҸчӮіӮсҒ\Ғ\ӮДҢДӮС‘ұӮҜӮйӮМӮаҺё—зӮ©ӮИҒBӮЁ–ј‘OӮНҒHҒv
ҒuӮвҒAҒcҒc–цҒAӮЕӮ·Ғv
Ғ@ҢіӮМҗlҚDӮ«ӮМӮ·ӮйҸОӮЭӮЙ–ЯӮБӮҪӮӘҒA–цӮНҢxүъӮрүрӮҜӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ғuғ„ғiғMӮіӮсҒAӮЛҒBғ{ғNӮНғPғCҒBӮжӮлӮөӮӯҒv
Ғ@–ј‘OӮрҠm”FӮөӮҪӮұӮЖӮЕҒAҳbӮр‘ұӮҜӮйҲУҺvӮӘӮ ӮйӮаӮМӮЖҺvӮнӮкӮҪӮзӮөӮўҒBғPғCӮН‘ұӮҜӮҪҒB
ҒuҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮрҚмӮБӮҪӮМӮНҒAӮұӮМ’jӮҫӮжҒBӮаӮБӮЖӮаҒAғ{ғNӮа–ј‘OӮр’mӮзӮИӮўӮҜӮЗӮЛҒv
Ғ@ҺӢҗьӮрҲЪӮ·ӮЖҒAғҠғҮғEӮН•sӢ@ҢҷӢЙӮЬӮиӮИӮўҠзӮрӮөӮДӮўӮйҒBӮҫӮӘҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮа”Ы’иӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuҒcҒcғҠғҮғEҒA–{“–ӮИӮМҒHҒv
ҒuӮЦӮҰҒAҒwғҠғҮғEҒxӮЛҒBҒcҒcӮЗӮБӮҝӮМҒHҒv
Ғ@ғҠғҮғEӮН“ҡӮҰӮИӮўҒB“ҡӮҰӮрҺқӮҪӮИӮўӮМӮ©ҒAӮ»ӮкӮЖӮа“ҡӮҰӮйӮұӮЖӮӘҢҷӮИӮМӮ©ҒBӮ»ӮкӮжӮиӮаҒA–цӮЙӮНҢг”јӮМҢҫ—tӮЙӢ^–вӮр•шӮўӮҪҒBҒuӮЗӮБӮҝӮМҒvӮЖӮНҒAӮЗӮӨӮўӮӨҲУ–ЎӮИӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
Ғ@Ӯ»ӮсӮИ–цӮМӢ^–вӮЙӢC•tӮўӮҪӮМӮ©ҒAғPғCӮӘ“ҡӮҰӮрҸoӮөӮҪҒB
Ғuғ„ғiғMӮіӮсҒAӮұӮўӮВӮНӮЛҒAӮЗӮБӮҝӮВӮ©ӮёӮМ— җШӮиҺТӮҫӮжҒBҒ\Ғ\’NӮМ–Ў•ыӮЙӮИӮйӮұӮЖӮаӮИӮўҒv
Ғ@’NӮМ–Ў•ыӮЙӮаӮИӮзӮёҒA’NӮМ“GӮЙӮаӮИӮзӮИӮўҒBӮ»ӮкӮұӮ»ӮӘҒAғҠғҮғEӮМ–{ҺҝӮИӮМӮҫӮЖҒBӮҜӮкӮЗҒAӮ»ӮкӮҫӮҜӮЕӮН—қүрӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuҒcҒcӮЗӮӨӮўӮӨӮұӮЖҒHҒv
Ғu“сҺн—ЮӮМҒwҸpҺtҒxӮЖӮөӮДӮМ—НӮрҺқӮБӮДӮўӮйҒBӮЗӮҝӮзӮМҲк‘°ӮЙӮа‘®ӮөҒAӮЗӮҝӮзӮМҲк‘°ӮЙӮа‘®ӮіӮИӮўҒBӮ»ӮӨӮўӮӨӮұӮЖӮҫӮжҒv
Ғ@үҪӮӘҒuӮ»ӮӨӮўӮӨӮұӮЖҒvӮИӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒB–цӮӘ•·Ӯ«ӮҪӮ©ӮБӮҪӮМӮНҒAӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮЕӮНӮИӮўҒB
ҒuӮ»ӮаӮ»ӮаҒwҸpҺtҒxӮМ—НӮрҺқӮДӮйӮМӮНҸ—ӮҫӮҜӮҫҒB’jӮМҒwҸpҺtҒxӮЖӮўӮӨӮҫӮҜӮЕӮаҲЩҺҝӮИӮМӮЙҒAӮ»ӮкӮҫӮҜ‘еӮ«ӮИ—НӮрҺқӮВӮЖҲЩ’[ӮЕӮөӮ©ӮИӮўҒv
Ғ@‘еӮ«ӮИ—НӮНҒAҺһӮЙҚРӮўӮрҢДӮФҒBӮ»ӮкӮНӮ»ӮкӮЕ—қүрӮЕӮ«ӮйҒBӮҫӮӘҒA–цӮМ’ҶӮЕүҪӮ©ӮӘҗШӮкӮҪҒBӮ»ӮкӮНҒA‘ӯӮЙҠ¬”E‘ЬӮЖҢДӮОӮкӮйӮаӮМӮҫӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB
Ғu’NӮӘӮ ӮсӮҪӮЙ•·ӮўӮДӮйӮМӮжғPғCҒIҒIҒ@ӮіӮБӮ«Ӯ©ӮзҲкҗlӮЕғyғүғyғү’қӮБӮДҒIҒIҒ@ғҠғҮғEҒAӮЗӮӨӮИӮМҒIҒHҒv
Ғ@•Щ–ҫҒAҺЯ–ҫҒAӮ»ӮМ‘јҸ”ҒXӮМҲкҗШӮр•ъҠьӮөӮҪ‘Ф“xӮЙҒAӮЖӮЙӮ©Ӯӯ• ӮӘ—§ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӢCӮЙӮИӮкӮО—НӮёӮӯӮЕӮа”[“ҫӮіӮ№ӮйҒAӮ»ӮсӮИӢCҠTӮӘ‘SӮӯҢ©ӮҰӮИӮўҒB–цӮЙӮНҒAӮИӮәӮ©Ҹ¬”nҺӯӮЙӮөҗШӮБӮҪ‘Ф“xӮөӮ©Ң©Ӯ№ӮДӮўӮИӮўӮӯӮ№ӮЙҒB
ҒuӮЗӮӨӮЖӮЕӮаҒB“ҡӮҰӮИӮЗҒA’NӮЙҗqӮЛӮйӮ©ӮЕҲбӮӨӮҫӮлӮӨҒv
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒAғҠғҮғEӮНӮЗӮӨҺvӮӨӮМҒHҒv
Ғ@ӢtӮЙҗqӮЛӮйӮЖҒAғҠғҮғEӮН”чӮ©ӮЙ•\ҸоӮр—hӮзӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮӘӮЗӮкӮҫӮҜ–цӮрӢБӮ©Ӯ№ӮҪӮ©ҒAғҠғҮғEӮӘ’mӮйӮұӮЖӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨҒBӮ»ӮМӮӯӮзӮўҒAҚЎӮЬӮЕӮНүҪӮаӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ғu•КӮЙҒAүҪӮаҒBӮ»ӮӨҢҫӮнӮкӮДӮ«ӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒAӮ»ӮӨҺvӮБӮДӮўӮйӮҫӮҜӮҫҒv
ҒuҺ–ҺАӮЕӮаӮ ӮйӮөӮЛҒv
Ғ@ғPғCӮӘҢыӮрӢІӮсӮҫҒBғLғbӮЖбЙӮЭҒA–цӮН‘ұӮҜӮйҒB
ҒuҒ\Ғ\–{“–ӮЙҒHҒv
Ғ@үҪӮаҺvӮнӮИӮўӮИӮЗӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮӘҒA–{“–ӮЙӮ ӮйӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBҺһӮЖӢӨӮЙүҪӮаҺvӮнӮИӮӯӮИӮйӮұӮЖӮНӮ ӮБӮДӮаҒAҚЕҸүӮ©ӮзүҪӮаҠҙӮ¶ӮИӮўӮИӮЗӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНҸӯӮИӮўҒBүҪӮаҠҙӮ¶ӮИӮўӮМӮНҒAӢ»–ЎӮМӮИӮўӮұӮЖӮҫӮ©ӮзҒBҺ©•ӘӮЖӮНҒAүҪӮМҠЦҢWӮаӮИӮўӮұӮЖӮҫӮ©ӮзҒB
Ӯ»ӮкӮӘҺ©•ӘӮМӮұӮЖӮИӮзӮОҒAӮ№ӮЯӮДҚЕҸүӮӯӮзӮўӮНүҪӮ©Ӯ ӮБӮҪӮНӮёӮИӮМӮҫҒBҗlӮЕӮ ӮйӮИӮзӮОҒA“–‘RӮМҠҙҸоӮӘҒB
Ғu–{“–ӮЙҒAүҪӮаҺvӮнӮИӮ©ӮБӮҪӮМҒHҒv
ҒuӮіӮ ӮИҒBӮаӮӨ–YӮкӮҪҒv
Ғ@‘fӮБӢCӮИӮў“ҡӮҰӮөӮ©•ФӮБӮДӮұӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒA–цӮН•sҠ®‘S”RҸДӮөӮ©ӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮрҚXӮЙҒAғPғCӮӘ’ЗӮў‘ЕӮҝӮрӮ©ӮҜӮйҒB
ҒuӮЬҒAӮ»ӮиӮбӮ»ӮӨӮҫӮлӮӨӮЛӮҰҒv
Ғ@ғҠғҮғEӮӘүҪӮаҠҙӮ¶ӮИӮўҒAӮ»ӮМӮұӮЖӮр“–‘RӮЖҺуӮҜҺ~ӮЯҺуӮҜ“ьӮкӮДӮўӮйҒBӮЗӮұӮӘ“–‘RӮИӮМӮ©ҒA–вӮўӢlӮЯӮДӮЭӮҪӮӯӮИӮБӮҪҒB
ҒuӮ»ӮкӮжӮиӮЛҒAғ„ғiғMӮіӮсҒBҲ«ӮўӮсӮҫӮҜӮЗҒ\Ғ\ӮвӮБӮПӮиҒAӮұӮұӮЕҒwӮіӮжӮИӮзҒxҒv
ҒuӮҰҒcҒcҒHҒv
Ғ@ғPғCӮМҺwҗжӮ©ӮзӢвҗFӮМҺ…ӮӘҢ»ӮкҒA–цӮМҗg‘МӮЙ—ҚӮЭӮВӮӯҒBҗgӮМҠлҢҜӮрүzӮҰҒA–ҪӮМҠлҢҜӮрҠҙӮ¶ӮҪҒB
ҒuҺЧ–ӮӮіӮкӮйӮсӮ¶ӮбҒAғ{ғNӮаҚўӮйҒBӮҫӮБӮҪӮзҠлҢҜӮИүиӮН“EӮсӮЕӮЁӮ©ӮИӮўӮЖҒv
ҒuӮ«ӮбҒcҒcҒv
Ғ@’NӮЙҸ•ӮҜӮрӢҒӮЯӮкӮОӮўӮўӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒB–цӮМ—НӮНҺгӮўӮМӮҫӮЖҢҫӮБӮДӮўӮҪҒBӮИӮзӮОҒA“GӮӨӮаӮМӮЕӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB
ҒuҒwӮіӮжӮИӮзҒxҒ\Ғ\ӮБӮДҒAҚЎ“ъүпӮБӮҪӮОӮБӮ©ӮиӮҫӮБӮҪӮЛҒv
ҒuҒ\Ғ\ӮБҒIҒIҒv
Ғ@Ӯ»ӮМҺһҒAҗg‘МӮМүңӮӘ”MӮӯӮИӮБӮҪҒBҸuӮӯҠФӮЙ”MӮН‘еӮ«ӮӯӮИӮиҒA‘SҗgӮЙҚLӮӘӮйҒBҺwҗжӮЬӮЕҚLӮӘӮБӮҪҺһҒA”ҪүһӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮНҗg‘МӮМҠOӮ©ӮзӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮИӢCӮӘӮөӮҪҒB
Ғ@ӢЯӮӯӮЙ—ҺӮЖӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪҠ“Ӯ©ӮзҒA•”ҠҲӮЕҸ‘Ӯ«‘№Ӯ¶ӮҪ”јҺҶӮӘҸoӮДӮӯӮйҒB
Ғu”nҺӯӮИҒIҒHҒv
Ғ@–цӮМҗg‘МӮЙ—ҚӮЭӮВӮўӮДӮўӮҪӢвҺ…ӮӘҒA”RӮҰӮДӮўӮҪҒBӮҜӮкӮЗ”MӮӯӮНӮИӮўҒB
ҲкҸuӮЖӮаҢҫӮҰӮйӮжӮӨӮИ’ZӮўҺһҠФӮЕҺ…ӮрҸДӮ«җsӮӯӮөҒAҚgҳ@ӮМүҠӮНҸБӮҰӮҪҒB
ҒuҚЎҒAүҪӮӘҒcҒcҒHҒv
Ғ@–уӮӘ•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮЬӮЬҒAҺ©•ӘӮМ—јҺиӮрҢ©ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA•ПӮнӮБӮҪҸҠӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҺиӮЙҒAӮіӮБӮ«ӮНҺӢҠEӮМ’[ӮЙүfӮБӮҪӮҫӮҜӮМ”јҺҶӮӘ—ҺӮҝӮйҒB
ҒuӮ ӮБҒIҒHҒv
Ғ@ҠmӮ©ӮЙҸ‘ӮўӮҪӮНӮёӮМҒuӢCүҠ–ңҸдҒvӮМ•¶ҺҡӮ©ӮзҒAҒuүҠҒvӮҫӮҜӮӘҸБӮҰӮДӮўӮйҒB
ҒuӮИӮйӮЩӮЗҒBӮ»ӮӨӮөӮД—НӮрҺgӮӨӮМӮ©Ғv
Ғ@”[“ҫӮөӮҪӮжӮӨӮИҢы’ІӮЕғҠғҮғEӮӘҷкӮўӮҪҒB
Ғu•¶ҺҡӮЙ—НӮрҚһӮЯӮйҒAӮ»ӮкӮӘ—НӮМҺgӮў•ыӮҫӮИҒv
Ғu”[“ҫӮөӮДӮИӮўӮЕҒIҒIҒ@ӮЗӮӨӮөӮДҗжӮЙӢіӮҰӮДӮӯӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮжҒIҒHҒv
Ғ@ҚRӢcӮ·ӮйӮаҒAғҠғҮғEӮН—БӮөӮўҠзӮЕ“ҡӮҰӮйҒB
Ғu’mӮзӮИӮўӮаӮМӮрҒAӮЗӮӨӮвӮБӮДӢіӮҰӮлӮЖҢҫӮӨӮсӮҫҒHҒ@—НӮМҺgӮў•ыӮНҒAӮ»ӮкӮјӮкӮМҒwҸpҺtҒxӮӘҺ©—НӮЕҢ©ӮВӮҜӮйӮөӮ©ӮИӮўҒv
Ғ@ӮҫӮБӮҪӮзӮ№ӮЯӮДҒAӮ»ӮкӮрҢҫӮБӮДӮЩӮөӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮӨӮ·ӮкӮО–цӮҫӮБӮДҒA•ы–@Ӯр’TӮ»ӮӨӮЖүҪӮ©“®ӮӯӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒB
ҒuӮ»ӮкӮжӮиӮаҒA–в‘иӮНғAғҢӮҫӮлӮӨҒv
Ғ@ғҠғҮғEӮӘҺwҚ·ӮөӮҪӮМӮНҒAғPғCӮҫӮБӮҪҒB–цӮМҺқӮВ”јҺҶӮрӢГҺӢӮөҒA•ъҗSӮөӮДӮўӮйҒB
ҒuӮИӮәҒAғ{ғNӮМҒwҸpҒxӮӘҒcҒcҒv
Ғu—НӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪӮҫӮҜӮҫҒBҢ©ҢлӮБӮҪӮИҒv
Ғ@үҪӮӘӢNӮ«ӮҪӮМӮ©ҒA–{җlӮЕӮ·ӮзӮа•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒB—НӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮаҒAҺАҠҙӮӘ—NӮ©ӮИӮўӮМӮҫҒB
ҒuӮЬӮіӮ©ҒcҒcҒwҚ°ӮМ”ә—өҒxӮМҒcҒcҒHҒv
ҒuҚlӮҰӮзӮкӮйӮМӮНҒAӮ»ӮМӮӯӮзӮўӮҫӮлӮӨҒv
Ғ@ӮЬӮҪҒA–цӮМ’mӮзӮИӮўҢҫ—tӮӘҸoӮДӮӯӮйҒBҺ©•ӘӮМӮұӮЖӮИӮМӮЙҒA–цӮҫӮҜӮӘ•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒBғҠғҮғEӮағPғCӮаҒA–цӮМӮұӮЖӮИӮМӮЙ•ӘӮ©ӮБӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨӮМӮЙҒB
Ғ@ӮаӮӨҒA‘SӮД•ъҠьӮөӮДӮаӮўӮўӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
Ғ@ӮУӮЖҒAӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮрҚlӮҰӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB“сҗlӮӘ•ӘӮ©ӮБӮДӮўӮйӮИӮзҒA–цӮӘҺиӮрҸoӮ·•K—vӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB“сҗlӮЕ•Р•tӮҜӮДӮӯӮкӮкӮОҒAӮ»ӮкӮЕүрҢҲӮ·ӮйӮМӮЕӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨӮ©ҒB–рӮЙ—§ӮҪӮИӮўӮМӮЕӮ ӮкӮОҒA–цӮӘӮўӮйҲУ–ЎӮӘӮИӮўҒB
ҒuӮЖӮЙӮ©ӮӯҒA—НӮМҺgӮў•ыӮа•ӘӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮкӮЕҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮр••ҲуӮЕӮ«ӮйҒv
ҒuҒcҒcҺ„ҒAҚsӮ©ӮИӮўҒv
Ғ@–цӮМҷкӮ«ӮЙҒA“сҗlӮН“ҜҺһӮЙҗUӮи•ФӮБӮҪҒB
ҒuүҪӮрҒcҒcҒv
Ғu“сҗlӮӘ•ӘӮ©ӮБӮДӮйӮИӮзҒA“сҗlӮЕҚsӮҜӮОӮўӮўӮ¶ӮбӮИӮўҒv
Ғ@ғҠғҮғEӮрҺХӮиҒA–цӮНҚҗӮ°ӮҪҒBүҪӮа•ӘӮ©ӮзӮИӮў–цӮжӮиҒAӮ«ӮҝӮсӮЖ•ӘӮ©ӮБӮДӮўӮй“сҗlӮМ•ыӮӘ‘ҒӮӯҚПӮЮӮҫӮлӮӨҒB
Ғu•ӘӮ©ӮБӮДӮИӮўӮИӮ ҒAғ„ғiғMӮіӮсҒBғ{ғNӮЖҒcҒcӮҰҒ[ӮБӮЖҒAғҠғҮғEҒHҒ@ӮЕҠЫӮӯүё•ЦӮЙҚПӮЮӮНӮёӮИӮўӮБӮДҒv
ҒuҒcҒcӮ»ӮӨӮ¶ӮбӮИӮўӮҫӮлӮӨҒv
Ғ@Ҹз’kӮМӮжӮӨӮИҢы’ІӮМғPғCӮЖӮН‘ОҸЖ“IӮЙҒAғҠғҮғEӮНҸaӮўҠзӮрӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҒAғPғCӮМ•ыӮН–{ӢCӮЕӮ ӮйҒB
ҒuӮДӮўӮӨӮ©ғ{ғNҒAӮұӮсӮИ–уӮМ•ӘӮ©ӮзӮИӮў“zӮЖҚsӮӯӮМҢҷӮҫӮжҒBӮ»ӮаӮ»Ӯа••ҲуӮ·ӮйӮВӮаӮиӮИӮўӮөҒv
ҒuҒcҒcӢM—lҒAҸӯӮө–ЩӮБӮДӮлҒv
Ғ@ӮВӮўӮЙғҠғҮғEӮӘҲк”ӯүЈӮБӮД—НӮёӮӯӮЕ–ЩӮзӮ№ҒA–цӮЙүsӮўҺӢҗьӮр“ҠӮ°ӮҪҒBӢҜӮЭӮ»ӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮӘҒAҗhӮӨӮ¶ӮД“ҘӮЭӮЖӮЗӮЬӮйҒB
ҒuӮЗӮӨӮўӮӨӮВӮаӮиӮҫҒv
ҒuҺ„ҒAүҪӮа•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮ©ӮзҒB“сҗlӮӘ•ӘӮ©ӮБӮДӮйӮИӮзҒA“сҗlӮЕҚsӮҜӮОӮўӮўӮ¶ӮбӮИӮўҒv
Ғ@ӮЗӮӨӮЕӮаӮўӮўӮЖҺvӮБӮҪҒB–цӮЕӮИӮӯӮДӮаӮўӮўӮМӮИӮзҒA–цӮӘҚsӮӯ•K—vӮНӮИӮўҒBғҠғҮғEӮағPғCӮаҒwҸpҺtҒxӮИӮМӮИӮзӮОҒAӮИӮәӮнӮҙӮнӮҙ–цӮЙ—ҠӮаӮӨӮЖҺvӮБӮҪӮМӮ©ҒBҒ\Ғ\“БӮЙҒAғҠғҮғEӮНҒB
ҒuҺ„ӮӘҚsӮӯ•K—vҒAӮИӮўӮ¶ӮбӮИӮўҒv
Ғu•ӘӮ©ӮБӮДӮИӮўӮИӮ ҒAғ„ғiғMӮіӮсҒBғ{ғNӮӘӮұӮўӮВӮЙҺиӮр‘ЭӮ·Ӣ`—қӮНҒAӮЗӮұӮЙӮаӮИӮўӮжҒv
Ғ@ғPғCӮНҢyӮўҢы’ІӮЕҢЁӮрвҗӮЯӮҪҒB
ҒuӮаӮБӮЖӮаҒAғ„ғiғMӮіӮсӮЙҢҫӮнӮкӮкӮО•КӮҫӮҜӮЗӮЛҒv
ҒuҒcҒcӮЗӮӨӮўӮӨӮұӮЖҒHҒv
Ғ@•·Ӯ«•ФӮ·ӮЖҒAғPғCӮНӮ¬ӮеӮБӮЖӮөӮДғҠғҮғEӮрҗUӮи•ФӮБӮҪҒBғrғVғbӮЖғҠғҮғEӮрҺwҚ·ӮөҒAҺvӮўӮБӮ«ӮиӢ©ӮФҒB
ҒuӮҝӮеӮБӮЖ‘ТӮБӮҪҒBҢNӮЬӮіӮ©ҒAғ„ғiғMӮіӮсӮЙүҪӮБӮБӮБӮЙӮаҳbӮөӮДӮИӮўӮМҒIҒHҒv
ҒuүҪӮрҳbӮ№ӮЖҢҫӮӨӮсӮҫҒHҒv
Ғ@Ӯ©ӮИӮи–{ӢCӮЕ•·Ӯ«•ФӮөӮҪғҠғҮғEӮЙҒAғPғCӮН“ӘӮр•шӮҰӮДӮөӮбӮӘӮЭҚһӮсӮҫҒB
ҒuӮ©Ғ[ӮБҒBӮұӮсӮИ“Ӯ•П–ШӮЙҗәӮ©ӮҜӮзӮкӮҪғ„ғiғMӮіӮсӮЙ“ҜҸоӮ·ӮйӮжҒBүҪӮа’mӮзӮ№ӮёӮЙҒAӮжӮӯӮ»ӮсӮИ–К“|ӮИӮұӮЖӮӘ—ҠӮЯӮйӮЛҒv
Ғ@үҪӮр’mӮзӮіӮкӮДӮўӮИӮўӮМӮ©ҒA–цӮЙӮН•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒBӮЖӮўӮӨӮ©ҒAӮ»ӮМ•УӮМҺ–ҸоӮНғPғCӮЙҳbӮөӮДӮаӮзӮБӮҪ•ыӮӘҢ«–ҫӮИӢCӮӘӮөӮДӮ«ӮҪҒB
ҒuӮ ӮМҒAҒcҒcүҪӮМҳbҒHҒv
Ғuғ„ғiғMӮіӮсҒAғ{ғNӮӘҗFҒXҳbӮөӮДӮ Ӯ°ӮйӮ©ӮзӮЛӮБҒIҒIҒv
ҒuҒcҒcӮНӮ ҒBҒv
Ғ@ғҠғҮғEӮр–Ў•ыӮЕӮНӮИӮўӮЖӮ©ҺUҒXӮИӮұӮЖӮрҢҫӮБӮДӮЁӮ«ӮИӮӘӮзҒAғPғCӮМ•ыӮа“GӮ©–Ў•ыӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮӯӮИӮБӮДӮ«ӮҪҒBӮЖӮўӮӨӮ©ҒA’iҒXӮЖҢ©•ыӮЙҢXӮўӮДӮ«ӮҪӢCӮӘӮ·ӮйӮМӮН–цӮҫӮҜӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
ҒuӮіӮ ҒAӮЗӮұӮ©ӮзҳbӮ»ӮӨӮ©ҒBӮвӮБӮПӮиӮұӮұӮНҒAғ{ғNӮЖғҠғҮғEӮМҸoүпӮўӮ©ӮзҒcҒcҒv
ҒuӮ»ӮұӮН”тӮОӮөӮДӮўӮўӮЕӮ·Ғv
Ғ@ҸoүпӮўӮЖӮ©ҢҫӮнӮкӮДӮаҒAӮ ӮЬӮи•·ӮўӮДӮаҠyӮөӮўҳbӮЕӮНӮИӮўӢCӮӘӮ·ӮйҒBҠөӮкҗхӮЯӮЖӮ©ҢҫӮнӮИӮў•УӮиҒAӮЬӮҫғ}ғVӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮӘҒB
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒAүҪӮ©ӮзҒHҒv
Ғ@Ӯ Ӯ©ӮзӮіӮЬӮЙ•s–һӮ»ӮӨӮИғPғCӮЙҗqӮЛӮзӮкҒA–цӮНҸӯӮөӮҫӮҜҚlӮҰӮҪҒBӮЬӮёӮНҒAүҪӮ©Ӯз’mӮйӮЧӮ«ӮИӮМӮҫӮлӮӨӮ©ӮЖҒB
ҒuҒcҒcҒwҚ°ӮМ”ә—өҒxӮБӮДүҪҒHҒv
Ғ@үҪӮжӮиӮаҺ©•ӘӮЙҠЦҢWӮ ӮйҒiӮЖҺvӮӨҒjӮұӮЖӮ©ӮзҗqӮЛӮҪҒBҗіҠmӮЙӮНҒAҒuҒwҚ°ӮМ”ә—өҒxӮМҒvӮҫӮБӮҪӮӘҒB
ҒuҠ®‘SӮЙүA—zӮӘҠҡӮЭҚҮӮБӮҪ•v•wӮрҒAӮ»ӮӨҢДӮФӮсӮҫӮжҒBӮұӮМҗўӮЕӮҪӮБӮҪҲкҗlӮМҒAӮ ӮйҲУ–ЎӮЕӮНү^–ҪӮМ‘ҠҺиӮрҒv
Ғ@•Ғ’КӮНҸoүпӮБӮҪӮиӮөӮИӮў‘¶ҚЭҒBӮҜӮкӮЗҒAӮұӮМҗўӮМӮЗӮұӮ©ӮЙ•KӮё‘¶ҚЭӮөӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМ‘ҠҺиӮЖҸoүпӮӨӮЖҒAҒwҸpҺtҒxӮМҗўҠEӮМҸнҺҜӮр’ҙүzӮөӮҪӮұӮЖӮаӢNӮұӮиӮӨӮйӮЖӮўӮӨҒBӮҪӮЖӮҰӮО—НӮӘ‘қ•қӮіӮкӮҪӮиҒAӮ ӮйӮўӮНҗg‘МӮМҺЎ–ь”\—НӮӘӢӯӮЬӮБӮҪӮиӮ·ӮйҒB
ӮЬӮҪҒA–{—ҲӮНҢҢӮЕҢҲ’иӮ·ӮйӮНӮёӮМҒwҸpҺtҒxӮЖӮөӮДӮМ—НӮӘҒAҢҢӢШӮЙҠЦҢWӮИӮӯӢӯӮў—НӮрҺқӮВҺqӢҹӮӘҺYӮЬӮкӮҪӮиӮаӮ·ӮйӮзӮөӮўҒBҒ\Ғ\–цӮМ—јҗeӮНҒAӮЁӮ»ӮзӮӯҒwҚ°ӮМ”ә—өҒxҒBӮҫӮ©ӮзӮұӮ»ҒwҸpҺtҒxӮЖӮөӮДӢӯӮўҢҢӢШӮрҺқӮВӮНӮёӮМғPғCӮМҒwҸpҒxӮрқӣӮЛ•ФӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮНҒA•Ғ’КӮЕӮНӮ Ӯи“ҫӮИӮўӮұӮЖҒB
ҒuҢгӮЛҒAғ{ғNӮМҒwҸpҒxӮрқӣӮЛ•ФӮөӮҪӮұӮЖӮЖҠЦҢWӮ ӮйӮсӮҫӮҜӮЗҒBғ{ғNӮНғ„ғiғMӮіӮсӮЙ•үӮҜӮҪҒBӮҫӮ©ӮзҒAғ{ғNӮНғ„ғiғMӮіӮсӮЙҸ]ӮӨӮжҒv
Ғ@–цӮрҠЬӮЮҒwҸpҺtҒxӮМҗўҠEӮНҒA—НӮМӢӯӮўҺТӮӘҗіӢ`ҒBҸҹӮБӮҪҺТӮН•үӮҜӮҪҺТӮрҸ]ӮҰҒA•һҸ]ӮрҗҫӮӨҒBӮҫӮ©ӮзғPғCӮНҒA–цӮЙҸ]ӮӨӮұӮЖӮӘҢҲ’иӮөӮҪҒBҒ\Ғ\ғPғCӮМҒwҸpҒxӮрҒA–цӮӘқӣӮЛ•ФӮөӮҪҺһ“_ӮЕҒB
ҒuӮЗӮсӮИ—қ•sҗsӮИ–Ҫ—ЯӮЙӮЕӮаҒAғ{ғNӮНҸ]ӮӨҒBӮ»ӮкӮӘқ|ӮҫӮ©ӮзӮҫҒv
Ғ@җ^ҠзӮЙӮИӮБӮҪғPғCӮНҒAҗ^ӮБ’јӮ®ӮЙ–цӮрҢ©ӮҪҒB“а•п•ЁӮМӮИӮў•уҗОӮМӮжӮӨӮИ“өӮЙҒAҸОӮўӮНҢҮ•РӮаӮИӮўҒBйGҒXӮЖӮөӮДӮўӮйӮжӮӨӮЙҢ©ӮҰӮДӮаҒAғPғCӮМ–{ҺҝӮНӮұӮұӮЙӮ ӮйҒB
ҒuӮҫӮ©ӮзӮЛҒAӮаӮөғ„ғiғMӮіӮсӮӘҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮр••ҲуӮөӮЙҚsӮ«ӮҪӮӯӮИӮўӮИӮзҒAғ{ғNӮНғ„ғiғMӮіӮсӮрҺзӮйӮжҒBҒ\Ғ\Ӯ»ӮӨӮўӮӨӮұӮЖҒv
ҒuӮ¶ӮбӮ ҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮНҒAүҪӮМӮҪӮЯӮЙӮ ӮйӮМҒHҒv
ҒuӮ»ӮкӮНҗ»ҚмҺТӮЙ•·Ӯӯ•ыӮӘ‘ҒӮўӮжҒv
Ғ@ӮУӮЖҢіӮМҢyӮў’ІҺqӮЙ–ЯӮиҒAғҠғҮғEӮрҗUӮи•ФӮБӮҪҒBҸaӮўҠзӮрӮөӮДӮўӮй”Ҫ–КҒA’·Ӯўҗа–ҫӮрҸИ—ӘӮЕӮ«ӮҪӮұӮЖӮЕҠyӮрӮөӮҪӮЖӮЕӮаҺvӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮИҠзӮрӮөӮДӮўӮйҒB
ҒuҒcҒcӮ ӮЬӮиӮЙӮаҗ¶ҠҲҺи’iӮрҺқӮҪӮИӮўҺТӮМӮҪӮЯӮЙҒAӮ№ӮЯӮДӢҷӢЖӮЕҗ¶ҢvӮр—§ӮДӮзӮкӮйӮжӮӨӮЙӮөӮҪӮҫӮҜӮҫҒBҠCӮ©ӮзӮМүБҢмӮӘҲк•РӮЕӮаӮ ӮкӮОҒAүҪӮЖӮ©ӮИӮйӮ©ӮзӮИҒv
Ғ@ҠCӮЙӢЯӮўҸкҸҠӮЕӮН”_ӢЖӮӘҗ¬Ӯи—§ӮҪӮИӮўҒBӮ»ӮМ‘гӮнӮиӮЖӮөӮДҒAӢҷӢЖӮӘҚsӮҰӮй’ц“xӮМ—НӮрҚһӮЯӮҪӮзӮөӮўҒBӮ»ӮМҢ№ӮЙӮНҒAӮ©ӮИӮиӮМ—НӮрҺcӮөӮД••ҲуӮөӮДӮЁӮўӮҪҒBҸӯӮөӮёӮВҸӯӮөӮёӮВҒA•ӘҠ„ӮөӮДүБҢмӮр“ҫӮзӮкӮйӮжӮӨӮЙҒB
ҒuӮҪӮҫӮө••ҲуӮрүрӮўӮДӮөӮЬӮҰӮОҒAҗв‘О“IӮЙҠCҗ_ӮМүБҢмӮр“ҫӮзӮкӮйҒBӮ»ӮкӮр‘_ӮБӮДӮўӮй”yӮӘҒAҚЕӢЯӮЙӮИӮБӮД“®Ӯ«ҸoӮөӮҪҒv
Ғ@ҠCҗ_ӮМүБҢмӮр“ҫӮДӮөӮЬӮҰӮОҒA’nӢ…ӮМҺөҠ„ӮрҺx”zӮөӮҪӮа“Ҝ‘RӮЙӮИӮйҒBӮҫӮ©ӮзӮұӮ»ҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮр‘_ӮӨҺТӮНҢгӮрҗвӮҪӮИӮўҒBҚЎӮЬӮЕӮН••ҲуӮӘӢӯ—НӮҫӮБӮҪӮҪӮЯҲА‘SӮҫӮБӮҪӮӘҒAҺһӮЖӢӨӮЙ••ҲуӮаҠЙӮЭҺnӮЯӮДӮўӮйҒBӮұӮМӮЬӮЬӮЕӮНӮўӮёӮк••ҲуӮӘүрӮҜҒAүҪҺТӮ©ӮӘҠCӮМ”eҢ ӮрҲ¬ӮБӮДӮөӮЬӮӨӮМӮҫҒB
ҒuӮұӮұӮЬӮЕҳbӮ·ӮВӮаӮиӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮсӮҫӮӘҒAӮ»ӮұӮМҲў•рӮӘ—ҚӮсӮҫӮМӮЕӮНҺd•ыӮИӮўҒBҒ\Ғ\ӮЗӮӨӮ·ӮйҒHҒv
Ғ@ӮЗӮӨӮ·ӮйӮЖ–вӮнӮкӮДӮаҒAӮ ӮЬӮиӮЙӮаӢK–НӮӘ‘еӮ«ӮўҒBӮҪӮҫӮМҚӮҚZҗ¶ӮӘҒAӮИӮәҗўҠEӮМҚs•ыӮр–вӮнӮкӮИӮӯӮДӮНӮИӮзӮИӮўӮМӮ©ҒBӮ·Ӯ®ӮЙӮН“ҡӮҰӮӘҸoӮ№ӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuӮ ҒAӮҝӮИӮЭӮЙҒBғ{ғNӮҫӮҜӮр“Ӯ•П–ШӮЖҲкҸҸӮЙҚsӮ©Ӯ№ӮйӮБӮДӮМӮН–і—қӮҫӮ©ӮзҒBқ|Ӯ¶ӮбҒAғ{ғNӮНғ„ғiғMӮіӮсӮҫӮҜӮрҺзӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮйӮ©ӮзӮЛҒv
Ғ@ӮИӮзӮОҢӢӢЗҒA–цӮӘҚsӮ©ӮИӮӯӮДӮНӮИӮзӮИӮўҒBӮҪӮЖӮҰүҪӮа•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮЖӮөӮДӮаҒAӮ»ӮкӮНҗVӮҪӮЙҠwӮСӮИӮӘӮзҒBҒcҒcӢіҺtӮӘӢіҺtӮҫӮҜӮЙҒAҸӯҒX•sҲАӮНҺcӮйӮМӮҫӮӘҒB
ҒuҒ\Ғ\•ӘӮ©ӮБӮҪӮнҒv
Ғ@–цӮНҗSӮрҢҲӮЯӮҪҒBӮЬӮҫүҪӮҫӮ©ӮжӮӯ•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮӘҒAҒwҠCӮМ’ҶӮМ’nҗ}ҒxӮН•KӮёҺ©•ӘӮӘ••ҲуӮ·ӮйӮЖҒB
ҒuӮЬҒAҺи“`ӮӨӮМӮНӮ»ӮұӮМ“Ӯ•П–ШӮҫӮҜӮ¶ӮбӮИӮўӮөӮЛҒv
ҒuҒcҒcӮіӮБӮ«Ӯ©Ӯз•·ӮўӮДӮўӮкӮОҒA“Ӯ•П–ШӮЖүҪ“xҢҫӮӨӢCӮҫҒBӮжӮӯ–OӮ«ӮИӮўӮаӮМӮҫӮИҒv
ҒuҺ–ҺАӮНүҪ“xҢҫӮБӮДӮа•ПӮнӮзӮИӮўӮ©ӮзӮЛӮҘҒv
Ғ@ғPғCӮМ—ӯӮЯ‘§ҒB
Ғ@ӮвӮНӮиҒA–цӮЙӮН–ҹҚЛӮЙӮөӮ©Ң©ӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒBүҪӮЖӮўӮӨӮ©ҒAӮЗӮұӮЬӮЕҢҫӮБӮДӮаӮұӮМ’ІҺqӮЕ“ЛӮБ‘–ӮйӮМӮ©ӮЖҺvӮӨӮЖҗжӮӘҺvӮўӮвӮзӮкӮйҒB—ҠӮЮӮ©ӮзҠМҗSӮИҺһӮЙҒAӢCӮМ”ІӮҜӮйӮжӮӨӮИӮұӮЖӮНҢҫӮБӮДӮЩӮөӮӯӮИӮўӮаӮМӮҫҒBҒcҒcӮЬӮіӮ©‘еҸд•vӮҫӮЖҺvӮўӮҪӮўӮӘҒB
ҒuӮ»ӮкӮ¶ӮбҒAӮЬӮёӮНӮаӮБӮЖӢп‘М“IӮИӮұӮЖӮрӢіӮҰӮДӮҝӮеӮӨӮҫӮўҒBҺ„ҒA•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮұӮЖӮӘҺRҗПӮЭӮИӮсӮҫӮ©ӮзҒv
Ғ@“сҗlӮрҺ~ӮЯҒAҗжӮЙ•аӮ«ҸoӮөӮДӮ©ӮзҗUӮи•ФӮБӮҪҒB
ҒcҒcҒcҒcӮІӮЯӮсӮИӮіӮўҒA‘ұӮӯҒB
|
|
|
|
| ҒuThe last songҒv ҳAҚЪҺ®ҒHҒ@’ҳҒ@“с”Nҗ¶Ғ@ҒFӮВӮйӮМӮвӮЬӮҫ |
|
|
|
ӮP
Һ©•ӘӮМӢCҺқӮҝӮӘ•ӘӮ©ӮзӮИӮӯӮИӮиҢъӮўүJү_ӮЙҺpӮрҺNӮ·ҒBҺ„ӮНүҪҢМӮұӮұӮЙӮўӮйӮМӮЕӮ ӮлӮӨӮ©ҒBҺ©•ӘӮЕӮНӮұӮұӮЙӢҸӮДӮНӮўӮҜӮИӮўӮЖӮўӮӨ”OӮЙӢмӮзӮкӮДӮўӮйӮМӮЙҒBӮ ӮМҸtӮМ“ъҒBӮёӮБӮЖ‘OӮрҢьӮўӮДӮўӮҪӮ ӮИӮҪӮНҒAӮўӮ«ӮИӮиҸБӮҰӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB“сҗlӮЖӮа—§”hӮЙҗ¬’·ӮөӮҪӮЖӮ«ҒA‘еҗlӮЙӮИӮБӮҪӮЖӮ«ҒAҸtӮМ’ӢүәӮӘӮиӮЙӮЕӮаүпӮўӮЬӮөӮеӮӨӮЖ–с‘©ӮөӮҪҒBӮЕӮаүпӮҰӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB•КӮкӮйӮЖӮ«Һ„ӮНҢҫӮБӮҪҒB
ҒuӮұӮМҢҫ—tӮНҸIӮнӮиӮМҢҫ—tӮЕӮаӮ ӮиҒA‘ұӮӯҢҫ—tӮЕӮаӮ ӮйӮМӮжҒv
Ӯ ӮИӮҪӮНҸОӮБӮДҒAҒuӮЬӮҪүпӮўӮЬӮөӮеӮӨҒvӮЖҢҫӮўҸo”ӯӮөӮҪҒB
Ӯ»ӮМҢгҒAӮ ӮИӮҪӮ©Ӯз“НӮӯҺиҺҶӮрҲк“xӮа“ЗӮЬӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮНӮИӮўҒBҺ„ӮНҺ„ӮИӮиҒAҺҹӮЙүпӮӨӮЖӮ«ӮЙҠзӮрҢ©Ӯ№ӮзӮкӮйӮжӮӨӮЙ“®ӮўӮДӮ«ӮҪҒBӮҫӮҜӮЗӮ ӮИӮҪӮНӮўӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҲӨӮ·ӮйҺ„ӮрҺcӮөӮДҚsӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB“–ӮДӮжӮӨӮМӮИӮўҗ[ӮўҢОӮМ’кӮМӮжӮӨӮЙҚ•ӮӯҒAҸ¬“ҒӮМӮжӮӨӮЙҗлӮБӮҪӢCҺқӮҝӮрӮЗӮӨӮөӮҪӮзӮўӮўӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB
ӮұӮМӢCҺқӮҝӮр•шӮ«ӮөӮЯҒAҺhӮіӮБӮҪҗSӮ©Ӯз—¬ӮкӮйҢҢӮрҺ~ӮЯӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮйӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBӮұӮМӮЬӮЬҺ„ӮМҗSӮН”MӮрҺёӮБӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮөӮДҒAӮ ӮИӮҪӮМҢіӮЙҚsӮБӮДӮөӮЬӮўӮҪӮўҒBӮҫӮҜӮЗҒAҢҲӮөӮД‘Ҡ—eӮкӮИӮўҗўҠEӮҫӮ©ӮзҒAҺ„ӮЙӮНҚsӮӯҢ —ҳӮӘ–іӮўҒBӮұӮМӮЗӮӨӮЙӮаҸo—ҲӮИӮўҸуӢөӮЙӢtӮзӮҰӮОӢtӮзӮӨ’цӮ ӮИӮҪӮН—ЈӮкӮДҚsӮБӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮөӮДҒAҺ„ӮНҺhӮіӮБӮҪӮЬӮЬӮМҗSӮр”w•үӮўҒA–°ӮкӮёӮЙ—вӮвӮвӮ©ӮИ’n–КӮЙ—§ӮБӮДӮўӮйҒB
•аӮ«ҸoӮ№ӮОҒA“ҡӮҰӮӘҢ©ӮВӮ©ӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮЕӮаҒAӮ»ӮкӮӘҲкҗ¶Ӯ ӮИӮҪӮЙүпӮӨҺи’iӮр–іӮӯӮ·Ӯ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮЖҺvӮӨӮЖ“ҘӮЭҸoӮ№ӮИӮўҒBӮвӮНӮиҺ„ӮЙӮНӮ ӮИӮҪӮӘ‘еҗШӮ·Ӯ¬ӮйҒBҸ\”NӮЖӮўӮӨ’ZӮўӮжӮӨӮЕ’·ӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҺһҠФӮрүЯӮІӮөӮҪӮұӮЖӮрҚЎҚXҺМӮДӮйӮұӮЖӮИӮсӮДҸo—ҲӮИӮўҒBҺ„ӮЙӮНӮ ӮИӮҪӮр”Ы’иӮ·ӮйӮұӮЖӮИӮсӮДҸo—ҲӮИӮўҒB
Һ„ӮМӢLүҜӮМ’ҶӮЙӮНӮ ӮИӮҪӮЖҲкҸҸӮЙӮўӮҪӮұӮЖӮЕ‘тҺRӮЕҒAүҪҲкӮВҺМӮДӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҒB
ӢCӮГӮҜӮОүJӮӘҚ~ӮБӮДӮ«ӮДҒAҺ„ӮМ‘МӮр”GӮзӮөҺnӮЯӮйҒBҸo—ҲӮйӮМӮИӮзҺ„ӮМҗSӮ©Ӯз—¬ӮкӮйҢҢӮрҗфӮў—¬ӮөӮДӮӯӮкҒBҒ\Ғ\‘Мү·ӮИӮсӮДҠЦҢWӮИӮўҒBӮ·ӮЕӮЙӮ ӮИӮҪӮӘӮўӮИӮӯӮИӮБӮҪӮЖӮ«ӮЙҺ„ӮМҗg‘МӮН—вӮЯҗШӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮаӮМҒBӮаӮНӮв’ЙҠoӮМҺёӮБӮҪҗSӮЙүJӮНҹҺӮЭӮИӮўҒBӮ ӮИӮҪӮӘӮўӮИӮӯӮИӮБӮДҲк”NӮЖҺөҸ\Һl“ъҒBӮұӮӨӮөӮДүJӮЙ”GӮкӮйӮМӮН“сҸ\Һlүс–ЪҒBӮЬӮҫӮ ӮИӮҪӮӘҢ©ӮҰӮИӮўҒB
—ЬӮӘҺ©‘RӮЙ—¬ӮкҒAүJӮЙҚ¬Ӯ¶Ӯи—ҺӮҝӮДӮўӮӯҒB”–ӮӯӮИӮБӮҪ—ЬӮМ–ЎӮНҺ„ӮЙӮН“ЕӮЖӮөӮ©ҺvӮҰӮИӮўҒBҺ©•ӘӮМ’ҶӮЙҚLӮӘӮй“ЕӮМбғӮкӮЙҗkӮҰӮДӮўӮйӮЖҒAҺ„ӮМҚ¬—җӮөӮҪҗўҠEӮӘ“ӘӮМ’ҶӮЙ•ӮӮ©ӮсӮЕӮ«ӮҪҒB
Қ•ӮӯҚКӮзӮкӮҪғhғҢғXӮЙҗgӮр•пӮЭҒAҗФӮӯҚзӮ«—җӮкӮҪ”ЮҠЭүФӮМ’ҶӮЙ–„ӮаӮкӮйҺ„ҒB”ЮҠЭүФӮМҢ`ӮЖҗFӮЙүxӮЙҗZӮйҺ„ҒBҢьӮұӮӨ‘ӨӮ©Ӯз•аӮўӮДӮӯӮйӮ ӮИӮҪҒBҒuӮвӮБӮЖӮ ӮИӮҪӮЙүпӮҰӮЬӮөӮҪҒvӮЖҺиӮрҗLӮОӮөӮҪҸuҠФӮЙҺ„ӮМҳrӮНӮ©ӮФӮкӮДӮўӮӯҒB”ЮҠЭүФӮМ“ЕӮ©ҒAӮаӮөӮӯӮНҺ„ӮМ—ЬӮ©ҒBӮ©ӮФӮкӮНӮЗӮсӮЗӮсҚLӮӘӮБӮДӮўӮ«ҒAӮвӮӘӮДҺ„ӮМҺӢҠEӮрүBӮ·ҒB–ІӮМҗўҠEӮЕӮаӮ ӮИӮҪӮЙӮНүпӮҰӮИӮўӮМӮ©ҒB
ҒuғҶғҠҺoӮіӮсҒIҒv
Ӯ»ӮМҢҫ—tӮЙҺ„ӮНүдӮЙ•ФӮйҒBүJҚ~Ӯй–йӮМ’КӮиӮЙҺ„ӮН“XӮМғVғғғbғ^Ғ[ӮЙӮӨӮИҗӮӮкӮДӮўӮҪҒB
ҒuғWғ…Ғ[ғX”ғӮБӮДӮӯӮйӮБӮДҢҫӮБӮДҸoӮДҚsӮБӮҪӮМӮЙҒAӢAӮиӮӘ’xӮўӮ©ӮзҢ©ӮЙҚsӮБӮҪӮзҒv
Ғu‘еҸд•vӮжҒBӮ»ӮкӮжӮиҚЎүҪҺһҒHҒv
ҒuӮҰҒBҚЎӮНҒcҒcҢЯ‘O—лҺһҺOҸ\Һl•ӘҒBӮ»ӮкӮжӮиҺPҺқӮБӮДҚsӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзҗS”zӮөӮҪӮжҒv
ҒuӮІӮЯӮсӮЛҒBӮЁҺoӮҝӮбӮсҒAӮўӮВӮаҺP–YӮкӮҝӮбӮӨӮМӮжҒv
ҒuӮаӮӨҒcҒcҒBӮЩӮзҺPҺқӮБӮДҒAӮұӮсӮИҸҠӮЙӮўӮйӮЖ•—ҺЧӮРӮўӮҝӮбӮӨӮжҒB‘ҒӮӯӢAӮлӮӨҒv
’нӮНҺ„ӮЙҺPӮр“nӮөҒA‘OӮр•аӮўӮДӮўӮӯҒBҚKӮўҒAҺ„ӮӘ•ЁҺvӮўӮЙ’^ӮБӮДӮўӮҪӮұӮЖӮН’mӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮЭӮҪӮўӮҫҒBӮўӮўүБҢёӮЙӮұӮМ•ЁҺvӮўӮр–іӮӯӮіӮИӮӯӮДӮНӮИӮзӮИӮўҒB“ҡӮҰӮӘ–іӮў–вӮрҚlӮҰӮДӮўӮҪӮБӮДҒAҺ©•ӘӮӘҸқӮВӮӯӮҫӮҜӮҫҒBӮ ӮкӮЩӮЗҒAҗжҗ¶ӮЙ–YӮкӮИӮіӮўӮЖҢҫӮнӮкӮҪӮМӮЙҒAҺ„ӮН–ўӮҫӮЙҗUӮиҗШӮкӮИӮўҒBҚЎӮЬӮЕӮЙ–іӮўҚlӮҰӮр•шӮўӮДҒA“ҡӮҰӮрҢ©ӮВӮҜӮзӮкӮИӮўҒBӮұӮкӮЩӮЗ”nҺӯӮИӮұӮЖӮНӮ ӮйӮ©ҒB
ҒuӮЛӮҘҒAғRғEӮӯӮсҒv
Һ„ӮН’нӮЙ–вӮўӮ©ӮҜӮйҒBӮЬӮҫ’ҶҠwҗ¶ӮЕҺvҸtҠъӮМӢC”zӮаӮИӮў’нӮЙ•·ӮўӮДӮа–і‘КӮҫӮЖҺvӮБӮҪҒBӮЕӮаҚЎӮНҳbӮө‘ҠҺиӮӘ—~ӮөӮўҒB’ҫӮсӮҫӢCҺқӮҝӮӘ—қүрӮЕӮ«ӮИӮӯӮЖӮаҒAӮЖӮЙӮ©ӮӯҳbӮөӮДӮӯӮкӮкӮОӮўӮўҒBҺ„ӮНҚXӮЙ•tӮҜүБӮҰӮйҒB
Ғu‘еҗШӮИҗlӮрҺёӮБӮҪӮзҒAӮ ӮИӮҪӮНӮЗӮӨӮ·ӮйҒHҒv
ҒuҺёӮӨҒcҒcҒHҒ@‘еҗШӮИҗlӮрҺёӮБӮҪӮзҒA”ЯӮөӮЮҒB–lӮЙӮНҒAӮ»ӮкӮөӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮжҒv
Ғu”ЯӮөӮўӮМӮН“–ӮҪӮи‘OӮжҒB”ЯӮөӮсӮҫҢгҒAӮ ӮИӮҪӮНӮЗӮӨӮ·ӮйӮМҒHҒv
ӮИӮсӮДӢрӮ©ӮИӮМӮҫӮлӮӨҒBҚЯӮМӮИӮў’нӮрҢҫ—tӮЕҚUӮЯӮйҒBҺoӮЖӮөӮДӮНӮвӮБӮДӮНӮўӮҜӮИӮўҚsҲЧӮҫҒB’нӮЙҺҰӮөӮӘ•tӮ©ӮИӮўҒBӮЕӮаҺ„ӮМҚAӮМүңӮ©ӮзҹшӮЭҸoӮйҗhӮіӮНҸ•ӮҜӮр—~ӮөӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA“ҜҺһӮЙҗhӮіӮНҚAӮрҸДӮ«җsӮӯӮ·ӮжӮӨӮЙҺ„ӮМҢҫ—tӮр’DӮБӮДӮўӮБӮҪҒB
ҒuҺoҒcҒcӮіӮсҒHҒ@‘еҸд•vҒHҒv
Һ©ҢИҢҷҲ«ӮЙҠЧӮйҺ„Ӯр’нӮӘҺxӮҰӮйҒB‘SӮӯҒAҺ„ӮН‘К–ЪӮИҺoӮҫҒB’нӮЙҗS”zӮіӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮЕӮНҒAӮ ӮМҗlӮЙӮ»ӮБӮЫӮрҢьӮ©ӮкӮДӮөӮЬӮӨҒB
ҒuӮЬӮҫҒAӮ ӮМҗlӮМӮұӮЖӮр–YӮкӮзӮкӮИӮўӮМҒHҒv
’нӮМҢҫ—tӮНҠФҲбӮўӮИӮӯҺң”ЯӮҫӮлӮӨҒBӮөӮ©ӮөҒAҚЎӮМҺ„ӮЙӮН•Һ•МӮЙ‘ЁӮҰӮзӮкӮҪҒBӢCӮГӮҜӮОҺ„ӮНҗSӮМҗ[‘wӮ©Ӯз“fӮ«ҸoӮ·ӮжӮӨӮЙӮөӮДҢҫӮБӮҪҒB
Ғu–ЩӮБӮДҒv
Ӯ ӮМҗlӮЙӮВӮўӮДӮНҗGӮкӮИӮўӮЕҒBҺ„ӮН’нӮрбЙӮЭ•tӮҜӮДӮўӮҪҒBӮЬӮҫҒAҒu–ЩӮкҒvӮЙӮИӮБӮДӮўӮИӮўӮҫӮҜғ}ғVӮҫӮЖҺvӮБӮҪҒBӮҫӮӘҒAӮ»ӮМҗәҺҝӮЙӮНҠ®‘SӮЙҒwҚҰӮЭҒxӮӘҚ¬Ӯ¶ӮБӮДӮўӮҪӮЙҲбӮўӮИӮўҒBӮЬӮіӮ©’нӮЙҺ©•ӘӮМ’pӮ¶ӮйӮЧӮ«“а–КӮрҺNӮөӮДӮөӮЬӮӨӮЖӮНҒAҸоӮҜӮИӮўҒBҺ©ҢИҢҷҲ«ӮӘҚXӮЙҗ[ӮЬӮйӮМӮрҠҙӮ¶ҒAҺ„ӮНҢҫ—tӮрүБӮҰӮҪҒB
ҒuҒ\Ғ\ғRғEӮӯӮсҒBҺ„ҒAӮаӮӨҸӯӮөҚlӮҰӮДӮЭӮҪӮўӮМҒBӮҫӮ©ӮзӮЁҠиӮўҒv
ӮұӮұӮЬӮЕӮӯӮйӮЖӮаӮӨғGғSӮЕӮөӮ©ӮИӮўҒB’нӮаӮ»ӮкӮрҢеӮБӮҪӮМӮ©ҒA
Ғu•ӘӮ©ӮБӮҪӮжҒBӮЕӮағ„ғoӮ©ӮБӮҪӮз–lӮЙ‘Ҡ’kӮ·ӮйӮсӮҫӮжҒv
’нӮЙҗS”zӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҺ„ӮНӮЗӮкӮҫӮҜ‘К–ЪӮИҺoӮИӮМӮҫҒB’нӮЙҗS”zӮіӮкӮҪӮиҒA’нӮЙ“{ӮиӮрҺUӮзӮөӮҪӮиӮЖҒAӮ ӮкӮ©ӮзүҪӮа–ьӮҰӮДӮўӮИӮўҒBҗSӮН–ўӮҫӮЙ’ҫӮсӮҫӮЬӮЬҒBүҪ“xӮаҢJӮи•ФӮ·–йӮЙӢк”YӮөӮДҒAҸқӮВӮўӮДҒAҺ©•ӘӮр—қүрӮіӮ№ӮжӮӨӮЖӮөӮДӮўӮйӮҜӮЗҒA‘К–ЪӮҫҒBӮЗӮӨӮөӮДҺ„ӮН”ЮӮрӢҒӮЯӮДӮөӮЬӮӨӮМӮ©ҒBӮЬӮҫҺһҠФӮӘ•K—vӮИӮжӮӨӮҫҒB
ҒuӮіӮҹӢAӮйӮжҒAҺoӮіӮсҒB•кӮіӮсӮҪӮҝӮӘҗS”zӮөӮДӮўӮйӮжҒv
’нӮ©ӮзҺPӮрҺуӮҜҺжӮиҒAҺ„ӮНӢAҳHӮЙӮВӮўӮҪҒBҺPӮрҚ·ӮөӮҪӮМӮЕҗg‘МӮЙүJӮН“–ӮҪӮзӮИӮўӮӘҒAҺ„ӮМҗSӮН“yҚ»Қ~ӮиӮЕ”GӮкӮҪӮЬӮЬҒBӮўӮВҗ°ӮкӮЙӮИӮйӮМӮ©ҒBҺ©•ӘӮЙ–вӮўӮ©ӮҜӮҪҒBӮвӮНӮи“ҡӮҰӮНҸoӮДӮұӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ӮQ
–ІӮНҢАӮиӮ ӮйӮаӮМӮЖ—қүрӮөӮДӮўӮйҒBӮҫӮ©ӮзӮұӮ»Һ©•ӘӮМҠиӮўӮӘ–ІӮМ’ҶӮЙҢ»ӮкӮйӮМӮҫҒBӮ ӮИӮҪӮН–ІӮМ’ҶӮЕҸoӮДӮ«ӮДҺ„ӮМ–јӮрҢДӮФҒBҺ„ӮНӮ»ӮМҗәӮЙүһӮҰӮ ӮИӮҪӮМҢіӮЙӢмӮҜӮВӮҜӮйҒB–ІӮИӮМӮЙӮИӮсӮЕӮұӮсӮИӮЙҠрӮөӮўӮМӮҫӮлӮӨҒB–ІӮМ’ҶӮЕӮН“с“xӮЖүпӮҰӮИӮўӮЖӮўӮӨҚlӮҰӮӘҠу”–ӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒB’NӮӘӮ»ӮМҺ–ҺАӮрӢLүҜӮ©ӮзҸБӮөӮіӮлӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮ©ҒB“ҡӮҰӮНӮЪӮсӮвӮиӮЖ•ӮӮ©ӮФӮӘҒAҚЎӮМҺ„ӮЙӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮрҚlӮҰӮДӮўӮй—]—TӮН–іӮ©ӮБӮҪҒB”ЮӮЖӮұӮӨӮөӮД•шӮ«ҚҮӮӨӮұӮЖӮӘҺ„ӮМ–ІӮИӮМӮҫҒBӮўӮВӮЬӮЕӮаӮұӮӨӮөӮДӮўӮҪӮўҒB
ӮөӮ©ӮөҒA—LҢАӮМ–ІӮН’·ӮӯӮН‘ұӮ©ӮИӮўҒB“ъӮӘҸёӮиҒAҺ„ӮЖ”ЮӮМҠФӮрҲшӮ«—фӮӯҒB—ЬӮр—¬Ӯө”Я–ВӮрҸгӮ°ҒA”ЮӮМ–јӮрҢДӮСӮИӮӘӮзҺ„ӮН–ІӮрҢ©ҸIӮҰӮйҒBӢNӮ«ӮҪҢгӮМҺ„ӮМҠзӮЙӮН—ЬӮМҗХӮӘ•tӮўӮДӮўӮҪҒB–ІӮҫӮҜӮЕӮНӮўӮВүпӮҰӮйӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒBҺ„ӮН–ІӮМ’ҶӮЕӮөӮ©”ЮӮЙүпӮҰӮИӮўӮұӮЖӮрҚҰӮсӮҫҒBӮ»ӮкӮЖ“ҜҺһӮЙ–ІҲИҠOӮЙүпӮӨ•ы–@Ӯр–НҚхӮөӮҪҒBҸoӮДӮӯӮйҚlӮҰӮНҲкӮВӮҫҒBӮ»ӮкӮНӢрӮ©ӮЕҲА’јӮЕ–ІҢ©ӮИҺ©•ӘӮЙӮЖӮБӮДӮНҺd•ыӮӘ–іӮўҚlӮҰӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮұӮЙӮўӮй—қ—RӮН–іӮўҒBӮаӮӨ”ЮӮН‘јӮМҗўҠEӮМҸZҗlҒAӮИӮзӮОҺ„ӮӘӮ»ӮҝӮзӮЙҚsӮӯӮЬӮЕӮҫҒBӮ ӮИӮҪӮЙҚДӮСүпӮБӮД•шӮ«ӮөӮЯҚҮӮӨӮЬӮЕӮНҒAҺ„ӮӘ“w—НӮ№ӮЛӮОӮИӮзӮИӮўҒBҺ„ӮНҠу–]ӮрҢ©ҸoӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮӘҒu”j–ЕҒvӮЖӮўӮӨ–јӮМ“№ӮЕӮ ӮБӮДӮаҒ\Ғ\ҒBбчӮМҲӨӮЙҗҫӮўҒAҺ„ӮНҗiӮЭҸoӮ·ҒB
________________________________________
ҳZҢҺҲк“с“ъ–Ш—j“ъҒ@ҢЯ‘OҺөҺһ“с”Ә•Ә
ҚЎ’©ӮНҚр“ъӮЬӮЕӮМүJӮӘүRӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮЙҗ°ӮкӮДӮўӮйҒBҠOӮНғXғYғҒӮМӮіӮҰӮёӮиӮӘӢҝӮ«ҒA’©ӮрҚҗӮ°ӮДӮўӮйҒBғҶғҠӮӘ–ІӮ©Ӯз–ЪҠoӮЯӮҪӮМӮНҢЯ‘OҺөҺһӮМӮұӮЖӮЕҒAӮ»ӮкӮ©ӮзҺ©•ӘӮМҠзӮЙ•tӮўӮҪ—ЬӮМҗХӮр—¬Ӯ·ӮҪӮЯӮЙҗф–КҸҠӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒB”ЮҸ—ӮНҗф–КҸҠӮЙҢьӮ©ӮӨҠФҒAҠзӮр•ўӮБӮДӮўӮҪҒBӮұӮсӮИҠзӮрүЖ‘°ӮЙҢ©ӮзӮкӮДӮН’pӮёӮ©ӮөӮўӮМӮЖҺ©•ӘӮЙ‘ОӮөӮДӮМҺ©ҡ}ӮМӢCҺқӮҝӮӘ•ҰӮўӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮҫҒB–°ӮиӮ©Ӯз–ЪҠoӮЯӮҪҢгӮМ–сҺOҸ\•ӘҒA”ЮҸ—ӮНҗ¶Ӯ«ӮҪҗS’nӮӘӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB”ЮҺҒӮЙүпӮӨӮҪӮЯӮЙҒu”j–ЕҒvӮрҠиӮБӮҪӮМӮҫҒBҚЎӮЬӮЕӮ»ӮсӮИҠи–]ӮрғҶғҠӮНҺқӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮИӮўҒB”ЮӮЖӮМ•К—ЈӮӘӮ»ӮкӮЩӮЗҸХҢӮӮр—^ӮҰӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮН”ЮҸ—ӮаҺ©ҠoӮөӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөүҪҢМҒAҺҖӮр‘IӮФӮжӮӨӮИӮұӮЖӮрҚlӮҰ•tӮӯӮМӮ©ҒBғҶғҠӮМӢCҺқӮҝӮНӮЬӮ·ӮЬӮ·Қ¬“ЧӮрҗ[ӮЯӮйӮОӮ©ӮиӮҫӮБӮҪҒB
ғҶғҠӮНҗф–КҸҠӮЕҠзӮрҗфӮўҒAҺ•Ӯр–ҒӮ«ғҠғrғ“ғOӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒB•кӮӘ’©җHӮрҚмӮБӮДӮўӮйҒB’нӮМҺpӮӘҢ©“–ӮҪӮзӮИӮўҒBӮЬӮҪҗQ–VӮ©ҒBӮЖӮиӮ ӮҰӮёғҶғҠӮН•кӮЙ•·ӮўӮДӮЭӮйӮұӮЖӮЙӮ·ӮйҒB
ҒuғRғEӮНӮЬӮҫҗQӮДӮўӮйӮМҒHҒ@ӮЬӮҪ’xҚҸӮ·ӮйӮнӮжҒv
ҒuӮ Ӯ ҒAғRғEҢNӮНӮЛӮҘҒAүҪӮ©Ғw’©Ӯ©ӮзӮвӮзӮЛӮОӮИӮзӮКӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒxӮЖӮ©ҢҫӮБӮДҒAҺөҺһӮӯӮзӮўӮЙҠwҚZҚsӮБӮҝӮбӮБӮҪӮжҒBӮУӮУӮУҒA•ПӮжӮЛҒB’©Ӯ©ӮзӮвӮзӮЛӮОӮИӮзӮКӮЖӮ©ҒAӮЬӮйӮЕӮЁҺҳӮіӮсӮЭӮҪӮўҒv
ҒuӮНӮҹҒcҒcҒv
Ғ@—\‘zҠOӮМ•Ф“ҡӮЙҠJӮўӮҪҢыӮӘҚЗӮӘӮзӮИӮўғҶғҠҒBӮЬӮіӮ©ҒAӮ ӮМүi”N’xҚҸ–VҺеғRғEӮӘ‘ҒӢNӮ«ӮрӮөӮД”ЮҸ—ӮӘ’©җHӮрҗHӮЧӮй‘OӮЙҠwҚZӮЙҚsӮӯӮЖӮНҚЎ“ъӮНӢGҗЯҠOӮкӮМҗбӮЕӮаҚ~ӮйӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮлӮӨӮ©ҒBғeҒ[ғuғӢӮЙҚАӮБӮҪғҶғҠӮНҒA
ҒuӮ ҒAҚЎ“ъӮНғgҒ[ғXғgҲк–ҮӮЕӮўӮўӮжҒv
Ғ@Ӯ»ӮкӮр•·ӮўӮҪ•кӮНҺvӮнӮёҺиӮЙҺқӮБӮДӮўӮҪҺMӮр—ҺӮЖӮөӮҪҒB•кӮЙӮЖӮБӮДҚЎ“ъӮНҠпҗХӮМҳA‘ұӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒB
ҒuғҶғҠӮҝӮбӮсҒcҒcӮРӮеӮБӮЖӮөӮД‘ҫӮБӮҪӮМҒHҒv
Ғu‘ҫӮБӮДӮИӮўӮнӮўҒIҒIҒv
ҒuӮҫӮБӮДҒAҚЕӢЯӮЁ•—ҳCҸгӮиӮЙӮҪӮЯ‘§ӮОӮ©Ӯи•tӮўӮДӮўӮҪӮ©ӮзҒcҒcҒv
ҒuӮЬӮҹӮҪӮЯ‘§ӮНҒcҒcӮЛҒBӮвӮБӮПӮ»ӮкӮаӮ ӮйӮҜӮЗҒAӮЖӮЙӮ©ӮӯҚЎ“ъӮНҗH—~ӮӘ–іӮўӮМҒBӮҫӮ©ӮзғgҒ[ғXғgҲк–ҮӮЕӮўӮўӮжҒv
Ғ@–әӮМһB–ҶӮИҢҫ—tӮЙ•кӮНӢ^”OӮр•шӮ«ӮИӮӘӮзӮаҒAғpғ“ӮрҲк–ҮғgҒ[ғXғ^Ғ[ӮЙ•ъӮиҚһӮсӮҫҒB•кӮНҚXӮЙҢҫ—tӮрүБӮҰӮйҒB
ҒuҒ\Ғ\Ӯ»ӮкӮЖӮаҚр“ъӮМӮұӮЖӮаҠЦҢWӮөӮДӮўӮйӮМҒHҒv
Ғ@ӮұӮкҲИҸгӢ^ӮнӮкӮДӮа‘o•ыӮМӢC•ӘӮӘҲ«ӮӯӮИӮйҒB•·Ӯ«—¬ӮөӮҪӮўӢCҺқӮҝӮЕӮНӮ ӮйӮӘҒAғҶғҠӮНүҪӮЖӮ©ҢҫӮў‘UӮӨӮұӮЖӮрҢҲӮЯӮҪҒBӮаӮҝӮлӮс—бӮМ”ЮӮЙӮВӮўӮДӮМҳb‘иӮрҸoӮіӮкӮИӮўӮжӮӨӮЙӮ·ӮйӮҪӮЯӮЕӮаӮ ӮйҒB
ҒuӮ»ӮӨӮИӮМӮжҒBҚр“ъҺP–YӮкӮДҸoӮҝӮбӮБӮДӮЛӮҰҒBӮўӮвӮҹҒAӮСӮөӮеӮСӮөӮеӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪ–уӮЕӮ·ӮжҒBғRғEӮӘ—ҲӮИӮҜӮкӮОҒAӮЗӮӨӮИӮйӮұӮЖӮ©ӮЖҺvӮўӮЬӮөӮҪӮМӮжҒB‘SӮӯҒBӮ»ӮөӮДҒA•—ҺЧӮрҲшӮўӮҝӮбӮБӮДҗH—~ӮӘ–іӮўӮМӮЕӮ·ӮжӮ§Ғv
Ғ@•—ҺЧӮНҲшӮўӮДӮўӮИӮўҒBӮЗӮӨӮЭӮДӮаүRӮҫӮЖғoғҢғoғҢӮЕӮ ӮйӮӘҒAҚЎӮМҸуӢөӮр’EҸoӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНӮұӮӨӮ·ӮйӮөӮ©ӮИӮўҒBғҶғҠӮНҠPӮрҸoӮөӮҪӮиӮөӮДҒA•—ҺЧӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮрғAғsҒ[ғӢӮөӮҪҒB•кӮНҲкӮВ‘§ӮрӮВӮӯӮЖҒA
ҒuӮ»ӮӨӮўӮӨӮұӮЖӮИӮзҺd•ыӮИӮўӮнӮЛҒB‘еҠwӮНӢxӮЬӮИӮӯӮДӮўӮўҒHҒv
ҒuӢxӮЮӮЩӮЗӮМ•—ҺЧӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮзҒB•ЧӢӯӮЙӮНҺxҸб–іӮўӮнҒv
ҒuҲкүһ–тӮрҲщӮсӮЕӮЁӮ«ӮИӮіӮўҒB‘еҠwӮЕ“|ӮкӮҪӮз‘е•ПӮИӮсӮҫӮ©ӮзҒv
ҒuӮНҒ[ӮўҒv
Ғ@‘дҸҠӮМүңӮ©Ӯз•—ҺЧ–тӮрҺқӮБӮДӮ«ӮҪ•кӮНғҶғҠӮЙ–тӮЖҗ…Ӯр“nӮөӮҪҒB”сҸнӮЙӢкӮөӮўүRӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA•кӮНҗMӮ¶ӮДӮўӮйҒB”ч–ӯӮИҚЯҲ«ҠҙӮрҺқӮҝӮИӮӘӮзӮаҒAғҶғҠӮНҲк–ҮӮМғgҒ[ғXғgӮЖ—О’ғӮрҢыӮМ’ҶӮЙ•ъӮиҚһӮсӮҫҒB–тӮр•һ—pӮөӮҪҢгҒA‘еҠwӮЙҚsӮӯҸҖ”хӮрӮөӮЙҒAҺ©•ӘӮМ•”ү®ӮЙ“ьӮБӮҪҒB
ғҶғҠӮН•һӮр’…‘ЦӮҰӮДӮўӮйҠФҒAҚр”УӮМӮұӮЖӮрҺvӮўҸoӮөӮДӮўӮҪҒBғRғEӮН”ЮҸ—ӮрҗS”zӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖӮНҠФҲбӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒB•кӮаӮ ӮсӮИӮұӮЖӮрҢҫӮБӮДҒA”ЮҸ—ӮӘ•—ҺЧӮҫӮЖҺvӮБӮДӮўӮйӮӘҒAҺАҚЫӮНүRӮҫӮЖҢ©”ІӮўӮДӮўӮйӮҫӮлӮӨҒBҒ\Ғ\үЖ‘°ӮЙ–АҳfӮрӮ©ӮҜӮДӮўӮйӮЖҠmҗMӮөӮҪғҶғҠӮНҺ©•ӘӮЙ‘ОӮөӮДӮМ•sҚb”гӮИӮіӮрҠҙӮ¶ӮҪҒBӢғӮ«ӮҪӮўӮЖҺvӮБӮҪӮӘҒAҚр“ъӮМӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAҺһҠФӮӘӮЬӮҫ”ӘҺһ‘OӮҫӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕҠ¬ӮҰӮҪҒBҒuҺ„ӮНӮ»ӮұӮЬӮЕҺгӮўҒ\Ғ\җlҠФӮЕӮНӮИӮўҒvӮЖҢҫӮў•·Ӯ©Ӯ№ӮДҒAғҶғҠӮНҢәҠЦӮЦҚ~ӮиӮДӮўӮБӮҪҒB
ҒuҚЎ“ъӮНүҪҺһӮЬӮЕӮЙӮИӮйӮМҒv
ҒuӮсҒ[ҒAҚЎ“ъӮНғTҒ[ғNғӢӮа–іӮўӮө•КӮЙ—F’BӮЖӮа–с‘©ӮөӮДӮИӮўӮ©Ӯзҗ^ӮБ’јӮ®ӢAӮБӮДӮӯӮйӮ©ӮИҒv
ҒuӮ»ӮӨҒcҒcҒBҚЎ”УӮНғJғҢҒ[ӮжҒBҠyӮөӮЭӮЙӮөӮДӮўӮИӮіҒ[ӮўҒv
Ғ@–ҫӮйӮў•\ҸоӮЕ–әӮр‘—Ӯй•кӮМ–ЪӮНҲЈӮкӮЭӮӘҠЬӮЬӮкӮДӮўӮҪҒBғҶғҠӮӘғhғAӮрҠJӮҜӮДүЖӮ©ӮзҸoӮйӮЖӮ«ӮЙ•кӮНҢҫӮБӮҪҒB
ҒuғҶғҠӮҝӮбӮсҒcҒcҒBӮ»ӮсӮИӮЙ”YӮЬӮИӮӯӮДӮаӮўӮўӮМӮжҒBӮўӮВӮЕӮаӮўӮўӮ©ӮзҺ„ӮЙ‘Ҡ’kӮөӮЙ—ҲӮИӮіӮўҒBҒ\Ғ\–і—қӮНӢЦ•ЁӮжҒv
Ғ@ӮвӮНӮиғoғҢӮДӮўӮҪӮ©ӮЖғҶғҠӮНҗOӮрҠҡӮЮҒBӮіӮ·ӮӘ•кӮҫӮИӮЖҺvӮўӮИӮӘӮзҒA
ҒuӮ ӮиӮӘӮЖӮӨӮЁ•кӮіӮсҒBӮЕӮаҒAӮЬӮҫҚlӮҰӮіӮ№ӮДҒBҺһҠФӮӘӢ–Ӯ·ҢАӮиҚlӮҰӮіӮ№ӮДҒcҒcҒv
ҒuҺ©•ӘӮЕ“ҡӮҰӮрҢ©ӮВӮҜӮИӮіӮўҒBүҪӮЕӮаҚЕҢгӮНҺ©•ӘӮЕ“ҡӮҰӮрҢ©ӮВӮҜӮИӮҜӮкӮОӮўӮҜӮИӮўӮМӮӘҗlӮҫӮ©ӮзҒBӮіӮҹҒA‘еҠwӮЙҚsӮБӮҪҚsӮБӮҪӮҹҒBӮұӮұӮЕғӮғ„ғӮғ„ӮөӮДӮйӮЖ’xҚҸӮөӮДӮөӮЬӮӨӮјҒB‘еҠwҗ¶ғbҒIҒIҒv
Ғ@ҢCӮр—ҡӮ«ҒAҢәҠЦӮрҸoӮДҚsӮБӮҪ–әӮрҢ©‘—Ӯй•кҒBӮЬӮҫҗS”zӮМӢCҺқӮҝӮНҺcӮБӮДӮўӮйӮӘҒA–әӮМ”ҪүһӮрҢ©ӮДҸӯӮөҲАҗSӮөӮҪҒB”ј”N‘OӮНҗGӮкӮйӮұӮЖӮаҸo—ҲӮИӮўҸу‘ФӮҫӮБӮҪҒBӮ ӮМҺһӮЖ”дӮЧӮДүс•ңӮНӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ ӮМҸo—ҲҺ–ӮН–әӮЙӮЖӮБӮДӮНҺSӮЯүЯӮ¬ӮҪҒBӮЬӮҫ”ЮҸ—ӮМҗSӮНҸқӮҫӮзӮҜӮЕҒA’ЙӮЭӮЕ–гӮҰӮйӮұӮЖӮаӮ ӮйҒBҠ®‘SӮЙүс•ңӮ·ӮйӮұӮЖӮН–іӮўӮЖӮөӮДӮаҒAҚДӮСҸОҠзӮрҺжӮи–ЯӮөӮД–бӮҰӮкӮО—ЗӮўӮЖ•кӮНҺvӮБӮҪҒB
(Ӯ»ӮМӮҪӮЯӮЙӮНҒAҺ„ӮҪӮҝүЖ‘°ӮӘҠж’ЈӮзӮИӮўӮЖӮЛҒcҒc)
Ғ@ғҶғҠӮМүс•ңӮрҠиӮӨ•кӮН”wҗLӮСӮрҲкүсӮөӮДҒAҗф‘у•ЁӮрҠұӮ·ӮҪӮЯӮЙҠOӮЙҸoӮҪҒBү_ӮРӮЖӮВ–іӮўҚ~җ…Ҡm—ҰӮOҒ“ӮМүхҗ°ҒBҗвҚDӮМҗф‘у“ъҳaӮЕӮ ӮйҒB
ҒuӮіӮҹӮДҒAҺ„ӮНҗф‘у•ЁӮрҠұӮөӮЬӮ·Ӯ©ҒIҒv
Ғ@•кӮНҗф‘уғJғSӮрҺиӮЙӮөӮҪҒB
ӮR
ҢЯ‘O”ӘҺһҺOҒZ•ӘҒ@–^Ӯa‘еҠwҒEҺҮ—zүФ’КӮи
Ғ@ӮўӮВӮаӮжӮиҸӯҒX’xӮЯӮЙүЖӮрҸoӮҪӮӘҒAҲкҺһҢА–ЪӮӘҺnӮЬӮйӮМӮНӢгҺһҺOҒZ•ӘӮИӮМӮЕҒAӮ ӮЬӮи–в‘иӮИӮ©ӮБӮҪҒBғҶғҠӮНйQғpғ“ӮрҷшӮҰӮИӮӘӮзҺҮ—zүФӮӘҚзӮ«ҢЦӮй—V•а“№Ӯр•аӮўӮДӮўӮйҒBҗі’јҒAӢCӮрҲшӮ©ӮИӮўӮҪӮЯӮЙғgҒ[ғXғgҲк–ҮӮЖҢҫӮБӮҪӮМӮӘӮўӮҜӮИӮ©ӮБӮҪҒB‘еҠwӮЙҢьӮ©ӮӨ“аӮЙғgҒ[ғXғgҲк–Ү•ӘӮМғGғlғӢғMҒ[ӮрҺgӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB•—ҺЧӮЕ“|ӮкӮйӮИӮзҺd•ыӮӘ–іӮўӮӘҒAӢу• ӮЕ“|ӮкӮйӮМӮН”nҺӯӮзӮөӮӯӮД—ЬӮаҸoӮИӮўҒBҺd•ыӮИӮӯ‘еҠw‘OӮМғRғ“ғrғjғGғ“ғXғXғgғAӮЕғpғ“ӮрҚw“ьӮ·ӮйӮЙҺҠӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҺцӢЖҠJҺnҲкҺһҠФ‘OӮЖӮўӮӨ—]—TӮМӮ ӮйҺһҠФӮҫӮБӮҪӮМӮӘҚKӮўӮҫӮБӮҪӮӘҒAӮұӮкӮӘҠJҺnҺOҒZ•Ә‘OӮЙӮИӮйӮЖ‘е•ПӮИӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB
Ғ@ҢіҒXҒA‘еҠw“аӮМ”„“XӮӘҠJӮӯӮМӮНҲкҒZҺһҒBҚuӢ`ӮӘҺnӮЬӮБӮДҺOҒZ•ӘҢoӮБӮДӮ©ӮзӮМҠJ“XӮҫҒBӮВӮЬӮиҒA‘еҠw“аӮЕ’©җHӮр”ғӮӨӮұӮЖӮН•sүВ”\ӮИӮМӮЕӮ ӮйҒBҺ©‘оӮЕ’©җHӮрҺжӮзӮёӮЙҒA“oҚZҒEҸoӢО“r’ҶӮМғRғ“ғrғjғGғ“ғXғXғgғA“ҷӮЕ’©җHӮр”ғӮӨӮұӮЖӮӘ•Ғ’КӮМӮұӮМҺһҗЁҒAҚXӮЙ‘еҠwӮЖӮўӮӨҸрҢҸӮӘҸdӮИӮйӮЖҺцӢЖҠJҺn’ј‘OӮМ“XӮНҚ¬ҺGӮрӢЙӮЯӮйҒBҲкӮВӮМғҢғWӮЙҢЬҒCҳZҗlӮМ—сӮӘ•WҸҖӮЕҒAҲкүс—сӮӘҠ®җ¬ӮөӮҪӮзҒAҚuӢ`ӮӘҠJҺnӮ·ӮйғMғҠғMғҠӮЬӮЕӢуӮӯӮұӮЖӮН–іӮўҒB—сӮЙӣЖӮБӮҪӮұӮЖӮЕҚuӢ`ӮЙ’xҚҸӮөӮҪҗlӮаҸӯӮИӮӯӮИӮўҒBғҶғҠӮМ—FҗlӮаӮұӮМ’©җHҚw“ьғүғbғVғ…ӮЙҠӘӮ«ҚһӮЬӮкӮД—ЬӮрҲщӮсӮҫӮзӮөӮўҒBғҶғҠӮНӮ»ӮсӮИӮаӮМӮЖӮНүҸӮӘ–іӮӯҺ©‘оӮЕ’©җHӮрҗHӮЧҒA—]—TӮрҺқӮБӮД“oҚZӮ·ӮйҒBҚЎүсӮН—бҠOӮҫӮБӮҪӮМӮҫҒB’©җHҚw“ьғүғbғVғ…ӮЦӮМӢ»–ЎӮНӮ ӮБӮҪӮӘҒA—FҗlӮМӢ°•|ӮЙ–һӮҝӮҪ‘МҢұ’kӮр•·ӮӯӮЖӮ»ӮМҚlӮҰӮНҸБӮҰӢҺӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB“O–й–ҫӮҜӮЕ–ЪӮӘҢҢ‘–ӮБӮДӮўӮй’jҠwҗ¶ҒAҗQ–VӮөӮДғpғWғғғ}ӮМӮжӮӨӮИҠiҚDӮМҸ—Ҡwҗ¶ӮвӮзғүғbғVғ…ӮЙ“Л“ьӮөӮҪ“XӮМ’ҶӮНӢ¶ӢCӮЙ–һӮҝӮҪӢуҠФӮЕӮ ӮБӮҪӮзӮөӮўҒB
ҒuӮіӮДҒAҚЎ“ъӮН–Ш—j“ъӮҫӮ©ӮзҒcҒcҺOҠKӮМҺOҒZҢЬҚҶҺәӮҫӮБӮҪӮҜӮИҒv
Ғ@ғҶғҠӮНҚuӢ`ҠJҺn–сҺlҢЬ•Ә‘OӮЙҚuӢ`ӮӘҚsӮнӮкӮйӢіҺәӮЙ’…ӮўӮДӮўӮҪҒB•Ғ’iӮИӮзғҶғҠӮӘҲк”ФҸжӮиӮЕ’…ӮӯӮМӮҫӮӘҒAҚЎ“ъӮНҲбӮБӮҪҒBӢіҺәӮМ‘Ӣ‘ӨӮМҢгӮлӮЙҲкҗlҚАӮБӮД–{Ӯр“ЗӮсӮЕӮўӮйҸ—җ«ҒB
(Ғ\Ғ\җXҗ—Һq(ӮРӮИӮұ)ҒIҒIҒ@ӮВӮўӮЙ”ЮҸ—ӮЙ•үӮҜӮҝӮбӮБӮҪӮ©ҒcҒc)
ғҶғҠӮНҲкҺһҢА–ЪӮ©ӮзҺnӮЬӮйҚuӢ`ӮӘӮ Ӯй“ъӮНҲк”ФӮЙӢіҺәӮЙ“ьӮйӮЖӮўӮӨ“дӮМғvғүғCғhӮрҺқӮБӮДӮўӮҪҒBҗ¶ӮЬӮкӮДӮұӮМ•ы“сҒZ”NҒB—c’tүҖҒAҸ¬ҠwҚZҒA’ҶҠwҚZҒAҚӮ“ҷҠwҚZӮЖ‘SӮДӮМ“ъӮЙӢіҺәҲк”ФҸжӮиӮрӮөӮДӮ«ӮҪғҶғҠӮЙӮЖӮБӮДӮНӮұӮМ”s–kӮНӢ–ӮіӮкӮҙӮйӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB
(ӮЕӮаҒcҒcҺ„ӮМҒcҒcҚЎӮЬӮЕӮМҲк”ФҸжӮиҒcҒcҺ„ӮМҚЎӮЬӮЕӮМғHғHғHғHҒcҒc)
Ғ@ғOғcғOғcҺПӮҰӮҪӮ¬ӮйӢCҺқӮҝӮр—}ӮҰӮВӮВҒAғҶғҠӮНҗИӮЦҢьӮ©ӮБӮҪҒBҗ—ҺqӮМ•ыӮЙҺӢҗьӮрҢьӮҜӮйӮЖҒA’ҡ“x–ЪӮӘҚҮӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB
(ӮөӮ©ӮөӮўӮВҢ©ӮДӮагY—нӮҫӮИӮҹ”ЮҸ—ҒcҒc)
–nӮр—¬ӮөӮҪӮжӮӨӮИҚ•Ӯў”ҜӮМ–СӮН”цҚңӮЬӮЕҗLӮСӮДӮЁӮиҒA’ғҗFӮўүҸӮМҠбӢҫӮЙҗцӮЮҠзӮНӮЗӮсӮИгY—нӮИүФӮЕӮаҺ©•ӘӮМҺpӮЙ’pӮ¶ӮйӮӯӮзӮўҗ®ӮБӮДӮўӮйҒBҗ«ҠiӮаҗГӮ©ӮЕӮЁҸiӮвӮ©ҒAҺһҒXҢ©Ӯ№ӮйҸОҠзӮНҢ©ӮйӮаӮМӮрҚң”ІӮ«ӮЙӮөӮДӮөӮЬӮӨҒB•ЧӢӯӮаҠw•”ғgғbғvғNғүғXҒA—ҝ—қӮаҸo—ҲӮД’ғ“№ӮаҡnӮсӮЕӮўӮйӮЖӮўӮӨү\ӮҫҒBӮұӮсӮИ‘fҗ°ӮзӮөӮў—eҺpӮМҺқӮҝҺеӮЕӮ ӮйҗXҗ—ҺqӮНҠw•”ҒAӮўӮв‘еҠw“аӮМғAғCғhғӢӮЕӮ Ӯи‘O”NӮМӮa‘еҠwҠwүҖҚХӮМғ~ғXӮa‘еӮЙ‘IӮОӮкӮҪӮЩӮЗӮЕӮ ӮйҒBӢБӮӯӮЧӮ«“_ӮНҒA”ЮҸ—ӮӘҚЎӮЬӮЕ’jӮЖӮўӮӨ‘¶ҚЭӮЖҢрҚЫӮөӮҪӮұӮЖӮӘ–іӮўӮЖӮўӮӨ“_ӮҫҒBүҳӮкӮа’mӮзӮКүіҸ—ӮЖӮўӮӨҺ–ҺАӮНҸ—җ«Ҹо•с–Ф“аӮЕӮМ”й–§Һ–ҚҖӮЕӮ ӮиҒAҢҲӮөӮДҳTӢӨӮЙ’mӮзӮкӮДӮНӮўӮҜӮИӮўҒB‘еҠw“ағiғ“ғoҒ[ӮPӮМ”ьӮөӮіӮрҺқӮВ”ЮҸ—ӮӘ–ўӮҫӮЙ’jӮЖ•tӮ«ҚҮӮБӮҪӮұӮЖӮӘ–іӮўӮЖӮўӮӨӮМӮҫӮ©ӮзҒAӮҪӮҫӮЕӮіӮҰүЯ”MӮөӮДӮўӮйү№ҺqӢҹӮМ‘ҲӮўӮЙ–ыӮр’ҚӮ®ӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨҒBҢМӮЙҺзӮзӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮЖӮўӮӨҸ—ӮҪӮҝӮМҲГ–ЩӮМ—№үрҒ\Ғ\ӮзӮөӮўҒB
(Ӯ»ӮұӮЬӮЕҺзӮзӮкӮ鑶ҚЭӮИӮМӮ©ӮИҒBҗ—ҺqӮіӮсҺ©‘МӮНӮЗӮӨҺvӮБӮДӮўӮйӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўӮҜӮЗҒBӮЕӮаҚЎӮМҺ„ӮЙӮНӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮНҚlӮҰӮзӮкӮИӮўӮөӮЛҒcҒc)
Ғ@ҢрҚЫӮЖӮўӮӨ’PҢкӮЙғҶғҠӮН–ЪӮр•ҡӮ№ӮҪҒB
(ӮвӮБӮПӮи”ј”N—§ӮБӮДӮаҲшӮ«ӮёӮйӮаӮМӮЛҒBӮЬӮҫҗhӮўӮжҒcҒcҺ„)
ҒuӮ ҒAӮ ӮМ‘еҸд•vӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒ@ҠзҗFӮӘ—DӮкӮИӮўӮЕӮ·ӮжҒv
Ғ@ғҶғҠӮӘӢC•tӮҜӮОҗXҗ—ҺqӮНғҶғҠӮМ–ЪӮМ‘OӮЙӮўӮҪҒBҠбӢҫӮрҠOӮөҒAғҶғҠӮМҠзӮрҗгӮ©Ӯз”`ӮӯҢ`ӮЕҢ©ӮДӮўӮйҒBӮўӮВӮМҠФӮЙғҶғҠӮМ‘OӮЙүсӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBғҶғҠӮН•ЁҺvӮўӮЙ’^ӮБӮДӮўӮйӮМӮаӮ ӮйӮӘҒAҗ—ҺqӮМӢC”zӮрҠҙӮ¶ҺжӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB
ҒuӮҫӮҫӮҫӮҫ‘еҸд•vҒIҒIҒ@’©ӮІӮНӮс”ІӮўӮДӮ«ӮҝӮбӮБӮҪӮ©ӮзҸӯӮөӮЯӮЬӮўӮӘӮөӮҪӮМӮжҒBӮҫӮ©ӮзӮ»ӮсӮИӮЙҗS”zӮөӮИӮўӮЕҒv
Ғ@ғҶғҠӮМ”ӯҢҫӮЙҸӯӮөҺc”OӮ»ӮӨӮИ•\ҸоӮрӮ·Ӯйҗ—ҺqҒBӮ»ӮМ‘МӮНҸӯӮөҗkӮҰӮДӮўӮйҒB
(ӮӨҒBӮўӮ«ӮИӮи“ЛӮБӮПӮЛӮҪҠҙӮ¶ӮЕ•ФӮөӮҝӮбӮБӮҪӮ©ӮзӮ©ӮИҒBӮіӮ·ӮӘӮЙӢғӮӯӮұӮЖӮН–іӮўӮЖҺvӮӨӮҜӮЗҒAҢҷӮИӢCҺқӮҝӮЙӮіӮ№ӮҝӮбӮБӮҪӮ©ӮИҒcҒcҒH)
Ғuҗ—ҺqӮіҒ[ӮсҒHҒv
Ғu–ј‘OӮрӢіӮҰӮДӮӯӮҫӮіӮўҒv
Ғ@ӮўӮ«ӮИӮиӮМҗ—ҺqӮМ–вӮўӮЙ–КҗHӮзӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪғҶғҠӮНҒuӮНӮўғbҒIҒvӮЖ— •ФӮБӮҪҗәӮЕ“ҡӮҰӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҗФӮӯӮИӮБӮҪҠзӮрүBӮөӮИӮӘӮзҒA
ҒuҒ\Ғ\ӮўӮ«ӮИӮи–ј‘OӮрҢДӮсӮЕӮІӮЯӮсӮЛҒBғҶғҠҒBҢ “ЎғҶғҠӮжҒBӢCӮЙӮ№ӮёүәӮМ–ј‘OӮЕҢДӮсӮЕӮўӮўӮ©ӮзҒv
Ғu•ӘӮ©ӮиӮЬӮөӮҪғҶғҠӮіӮсҒBӮ ӮИӮҪ’©ӮІӮНӮсӮрҗHӮЧӮДӮўӮИӮўӮБӮДҢҫӮўӮЬӮөӮҪӮжӮЛҒHҒv
ҒuӮНӮҹҒcҒcҒBӮЬӮҹҒAҚЎ’©ӮНӮ ӮсӮЬӮиҗHӮЧӮДӮұӮИӮ©ӮБӮҪӮҜӮЗҒBӮ»ӮкӮӘүҪӮМ–в‘иӮЕҒ\Ғ\Ғv
Ғu–в‘иӮЕӮ·ғbҒIҒ@‘е–в‘иӮЕӮ·ғbғbҒIҒIҒ@җlҠФӮӘҢЯ‘O’ҶӮЙҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮӯ”M—КӮр•вӮӨӮМӮӘ’©җHӮЕӮ·ҒBӮ»ӮкӮр”ІӮўӮДӮөӮЬӮӨӮИӮсӮДҒcҒcӮ ӮИӮҪӮНүҪӮДӮұӮЖӮрӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·Ӯ©ғbҒIҒIҒv
Ғ@җ—ҺqӮМҗҰӮў–Т(ӮаӮӨ)Ңы(ӮұӮӨ)ӮЙғҶғҠӮНҢҫ—tӮӘҸoӮИӮўҒBӮ ӮМ‘еҠwӮМғAғCғhғӢҗXҗ—ҺqӮӘҒAӮҪӮ©ӮӘ’©җH”ІӮ«ӮЕ—қҗ«Ӯр—җӮ·ӮЖӮНҒBҚЎӮЬӮЕғҶғҠӮӘ•шӮўӮДӮўӮҪҗ—ҺqӮМғCғҒҒ[ғWӮНҲкҸuӮМӮӨӮҝӮЙ•цӮкӢҺӮБӮҪҒB
ҒuғҶғҠӮіӮсҒA’©җHӮр”ІӮҜӮОҒA”M—КӮӘ–іӮўҒBҚЎӮМӮ ӮИӮҪҸу‘ФӮНғKғ\ғҠғ“ӮМ–іӮўҺФӮИӮМӮЕӮ·ӮжҒBҺФӮНғKғ\ғҠғ“ӮӘ–іӮҜӮкӮО“®Ӯ©ӮИӮўҒBӮВӮЬӮиҒAӮ ӮИӮҪӮН’ӢҗHӮЬӮЕ“®ӮҜӮИӮў‘МӮЕӮ·ҒBӮЛҒIҒ@ғҶғҠӮіӮсҒAҚЎӮЕӮаӮўӮўӮ©Ӯз’©җHӮНҗHӮЧӮЬӮөӮеӮӨҒI‘ҒӮӯӮөӮИӮўӮЖҚuӢ`ӮӘҺnӮЬӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒBӮ·Ӯ®ӮЙӢЯӮӯӮМғRғ“ғrғjӮЕ’©ӮІӮНӮсӮрӮіӮҹ‘ҒӮӯҒIҒIҒv
ҒuӮ ӮМҒcҒcҗ—ҺqӮҝӮбӮсҒHҒv
ҒuүҪӮ©ҢҫӮӨӮұӮЖӮӘӮ ӮиӮЬӮ·Ӯ©ҒHҒ@ӮЬӮҫҺһҠФӮНӮ ӮиӮЬӮ·ӮжҒIҒv
ҒuҒ\Ғ\Һ„ҒAҒwҚЎ’©ҒA’©җH”ІӮўӮҪҒxӮЬӮЕӮНҢҫӮБӮҪӮҜӮЗҒA‘еҠwӮЙҚsӮӯҚЫӮЙғRғ“ғrғjӮЙҠсӮБӮДғpғ“Ӯр”ғӮБӮҪӮсӮҫҒBӮЕҒAӮұӮұӮЬӮЕҚsӮӯҠФӮЙҗHӮЧӮҝӮбӮБӮҪҒcҒcҒv
Ғ@ғҶғҠӮМҺ©”’ҒBҗ—ҺqӮНӮЬӮйӮЕ‘МӮЙ“d—¬ӮӘ‘–ӮБӮҪӮжӮӨӮИ’ІҺqӮЕӢБңұӮөҒAӮ»ӮМҸкӮЙӮЦӮҪӮиҚһӮсӮҫҒB
ҒuӮ·ӮўӮЬӮ№ӮсҒcҒcҒB’©җH”ІӮ«ӮҫӮҜӮНӢ–Ӯ№ӮИӮӯӮДҒAӮВӮўҗЁӮўӮЙ”CӮ№ӮД’қӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМҢлүрӮМӮЁҳlӮСӮНүҪӮЖӮөӮҪӮз—ЗӮўӮМӮ©ҒcҒcҒv
Ғ@”eӢCӮӘ–іӮўҗәӮЕҗ—ҺqӮНғyғRғyғRӮЖ“ӘӮрүәӮ°ӮИӮӘӮзғҶғҠӮЙҺУҚЯӮрӮөӮДӮўӮйҒBҺУӮйҺpӮаүВҲӨӮзӮөӮӯҒAғҶғҠӮНҚЎӮЙӮаҗ—ҺqӮр•шӮ«ӮөӮЯӮДӮөӮЬӮўӮ»ӮӨӮИ’цҒAӢCҺқӮҝӮӘҚӮӮФӮБӮҪҒB“Ҝҗ«ҲӨ“IӮИҠҙҸоӮНҺқӮБӮДӮўӮИӮўӮӘҒAӮұӮсӮИҺpӮрҢ©Ӯ№ӮзӮкӮДҒA•ҪҗГӮЕӮўӮй•ыӮӘҲЩҸнӮҫӮлӮӨҒB
(Ӯ ӮМҗXҗ—ҺqӮӘ’©җH”@Ӯ«ӮЕ–\‘–Ӯ·ӮйӮИӮсӮДҒAҸнҗlӮЖӮНҸӯӮөғYғҢӮДӮўӮйӮИӮҹҒBӮұӮӨӮўӮӨ–КӮӘӮ ӮйҳbӮН•·ӮўӮҪӮұӮЖ–іӮўӮ©ӮзҒA“ҫӮрӮөӮҪӮЖӮўӮҰӮОҒA“ҫӮЛ)
Ғ@ғҶғҠӮӘҚЎӮЬӮЕҺқӮБӮДӮўӮҪҗ—ҺqӮМғCғҒҒ[ғWӮН“D’ҶӮМҳ@ҒA‘Ч‘RҺ©ҺбӮЖӮўӮӨҗўӮМҗlҠФӮӘ‘AӮЮ—v‘fӮрҺқӮБӮДӮўӮйҠҙӮ¶ӮҫӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮұӮМ’©җH”ІӮ«ӮЙӮжӮйғҶғҠӮЦӮМ’eҠNӮМӢӯ—уӮіҒAӮ»ӮкӮӘҗ—ҺqӮМҺvӮўҲбӮўӮҫӮЖӢC•tӮўӮҪ“r’[ӮЙҺУӮйҺpӮМӮөӮЁӮзӮөӮіҒA“БӮЙ‘OҺТӮНҚЎӮЬӮЕҢ©ӮҪӮұӮЖӮМ–іӮўҺА‘ҠӮЙғҶғҠӮНҗ—ҺqӮЙ‘ОӮөҚDӮўҠҙҗGӮрҺқӮБӮҪҒB
Ғu’©җHӮрҗHӮЧӮДӮўӮИӮўӮЖӮўӮӨҢлүрӮрҸөӮўӮҪӮМӮНҺУӮйӮжҒBӮҝӮбӮсӮЖ•ЁҺ–ӮрҢҫӮнӮИӮ©ӮБӮҪҺ„ӮӘҲ«ӮўӮсӮҫӮөҒB•КӮЙӢCӮЙӮ·Ӯй•K—vӮИӮўӮжҒB’©җH”ІӮ«ӮӘӮўӮҜӮИӮўӮМӮН“ҜҲУӮ·ӮйӮҜӮЗҒv
ҒuӮ»ӮӨӮЕӮ·ӮжӮЛҒIҒIҒv
Ғ@ғҶғҠӮМ“ҜҲУӮЙҗ—ҺqӮНихӮ«ҒAғҶғҠӮрҢ©ӮВӮЯӮйҒBӮ»ӮМ–ЪӮНӢPӮўӮДӮўӮДҒAҠзӮр”wӮҜӮҪӮӯӮИӮй’ц“§Ӯ«’КӮБӮДӮўӮйҒBғҶғҠӮНҺvӮнӮёҺ©•ӘӮМҠзӮӘ”MӮӯӮИӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮЙӢC•tӮўӮҪҒBӢ°ӮзӮӯҠзӮаҗФӮӯӮИӮБӮДӮўӮйӮҫӮлӮӨҒBӮҫӮӘҒAӮұӮсӮИӮұӮЖӮрӮөӮДӮўӮйҸкҚҮӮЕӮНӮИӮўҒB
ҒuӮаӮӨӮұӮсӮИҺһҠФӮҫӮҜӮЗҒAҗl—ҲӮИӮўӮИӮҹҒv
Ғ@ғҶғҠӮӘҢ©ӮҪҺһҢvӮНӢгҺһ“сҒZ•ӘӮрҺwӮөӮДӮўӮҪҒBҠJҺnҸ\•Ә‘OӮЙӮН‘е‘МҒAҗlӮӘҸWӮЬӮБӮДӮӯӮйӮМӮЙҒAӮұӮкӮНӮЁӮ©ӮөӮўҒBғҶғҠӮНҺOҒZҢЬҚҶҺәӮЙҚsӮӯ‘OӮЙӢxҚuҢfҺҰ”ВӮрҢ©ӮДҒAӮұӮМҚuӢ`ӮӘӢxҚuӮЕӮИӮўӮұӮЖӮрҠm”FӮөӮҪҒB
ҒuҒ\Ғ\ӮЬӮіӮ©Ғv
Ғ@ҢҷӮИ—\ҠҙӮӘӮөӮҪғҶғҠӮНӢ}ӮўӮЕҢg‘С“dҳbӮЙ“а‘ ӮіӮкӮДӮўӮйғҒғӮ’ ӮрҠJӮўӮҪҒBғҶғҠӮНҲк“ъӮМҚuӢ`ӮӘҚsӮнӮкӮйӢіҺәӮрҸ‘Ӯ«ҚһӮсӮЕӮ ӮБӮҪҒBғҒғӮ’ ӮЙӮНҒw–Ш—jҲкҢАҒEғAғCғfғ“ғeғBғeғBӮЖӢӨ‘¶ҒE“сҒZҢЬҚҶҺәҒxӮЖҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮ ӮБӮҪҒB
ҒuӮНӮНҒcҒcғrғ“ғSӮЛҒcҒcҒv
Ғuғrғ“ғSӮБӮДүҪӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
Ғ@җВӮҙӮЯӮйғҶғҠӮЙҗ—ҺqӮӘ–вӮўҠ|ӮҜӮйҒBҺ©ҡ}ӮЯӮўӮҪҢы’ІӮЕғҶғҠӮӘ•ФӮ·ҒB
ҒuҺ„ӮҪӮҝҒAӢіҺәҠФҲбӮҰӮҪӮжҒv
Ғ@Ң»ҚЭғҶғҠӮЖҗ—ҺqӮӘӮўӮйӢіҺәӮНҺOҠKӮМҺOҒZҢЬҚҶҺәҒAҺАҚЫҚuӢ`ӮНӮ»ӮМҗ^үәӮМ“сҠKҒE“сҒZҢЬҚҶҺәӮЕӮвӮйӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒAҺOҒZҢЬҚҶҺәӮӘҲкҢАӮМӮЖӮ«ӮЙӮНҚuӢ`ӮӘ–іӮўӮМӮЕҒAҠwҗ¶ӮӘӮұӮМӢіҺәӮЙ“ьӮБӮДӮӯӮйүВ”\җ«ӮНӮOҒ“ӮЕӮ ӮйҒB
ҒuӢ}ӮӘӮИӮўӮЖ’xҚҸӮЙӮіӮкӮҝӮбӮӨҒBҸҖ”хӮөӮДҒv
Ғ@ғҶғҠӮНҗ—ҺqӮЙ•РӮГӮҜӮр‘ЈӮөӮҪҢгҒAҺиӮрҗLӮОӮ·ҒB
ҒuӮҰҒcҒcӮЗӮұӮЙҚsӮӯӮМҒHҒv
ҒuҺOҒZҢЬҚҶҺәӮжҒIҒ@‘ҒӮӯӮөӮИӮіӮўҒIҒIҒ@Ӯ ӮМӢіҺtӮМҚuӢ`ҒA’xҚҸғCғRҒ[ғӢҢҮҗИӮЙӮИӮйӮМӮжҒBҺ„ӮНҢҮҗИӮрӢCӮЙӮ·ӮйҸ—ӮИӮМҒBӮіӮҹҚsӮӯӮжҒIҒv
Ғ@ҺиӮрҗLӮОӮ·ғҶғҠӮрҢ©ӮҪҗ—ҺqӮНүң’кӮ©ӮзҚһӮЭҸгӮ°ӮйӮаӮМӮрҠҙӮ¶ӮйҒBҸЕӮ°ӮйӮжӮӨӮЙ”MӮўғҶғҠӮМҢҫ—tӮрҗSӮЙ‘ЕӮҝӮВӮҜӮзӮкҒAҠҙӮЙҠ¬ӮҰӮИӮўӢCҺқӮҝӮЙӮИӮБӮҪҒB
ҒuҒ\Ғ\ӮНӮўҒAӮўӮ«ӮЬӮ·Ғv
Ғ@Қ·ӮөҗLӮОӮіӮкӮҪҺиӮрӮдӮБӮӯӮиҺуӮҜҺжӮБӮҪҗ—ҺqӮНғҶғҠӮЙҲшӮБ’ЈӮзӮкӮИӮӘӮзҒA“сҒZҢЬҚҶҺәӮЙҳAӮкӮДӮўӮ©ӮкӮҪҒBӮұӮМӮЖӮ«ҒAҗ—ҺqӮН•sҺvӢcӮИҠҙҠoӮрҠoӮҰӮДӮўӮҪҒB
ӮS
Ғ@ғҶғҠӮӘ‘o•ыӮМӢіҺәӮМҠФҲбӮҰӮЙӢCӮГӮўӮҪӮЁӮ©Ӯ°ӮЕ’xҚҸӮрӮ№ӮёӮЙҚПӮсӮҫҒBӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮз’xҚҸҗЎ‘OӮЕӢіҺәӮЙ“ьӮБӮҪӮұӮЖӮЕӮ·ӮЕӮЙҠwҗ¶ӮЕӮўӮБӮПӮўӮМӢіҺәӮНҠҪҗәӮЕ–„ӮЯҗsӮӯӮіӮкӮҪҒBӮ»ӮМ’ҶӮЙӮН”Я–ВӮЙҺ—ӮҪӢ©ӮСӮаҚ¬Ӯ¶ӮБӮДӮўӮҪҒBҢҙҲцӮНғҶғҠӮЖҗ—ҺqӮӘ“ьӮБӮДӮ«ӮҪҺpӮЙӮ ӮйҒBҺиӮрҢqӮўӮЕ“ьӮБӮДӮ«ӮҪ“сҗlӮМҺpӮӘҲк•”ӮМҺТӮҪӮҝӮЙӮНҒA—FҗlӮр’ҙӮҰӮҪҠЦҢWӮЙҢ©ӮҰӮҪӮжӮӨӮҫҒBҚЭӮйҺТӮНғnғ“ғJғ`Ғ[ғtӮрҠҡӮЭӮИӮӘӮз’n–КӮрҢқӮЕ’@ӮўӮДӮўӮйҒBҚЭӮйҺТӮНҢҢ—ЬӮр—¬ӮөҒAӢк–гӮМ•\ҸоӮр•ӮӮ©ӮЧҒA“ӘӮр•шӮҰӮИӮӘӮзӢкӮөӮсӮЕӮўӮйҒBҚ“ӮўҺТӮНӮ»ӮМҸкӮЕ‘ӢӮ©ӮзҠOӮЦ”тӮсӮЕӮөӮЬӮБӮҪӮӘҒAҚKӮўғxғүғ“ғ_ӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕүәӮЙ—ҺӮҝӮёӮЙҚПӮсӮҫҒBғҶғҠӮЖҗ—ҺqӮМҺиӮрҢqӮ®ҺpӮрҢ©ӮДҒAҠпүцӮИҚs“®ӮЙ’BӮөӮҪҺТӮЙӢӨ’КӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮўӮёӮкӮаҗ—Һqғtғ@ғ“ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮҫҒBҸӯҗ”ғҶғҠғtғ@ғ“ӮаӮўӮҪӮзӮөӮўӮӘҒA‘S‘МӮМӮTҒ“’ц“xӮЕӮ ӮБӮҪҒBғҶғҠӮЖҗ—ҺqӮӘҗИӮЙ’…ӮўӮҪҢгӮЕӮаҒAӮ»ӮМӢ©ӮСӮН‘ұӮӯҒB
ҒuүдҒXӮНҗ—ҺqҸмӮМ’үҺАӮИӮөӮаӮЧӮЕӮ ӮиҒA’үҺАӮИӮйҢўӮЕӮ ӮйғbҒIҒIүдҒXӮНҗ—ҺqҸмӮМҚKӮ№ӮрҺзӮйӮаӮМӮЕӮ ӮиҒA’үҺАӮИӮйӢRҺmӮЕӮ ӮйғbҒIҒIӮұӮМҚKӮ№ӮрүдҒXӮНҸlҒXӮЖҠҪҢ}Ӯ·ӮйӮаӮМӮЕӮ ӮиҒAҺзӮзӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўғbҒIҒIҒv
ҒuғMғғғ@Ғ[ҒIӮ ӮМҗ—ҺqӮҝӮбӮсӮӘҒIҗ—ҺqӮҝӮбӮсӮӘҺиӮрҢqӮўӮЕӮйғbҒIҺиӮрҢqӮўӮЕӮйғbҒIҺиӮрҺиӮрҺиӮрҺиӮрҺиӮрҺиғFғFғFғFғbғbҒIҒIҒIҒv
ҒuӮ Ӯ ҒcҒcӮіӮжӮӨӮИӮз–lӮМҗВҸtҒcҒcӮіӮжӮӨӮИӮз–lӮМҗlҗ¶ҒcҒcҒBҚЎ“ъӮЕҸIӮнӮиӮЕӮ·ҒBӮЁ•кӮіӮсҒAӮЁ•ғӮіӮсҒAүФҺqҒAғ|ғ`ҒAҚЎӮЬӮЕӮ ӮиӮӘӮЖӮИҒcҒcҒv
ҒuӮұӮзӮұӮзҒcҒcҠFӮіӮсҒAҗГӮ©ӮЙӮөӮИӮіӮўҒBҺцӢЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ№ӮсӮжҒv
Ғ@ҳVҚuҺt•iҗмӮӘӮ»ӮМҸкӮМҚ¬—җӮр’ҫӮЯӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӮӘҒAҳVҺtӮМҺгӮБӮҪҗәӮЕӮНӮұӮМҸу‘ФӮрҺЎӮЯӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҒBӮ»ӮМҺһҒAҺӢ“_ӮӘӮНӮБӮ«ӮиӮөӮДӮўӮИӮў‘үӮ№Ң^ӮМ’jӮӘ—§ӮҝҸгӮӘӮБӮҪҒBҗkӮҰӮй‘МӮ©ӮзҳRӮкӮйӮаӮМӮН–ҫӮзӮ©ӮЙ“{ӮиӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮИӮИӮИӮИүҪӮЕҒcҒcӮЪӮЪӮЪӮЪӮЪ–lӮМҗ—ӮҝӮбӮсӮӘӮ Ӯ Ӯ ӮсӮИҸ—ӮЙҒcҒcҒBӮдӮдӮдӮдӮдӢ–Ӯ№ӮсҒBӢ–Ӯ№ӮсӮјғHҒv
ҒuҒIҒHҒ@Ӯ Ӯ»ӮұӮЙӮўӮй’jӮр•ЯӮзӮҰӮлғbҒIҒIҒ@“zӮНҗ—ҺqҸмӮЖғҶғҠҺҒӮМ’ҮӮрҲшӮ«—фӮ©ӮсӮЖӮ·Ӯйүә‘GӮИ”yҒB“zӮр•ЯӮзӮҰҒA“сҚҶҠЩ’nүәӮЙ•ъӮиҚһӮЯғFғbҒIҒIҒ@үдҒXӮНӮa‘еҠw”сҢц”FҗXҗ—ҺqҸм–hүq‘аӮЕӮ ӮйҒIҒv
ҒuғTҒ[ҒAғCғGғbғTҒ[ҒIҒv
ҒuүҪӮҫҢNӮҪӮҝӮНҒAӮвҒAҺ~ӮЯӮйӮсӮҫӮҹҒcҒcӮ Ӯ ҒAӮ Ӯ Ӯ Ӯ Ғ[Ғ[Ғ[ғbҒIҒIҒv
Ғ@‘үӮ№Ң^ӮМ’jӮӘ–hүq‘аӮҪӮҝӮЙҳAӮкӮДӮўӮ©ӮкӮйҒBӮ ӮМ’jӮН“сҚҶҠЩ’nүәӮЕүҪӮрӮіӮкӮйӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBғҶғҠӮӘү\ӮЙ•·ӮўӮҪҸо•сӮҫӮЖҒA“сҚҶҠЩ’nүәӮЙӮН–hүq‘а–{•”ӮӘҗЭ’uӮіӮкӮДӮЁӮиҒAҗXҗ—ҺqӮМ‘еҠwҗ¶ҠҲӮрҺзӮйӮҪӮЯӮЙҗШбц‘ф–ҒӮөӮДӮўӮйӮзӮөӮўҒBҗXҗ—ҺqӮЙҠлҠQӮрүБӮҰӮйҺТӮН—eҺНӮөӮИӮўҒBӮ»ӮкӮНҗжӮЩӮЗҒAӢҘҗnӮрүБӮҰӮжӮӨӮЖӮөӮҪ‘үӮ№Ң^ӮМ’jӮрҠm•ЫӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҸШ–ҫӮіӮкӮҪҒB
ӮөӮ©ӮөҒAӮ ӮМ–hүq‘аӮҪӮҝӮӘӢф‘RӮҫӮЖӮНӮўӮўҒAғҶғҠӮЖҗ—ҺqӮӘҺиӮрҢqӮўӮЕӢіҺәӮЙ“ьӮБӮДӮ«ӮҪӮұӮЖӮрҺ^”ьӮөӮҪӮМӮНҚKү^ӮЖӮөӮ©ӮўӮҰӮИӮўҒBғҶғҠӮНӢіҺәӮЙ“ьӮйӮЬӮЕ–hүq‘аӮМ‘¶ҚЭӮр–YӮкӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAӢіҺәӮЙ“ьӮБӮДӢNӮұӮБӮҪ‘еҚ¬—җӮЕҺvӮўҸoӮөҒAҺ©•ӘӮМҲА”ЫӮрҗS”zӮөӮДӮўӮҪҒBӢ°ӮзӮӯ–hүq‘аӮМҺеӢ`ӮНҒuҗXҗ—ҺqӮМҚKӮ№ӮНүдӮзӮМҚKӮ№ҒvӮЕӮ ӮиҒAҗXҗ—ҺqӮӘҚKӮ№ӮИӮзӮО–hүq‘аӮНүҪӮЕӮа—ЗӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮрғҶғҠӮНҠmҗMӮөӮҪҒBӢҺ”NӮМ•¶ү»ҚХӮЕӮаҸo“XӮИӮЗӮрүсӮйҗ—ҺqӮрүeӮИӮӘӮзҺзӮБӮДӮўӮҪӮзӮөӮўҒBӮ»ӮМҢӢүКҒA•¶ү»ҚХ“ъ’ц“аӮЙӮНҗ—ҺqӮЙҠЦӮ·ӮйҚ¬—җӮНҲкҢҸӮаӢNӮұӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB‘S–hүq‘аҲхҗ”ҒA’jҸ—ҠЬӮЯ–сҢЬҒZҒZҗlҒAӮұӮкӮҫӮҜӮўӮкӮОҗ—ҺqӮМ‘еҠwҗ¶ҠҲӮӘҲА‘SӮИӮМӮаихӮҜӮйҒBӮұӮкӮҫӮҜӮМ’ҒҸҳӮр•ЫӮДӮйӮМӮНҲк•”ӢіҺцӮ©ӮзӮМҺxүҮӮӘӮ ӮйӮ©ӮзӮЖӮМү\ӮаӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮҫӮҜҗXҗ—ҺqӮЙҲшӮ©ӮкӮйҗlӮН‘ҪӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮҫҒB
‘үӮ№’jӮМ—җҗSӮМҢгҒA–hүq‘аӮЙӮжӮБӮДҚ¬—җӮНүрҸБӮіӮкӮҪҒBӮвӮБӮЖ—ҺӮҝ’…ӮўӮДҚuӢ`ӮрҺуӮҜӮзӮкӮйӮЖҺvӮўҒAғҶғҠӮН‘§ӮрӮВӮўӮҪҒBӮ»ӮМӮЖӮ«ҒAғҶғҠӮМҢg‘С“dҳbӮӘ“dҺqғҒҒ[ғӢӮрҺуҗMӮөӮҪҒB‘ҠҺиӮН—FҗlӮМҗмҚиӢMҺuӮ©ӮзӮЕӮ ӮБӮҪҒBӢMҺuӮНғҶғҠӮЖҗ—ҺqӮжӮиҢгӮлӮМҗИӮЙҚАӮБӮДӮўӮйҒBғҶғҠӮН’j—F’BӮЖҲкҸҸӮЕҸ¬җәӮЕҳbӮөӮДӮўӮйӮМӮӘҢ©ӮҰӮҪҒB
[ӮЁ‘OҒAҗXӮіӮсӮЖӮЗӮсӮИҠЦҢWӮҫҒIҒH]
Ғ@—\‘zӮЕӮ«ӮҪ“а—eӮЙҒAғҶғҠӮН“БӢZӮМғLҒ[‘Ғ‘ЕӮҝ(Ҳк•bҠФӮЙҢЬ•¶ҺҡӢL“ьүВ”\)ӮЕӮ·Ӯ®ӮіӮЬ•ФҗMӮ·ӮйҒB
[Ӯ ӮкӮНғnғvғjғ“ғOӮИӮМҒIҒ@ӢCӮЙӮөӮИӮўӮЕҒIҒ@Ӯ»ӮсӮИӮұӮЖӮжӮиҒAүҪӮЕҺ„ӮӘ–hүq‘аӮЙ•ЯӮЬӮзӮИӮў–уҒHҒ@Ӯ ӮМҺpӮН”ЮӮзӮЙӮЖӮБӮД‘Ҡ“–ғVғҮғbғNӮМӮНӮёӮжҒI]
Ғ@ғҶғҠӮӘҚЎҲк”Ф’mӮиӮҪӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮНҒAҒuүҪҢМҺ©•ӘӮӘ–hүq‘аӮЙ•ЯҠlӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮ©ҒvӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮӘӮНӮБӮ«ӮиӮөӮИӮўӮЖҚuӢ`ӮЙҸW’ҶӮЕӮ«ӮИӮўҒBҗFҒXӮЖҚlӮҰӮДӮўӮйӮӨӮҝӮЙӢMҺuӮ©ӮзғҒҒ[ғӢӮӘ•ФӮБӮДӮ«ӮҪҒB
[ӮҫӮБӮДҒcҒc“ьӮБӮДӮ«ӮҪӮЖӮ«ӮМҗXӮіӮсӮМҠзҒBҚKӮ№Ӯ»ӮӨӮМҲкҢҫӮҫӮБӮҪӮә]
(ӮИӮйӮЩӮЗҒcҒcӮБӮДүҪӮӘӮИӮйӮЩӮЗӮ¶ӮбҒIҒ@Һ„ҒAҗ—ҺqӮіӮсӮЖӮ»ӮӨӮўӮӨҠЦҢWӮЕҢ©ӮзӮкӮДӮўӮйӮБӮДӮұӮЖҒIҒH)
Ғ@ӢіҺәӮЙ“ьӮБӮДӮ«ӮҪӮЖӮ«ӮЙғҶғҠӮН’xҚҸӮЦӮМҸЕӮиӮЕҗ—ҺqӮМҠзӮрҢ©ӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBӢMҺuӮЙӮжӮкӮОҒAҗ—ҺqӮМҠзӮН”сҸнӮЙүxӮЙҗZӮБӮДӮўӮҪӮзӮөӮўҒBҺиӮрҢqӮӘӮкӮҪӮҫӮҜӮЕӢC•ӘӮӘҚӮӮЬӮйӮнӮҜӮӘ–іӮўҒBӮ»ӮкӮЕӮНүҪӮЕҗ—ҺqӮӘӮ»ӮсӮИӮЙҚKӮ№Ӯ»ӮӨӮҫӮБӮҪӮМӮ©ҒBҳVҺt•iҗмӮМҺгӮБӮҪҗәӮНғҶғҠӮМҺЁӮЙ“НӮўӮДӮўӮИӮўҒBғҶғҠӮНҚuӢ`’ҶӮёӮБӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪҒBҲкӮВӮҫӮҜ•ӘӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮНҗ—ҺqӮМ•\ҸоӮМӮЁүAӮЕғҶғҠӮӘ–hүq‘аӮЙҸБӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮҫӮБӮҪҒB
ҒuӮдҒcҒcӮҝӮбҒcҒcғҶғҠӮҝӮбӮсҒcҒcҒv
Ғ@’NӮ©ӮМҗәӮӘ•·ӮұӮҰӮДӮ«ӮҪҒB
(’NӮҫӮлӮӨҒH)
ҒuғҶғҠӮҝӮбӮсҒIҒ@ҺwӮіӮкӮДӮўӮйӮжҒIҒv
ҒuӮҰҒHҒv
Ғ@ӢCӮӘӮВӮҜӮОҺ©•ӘӮЙҢьӮ©ӮБӮДҸОӮўҗәӮӘҸгӮӘӮБӮДӮўӮҪҒBҚlӮҰӮДӮўӮй“аӮЙғҶғҠӮНӮӨӮҪӮҪҗQӮрӮөӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒA•iҗмӮМҺw–јӮр–іҺӢӮөӮҪӮМӮҫҒB
ҒuӮЁҒ[ӮЁҒ[ҒcҒcҒBғ{Ғ[ғbӮЖӮөӮДӮҝӮбғ@ҒAӮўӮ©ӮсӮжғHҒBӮЖӮиӮ ӮҰӮёғvғҠғ“ғgӮМ“а—eӮрғHҒA“ЗӮсӮЕӮЭӮИӮіӮўҒv
Ғ@•iҗмӮНғҶғҠӮр’ҚҲУӮөӮҪҢгҒAғvғҠғ“ғgӮр“ЗӮЮӮжӮӨӮЙӮЖҺwҺҰӮөӮҪҒB–ЪӮрҺCӮиӮИӮӘӮзғҶғҠӮНӮЗӮұӮр“ЗӮЮӮМӮ©Ӯр’TӮөӮДӮўӮҪҒB
ҒuғҶғҠӮҝӮбӮсҒAӮұӮұӮҫӮжҒv
Ғ@җ—ҺqӮНғҶғҠӮӘ“ЗӮЮ“а—eӮрҺwҚ·ӮөӮҪҒB“Ҝҗ«ҲӨӮЙӮВӮўӮДҸ‘Ӯ©ӮкӮҪҳ_•¶ӮҫӮБӮҪҒBҒi“Ҝҗ«ҲӨӮ©ғ@ҒB’j“ҜҺmӮЕӮНғQғCӮЕҸ—“ҜҺmӮЕӮНғҢғYӮЛҒcҒcҒBғRғEӮӘӢШ“чғҖғLғҖғLӮМ’j“сҗlӮӘғҢғXғҠғ“ғOӮрӮвӮБӮДӮўӮй“®үжӮрҢ©ӮДҠмӮсӮЕӮўӮҪӮИҒBғRғEӮағQғCӮИӮМҒHҒ@”УҢд”СӮМӮЖӮ«ӮаҒwӮЛӮҘҒAҺoӮіӮсҒBҚЎ”УӮНйQӮ©ӮҜғ`ғғҒ[ғnғ“Ӯ©ӮўҒHҒxӮЖӮ©ҢҫӮБӮДӮўӮҪӮҜӮЗҒAүҪӮ©ҠЦҢWӮ ӮйӮМҒHҒ@ӮЕӮағRғEӮНғQғCӮ¶ӮбӮИӮўӮЖҗMӮ¶ӮйҒBӮЬӮҫ’ҶҠwҗ¶ӮҫӮаӮМҒBҒ\Ғ\ӮаӮөғQғCӮҫӮБӮҪӮзҒcҒcӮ»ӮМӮЖӮ«ӮНӮ ӮМҺqӮрӢҺҗЁӮіӮ№ӮйҒcҒcғbҒIҒj
Ғ@ӮұӮсӮИӮұӮЖӮрҚlӮҰӮИӮӘӮзҳ_•¶Ӯр“ЗӮсӮЕӮўӮҪғҶғҠӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAүЎ–ЪӮЕҢ©ӮҪҗ—ҺqӮМ•\ҸоӮНҗ^Ң•ӮҫӮБӮҪҒB
ҒiҺцӢЖ’ҶӮНҗ^–К–ЪӮҫӮИҒBӮіӮ·ӮӘғgғbғvғNғүғXӮМ“ӘӮЛҒj
Ғ@–сҺO•ӘҠ|ӮҜӮДғҶғҠӮНҳ_•¶Ӯр“ЗӮсӮҫҒBҗИӮЙҚАӮБӮҪғҶғҠӮЙҗ—ҺqӮНҸ¬җәӮЕҺҝ–вӮр“ҠӮ°Ҡ|ӮҜӮйҒBӮ»ӮМ•\ҸоӮНҸӯӮө“ЬӮБӮДӮўӮҪҒB
ҒuғҶғҠӮҝӮбӮсҒA“Ҝҗ«ҲӨӮБӮДӮЗӮӨҺvӮӨҒHҒv
Ғ@җ—ҺqӮМ—Ұ’јӮИҺҝ–вӮЙғҶғҠӮНҸӯӮөӮӨӮлӮҪӮҰӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҺҝ–вӮН•ФӮіӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒBӮөӮ©Ӯа‘ҠҺиӮНҗXҗ—ҺqӮҫҒB•ПӮЙү“ӮЬӮнӮөӮИ•Ф“ҡӮрӮөӮҪӮзҒAӮӘӮБӮ©ӮиӮіӮкӮ©ӮЛӮИӮўҒBғҶғҠӮНҗі’јӮЙ“ҡӮҰӮйӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒB
Ғu‘SӮӯӢCӮЙӮөӮИӮўӮжҒv
ҒuӮЦҒHҒv
ҒuӮЬӮҹҗFҒX•ҫҠQӮӘӮ ӮйӮЖҺvӮӨӮҜӮЗҒA‘o•ыӮӘҚKӮ№ӮИӮзӮОӮ»ӮкӮЕӮўӮўӮсӮ¶ӮбӮИӮўҒHҒ@•tӮ«ҚҮӮӨӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮжӮӯӮ ӮйӮұӮЖӮИӮсӮҫӮҜӮЗҒAҲк”Ф•|ӮўӮМӮН’uӮўӮДӮ«ӮЪӮиӮЙӮіӮкӮйӮұӮЖӮжҒ\Ғ\Ғv
Ғ@ғҶғҠӮНҗі’јӮЙҢҫӮБӮҪӮұӮЖӮрҢгүчӮөӮҪҒBӮ ӮМӢLүҜӮӘҢДӮСӢNӮұӮіӮкӮйҒBҲГӮўүң’кӮ©ӮзҸёӮБӮДӮӯӮйғҶғҠӮМҗSӮр“ЛӮ«ҺhӮ·ӮжӮӨӮИӢLүҜҒBҚр”УҢ©ӮҪҗSӮМҸқӮӘҗ¶ӮЮҒAҚKӮ№ӮрҲшӮ«—фӮӯ–ІӮа“ҜҺһӮЙҚҮӮнӮіӮБӮДӮЗӮс’кӮЙ“ЛӮ«—ҺӮЖӮ·ҒBӮЬӮҪӮҫҒB
ҒuғҶғҠӮҝӮбӮсҒA‘еҸд•vҒHҒv
Ғ@Ғ\Ғ\‘жҲкҺһҢАӮМҚuӢ`ӮӘҸIӮнӮйғ`ғғғCғҖӮӘ—¬ӮкӮДӮўӮйҒBҗ—ҺqӮӘғҶғҠӮМҚ¶ҺиӮрҲ¬ӮБӮДӮўӮҪҒBғҶғҠӮНӮ»ӮМҺиӮрҲ¬Ӯи’чӮЯӮйҒB
Ғu‘еҸд•vҒBӮҝӮеӮБӮЖ”жӮкӮДӮйӮҫӮҜҒcҒcҒBҚр”УғҢғ|Ғ[ғgӮрӮвӮБӮҪӮ©ӮзҒAӮ ӮсӮЬӮиҗQӮДӮИӮўӮМҒBӮІӮЯӮсӮЛҒAҗS”zҠ|ӮҜӮҝӮбӮБӮДҒv
Ғ@ғҶғҠӮН’©ӮЙ‘ұӮ«үRӮрӮВӮўӮҪҒBғҶғҠӮЙӮЖӮБӮДӮНүRӮНҺ©•ӘӮзӮөӮӯӮИӮўҚsҲЧӮЕӮ ӮйӮЖҺ©ҠoӮөӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮкӮҫӮҜӮНүЖ‘°ҲИҠOӮЙ’mӮзӮкӮҪӮӯӮИӮўҒBҺ©•ӘӮЙүRӮрӮВӮ«ҒA‘јҗlӮЙүRӮрӮВӮӯҒB“сҸdӮМүRӮӘҚЎӮМғҶғҠӮМ–hҢм•ЗӮЙӮИӮйҒBҸӯӮИӮӯӮЖӮаҺ©•ӘӮзӮөӮӯӮ ӮйӮҪӮЯӮЙӮН‘јҗlӮЙ’mӮзӮкӮёӮЙҺ©•ӘӮзӮөӮӯӮИӮўӮұӮЖӮрӮ·ӮйӮөӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒB
Ғuҗ—ҺqӮҝӮбӮсҒAӮұӮМҢгӮЗӮӨӮ·ӮйҒHҒ@Һ„ӮН“сҢАӮӘ–іӮўӮ©ӮзҗH“°ӮЕӮЁ’ӢҗHӮЧӮйӮҜӮЗҒv
ҒuҗҘ”сҒAӮІҲкҸҸӮөӮЬӮ·ҒIҒIӮЗӮұӮЕҗHӮЧӮЬӮ·Ӯ©ҒHҒv
ҒuӮ¶ӮбӮ ҲкҺlҚҶҠЩ’nүәӮЕӮўӮўӮсӮ©ӮИҒBҚЎғJғҢҒ[ғtғFғAӮвӮБӮДӮўӮйӮЖҺvӮӨӮ©ӮзҒv
ҒuӮ©ҒAғJғҢҒ[ҒcҒcҒIҒHҒ@–{“–ӮЙғJғҢҒ[ӮЕӮ·Ӯ©ҒHҒv
ҒuӮҰҒAӮ»ӮӨӮҫӮҜӮЗҒAғJғҢҒ[ҢҷӮўӮИӮМҒHҒv
ҒuӮўӮҰҒA‘еғbҚDӮ«ӮЕӮ·ғbҒIҒIҒv
Ғ@—}—gӮрӮВӮҜӮДғJғҢҒ[ӮӘҚDӮ«ӮИӮұӮЖӮрҺе’ЈӮөӮҪҗ—ҺqҒB’ҡ“xҒAғJғҢҒ[ғtғFғAӮӘӮ ӮйӮұӮЖӮЙӢCӮГӮўӮДӮжӮ©ӮБӮҪӮЖҺvӮӨғҶғҠҒBӮұӮкҲИҸгҒAғҶғҠӮМӢC•ӘӮӘ—ҺӮҝӮИӮўӮжӮӨӮЙӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНӮЖӮЙӮ©Ӯӯ‘OӮЙҗiӮЮӮұӮЖӮҫӮБӮҪҒB—§ӮҝҺ~ӮЬӮБӮҪӮзҢгӮлӮ©Ӯз”—ӮйӢCҺқӮҝӮЙғYғӢғYғӢӮЖҲшӮ«–ЯӮіӮкӮДӮөӮЬӮӨӮҫӮлӮӨҒB‘OӮЙүҪӮӘӮ ӮйӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒBӮөӮ©ӮөҒA“ҡӮҰӮН‘OӮЙҗiӮЬӮИӮҜӮкӮОҢ©ӮВӮҜӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮўҒBӮ»ӮкӮрҺvӮўҸoӮөӮҪғҶғҠӮНӢCҺқӮҝӮр—ҺӮҝ’…ӮҜӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBҗ—ҺqӮМҲкҸ•ӮаӮ ӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҗ—ҺqӮНӢCӮГӮўӮДӮўӮИӮўӮӘҒAҗ—ҺqӮӘғҶғҠӮМҺиӮрҲ¬ӮБӮДӮӯӮкӮҪӮұӮЖӮрҠҙҺУӮөӮҪҒBҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
Ғ@Ғi‘ұҒHҒj
|
|
|